『ロズウェルなんか知らない』篠田節子
面白かった!
いや~、面白かった。通勤時にチビチビ読もうかと思っていたのだが(なんせ文庫で600ページ以上あるので)、段々盛り上がってきて、日曜に一気に読んでしまった。面白くて、イタズラっぽくて、ドキドキして、ヒヤヒヤして、バビンチョ!じゃなくてうーんと唸って、ほっとして嬉しくなって、そして読み終えた後に現実を振り返って少し暗くなる。そんな感じ。
以下、若干のネタバレあり。
東京から中途半端に遠い寂れた町。スキー場は撤退し、温泉や名所もない。青年クラブの連中が、必死になって客を呼び込もうとしたのだが、現代の客商売を知らない頭の固い年寄り連のおかげで観光客の評判は芳しくない。ところが、一部の客がUFOが出たと勘違いし、それがネットで密かに話題になる。それを知った青年クラブの、特に都会から移住してきた連中が、「日本の四次元地帯」で町を売り出そうとする。なかば破れかぶれになったほかのメンバーたちも乗っかり、ストーンサークルをコッソリ作ったり、捨て置かれた遊園地のお化け屋敷を改造して宇宙人の死体解剖の再現場面を作ったりして、段々話題になり、客がわんさか押し寄せるようになる。そして…というお話。
何が面白いかと言うと、状況設定がリアルなのだ。長引く不況(景気のいいのは大企業だけだ)で落ち込む「地方」がとてもリアルに描かれている。また、保守的な年配の人々の姿がいかにもありそうな感じに描かれている。現在私は結構な地方に住んでいるのだけれども(県庁所在地ではあるが)、こちらに来て、仕事のつながりなどでずっとここに住んでおられる方々とお話などしていると、なるほどなあ、と思ってしまうところが多々あるのだ。「そんなのは町の恥だ!」とか、「挨拶は町長がしねえと」みたいな発想。
さらに、当然「四次元地帯」とか「UFO・宇宙人」で売り出せば、雑誌やテレビの取材がやってきて、やがてバッシングに変わる、といういかにもな展開をするわけだが、それがまたリアル。そして、その小説内で展開される批判が実に正しい。つまり、そういうオカルトめいたものを容認・助長する雰囲気こそが、オウムのような事件につながる遠因となるのである、と。
そして、どんなに論理的な批判がなされても、信じる人は信じる、ということがまた冷静に描かれているのが面白い。どれだけバッシングされても、それが逆に宣伝になって、人がわんさかやってくる。UFOとスピリチュアルを一体化したような連中まで現れる。
なのでそのラストの展開は、町を復興させようと必死になっている青年クラブの連中に感情移入して読んでいると、激しいバッシングにもかかわらず町に人を呼び込む展望が見えるので、ホッとするのだ。
ところが、小説の展開があまりにもリアルなので、結局信じたい人は何を言っても信じてしまう、ということもまた正面から見てしまうことになり、日常の自分がやっていることと重ね合わせて考えてみると、一体どうしたらいいんだ、と悩みは深まってしまうのだ。
というわけで、単純に小説としても面白いけど、ニセ科学に興味のある人には、より一層面白いと思う。
いや~、面白かった。通勤時にチビチビ読もうかと思っていたのだが(なんせ文庫で600ページ以上あるので)、段々盛り上がってきて、日曜に一気に読んでしまった。面白くて、イタズラっぽくて、ドキドキして、ヒヤヒヤして、バビンチョ!じゃなくてうーんと唸って、ほっとして嬉しくなって、そして読み終えた後に現実を振り返って少し暗くなる。そんな感じ。
以下、若干のネタバレあり。
東京から中途半端に遠い寂れた町。スキー場は撤退し、温泉や名所もない。青年クラブの連中が、必死になって客を呼び込もうとしたのだが、現代の客商売を知らない頭の固い年寄り連のおかげで観光客の評判は芳しくない。ところが、一部の客がUFOが出たと勘違いし、それがネットで密かに話題になる。それを知った青年クラブの、特に都会から移住してきた連中が、「日本の四次元地帯」で町を売り出そうとする。なかば破れかぶれになったほかのメンバーたちも乗っかり、ストーンサークルをコッソリ作ったり、捨て置かれた遊園地のお化け屋敷を改造して宇宙人の死体解剖の再現場面を作ったりして、段々話題になり、客がわんさか押し寄せるようになる。そして…というお話。
何が面白いかと言うと、状況設定がリアルなのだ。長引く不況(景気のいいのは大企業だけだ)で落ち込む「地方」がとてもリアルに描かれている。また、保守的な年配の人々の姿がいかにもありそうな感じに描かれている。現在私は結構な地方に住んでいるのだけれども(県庁所在地ではあるが)、こちらに来て、仕事のつながりなどでずっとここに住んでおられる方々とお話などしていると、なるほどなあ、と思ってしまうところが多々あるのだ。「そんなのは町の恥だ!」とか、「挨拶は町長がしねえと」みたいな発想。
さらに、当然「四次元地帯」とか「UFO・宇宙人」で売り出せば、雑誌やテレビの取材がやってきて、やがてバッシングに変わる、といういかにもな展開をするわけだが、それがまたリアル。そして、その小説内で展開される批判が実に正しい。つまり、そういうオカルトめいたものを容認・助長する雰囲気こそが、オウムのような事件につながる遠因となるのである、と。
そして、どんなに論理的な批判がなされても、信じる人は信じる、ということがまた冷静に描かれているのが面白い。どれだけバッシングされても、それが逆に宣伝になって、人がわんさかやってくる。UFOとスピリチュアルを一体化したような連中まで現れる。
なのでそのラストの展開は、町を復興させようと必死になっている青年クラブの連中に感情移入して読んでいると、激しいバッシングにもかかわらず町に人を呼び込む展望が見えるので、ホッとするのだ。
ところが、小説の展開があまりにもリアルなので、結局信じたい人は何を言っても信じてしまう、ということもまた正面から見てしまうことになり、日常の自分がやっていることと重ね合わせて考えてみると、一体どうしたらいいんだ、と悩みは深まってしまうのだ。
というわけで、単純に小説としても面白いけど、ニセ科学に興味のある人には、より一層面白いと思う。
- ロズウェルなんか知らない (講談社文庫 し 46-5)/篠田 節子
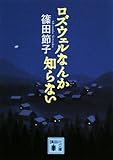
- ¥940
- Amazon.co.jp
どうして量子力学を齧ったサイエンスライターは観測問題とスピリチュアルを結び付けたがるのか
本屋でウロウロしていたら、桜井進氏の著作が何冊か並んでいたのに気がついた。で、その中の一冊を手にとってパラパラとめくっていたのだが。相変わらず、量子力学についてアヤシイ解説をしているので、ちょっと困ってしまう。
ミクロな世界を記述する「量子力学」の世界では、物質は「粒子性」と「波動性」の二つの側面を持つ。例えば「光」は波動であるが、同時に、「つぶつぶ」の性質も持つ(エネルギーの高い光、X線とかγ線とか、で特に顕著である)。同様に、「つぶつぶ」と思われていた電子のような粒子も、波動としての性質を持つ。電子顕微鏡とかね。
で、波というのはどこか一点にあるものではなくて、拡がったある領域に存在するもの。「波長」なんてまさにそれをあらわしている。点じゃなくて、長さを持つわけ。この「拡がった」性質と、一点にある粒子としての性質をどう両立させるか。これが「観測問題」(かなりフツーじゃない解説になってますが、こういう言い方でもたぶん間違ってないでしょう)。
スタンダードな解釈は、「観測」により、波が一点に収縮して、そこで粒子性を発現させる、というもの。たとえば原子の周囲には電子がまわっているが、太陽のまわりをまわる惑星のようにまわっているわけではなく、波として拡がった「電子雲」として存在している。ここになにか粒子なり光子なりをあてると、そのどこか一点で電子が観測される。つまり、「雲」が一瞬にして「点」に収縮した、と考えるわけ。
この「観測」がなんなのか、実はまだよくわかっていない。で、その極端な解釈として、「人間」による観測を特別視する連中がいる。「人間」が「視た」から、その点に収縮したのだ、と。だから、もしかしたら、「念ずる」ことによって、どこに収縮するか、コントロールできるかもしれない、と。
量子力学では、その「波」を表す「波動関数」(要するに波を表すサインとかコサインで書ける波なんだが)が存在確率に関係している(波動関数を自乗したものが存在確率)。どこに収縮するかは確率でしかわからないけど、しかし確率分布自体は決定論的に決まっているのだよね。そこに意識だの観測だのが介在する余地はない。
ところが、桜井氏は、それをにおわすのだ。スピリチュアルとの関係まで、「こういうところにあるかもしれない」みたいな感じで述べる。なんでこんなことを書くのだろう。本気でそうだと思っているのだろうか。それとも、書くとウケるから、みたいな感じなんだろうか。
数学についての解説本も一緒にならんでいたのだけど、そっち方面に専念したほうがいいんじゃないだろうか。
これがもっと進むと、このブログでも何度か触れた、奥健夫氏のようになるんだろうが…。
ちなみに桜井氏については、以前このエントリ で言及しています。
ミクロな世界を記述する「量子力学」の世界では、物質は「粒子性」と「波動性」の二つの側面を持つ。例えば「光」は波動であるが、同時に、「つぶつぶ」の性質も持つ(エネルギーの高い光、X線とかγ線とか、で特に顕著である)。同様に、「つぶつぶ」と思われていた電子のような粒子も、波動としての性質を持つ。電子顕微鏡とかね。
で、波というのはどこか一点にあるものではなくて、拡がったある領域に存在するもの。「波長」なんてまさにそれをあらわしている。点じゃなくて、長さを持つわけ。この「拡がった」性質と、一点にある粒子としての性質をどう両立させるか。これが「観測問題」(かなりフツーじゃない解説になってますが、こういう言い方でもたぶん間違ってないでしょう)。
スタンダードな解釈は、「観測」により、波が一点に収縮して、そこで粒子性を発現させる、というもの。たとえば原子の周囲には電子がまわっているが、太陽のまわりをまわる惑星のようにまわっているわけではなく、波として拡がった「電子雲」として存在している。ここになにか粒子なり光子なりをあてると、そのどこか一点で電子が観測される。つまり、「雲」が一瞬にして「点」に収縮した、と考えるわけ。
この「観測」がなんなのか、実はまだよくわかっていない。で、その極端な解釈として、「人間」による観測を特別視する連中がいる。「人間」が「視た」から、その点に収縮したのだ、と。だから、もしかしたら、「念ずる」ことによって、どこに収縮するか、コントロールできるかもしれない、と。
量子力学では、その「波」を表す「波動関数」(要するに波を表すサインとかコサインで書ける波なんだが)が存在確率に関係している(波動関数を自乗したものが存在確率)。どこに収縮するかは確率でしかわからないけど、しかし確率分布自体は決定論的に決まっているのだよね。そこに意識だの観測だのが介在する余地はない。
ところが、桜井氏は、それをにおわすのだ。スピリチュアルとの関係まで、「こういうところにあるかもしれない」みたいな感じで述べる。なんでこんなことを書くのだろう。本気でそうだと思っているのだろうか。それとも、書くとウケるから、みたいな感じなんだろうか。
数学についての解説本も一緒にならんでいたのだけど、そっち方面に専念したほうがいいんじゃないだろうか。
これがもっと進むと、このブログでも何度か触れた、奥健夫氏のようになるんだろうが…。
ちなみに桜井氏については、以前このエントリ で言及しています。
どっかで見たような
Yahoo掲示板での私のコメントをまた転載します。何度も転載しているので、この際と思って「マイナスイオン」のテーマを追加しました。
こちら 。
---
ssfs2007さん、
先に一つ確認しておきたいのですが、以下の2点については合意、ということでいいでしょうか?今後の議論の基礎を構築する上で、共通理解がどこにあるかを確認するのは重要だと思いますので。
(1)ドライヤーの評判の良さが「○○イオン」のせいであるかどうか、あるいは「○○イオン」が良い効果をもたらすかどうか、は未だ明確ではない。
(2)明確ではないにも関わらず、それを「効果がある」とうたって商品を販売するメーカーは無責任である。
以下、ssfs2007さんのコメントへのレスです。
>> そうではありません。それはニュートラルではありません。以前もコメントしたように、帰無仮説は「効果がない」にしなければなりません。帰無仮説は、一つ でも効果があれば否定できます。ですから、ニュートラルは「効果があるとは言えない」です。No.1330, 1332 の私のコメントをもう一度、どうかお読み下さい。
>
>私がどんな問題意識を持っているか、もう1度最初からログを読み直してください。一貫して「ドライヤーの何がユーザーの良い評判をもたらしているかを考えてみよう」です。
ええ、それはわかっています。ですから、私も「技報」の検討などもしてここに書き込んだわけです。なんてったって、実際に製造販売しているメーカーが出して いる報告ですからね、「○○イオン」の効果については、どんな細かいことでも、また多少は統計的には強弁であっても、可能な効果についてはなにかしら語っ ているだろうと期待したわけですね。
逆に言うと、その「技報」でさえ、それが出しているデータは、「ドライヤーの○○イオンがユーザーの良い評 判をもたらしているというわけではなさそう」ということを示唆しているわけです。そういう分析結果を私は出したわけで、その意味で、ssfs2007さん の問題意識よりは一歩先を進んでいると思いますが?
> 今のところ、ドライヤーが放出するイオンが有力だと考えています。ほかにどんな要因がありそうでしょうか? 思い浮かぶものが何もなく、ただイオン説を否 定したいのであれば、それはユーザー無視の態度です。そうした態度は kikulogでさんざん見てきたので、もう「おなかいっぱい」です。
「技 報」にはユーザーの報告が定量的に分析してあることは述べました。ユーザーの報告を見る限り、「ユーザーの良い評判」は「○○イオン」とは関係なさそう だ、と私はコメントしたはずです。つまり、「ドライヤーが放出するイオンが有力」とは考えられない、ということです。これは「ただイオン説を否定したい」 のではなく、メーカーの報告を、そしてユーザーの評価を検討した結果です。
もう一度、No.1330, 1332の私のコメントを読んでください。私が、「ユーザー無視」どころか、ユーザーの評価に基づいて議論をしているということがわかると思いますので。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835549&tid=a1va5dea5a4a5ja59a5a4a5aaa5sa1w4fbbkbcbc&sid=1835549&mid=1330
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835549&tid=a1va5dea5a4a5ja59a5a4a5aaa5sa1w4fbbkbcbc&sid=1835549&mid=1332
さて。
あなたは「ファクト」にこだわってるんでしょう?でしたら、メーカーの報告を真剣に受け止めてはどうですか?私は以前、この「技報」は査読を通るようなレベルのものではない、と書きましたが、その上で、出された結果については真剣に検討していますよ。
それから、帰無仮説はファクトを導くための重要な手段です。いや、「帰無仮説」なんてもったいぶった言葉はどうでもいいのですが、その中身は、科学的手続 きの大変重要な部分を構成していますので、ぜひ理解して欲しいと思います。その精神は、簡単に言えば、「あるかどうかもわからんことを、『ある』なんて軽 々しく言うな」と言うことになるかと思います。
---
こういう統計用語が理解できなかった人と言えば、あの人、つまり某A氏を思い出す(某A氏については、Jさんのブログ を見るのが一番わかりやすい)。AB○FAN氏とでもしておきましょうか。:p SSFSさんも、このままでは某A氏と同類なんだということをわかってほしいんですけどねえ…。
「立証責任」も「帰無仮説」も、厳密にはちゃんと統計を勉強しないといけないけれど、そのココロは、実はとても常識的な発想だったりする。SSFS氏に対しては、「立証責任」とか「挙証責任」とか言うと、内容の前に単語で脊髄反射されそうなので、あえてそういう言葉を使わずに、「それは無責任でしょ?」とか言い換えていたのだけど(ちなみに立証責任の単純な言い換えとは言えなくて、立証責任にはもう少し広い考えが必要ではあるけれど)。
しかし、どういう反応が返って来るか、ソレナリに予想というか覚悟はしていたけれど、「帰無仮説に逃げないこと」というのはなあ…。なかなかほほ笑ましいです。
あ、TAKESANさんが、さっそくエントリをあげておられる 。(^^;;
掲示板での、上のコメントの次の私のコメント(No.1493)とも関わってくるのだけど、「イオン説が有力」と考えるのはいいとして、そこからどうやって次のステップに進むつもりなんだろう?その道すじが、見えない。
こちら 。
---
ssfs2007さん、
先に一つ確認しておきたいのですが、以下の2点については合意、ということでいいでしょうか?今後の議論の基礎を構築する上で、共通理解がどこにあるかを確認するのは重要だと思いますので。
(1)ドライヤーの評判の良さが「○○イオン」のせいであるかどうか、あるいは「○○イオン」が良い効果をもたらすかどうか、は未だ明確ではない。
(2)明確ではないにも関わらず、それを「効果がある」とうたって商品を販売するメーカーは無責任である。
以下、ssfs2007さんのコメントへのレスです。
>> そうではありません。それはニュートラルではありません。以前もコメントしたように、帰無仮説は「効果がない」にしなければなりません。帰無仮説は、一つ でも効果があれば否定できます。ですから、ニュートラルは「効果があるとは言えない」です。No.1330, 1332 の私のコメントをもう一度、どうかお読み下さい。
>
>私がどんな問題意識を持っているか、もう1度最初からログを読み直してください。一貫して「ドライヤーの何がユーザーの良い評判をもたらしているかを考えてみよう」です。
ええ、それはわかっています。ですから、私も「技報」の検討などもしてここに書き込んだわけです。なんてったって、実際に製造販売しているメーカーが出して いる報告ですからね、「○○イオン」の効果については、どんな細かいことでも、また多少は統計的には強弁であっても、可能な効果についてはなにかしら語っ ているだろうと期待したわけですね。
逆に言うと、その「技報」でさえ、それが出しているデータは、「ドライヤーの○○イオンがユーザーの良い評 判をもたらしているというわけではなさそう」ということを示唆しているわけです。そういう分析結果を私は出したわけで、その意味で、ssfs2007さん の問題意識よりは一歩先を進んでいると思いますが?
> 今のところ、ドライヤーが放出するイオンが有力だと考えています。ほかにどんな要因がありそうでしょうか? 思い浮かぶものが何もなく、ただイオン説を否 定したいのであれば、それはユーザー無視の態度です。そうした態度は kikulogでさんざん見てきたので、もう「おなかいっぱい」です。
「技 報」にはユーザーの報告が定量的に分析してあることは述べました。ユーザーの報告を見る限り、「ユーザーの良い評判」は「○○イオン」とは関係なさそう だ、と私はコメントしたはずです。つまり、「ドライヤーが放出するイオンが有力」とは考えられない、ということです。これは「ただイオン説を否定したい」 のではなく、メーカーの報告を、そしてユーザーの評価を検討した結果です。
もう一度、No.1330, 1332の私のコメントを読んでください。私が、「ユーザー無視」どころか、ユーザーの評価に基づいて議論をしているということがわかると思いますので。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835549&tid=a1va5dea5a4a5ja59a5a4a5aaa5sa1w4fbbkbcbc&sid=1835549&mid=1330
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835549&tid=a1va5dea5a4a5ja59a5a4a5aaa5sa1w4fbbkbcbc&sid=1835549&mid=1332
さて。
あなたは「ファクト」にこだわってるんでしょう?でしたら、メーカーの報告を真剣に受け止めてはどうですか?私は以前、この「技報」は査読を通るようなレベルのものではない、と書きましたが、その上で、出された結果については真剣に検討していますよ。
それから、帰無仮説はファクトを導くための重要な手段です。いや、「帰無仮説」なんてもったいぶった言葉はどうでもいいのですが、その中身は、科学的手続 きの大変重要な部分を構成していますので、ぜひ理解して欲しいと思います。その精神は、簡単に言えば、「あるかどうかもわからんことを、『ある』なんて軽 々しく言うな」と言うことになるかと思います。
---
こういう統計用語が理解できなかった人と言えば、あの人、つまり某A氏を思い出す(某A氏については、Jさんのブログ を見るのが一番わかりやすい)。AB○FAN氏とでもしておきましょうか。:p SSFSさんも、このままでは某A氏と同類なんだということをわかってほしいんですけどねえ…。
「立証責任」も「帰無仮説」も、厳密にはちゃんと統計を勉強しないといけないけれど、そのココロは、実はとても常識的な発想だったりする。SSFS氏に対しては、「立証責任」とか「挙証責任」とか言うと、内容の前に単語で脊髄反射されそうなので、あえてそういう言葉を使わずに、「それは無責任でしょ?」とか言い換えていたのだけど(ちなみに立証責任の単純な言い換えとは言えなくて、立証責任にはもう少し広い考えが必要ではあるけれど)。
しかし、どういう反応が返って来るか、ソレナリに予想というか覚悟はしていたけれど、「帰無仮説に逃げないこと」というのはなあ…。なかなかほほ笑ましいです。
あ、TAKESANさんが、さっそくエントリをあげておられる 。(^^;;
掲示板での、上のコメントの次の私のコメント(No.1493)とも関わってくるのだけど、「イオン説が有力」と考えるのはいいとして、そこからどうやって次のステップに進むつもりなんだろう?その道すじが、見えない。
「○○イオンに効果があるとは言えない」ということ
またまた例のYahooの掲示板「マイナスイオン監視室」
に長文を投稿してしまった。「長すぎ」と怒られたので二つに分けました。まとめてここに掲載しておきます。No.1483
, No.1484
です。やっぱりループになっているので、ssfs2007さん(SSFSさん)には「おなかいっぱい」とか「つまらなすぎ」とか言う前に、多少長くても、ちゃんと読んで欲しいんですけどねえ。
でもまあ「○○イオンの効果がある」と現状では言えないという事はお認めになられたようで。そんな状況で「○○イオン」で物を売るのがどれだけ無責任か、ってことに思いを馳せてもらえればいいんですが…。
---
> 松下はニュースリリースと技報と特許で用語や説明をわざわざ変えたりして一貫性がありません。しかし、技術的な説明をまったくしないメーカーがたくさんあるなかでは、技報は一定レベルの解説にはなっていると思います。そうした技報やらその他のネットコンテンツやらをたくさん集めて、だんだんと理解を深めていけばいいわけで、即断する必要はまったくありません。
ええ、「○○イオンに効果がある」と即断する必要はまったくありません。その通りです。
> >なので、科学的な立場に立つならば、「マイナスイオン」「ナノイーイオン」の効果であるとは言えない、という結論になるのです。
>
> その結論はまずいです。「効果であるとは言えるかどうかは現時点では分からない」がニュートラルな表現。
そうではありません。それはニュートラルではありません。以前もコメントしたように、帰無仮説は「効果がない」にしなければなりません。帰無仮説は、一つでも効果があれば否定できます。ですから、ニュートラルは「効果があるとは言えない」です。No.1330, 1332 の私のコメントをもう一度、どうかお読み下さい。
> ただし、非常に数多くのユーザーから非イオン系ドライヤーよりイオン系、マイナスイオンよりナノイオンというコメントが出ているので、それは勘案すべきでしょう。
先日触れた「技報」で言えば、古い手持ちのドライヤーよりは新しいドライヤーが良い、新しいドライヤーでマイナスイオンのオン・オフの違いは誤差の範囲、ということになります。なので、定量的に示されたデータの範囲で言えば、現時点での暫定的な結論は、(1)確かに新しいドライヤーは良さそうであるが、(2)それが「○○イオン」の影響であるとは言えない、というものです。ついでに言えば、「○○イオン」の影響は、劇的なものではない、ということも示していますね、あの「技報」は。
なおこれも以前触れたことですが、使用感と言えどもなんらかの形でのブラインドテストは必要です。なんで「利き酒」をするのか、考えてみてください。
> >そして、効果の根拠を断定できないにも関わらず、「○○イオンの効果だ」と断定して販売するメーカーを、マーケティングだからと言って許容していいんですか?と話はつながるわけですね。
>
> 先に家電公取協の仕事を取り上げましたが、まず誰かがマーケティングの落ち度を指摘する必要があるでしょう。イオンの効果ではないことを fsm_fireflysquidさんが例証できますか? 私がkikulog以来ずっと言っていることはそれですよ。イオンの効果という宣伝が気に入らないなら、文句ばかり言っていないで、何か説得材料を見つけなきゃ。
上で述べたように、誰かが述べた「○○イオンの効果である」という結論に対し、「それは本当か?」と考えるのが批判的思考というものです。なぜなら「効果はない」というのが帰無仮説であり、それが何かを主張しようとする場合の標準的なやり方だからです。「○○イオン」の効果であることが立証されていないのに、「これは○○イオンの効果だ」と言って売るのは無責任でしょう?気に入る気に入らないの話じゃなくて、確定していないものを確定したかのように言うのが無責任だ、と言っているのです。「マイナスイオン」では人は死なないだろうから薬事法にも引っかからないですが、話としては薬と同じですよ。「○○イオン」を宣伝文句に何かを売ろうとするなら、ちゃんと効果を証明してからじゃなきゃ。
何度も言いますが、説得するのは売るほうですよ。無責任な言動で商売するのは、少なくとも道義的には問題あるでしょ?私が言っているのは、「メーカーは無責任なことをするな」ということです。「技報」で報告するのは責任を取ろうと言う姿勢が多少なりとも伺えるので評価はしたいところですが、物を売りながら効果について調べるってのは順番が逆じゃないですかね?
なお、ssfs2007さんが引用された私のコメントの前段を再掲します。「なので、科学的立場に立つならば~」の前の部分です。
> つまり、本来、「マイナスイオン」「ナノイーイオン」は重要である、という主張をすべき(あるいは実証すべき)メーカーが出している「技報」において *さえ*、「○○イオンの効果である」と断定できるほどのデータは出せていない、ということを意味しているのです。メーカーでさえ断定できないものを、第三者が「穴があるから」云々ということで無視はできないでしょう。ssfs2007さんが何を持って「穴」とおっしゃっているのかわかりませんが(指摘していただけると助かります)、「穴」も含めて根拠と言っていいかと思います。
どうか「おなかいっぱい」でも読んでください。どれもすでに書いたことです。とりあえず、「○○イオン」に効果がある、と断定はできない、という点で認識が一致できたのは議論が進展している証拠だとは思いますが…。
でもまあ「○○イオンの効果がある」と現状では言えないという事はお認めになられたようで。そんな状況で「○○イオン」で物を売るのがどれだけ無責任か、ってことに思いを馳せてもらえればいいんですが…。
---
> 松下はニュースリリースと技報と特許で用語や説明をわざわざ変えたりして一貫性がありません。しかし、技術的な説明をまったくしないメーカーがたくさんあるなかでは、技報は一定レベルの解説にはなっていると思います。そうした技報やらその他のネットコンテンツやらをたくさん集めて、だんだんと理解を深めていけばいいわけで、即断する必要はまったくありません。
ええ、「○○イオンに効果がある」と即断する必要はまったくありません。その通りです。
> >なので、科学的な立場に立つならば、「マイナスイオン」「ナノイーイオン」の効果であるとは言えない、という結論になるのです。
>
> その結論はまずいです。「効果であるとは言えるかどうかは現時点では分からない」がニュートラルな表現。
そうではありません。それはニュートラルではありません。以前もコメントしたように、帰無仮説は「効果がない」にしなければなりません。帰無仮説は、一つでも効果があれば否定できます。ですから、ニュートラルは「効果があるとは言えない」です。No.1330, 1332 の私のコメントをもう一度、どうかお読み下さい。
> ただし、非常に数多くのユーザーから非イオン系ドライヤーよりイオン系、マイナスイオンよりナノイオンというコメントが出ているので、それは勘案すべきでしょう。
先日触れた「技報」で言えば、古い手持ちのドライヤーよりは新しいドライヤーが良い、新しいドライヤーでマイナスイオンのオン・オフの違いは誤差の範囲、ということになります。なので、定量的に示されたデータの範囲で言えば、現時点での暫定的な結論は、(1)確かに新しいドライヤーは良さそうであるが、(2)それが「○○イオン」の影響であるとは言えない、というものです。ついでに言えば、「○○イオン」の影響は、劇的なものではない、ということも示していますね、あの「技報」は。
なおこれも以前触れたことですが、使用感と言えどもなんらかの形でのブラインドテストは必要です。なんで「利き酒」をするのか、考えてみてください。
> >そして、効果の根拠を断定できないにも関わらず、「○○イオンの効果だ」と断定して販売するメーカーを、マーケティングだからと言って許容していいんですか?と話はつながるわけですね。
>
> 先に家電公取協の仕事を取り上げましたが、まず誰かがマーケティングの落ち度を指摘する必要があるでしょう。イオンの効果ではないことを fsm_fireflysquidさんが例証できますか? 私がkikulog以来ずっと言っていることはそれですよ。イオンの効果という宣伝が気に入らないなら、文句ばかり言っていないで、何か説得材料を見つけなきゃ。
上で述べたように、誰かが述べた「○○イオンの効果である」という結論に対し、「それは本当か?」と考えるのが批判的思考というものです。なぜなら「効果はない」というのが帰無仮説であり、それが何かを主張しようとする場合の標準的なやり方だからです。「○○イオン」の効果であることが立証されていないのに、「これは○○イオンの効果だ」と言って売るのは無責任でしょう?気に入る気に入らないの話じゃなくて、確定していないものを確定したかのように言うのが無責任だ、と言っているのです。「マイナスイオン」では人は死なないだろうから薬事法にも引っかからないですが、話としては薬と同じですよ。「○○イオン」を宣伝文句に何かを売ろうとするなら、ちゃんと効果を証明してからじゃなきゃ。
何度も言いますが、説得するのは売るほうですよ。無責任な言動で商売するのは、少なくとも道義的には問題あるでしょ?私が言っているのは、「メーカーは無責任なことをするな」ということです。「技報」で報告するのは責任を取ろうと言う姿勢が多少なりとも伺えるので評価はしたいところですが、物を売りながら効果について調べるってのは順番が逆じゃないですかね?
なお、ssfs2007さんが引用された私のコメントの前段を再掲します。「なので、科学的立場に立つならば~」の前の部分です。
> つまり、本来、「マイナスイオン」「ナノイーイオン」は重要である、という主張をすべき(あるいは実証すべき)メーカーが出している「技報」において *さえ*、「○○イオンの効果である」と断定できるほどのデータは出せていない、ということを意味しているのです。メーカーでさえ断定できないものを、第三者が「穴があるから」云々ということで無視はできないでしょう。ssfs2007さんが何を持って「穴」とおっしゃっているのかわかりませんが(指摘していただけると助かります)、「穴」も含めて根拠と言っていいかと思います。
どうか「おなかいっぱい」でも読んでください。どれもすでに書いたことです。とりあえず、「○○イオン」に効果がある、と断定はできない、という点で認識が一致できたのは議論が進展している証拠だとは思いますが…。
ムペンバ効果:過冷却?
なんかムペンバ効果について色々考えてしまったので、「ムペンバ効果」というテーマを新たに設けました。以前のエントリも、そちらに変更する予定。
さて、ムペンバ効果があるとした場合の話であるが、「ガリレオ工房」の滝川洋二さんの解説に引きずられて、とりあえずマクロ系の決定論的な解釈をいままで試みてきた。ただ、もちろん別の解釈もありうるのである。その一つが、過冷却によるものだ。
これは wikipedia の解説 にも簡単に触れられている。水は通常は0℃まで冷やされたら、そこで水は一旦温度低下が止まり、液体から固体への相転移が始まる。潜熱を解放して固体になったら、そこからまた冷却が始まる。ところが、固体になるためには、核となるものが必要だ。まあ通常は不純物がバリバリに含まれているので、そう簡単に過冷却になるとは思えない(が、実際のところどの程度のものかは私はよく知らない)。wikipediaの解説に基づけば、高温の水のほうが過冷却状態になりにくく、一方低温から冷やし始めると過冷却になりやすいので、過冷却状態から相転移を起こして固体になるまでの時間が長く、その間に高温の水が氷になってしまう、ということのようだ。
上で書いたように、通常は不純物が大量に含まれているし、容器(製氷皿など)の表面もでこぼこなので、過冷却状態がそう長く続くとは(私の)直感的には思えないのだが、果たしてどうだろうか。
この間見つけて画面上だけでざっと眺めた論文があるのだが(ざっと眺めて、そのうち時間があるとき読もうと放置^^;;)、どうも同じ論文を apj さんが紹介 してくれているようだ。
apj さんの解説によると、どの温度から冷却を開始しようが0℃まで達する時間は事実上短く、過冷却になってから氷になるまでの時間のほうが長い、またいつ相転移が起こるかは確率的で、えらい長い時間かかるやつもいる、なので、低温から冷やし始めたほうが氷になるまで時間のかかるやつがいてもおかしくない、ということのようだ。
また大阪市大の吉野さんによる解説(PDF) でも、そのような解釈が述べられている(「という説明が提案されている」という表現で)。
上記の論文はおそらくコレ で、このFIG.1を見ると、確かに過冷却に達してからえらい長時間がたって、確率的に氷に転移しているように見える。まあ apj さんの解説を読んだ上で、その図を見て言っているだけなのですが。ちゃんと論文読まないかんな。
そうだとすると、氷になるまでの時間は、最初に入れる水の温度とは事実上無関係、ということになり、ムペンバ効果が観察されることの説明にはなっても、確率的な事象ということで、私としてはイマイチ面白くない。まあ説明できるほうがいいのではあるけれど。
ただまあ論文ちゃんと読まないとわからないけど、不純物ありきの状態でもそんなに過冷却が続くものなんだろうか?つまり、日常生活でも、そんなに過冷却が長時間起きているものなんだろうか?そこが解決しないと、個人的にはどうもスッキリしないのだなあ。
さて、ムペンバ効果があるとした場合の話であるが、「ガリレオ工房」の滝川洋二さんの解説に引きずられて、とりあえずマクロ系の決定論的な解釈をいままで試みてきた。ただ、もちろん別の解釈もありうるのである。その一つが、過冷却によるものだ。
これは wikipedia の解説 にも簡単に触れられている。水は通常は0℃まで冷やされたら、そこで水は一旦温度低下が止まり、液体から固体への相転移が始まる。潜熱を解放して固体になったら、そこからまた冷却が始まる。ところが、固体になるためには、核となるものが必要だ。まあ通常は不純物がバリバリに含まれているので、そう簡単に過冷却になるとは思えない(が、実際のところどの程度のものかは私はよく知らない)。wikipediaの解説に基づけば、高温の水のほうが過冷却状態になりにくく、一方低温から冷やし始めると過冷却になりやすいので、過冷却状態から相転移を起こして固体になるまでの時間が長く、その間に高温の水が氷になってしまう、ということのようだ。
上で書いたように、通常は不純物が大量に含まれているし、容器(製氷皿など)の表面もでこぼこなので、過冷却状態がそう長く続くとは(私の)直感的には思えないのだが、果たしてどうだろうか。
この間見つけて画面上だけでざっと眺めた論文があるのだが(ざっと眺めて、そのうち時間があるとき読もうと放置^^;;)、どうも同じ論文を apj さんが紹介 してくれているようだ。
apj さんの解説によると、どの温度から冷却を開始しようが0℃まで達する時間は事実上短く、過冷却になってから氷になるまでの時間のほうが長い、またいつ相転移が起こるかは確率的で、えらい長い時間かかるやつもいる、なので、低温から冷やし始めたほうが氷になるまで時間のかかるやつがいてもおかしくない、ということのようだ。
また大阪市大の吉野さんによる解説(PDF) でも、そのような解釈が述べられている(「という説明が提案されている」という表現で)。
上記の論文はおそらくコレ で、このFIG.1を見ると、確かに過冷却に達してからえらい長時間がたって、確率的に氷に転移しているように見える。まあ apj さんの解説を読んだ上で、その図を見て言っているだけなのですが。ちゃんと論文読まないかんな。
そうだとすると、氷になるまでの時間は、最初に入れる水の温度とは事実上無関係、ということになり、ムペンバ効果が観察されることの説明にはなっても、確率的な事象ということで、私としてはイマイチ面白くない。まあ説明できるほうがいいのではあるけれど。
ただまあ論文ちゃんと読まないとわからないけど、不純物ありきの状態でもそんなに過冷却が続くものなんだろうか?つまり、日常生活でも、そんなに過冷却が長時間起きているものなんだろうか?そこが解決しないと、個人的にはどうもスッキリしないのだなあ。