「ウルトラ・スペシャル・マイティ・ストロング・スーパーよろい」とホメオパシー
…ホメオパシーが効かないということは、『水からの伝言』が反証実験をやるまでもなく自明のことと同じレベルで自明のこと(なんせ効能をもたらす分子が一つも入っていないのだから)である、ということは、もっと強調されていいのでは、というようなエントリを書こうと思っていたら、kikulogに出てしまったので、悔しいのでさっき思いついたことを垂れ流す。(^^)
タイトルの「ウルトラ・スペシャル・マイティ・ストロング・スーパーよろい」とは、もちろん(?)ドラえもんに出てくるものですが(「ウルトラよろい」)、知ってる人はご存知のように、これドラえもんがのび太に対してジョークとして言ったもので、実際には存在しない道具。ドラえもんがのび太に「ことわっておくけど、これはばかには見えない」「それに、ばかな人だとこれを着ても役にたたないんだ。」「おい、まさか……。きみはこのよろいが見えないほどのばかじゃないだろうな。」のび太「み、見えるとも。」という会話ののちに、のび太は勇んでジャイアンをぶんなぐりに出かけてしまって、ドラえもんが「まさか本気にするとは思わなかった。」「『はだかの王さま』の話を知らないのか。」と慌てて追いかける。
まあ話自体は読んでいただくとして(『F全集』のドラの9巻所収、8月配本^^)、これってある意味ホメオパシーに似てるよねえ、と。ホメオパシーの効果がプラセボ効果でしかないことを知りつつ、プラセボでもいいじゃん、という場合のほうがもっと近いかな。
素直に見れば、効能をもたらす分子が一つもない、つまり「裸」の状態であって、そんなものは効くわけがないのに、裸であることを認めたくないもんだから、水の記憶がどうとか「荒唐無稽」なことを言い出して。なぜ効かないかのメカニズムまでわかっている、実に稀有な例ですよね。
いやまあただ思いついただけの話なんですが。
***
ところで、「特異的効果」って specific effect の訳だと思うのですが、「特異的」という訳語は定着したものなんでしょうか?門外漢としては日本語的にかなり違和感を感じていて、「固有効果」とか「特有の効果」とかの方がいいんじゃないか、と素人としては思うのだけど…。「~の効果は~に特異的である」というような使われ方ならしっくりくるのですが。
藤子・F・不二雄大全集 ドラえもん 9/藤子・F・不二雄

¥1,680
Amazon.co.jp
タイトルの「ウルトラ・スペシャル・マイティ・ストロング・スーパーよろい」とは、もちろん(?)ドラえもんに出てくるものですが(「ウルトラよろい」)、知ってる人はご存知のように、これドラえもんがのび太に対してジョークとして言ったもので、実際には存在しない道具。ドラえもんがのび太に「ことわっておくけど、これはばかには見えない」「それに、ばかな人だとこれを着ても役にたたないんだ。」「おい、まさか……。きみはこのよろいが見えないほどのばかじゃないだろうな。」のび太「み、見えるとも。」という会話ののちに、のび太は勇んでジャイアンをぶんなぐりに出かけてしまって、ドラえもんが「まさか本気にするとは思わなかった。」「『はだかの王さま』の話を知らないのか。」と慌てて追いかける。
まあ話自体は読んでいただくとして(『F全集』のドラの9巻所収、8月配本^^)、これってある意味ホメオパシーに似てるよねえ、と。ホメオパシーの効果がプラセボ効果でしかないことを知りつつ、プラセボでもいいじゃん、という場合のほうがもっと近いかな。
素直に見れば、効能をもたらす分子が一つもない、つまり「裸」の状態であって、そんなものは効くわけがないのに、裸であることを認めたくないもんだから、水の記憶がどうとか「荒唐無稽」なことを言い出して。なぜ効かないかのメカニズムまでわかっている、実に稀有な例ですよね。
いやまあただ思いついただけの話なんですが。
***
ところで、「特異的効果」って specific effect の訳だと思うのですが、「特異的」という訳語は定着したものなんでしょうか?門外漢としては日本語的にかなり違和感を感じていて、「固有効果」とか「特有の効果」とかの方がいいんじゃないか、と素人としては思うのだけど…。「~の効果は~に特異的である」というような使われ方ならしっくりくるのですが。
藤子・F・不二雄大全集 ドラえもん 9/藤子・F・不二雄

¥1,680
Amazon.co.jp
「TOM★CAT ベスト」
はいそこ笑わない! (^^)
ちょっと前のこと。たまに行くレンタルCD屋が、1枚100円セール(売ってるわけじゃないからセールじゃないか)をやってたんですよ。で、目にとまって、つい借りてしまった。(^^;;
TOM☆CATというと、私にとっては学食のイメージが抜けきれない。夕食をとりにキャンパスの隅っこのしみったれた食堂に行くと、再放送の「北斗の拳」をやっていたのです。その主題歌の一つがTOM☆CATのものでした。
まあそれ以上でも以下でもない、という感じだったんですが、魔がさしたというかなんというか。(^^;;
しかししかし。私はやられちまいましたよ。2曲目の「LADY BLUE」。吹き出しそうになるのをこらえつつ、しかし聞いていくと思わず泣いてしまいそうになる自分がそこにはいたのです(大袈裟)。
サビのところはこんなん(歌詞はこちらへ)。
(*^.^*)
笑うな!! (^^;;
これがいいんだ。なんかこう疲れているときにこれを聴くと、「まあなんだ、その、明日もがんばるか」と、ちょっと思えるんですよ。山口美江のしば漬けみたいなもんか(時代的に)。^^;;
下のほうに、久松史奈バージョンを貼っておきます。これがデビューだとは知らんかった。「天使の休息」かと思っていたよ。
もちろん歌詞の背景まで踏み込めば、もっと考えなきゃいけないこともあるだろうとか思うこともあるんですが、それはそれとして。
人を信じられるって素敵だなあ、と思うのです。
このブログで主に取り上げているニセ科学の問題では、「善意」ってのと切っても切れない関係にあるのはご存知の通りで。「地獄への道は善意で敷きつめられている」なんてよく言いますが、この言葉が意味を持つのは、天国への階段が善意でできているからなんだよね、きっと。世の中は難しい。それだけに、少しでもニセ科学の害が減らせるといいと思って色々やってるわけですが。
* * *
ちょっと飛躍するけど、島本和彦の『無謀キャプテン』には
サンデル先生だったらどう言うかな。その選択こそが、正義の一つの形かもしれない、とかかな。
* * *
ベスト TOM☆CAT/TOM☆CAT
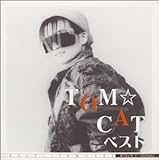
¥2,000
Amazon.co.jp
これからの「正義」の話をしよう――いまを生き延びるための哲学/マイケル・サンデル
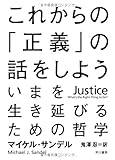
¥2,415
Amazon.co.jp
無謀キャプテン 1 (リュウコミックス)/島本 和彦
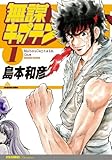
¥690
Amazon.co.jp
無謀キャプテン 2 (リュウコミックス)/島本 和彦

¥690
Amazon.co.jp
ちょっと前のこと。たまに行くレンタルCD屋が、1枚100円セール(売ってるわけじゃないからセールじゃないか)をやってたんですよ。で、目にとまって、つい借りてしまった。(^^;;
TOM☆CATというと、私にとっては学食のイメージが抜けきれない。夕食をとりにキャンパスの隅っこのしみったれた食堂に行くと、再放送の「北斗の拳」をやっていたのです。その主題歌の一つがTOM☆CATのものでした。
まあそれ以上でも以下でもない、という感じだったんですが、魔がさしたというかなんというか。(^^;;
しかししかし。私はやられちまいましたよ。2曲目の「LADY BLUE」。吹き出しそうになるのをこらえつつ、しかし聞いていくと思わず泣いてしまいそうになる自分がそこにはいたのです(大袈裟)。
サビのところはこんなん(歌詞はこちらへ)。
そこの Ladyに告ぐ
ただちに武装解除セヨ
無駄な抵抗はやめて恋に堕ちなさい
崩れて、ひと思いに
そこの Ladyに告ぐ
ただちに武装解除セヨ
錆びた鎧脱ぎ捨てて頬を染めなさい
恥ずかしいことじゃない
(*^.^*)
笑うな!! (^^;;
これがいいんだ。なんかこう疲れているときにこれを聴くと、「まあなんだ、その、明日もがんばるか」と、ちょっと思えるんですよ。山口美江のしば漬けみたいなもんか(時代的に)。^^;;
下のほうに、久松史奈バージョンを貼っておきます。これがデビューだとは知らんかった。「天使の休息」かと思っていたよ。
もちろん歌詞の背景まで踏み込めば、もっと考えなきゃいけないこともあるだろうとか思うこともあるんですが、それはそれとして。
人を信じられるって素敵だなあ、と思うのです。
このブログで主に取り上げているニセ科学の問題では、「善意」ってのと切っても切れない関係にあるのはご存知の通りで。「地獄への道は善意で敷きつめられている」なんてよく言いますが、この言葉が意味を持つのは、天国への階段が善意でできているからなんだよね、きっと。世の中は難しい。それだけに、少しでもニセ科学の害が減らせるといいと思って色々やってるわけですが。
* * *
ちょっと飛躍するけど、島本和彦の『無謀キャプテン』には
正義ではないなんて言葉があったりします。
いまは友が優先
サンデル先生だったらどう言うかな。その選択こそが、正義の一つの形かもしれない、とかかな。
* * *
ベスト TOM☆CAT/TOM☆CAT
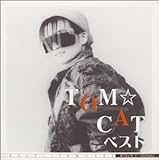
¥2,000
Amazon.co.jp
これからの「正義」の話をしよう――いまを生き延びるための哲学/マイケル・サンデル
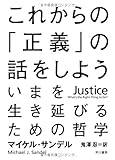
¥2,415
Amazon.co.jp
無謀キャプテン 1 (リュウコミックス)/島本 和彦
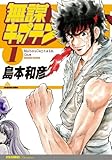
¥690
Amazon.co.jp
無謀キャプテン 2 (リュウコミックス)/島本 和彦

¥690
Amazon.co.jp
民主党代表選挙雑感
なんか色々賑やかですが。どっちがどうとかいう話ではなくて、眺めてて思ったことを書き散らしてみます。
【議員政党と組織政党】
理念というものをどう考えるか、ということに関わるのですが。自民党がヌエのような政党、とはよく言われることで。これは、要するに理念もなにもなくて(口先ではともかく)、個々の議員の利害で組織が成り立っているということでしょう。派閥というのも、なんとなくハト派タカ派というのはあれど、じゃあ理念でつながっているのかと言えばそうではないわけで、結局はカネでつながっている。
民主党も、その大半は自民党的なものを受け継いでできているわけで、そういう体質は十分に持っているわけです。ところが、自民党への対抗上、なんらかの理念を出さざるを得ない。政権交代の前は、「対立軸が必要」なんてあちこちで言われていたわけですが、この言葉に端的に表れているように、民主党ってのは「自民党がやってる政治のここが問題」だからなんとかしよう、ということでできたわけではなくて、自民党にいるより外に出た方がいいやと思った人の集合なわけです(もちろん、結党後に議員になった人の中には、自分なりの理念を持っている人もいることでしょう。でも、それはその人個人の理念であって、民主党の理念じゃない)。つまり、「自分が議員でいるために最適な行動はなにか」という問題の解として、民主党にいるのだ、と。
そういうところに、何らかの形での理念めいたものを持ち込もうとすれば、当然摩擦が起きる。自民党みたいに、理念のないことが理念だというような開き直りもできない。今回の代表選も、傍から見ていると、何を問題にして争っているのかまったく理解できない。もちろん党内の事情があるのだろうということは理解していますが、それは内部の話であって、民主党が一体どういう政治をやりたいのか、ということとは関係ないし、間接的には関係あるのだとしても、党外の人間がわざわざ忖度してやるようなものでもないでしょう。
根本的には、教科書的に言うなら「議員政党」という前近代的な党のあり方に問題があるのではないでしょうか。個々の議員の思惑の総和として組織の運動が決定される、という。自民党は「それでいいよ」という事実上の合意が内部的にはあったのだと思いますが、民主党はタテマエ上そうはいかないわけです。とすると、理念をもとに組織を作り、その理念を実現するための手段として議員を送り込むという近代的な組織政党に脱皮しなければ、いつまでたっても同じことの繰り返しになるのではないでしょうか。
国民が望む政治の姿(政党のありかたは措いといて)と自民党政治の乖離が民主党への政権交代への原動力になったのだとすれば、これは今の民主党における根本問題だとも思えるのです。
【選挙制度と政権交代】
さて、いまの衆議院の選挙制度はいわゆる小選挙区比例代表並立制、ってやつです。民主党内では比例部分を削れという声も大きいのですが、ここでは小選挙区の方について考えてみます。
中選挙区制を廃して小選挙区制を導入した理由の一つが、「政権が安定する」でした。安直に考えれば、ほんのちょっとの得票率の違いを大きく拡大して議席率の違いにしてくれるわけですから、「二大政党」とやらが確立すれば、ちょっとの民意の変化でもそれを拡大して政権交代につなげることができる…というわけです。
じゃあ実際起こっていることはなんでしょうか?
政党間の交代以前に、首相に注目すれば、もうここ何年も、毎年首相が変わるという事態に陥っているわけです。全然政権安定してないじゃん、と。当初の小選挙区制の予想とはまったく違うことが起きている。予想通りなのは、得票率と大きく乖離した(違いを拡大した)議席率の実現。
結局、選挙制度で政権の安定を云々する、という発想自体が間違っているのだと思います。制度という手段が結果を左右するということがまずおかしいという上に、当初のねらいだった政権の安定ということが実現できていないわけですから。
【国民の望む政治を実現するためには】
…なんて大上段な小見出しをつけてしまいましたが、なんでコロコロと首相が変わるかと言えば、その理路はともかくとして、現象論としては、国民の願いと政治のあり方の乖離が原因なのだろうと思います。国民が「こうなってほしい」と期待して、その期待を実現するかのように訴える人が表舞台に出てきて、で国民が失望し、政権が交代する。もちろん選挙があるから民意を気にしてこう不安定になるわけですが、要するに国民が望むことを本当にやろうとしない限りは、どんな制度にしようが政権は不安定にならざるを得ないでしょうね。
ただし、不安定にも色々あって、比例代表を本当に大幅に削ってしまえば、国民が望む声は国会内に反映されなくなって、個々の議員が生き残るためにその場限りの主張をして権力を獲得する、ということの繰り返しになるだろうと思います。その度に国民は失望し、やがて英雄待望論が(小泉賛美どころではなく)本気で出てきやしないか…と、とても心配してしまいます。
どういう結果になるのかわかりませんが、ま、あまり期待できる政治にはならないということだけははっきりしているのでしょうね。というか普天間の件はどうなったの?
【議員政党と組織政党】
理念というものをどう考えるか、ということに関わるのですが。自民党がヌエのような政党、とはよく言われることで。これは、要するに理念もなにもなくて(口先ではともかく)、個々の議員の利害で組織が成り立っているということでしょう。派閥というのも、なんとなくハト派タカ派というのはあれど、じゃあ理念でつながっているのかと言えばそうではないわけで、結局はカネでつながっている。
民主党も、その大半は自民党的なものを受け継いでできているわけで、そういう体質は十分に持っているわけです。ところが、自民党への対抗上、なんらかの理念を出さざるを得ない。政権交代の前は、「対立軸が必要」なんてあちこちで言われていたわけですが、この言葉に端的に表れているように、民主党ってのは「自民党がやってる政治のここが問題」だからなんとかしよう、ということでできたわけではなくて、自民党にいるより外に出た方がいいやと思った人の集合なわけです(もちろん、結党後に議員になった人の中には、自分なりの理念を持っている人もいることでしょう。でも、それはその人個人の理念であって、民主党の理念じゃない)。つまり、「自分が議員でいるために最適な行動はなにか」という問題の解として、民主党にいるのだ、と。
そういうところに、何らかの形での理念めいたものを持ち込もうとすれば、当然摩擦が起きる。自民党みたいに、理念のないことが理念だというような開き直りもできない。今回の代表選も、傍から見ていると、何を問題にして争っているのかまったく理解できない。もちろん党内の事情があるのだろうということは理解していますが、それは内部の話であって、民主党が一体どういう政治をやりたいのか、ということとは関係ないし、間接的には関係あるのだとしても、党外の人間がわざわざ忖度してやるようなものでもないでしょう。
根本的には、教科書的に言うなら「議員政党」という前近代的な党のあり方に問題があるのではないでしょうか。個々の議員の思惑の総和として組織の運動が決定される、という。自民党は「それでいいよ」という事実上の合意が内部的にはあったのだと思いますが、民主党はタテマエ上そうはいかないわけです。とすると、理念をもとに組織を作り、その理念を実現するための手段として議員を送り込むという近代的な組織政党に脱皮しなければ、いつまでたっても同じことの繰り返しになるのではないでしょうか。
国民が望む政治の姿(政党のありかたは措いといて)と自民党政治の乖離が民主党への政権交代への原動力になったのだとすれば、これは今の民主党における根本問題だとも思えるのです。
【選挙制度と政権交代】
さて、いまの衆議院の選挙制度はいわゆる小選挙区比例代表並立制、ってやつです。民主党内では比例部分を削れという声も大きいのですが、ここでは小選挙区の方について考えてみます。
中選挙区制を廃して小選挙区制を導入した理由の一つが、「政権が安定する」でした。安直に考えれば、ほんのちょっとの得票率の違いを大きく拡大して議席率の違いにしてくれるわけですから、「二大政党」とやらが確立すれば、ちょっとの民意の変化でもそれを拡大して政権交代につなげることができる…というわけです。
じゃあ実際起こっていることはなんでしょうか?
政党間の交代以前に、首相に注目すれば、もうここ何年も、毎年首相が変わるという事態に陥っているわけです。全然政権安定してないじゃん、と。当初の小選挙区制の予想とはまったく違うことが起きている。予想通りなのは、得票率と大きく乖離した(違いを拡大した)議席率の実現。
結局、選挙制度で政権の安定を云々する、という発想自体が間違っているのだと思います。制度という手段が結果を左右するということがまずおかしいという上に、当初のねらいだった政権の安定ということが実現できていないわけですから。
【国民の望む政治を実現するためには】
…なんて大上段な小見出しをつけてしまいましたが、なんでコロコロと首相が変わるかと言えば、その理路はともかくとして、現象論としては、国民の願いと政治のあり方の乖離が原因なのだろうと思います。国民が「こうなってほしい」と期待して、その期待を実現するかのように訴える人が表舞台に出てきて、で国民が失望し、政権が交代する。もちろん選挙があるから民意を気にしてこう不安定になるわけですが、要するに国民が望むことを本当にやろうとしない限りは、どんな制度にしようが政権は不安定にならざるを得ないでしょうね。
ただし、不安定にも色々あって、比例代表を本当に大幅に削ってしまえば、国民が望む声は国会内に反映されなくなって、個々の議員が生き残るためにその場限りの主張をして権力を獲得する、ということの繰り返しになるだろうと思います。その度に国民は失望し、やがて英雄待望論が(小泉賛美どころではなく)本気で出てきやしないか…と、とても心配してしまいます。
どういう結果になるのかわかりませんが、ま、あまり期待できる政治にはならないということだけははっきりしているのでしょうね。というか普天間の件はどうなったの?
ホメオパシーに信頼を寄せてきた皆さんへ
ホメオパシーを信頼していた皆さん、
この一ヶ月ほど、ホメオパシーを取り巻く状況に激しい動きがありました。山口のK2シロップの件で亡くなられた赤ちゃんのお母さんの提訴に関する報道に端を発し、各種メディアがホメオパシーを批判的に取り上げ、つい最近は「学者の国会」とも呼ばれることのある日本学術会議の会長がホメオパシーを全面否定する談話を発表し、多くの医療系団体が賛同を表明するに至りました。この状況に動揺され悩んでいる方も多いかと存じます。そのような方に、ぜひ聞いていただきたいことがあります。少し長くなりますが、お付き合いいただければ幸いです。
【ホメオパシーを始めた初心は?】
さて、あなたがホメオパシーを始めるきっかけは、なんだったでしょうか。「自然な感じ」がいいと思った方もいれば、重い病気や難病をなんとか治したかったからという方もいらっしゃることでしょう。人それぞれ、様々な動機があるのだろうと思います。しかし、おそらく共通しているのは、より良く生きたい、健康な生活を送りたい、ということではないでしょうか。
先日帰省した折、難病で苦しんでいる私の少し遠い親戚が、最近ホメオパシーを始めていたことを知りました(彼女とはもう長いこと会っていないのですが、親が時々見舞いに行ったり外出の手伝いをしているのです)。病院には通っていて、その上での使用だったようです。もちろん本心はわかりませんが、なんとか治したいという気持ちの表れのようです。
ちなみに私もレメディを服用したことがあります。随分前にイギリスに行った際、帰りの飛行機用の酔い止めがなく、薬局で買い求めたものです。酔いやすい体質なもので、飛行機で酔いたくなかったのですね。もっとも当時はホメオパシーということ自体を知らなかったのですが…。
【現代医療をどう見るか】
もう一つ、皆さんのうちの何割かの方々に共通するであろうことは、現代医療への不信ではないでしょうか。なかなか治らないのにやたらと多くの薬を処方される、慢性疾患で薬を飲み続けないといけない、副作用もあると言われ恐しい、世の中には薬害で苦しんでいる人もいる…確かに困ることが多いですね。なんとかならないものだろうか、と私も思います。
ただ、ちょっとだけ考えてみてほしいのです。本当に現代の医療よりもホメオパシーは「より良い」のか?と。
200年前、ハーネマンがホメオパシーを始めたころの「標準」医療は、それはひどいものでした。「瀉血(しゃけつ)」と言って、病気になるのは血が悪いからだ、悪い血を出させれば良くなる、ということで、わざと傷をつけて血を出したり、ヒルに大量の血を吸わせたりしていました。近代医療が成立する前の話です。いまから考えれば、患者の体力を奪い、かえって害となるものだったことは明らかですね。それに比べれば、ホメオパシーは随分と良い医療を提供したのでしょう。
ところが、医学は発展を続けます。瀉血に効果はない、むしろかえって悪いのだ、ということが検証されていきます。そして、瀉血は原則として標準医療から排除されました。古代ギリシャでも行われ、1000年を優に越える歴史を持っていた瀉血でさえも、効果がないとわかれば捨てられたのです(もちろんそこには瀉血を支持する医者たちとのたたかいもあれば、それまで瀉血を行ってきた医者自身の中での葛藤もあったでしょう)。しかし、考えてみれば体に悪いことが明らかな「瀉血」が、どうして1000年以上も続いてきたのでしょう?不思議ですね。
さて、その後、医学は科学を取り込み、「おまじない」を越える効果を検証する方法を編み出してきました。様々な特効薬も開発されてきました。有名なところでは結核ですね。結核で亡くなる方は、昔はとても多かったのが、いまではほとんど無くなりました。歴史的に重要なところでは、ハンセン病の特効薬「プロミン」があります。ハンセン病については時折ニュースなどで話題になりますからきっとご存知でしょう。根拠もなく危険な伝染病とされ患者は強制隔離されてきました。もともと感染力も非常に低いので隔離する必要もなかったのですが、特効薬のおかげで治癒する病気となりました。
最近、知り合いと久々に会って話をしていたのですが、彼は子どものころ病弱で、いつも寝ており、満足に学校にも通えませんでした。その彼が、「医学が発展してくれたおかげで今こうして生きていられるんだよなあ」と、しみじみと語ってたことが心に残っています。
日本人の平均寿命は、戦前に比べずっと長くなりました。もちろん戦争の影響は大きいのですが、戦後もずっと、ほぼ伸び続けています。これは、衛生や栄養の改善とともに、医療の発展が大きく貢献しているでしょう。つまり、現代医療は、私たちの寿命を伸ばし、健康に生きるベースを作ってくれていると言えるのではないでしょうか。
その上で、です。人間がやることですから、限界もありますし、すべてのお医者さんがいつでも最善をつくせるわけでもないでしょう。中には悪徳な医師や企業もあるでしょう。副作用が出る場合もあるかもしれません。大事なのは、いま同じ社会に生きている者として、どのように現代医療とつきあっていくか、ということではないでしょうか。いたずらに不安・不信を煽るだけでは、また昔のように多くの人が若いうちに亡くなってしまう世の中にタイムスリップしてしまいます。
【「自然」はいつでも素晴らしいだろうか】
さて、皆さんの中には、自然に近い感じがいい、自然な治癒力をサポートしてくれるというのがいい、という方もいらっしゃると思います。
病気になっても自然に治ってくれるなら、それに越したことはないですよね。そもそも、病気にならないでくれたら、いつでも元気でいられたら…とても素晴らしいことだと思います。
じゃあ、自然にまかせたら、そんな素晴らしいことになるのでしょうか?
残念ながら、いつもそうとは限りませんよね。手術が必要な病気もあります。自然に治る場合があるにせよ、薬を飲んだ方が治る率が明らかに上昇する場合もあります。完全に治らず、後遺症が残る場合だってあります。
自然は時に恐ろしいものです。私たち人間のことなんて、配慮なんかしてくれません。地震や台風、洪水…人間を脅かす自然現象は枚挙にいとまがありません。それだけではありません。自然の「毒」もいっぱいあります。毒キノコってありますよね。他にも毒はいっぱいあります。危険なカビとはいつも隣り合わせですし、ね。天然の「化学物質」はそこらじゅうにあります。というより、世の中に存在するものはすべて「化学物質」です。いいも悪いもなく、です。大事なことは、「自然」というキーワードで「良いもの」と即断するのではなく、自然か人工かを問わず、私たちにとって良いのか悪いのかを考えることではないでしょうか。
【ホメオパシーについて】
では、いよいよ、ホメオパシーそのものについて、少しお話したいと思います。
ホメオパシーに期待していた方には大変申し訳ないのですが、実際のところ、ホメオパシーには薬としての効き目はありません。学術会議会長の談話で述べられているとおりです。多くの臨床試験の結果、「おまじない」を越えるものではない、ということが既にわかってしまっています。
レメディをつくる際には希釈をしますが、一つのレメディには、元になる物質が一分子も含まれていないこともわかっています。これは、ハーネマンの時代にはわからなかったことですが、その後、物質は原子や分子から成り立っていることがわかり、その結果、レメディには元の物質が含まれないことがわかってしまいました。
ホメオパシー団体の中には、「水が記憶する」から効き目が保たれるのだ、と言っているところもあります。しかし、これも学術会議会長談話で言われているように、残念ながら「荒唐無稽」な話なのです。都合良く、元物質の記憶だけを保持するわけにはいきません。もっとも、水が記憶するということ自体、ないということがわかっていると言っていいでしょう。
では、なんで「効いた」と思ってしまうのでしょうか?
色々な理由があります。一つは、何もしなくても、元から治る病気だった可能性です。二つ目は、他に飲んだものが効いていた可能性です。三つめは、効くと思って飲んだため、心理的な効果が働き、治ったという可能性です。人間の精神力はたいしたもので、効くと思って飲めば、なんの役にも立たないのにまるで薬のように効いたと思えるときがあります。日本のことわざでも「鰯(いわし)の頭も信心から」なんて言ったりしますね。他にも理由は考えられるでしょう。
次の疑問は、じゃあ効かないのだったら、「鰯の頭」ほどの効き目しかないのだったら、どうして200年もホメオパシーは続いてきたの?ということかと思います。もっともな疑問だと思います。
しかし、思い出してください。どう考えても体に悪い「瀉血」は、1000年以上も続いてきたのです。昔のお医者さんは、決して患者に悪さをしようと思って瀉血を施したわけではないでしょう。昔のお医者さんは、瀉血によって患者が治ったと思っていたはずです。
このことが示しているのは、個人的な体験だけでは、薬や治療法に本当に効き目があるのかどうかはわからない、ということです。科学的な検証をしなければ、どう考えても体に悪いことでさえ、1000年も続くのです。ですから、200年続いた、ということは、残念ながら検証にはなり得ないわけです。
【私からのお願い】
ホメオパシーを信頼してきた皆さんに、私からのお願いです。
以上をふまえた上で、皆さんがホメオパシーを今後も続けられるかどうかは、皆さん一人一人が判断して決めることです。しかし、以下のことだけは、お願いです、どうか守ってください。
ホメオパシーとどう付き合っていくかは、皆さん一人一人が判断することです。しかし、ホメオパシーがおまじないを越えるものではないことは、好むと好まざるとにかかわらず、既にわかっていることです。効きめがあると思いたくても、こればかりはどうしょうもありません。まずはここを理解していただきたいと思います。
そして、現代医療はまだまだ限界があるとはいえ、多くの人々の命を救ってきたのもまた事実です。昔は助からなかった命も現代では助かる場合も多いです。手遅れにならないよう、標準とされる医療を避けることのないようにお願いします。
そして、おまじないを越えるものではないホメオパシーは、一見すると本当の薬のような効き目があるかのように思いがちです。なので、他人にすすめることはつつしむべきです。あなたにとってホメオパシーが大事なものであるならば、それは大切にされたらいいと思います。しかし、それは「お守り」と同じです。他人にすすめるようなものではないでしょう。
ホメオパシーに効き目がない、という現実を受け入れるのは、とてもつらいことだと思います。しかし、人間は、真実を見つめ、受け入れ、さらなる真実を求めることで発展してきました。瀉血は害悪である、ということを受け入れた昔のお医者さんも、きっとつらかったと思います。しかし、ここは一つ、あなたの「初心」を思い出してください。健康に、より良く生きたい。そのために必要なことは、いつまでもホメオパシーにすがることではないのではないか…と、私は思います。
【終わりに】
随分と長くなってしまいました。ここまで読んでいただき、ありがとうございます。一人でも多くの人が、楽しく幸せに、健康に生きることができることを願っての文章だということをご理解いただければと思います。
ところで、最初のほうでお話した、私が飲んだ酔い止めのレメディー。どうだったかというと…実は全然効いた気がしませんでした! その顛末は、以前こちらのエントリで書いたことがあります。ま、私個人の体験談なんで、これで万事を語るわけにはいかないんですけれども、ね。いちおう、私も体験者、ということで。
【参考】
「ホメオパシーについての会長談話」日本学術会議
『朝日』のホメオパシーを含む記事一覧(アピタル)
この一ヶ月ほど、ホメオパシーを取り巻く状況に激しい動きがありました。山口のK2シロップの件で亡くなられた赤ちゃんのお母さんの提訴に関する報道に端を発し、各種メディアがホメオパシーを批判的に取り上げ、つい最近は「学者の国会」とも呼ばれることのある日本学術会議の会長がホメオパシーを全面否定する談話を発表し、多くの医療系団体が賛同を表明するに至りました。この状況に動揺され悩んでいる方も多いかと存じます。そのような方に、ぜひ聞いていただきたいことがあります。少し長くなりますが、お付き合いいただければ幸いです。
【ホメオパシーを始めた初心は?】
さて、あなたがホメオパシーを始めるきっかけは、なんだったでしょうか。「自然な感じ」がいいと思った方もいれば、重い病気や難病をなんとか治したかったからという方もいらっしゃることでしょう。人それぞれ、様々な動機があるのだろうと思います。しかし、おそらく共通しているのは、より良く生きたい、健康な生活を送りたい、ということではないでしょうか。
先日帰省した折、難病で苦しんでいる私の少し遠い親戚が、最近ホメオパシーを始めていたことを知りました(彼女とはもう長いこと会っていないのですが、親が時々見舞いに行ったり外出の手伝いをしているのです)。病院には通っていて、その上での使用だったようです。もちろん本心はわかりませんが、なんとか治したいという気持ちの表れのようです。
ちなみに私もレメディを服用したことがあります。随分前にイギリスに行った際、帰りの飛行機用の酔い止めがなく、薬局で買い求めたものです。酔いやすい体質なもので、飛行機で酔いたくなかったのですね。もっとも当時はホメオパシーということ自体を知らなかったのですが…。
【現代医療をどう見るか】
もう一つ、皆さんのうちの何割かの方々に共通するであろうことは、現代医療への不信ではないでしょうか。なかなか治らないのにやたらと多くの薬を処方される、慢性疾患で薬を飲み続けないといけない、副作用もあると言われ恐しい、世の中には薬害で苦しんでいる人もいる…確かに困ることが多いですね。なんとかならないものだろうか、と私も思います。
ただ、ちょっとだけ考えてみてほしいのです。本当に現代の医療よりもホメオパシーは「より良い」のか?と。
200年前、ハーネマンがホメオパシーを始めたころの「標準」医療は、それはひどいものでした。「瀉血(しゃけつ)」と言って、病気になるのは血が悪いからだ、悪い血を出させれば良くなる、ということで、わざと傷をつけて血を出したり、ヒルに大量の血を吸わせたりしていました。近代医療が成立する前の話です。いまから考えれば、患者の体力を奪い、かえって害となるものだったことは明らかですね。それに比べれば、ホメオパシーは随分と良い医療を提供したのでしょう。
ところが、医学は発展を続けます。瀉血に効果はない、むしろかえって悪いのだ、ということが検証されていきます。そして、瀉血は原則として標準医療から排除されました。古代ギリシャでも行われ、1000年を優に越える歴史を持っていた瀉血でさえも、効果がないとわかれば捨てられたのです(もちろんそこには瀉血を支持する医者たちとのたたかいもあれば、それまで瀉血を行ってきた医者自身の中での葛藤もあったでしょう)。しかし、考えてみれば体に悪いことが明らかな「瀉血」が、どうして1000年以上も続いてきたのでしょう?不思議ですね。
さて、その後、医学は科学を取り込み、「おまじない」を越える効果を検証する方法を編み出してきました。様々な特効薬も開発されてきました。有名なところでは結核ですね。結核で亡くなる方は、昔はとても多かったのが、いまではほとんど無くなりました。歴史的に重要なところでは、ハンセン病の特効薬「プロミン」があります。ハンセン病については時折ニュースなどで話題になりますからきっとご存知でしょう。根拠もなく危険な伝染病とされ患者は強制隔離されてきました。もともと感染力も非常に低いので隔離する必要もなかったのですが、特効薬のおかげで治癒する病気となりました。
最近、知り合いと久々に会って話をしていたのですが、彼は子どものころ病弱で、いつも寝ており、満足に学校にも通えませんでした。その彼が、「医学が発展してくれたおかげで今こうして生きていられるんだよなあ」と、しみじみと語ってたことが心に残っています。
日本人の平均寿命は、戦前に比べずっと長くなりました。もちろん戦争の影響は大きいのですが、戦後もずっと、ほぼ伸び続けています。これは、衛生や栄養の改善とともに、医療の発展が大きく貢献しているでしょう。つまり、現代医療は、私たちの寿命を伸ばし、健康に生きるベースを作ってくれていると言えるのではないでしょうか。
その上で、です。人間がやることですから、限界もありますし、すべてのお医者さんがいつでも最善をつくせるわけでもないでしょう。中には悪徳な医師や企業もあるでしょう。副作用が出る場合もあるかもしれません。大事なのは、いま同じ社会に生きている者として、どのように現代医療とつきあっていくか、ということではないでしょうか。いたずらに不安・不信を煽るだけでは、また昔のように多くの人が若いうちに亡くなってしまう世の中にタイムスリップしてしまいます。
【「自然」はいつでも素晴らしいだろうか】
さて、皆さんの中には、自然に近い感じがいい、自然な治癒力をサポートしてくれるというのがいい、という方もいらっしゃると思います。
病気になっても自然に治ってくれるなら、それに越したことはないですよね。そもそも、病気にならないでくれたら、いつでも元気でいられたら…とても素晴らしいことだと思います。
じゃあ、自然にまかせたら、そんな素晴らしいことになるのでしょうか?
残念ながら、いつもそうとは限りませんよね。手術が必要な病気もあります。自然に治る場合があるにせよ、薬を飲んだ方が治る率が明らかに上昇する場合もあります。完全に治らず、後遺症が残る場合だってあります。
自然は時に恐ろしいものです。私たち人間のことなんて、配慮なんかしてくれません。地震や台風、洪水…人間を脅かす自然現象は枚挙にいとまがありません。それだけではありません。自然の「毒」もいっぱいあります。毒キノコってありますよね。他にも毒はいっぱいあります。危険なカビとはいつも隣り合わせですし、ね。天然の「化学物質」はそこらじゅうにあります。というより、世の中に存在するものはすべて「化学物質」です。いいも悪いもなく、です。大事なことは、「自然」というキーワードで「良いもの」と即断するのではなく、自然か人工かを問わず、私たちにとって良いのか悪いのかを考えることではないでしょうか。
【ホメオパシーについて】
では、いよいよ、ホメオパシーそのものについて、少しお話したいと思います。
ホメオパシーに期待していた方には大変申し訳ないのですが、実際のところ、ホメオパシーには薬としての効き目はありません。学術会議会長の談話で述べられているとおりです。多くの臨床試験の結果、「おまじない」を越えるものではない、ということが既にわかってしまっています。
レメディをつくる際には希釈をしますが、一つのレメディには、元になる物質が一分子も含まれていないこともわかっています。これは、ハーネマンの時代にはわからなかったことですが、その後、物質は原子や分子から成り立っていることがわかり、その結果、レメディには元の物質が含まれないことがわかってしまいました。
ホメオパシー団体の中には、「水が記憶する」から効き目が保たれるのだ、と言っているところもあります。しかし、これも学術会議会長談話で言われているように、残念ながら「荒唐無稽」な話なのです。都合良く、元物質の記憶だけを保持するわけにはいきません。もっとも、水が記憶するということ自体、ないということがわかっていると言っていいでしょう。
では、なんで「効いた」と思ってしまうのでしょうか?
色々な理由があります。一つは、何もしなくても、元から治る病気だった可能性です。二つ目は、他に飲んだものが効いていた可能性です。三つめは、効くと思って飲んだため、心理的な効果が働き、治ったという可能性です。人間の精神力はたいしたもので、効くと思って飲めば、なんの役にも立たないのにまるで薬のように効いたと思えるときがあります。日本のことわざでも「鰯(いわし)の頭も信心から」なんて言ったりしますね。他にも理由は考えられるでしょう。
次の疑問は、じゃあ効かないのだったら、「鰯の頭」ほどの効き目しかないのだったら、どうして200年もホメオパシーは続いてきたの?ということかと思います。もっともな疑問だと思います。
しかし、思い出してください。どう考えても体に悪い「瀉血」は、1000年以上も続いてきたのです。昔のお医者さんは、決して患者に悪さをしようと思って瀉血を施したわけではないでしょう。昔のお医者さんは、瀉血によって患者が治ったと思っていたはずです。
このことが示しているのは、個人的な体験だけでは、薬や治療法に本当に効き目があるのかどうかはわからない、ということです。科学的な検証をしなければ、どう考えても体に悪いことでさえ、1000年も続くのです。ですから、200年続いた、ということは、残念ながら検証にはなり得ないわけです。
【私からのお願い】
ホメオパシーを信頼してきた皆さんに、私からのお願いです。
以上をふまえた上で、皆さんがホメオパシーを今後も続けられるかどうかは、皆さん一人一人が判断して決めることです。しかし、以下のことだけは、お願いです、どうか守ってください。
- ホメオパシーはおまじないを越えるものではないこと(つまり、薬としての効き目はないこと)を理解すること。
- 通常の医療や薬、予防接種を避けないこと。
- ホメオパシーを、他人にすすめないこと。
ホメオパシーとどう付き合っていくかは、皆さん一人一人が判断することです。しかし、ホメオパシーがおまじないを越えるものではないことは、好むと好まざるとにかかわらず、既にわかっていることです。効きめがあると思いたくても、こればかりはどうしょうもありません。まずはここを理解していただきたいと思います。
そして、現代医療はまだまだ限界があるとはいえ、多くの人々の命を救ってきたのもまた事実です。昔は助からなかった命も現代では助かる場合も多いです。手遅れにならないよう、標準とされる医療を避けることのないようにお願いします。
そして、おまじないを越えるものではないホメオパシーは、一見すると本当の薬のような効き目があるかのように思いがちです。なので、他人にすすめることはつつしむべきです。あなたにとってホメオパシーが大事なものであるならば、それは大切にされたらいいと思います。しかし、それは「お守り」と同じです。他人にすすめるようなものではないでしょう。
ホメオパシーに効き目がない、という現実を受け入れるのは、とてもつらいことだと思います。しかし、人間は、真実を見つめ、受け入れ、さらなる真実を求めることで発展してきました。瀉血は害悪である、ということを受け入れた昔のお医者さんも、きっとつらかったと思います。しかし、ここは一つ、あなたの「初心」を思い出してください。健康に、より良く生きたい。そのために必要なことは、いつまでもホメオパシーにすがることではないのではないか…と、私は思います。
【終わりに】
随分と長くなってしまいました。ここまで読んでいただき、ありがとうございます。一人でも多くの人が、楽しく幸せに、健康に生きることができることを願っての文章だということをご理解いただければと思います。
ところで、最初のほうでお話した、私が飲んだ酔い止めのレメディー。どうだったかというと…実は全然効いた気がしませんでした! その顛末は、以前こちらのエントリで書いたことがあります。ま、私個人の体験談なんで、これで万事を語るわけにはいかないんですけれども、ね。いちおう、私も体験者、ということで。
【参考】
「ホメオパシーについての会長談話」日本学術会議
『朝日』のホメオパシーを含む記事一覧(アピタル)
歴史は動いた
盆前進行が盆明けまで続いて(自分でも何言ってるのかわからん^^;;)、やっと休暇を取れた間に、色々動きがありました。多くの犠牲の上にではありますが、影響力の大きい団体やメディアによりホメオパシーについて広範な人々に効果がないことが周知されました。特に、渦中の日本助産師会が、以下に引用したような声明を出し、ホメオパシーに否定的な態度を明確にしたことは、実に大きな一歩であったと思います。私は何もできませんでしたが、山口のお母さんの声を琴子の母さんが取り上げ、勇気を出して提訴され、多くの人々が声をあげ、メディアを動かし、学術会議や関係諸団体が足並みを揃えて声明を出し、ついに助産師会が自らの手で総括に踏み出したことは、国家権力に手を出させることなく人々の力によって世の中を一歩前に進めた経験として記憶されるのではないでしょうか(もっとも権力がホメオパシーを擁護しかけているという皮肉な状況でもあるわけですが)。この一連の動きは感動ですらあります。
以下にその助産師会の声明を引用します。
無論、これは第一歩にすぎません。しかし大きな一歩だと思います。助産師会の内部でも、きっと尽力され苦労された方が大勢いたのではないかと思います。
さて、今回の件では、改めてマスメディアの威力を思い知った方が多かったのではないかと思います。ネットの力なんて小さいものなんですよね、世の中を動かすという点では(もちろん、メディアを動かす貴重な情報源であり、また問題意識を共有する人々がその土台を強化し連帯するための重要なツールではあるわけですが)。マスメディアはやはり必要なものであり、ネットがあればいいというものではないことを再確認できたと思います。それだけに、私たちはマスメディアの動向を注視し、良い記事は賛意を表し、問題のある記事には批判を加えていくことが必要なのだと思います。「私たちのメディア」として、一緒に育っていくことが必要なのだろうと思います。今回、『朝日』の記者の貢献は多大なものがあったと思いますが、もちろん『読売』『毎日』をはじめ、おそらくは地方紙でも同様の記事が載ったところも多かったのではないかと思います。普通に生きる人々に寄り添った記事を、これからも期待したいと思います。
私も仕事が一段落したので(本当に一段落したのか?^^;;)、ぼちぼちブログを再開していきたいなと思っています。
以下にその助産師会の声明を引用します。
「ホメオパシー」への対応について
今般、日本学術会議金澤一郎会長は8月24日付けで「ホメオパシー」の治療効果は科学的に明確に否定されており医療従事者が治療に使用することは厳に慎むべき行為という談話を発表されました。日本助産師会はその内容に全面的に賛成します。
日本助産師会は、山口県で乳児がビタミンK欠乏性出血症により死亡した事例を受け、ホメオパシーのレメディはK2シロップに代わりうるものではないと警告し、全会員に対して、科学的な根拠に基づいた医療を実践するよう、8月10日に勧告を出しておりますが、一昨日出されました日本学術会議の談話を重く受けとめ、会員に対し、助産業務としてホメオパシーを使用しないよう徹底いたします。
助産師は女性に寄り添い、女性の思いを受容し、援助することが使命ですが、医療現場にあり、命を預かるものとしての責務もございます。私たち助産師の言葉や行動は、女性にとって大きな影響力を持っているということも自覚しております。科学的に否定されているものを助産師が使えば、本来受けるべき通常の医療から遠ざけてしまいかねません。しかるべきタイミングで医療を受けられるようにすることは、助産師の重要な役割です。
日本助産師会としては、現段階で治療効果が明確に否定されているホメオパシーを、医療に代わる方法として助産師が助産業務として使用したり、すすめたりすることのないよう、支部を通して会員に通知するとともに、機関誌及びホームページに掲載することで、周知徹底いたします。出産をサポートし、母子の健康を守ることができるよう、会をあげて、真摯にこの問題に取り組んでまいりたいと存じます。
また、現在、分娩を取り扱う開業助産師について、ホメオパシーの使用に関する実態調査をしており、集計がまとまり次第公表いたします。
なお、妊娠、出産、子育て期にある女性やそのご家族におかれましても、助産師が助産業務においてホメオパシーを使用しないことをご理解いただきと存じます。助産師は、皆様にとって不利益のないよう、正確な情報の提供に努めてまいります。
無論、これは第一歩にすぎません。しかし大きな一歩だと思います。助産師会の内部でも、きっと尽力され苦労された方が大勢いたのではないかと思います。
さて、今回の件では、改めてマスメディアの威力を思い知った方が多かったのではないかと思います。ネットの力なんて小さいものなんですよね、世の中を動かすという点では(もちろん、メディアを動かす貴重な情報源であり、また問題意識を共有する人々がその土台を強化し連帯するための重要なツールではあるわけですが)。マスメディアはやはり必要なものであり、ネットがあればいいというものではないことを再確認できたと思います。それだけに、私たちはマスメディアの動向を注視し、良い記事は賛意を表し、問題のある記事には批判を加えていくことが必要なのだと思います。「私たちのメディア」として、一緒に育っていくことが必要なのだろうと思います。今回、『朝日』の記者の貢献は多大なものがあったと思いますが、もちろん『読売』『毎日』をはじめ、おそらくは地方紙でも同様の記事が載ったところも多かったのではないかと思います。普通に生きる人々に寄り添った記事を、これからも期待したいと思います。
私も仕事が一段落したので(本当に一段落したのか?^^;;)、ぼちぼちブログを再開していきたいなと思っています。