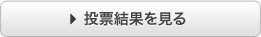民主主義社会の構成員であるということ(4)
 ブログネタ:投票権は何歳からがいいと思う?
参加中
ブログネタ:投票権は何歳からがいいと思う?
参加中私は18歳 派!
本文はここから
前エントリ 、前々エントリ 、さらにその前のエントリ からの続き。
18歳で大人、というのが世界のコンセンサスでしょう。日本もその仲間入りを早くして欲しいと思います。
18歳はまだまだコドモ、とか言う人がいますが、じゃあ何歳から大人だというのでしょう。40だって50だって、コドモみたいな人はいますよね。だから、「まだまだコドモ」というのは何の反論にもなっていないのです。むしろ、ちゃんと18で一人前になれるよう、社会的に教育をしっかりやらないといけないし、18歳未満の人々も、その覚悟でしっかし勉強して欲しいのです。
18ではコドモで、20になったらイキナリ大人、になんかなるわけありません。高校ぐらいから、世の中のことにちゃんとアンテナ張って、色々考えてほしいと思います。もう世の中の裏だって薄々見えてきている年頃でしょう。
「子どもの権利条約」だって、18歳未満が子ども、と言ってるわけです。18歳は、国際的には、もう子どもじゃないんですよ。
このシリーズの(1)でも書きましたが、選挙権てのは、人民が獲得してきた貴重な権利です。そして、有権者の範囲をひろげてきたのもまた歴史です。18歳になれば一人前の大人として扱いましょう、というのが国際的なコンセンサス。であれば、日本においても、18歳から選挙権を持つべきでしょう。
時間はほっといても進みますが、歴史は放置すれば後退します。18歳選挙権を実現するよう努力しましょう。
前エントリ 、前々エントリ 、さらにその前のエントリ からの続き。
18歳で大人、というのが世界のコンセンサスでしょう。日本もその仲間入りを早くして欲しいと思います。
18歳はまだまだコドモ、とか言う人がいますが、じゃあ何歳から大人だというのでしょう。40だって50だって、コドモみたいな人はいますよね。だから、「まだまだコドモ」というのは何の反論にもなっていないのです。むしろ、ちゃんと18で一人前になれるよう、社会的に教育をしっかりやらないといけないし、18歳未満の人々も、その覚悟でしっかし勉強して欲しいのです。
18ではコドモで、20になったらイキナリ大人、になんかなるわけありません。高校ぐらいから、世の中のことにちゃんとアンテナ張って、色々考えてほしいと思います。もう世の中の裏だって薄々見えてきている年頃でしょう。
「子どもの権利条約」だって、18歳未満が子ども、と言ってるわけです。18歳は、国際的には、もう子どもじゃないんですよ。
このシリーズの(1)でも書きましたが、選挙権てのは、人民が獲得してきた貴重な権利です。そして、有権者の範囲をひろげてきたのもまた歴史です。18歳になれば一人前の大人として扱いましょう、というのが国際的なコンセンサス。であれば、日本においても、18歳から選挙権を持つべきでしょう。
時間はほっといても進みますが、歴史は放置すれば後退します。18歳選挙権を実現するよう努力しましょう。
民主主義社会の構成員であるということ(3)
 ブログネタ:ネットの選挙、どう思う?
参加中
ブログネタ:ネットの選挙、どう思う?
参加中私は選挙活動に限ってOK 派!
本文はここから
前エントリ 、前々エントリ からの続きです。
ネット投票にはまだ賛成はしかねるのですが(投票の秘密がどれだけ確保されるのかが疑問)、選挙活動については全面解禁すべきでしょう。というか、日本の選挙はあまりにも制限が多すぎる。政策を伝える機会がなかなか作れないので、名前の連呼になっちゃうわけです(注:停止していない車上ではそもそも連呼しか許されていません)。もちろん、それは訴える中身がないので名前だけ連呼する、という場合が多いわけですが、逆に、そういう連中がいつまでものさばっているから、政策で勝負したい人々がなかなか議会で多数になれない。
個別訪問だってビラ配布だってなんだって完全自由にすればいいのです。先進国なら、たいてい自由じゃない?個別訪問って政策伝える重要な手段ですよね。直接政策を質問しながら訊ける貴重な機会だ。
そういうわけで、選挙活動については、ネットに限らず、全面的に解禁すべきです。
(追記)参考までに公職選挙法を一部掲載します。
前エントリ 、前々エントリ からの続きです。
ネット投票にはまだ賛成はしかねるのですが(投票の秘密がどれだけ確保されるのかが疑問)、選挙活動については全面解禁すべきでしょう。というか、日本の選挙はあまりにも制限が多すぎる。政策を伝える機会がなかなか作れないので、名前の連呼になっちゃうわけです(注:停止していない車上ではそもそも連呼しか許されていません)。もちろん、それは訴える中身がないので名前だけ連呼する、という場合が多いわけですが、逆に、そういう連中がいつまでものさばっているから、政策で勝負したい人々がなかなか議会で多数になれない。
個別訪問だってビラ配布だってなんだって完全自由にすればいいのです。先進国なら、たいてい自由じゃない?個別訪問って政策伝える重要な手段ですよね。直接政策を質問しながら訊ける貴重な機会だ。
そういうわけで、選挙活動については、ネットに限らず、全面的に解禁すべきです。
(追記)参考までに公職選挙法を一部掲載します。
第百四十一条の三
何人も、第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第百四十条の二第一項ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。
第百四十条の二
何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。
2
前項ただし書の規定により選挙運動のための連呼行為をする者は、学校(学校教育法第一条に規定する学校をいう。以下同じ。)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない。
民主主義社会の構成員であるということ(2)
 ブログネタ:選挙についてどう思う?
参加中
ブログネタ:選挙についてどう思う?
参加中私は絶対に行くべし! 派!
本文はここから
前のエントリ で書いたように、行きましょう。あなたが権利を放棄したら、それはあなただけの問題ではなくなる。人々の意見が政治に反映されにくくなる方向に加担する、ということを意味します。非正規労働者が異常に増えているのも、簡単に首を切られるのも、大学の学費が高いのも、この日本で餓死してしまう人がいるのも、すべて政治と密接に関係しています。
自分は自分の権利を行使するのだ、と表明するだけでも大きな意味があります。その意思を表明するのは投票することです。ぜひ、投票に行きましょう。
前のエントリ で書いたように、行きましょう。あなたが権利を放棄したら、それはあなただけの問題ではなくなる。人々の意見が政治に反映されにくくなる方向に加担する、ということを意味します。非正規労働者が異常に増えているのも、簡単に首を切られるのも、大学の学費が高いのも、この日本で餓死してしまう人がいるのも、すべて政治と密接に関係しています。
自分は自分の権利を行使するのだ、と表明するだけでも大きな意味があります。その意思を表明するのは投票することです。ぜひ、投票に行きましょう。
民主主義社会の構成員であるということ(1)
 ブログネタ:選挙、行く?
参加中
ブログネタ:選挙、行く?
参加中本文はここから
総選挙が近いので、アメーバブログでも色々やっているようです。大事な話だと思うので、ちょっと乗っかっておきます。
選挙権というのは、歴史的に見れば、人民が勝ち取ってきた貴重な権利です。日本だって、つい最近まで-いまの憲法が施行されるまで-有権者は限られた人々でした。女性は参加できなかった。世界中で、人民を政治に参加させよという圧力、たたかいがあって、ここまで来てるんです。
権利は行使せねば。放置していれば、いいように扱われます。入れたい候補がなければ白票だって立派な意思表明です。「勝馬」に投票するのが選挙じゃない。自分の意思を政治に反映させるのが選挙だ。当選した候補に白紙委任するんじゃない。たとえ自分が投票した人が当選しなくても、その票数は圧力になります。「下手をすれば次は落ちるぞ」と。
だから、行きましょう。私ももちろん投票します。
総選挙が近いので、アメーバブログでも色々やっているようです。大事な話だと思うので、ちょっと乗っかっておきます。
選挙権というのは、歴史的に見れば、人民が勝ち取ってきた貴重な権利です。日本だって、つい最近まで-いまの憲法が施行されるまで-有権者は限られた人々でした。女性は参加できなかった。世界中で、人民を政治に参加させよという圧力、たたかいがあって、ここまで来てるんです。
権利は行使せねば。放置していれば、いいように扱われます。入れたい候補がなければ白票だって立派な意思表明です。「勝馬」に投票するのが選挙じゃない。自分の意思を政治に反映させるのが選挙だ。当選した候補に白紙委任するんじゃない。たとえ自分が投票した人が当選しなくても、その票数は圧力になります。「下手をすれば次は落ちるぞ」と。
だから、行きましょう。私ももちろん投票します。
平和宣言
今日(というか昨日)は長崎原爆の日。あのアメリカでさえ期限をきった核兵器廃絶を口にするようになっているのに対し、麻生首相が放つ言葉の思考停止ぶりが際だっているのだが、このあたりのブクマコメント
を見ると、まだまだ「核の傘」や「核抑止」論の軛から逃れられない人々が多いのだろうな、と思ってしまう。核兵器を持つ/頼るということのリスクやデメリットを、一度真剣に考えて欲しいと思う。
さて、「長崎平和宣言 」はそのような古臭い思考からは既に脱却し、未来へ向かって進もうとしている。全文は見ていただくとして、印象深いところをいくつか引用したいと思う。
まずは冒頭。
核兵器が大量に存在するという現実を、ただ追認することをもって「現実的」と勘違いする人がいまだに多いが、ほうっておけば核兵器はどんどん拡散していき、ますます危険になるというのが「現実」である。時間がかかっても、核兵器を廃絶することの方が、人類の未来を開くという視点からははるかに現実的であろう。日本がその道を切り開く名誉ある地位を占めて欲しいものだと切に願う。
さて、「長崎平和宣言 」はそのような古臭い思考からは既に脱却し、未来へ向かって進もうとしている。全文は見ていただくとして、印象深いところをいくつか引用したいと思う。
まずは冒頭。
今、私たち人間の前にはふたつの道があります。ここには「核との共存」を明確に否定する発想がある。「核兵器のない世界」へ進まない限り、また広島・長崎の惨状が繰り返されるだろう、と。
ひとつは、「核兵器のない世界」への道であり、もうひとつは、64年前の広島と長崎の破壊をくりかえす滅亡の道です。
日本政府はプラハ演説を支持し、被爆国として、国際社会を導く役割を果たさなければなりません。また、憲法の不戦と平和の理念を国際社会に広げ、非核三原則をゆるぎない立場とするための法制化と、北朝鮮を組み込んだ「北東アジア非核兵器地帯」の実現の方策に着手すべきです。核兵器をなくそうという立場に立ってこそ、北朝鮮に対しても核開発を断念させる道義ある交渉が可能というものである。こちらが核で迫れば屈服するだろうなどというのは、あまりにも能天気な発想だ。
オバマ大統領、メドベージェフ・ロシア大統領、ブラウン・イギリス首相、サルコジ・フランス大統領、胡錦濤・中国国家主席、さらに、シン・インド首相、ザルダリ・パキスタン大統領、金正日・北朝鮮総書記、ネタニヤフ・イスラエル首相、アフマディネジャド・イラン大統領、そしてすべての世界の指導者に呼びかけます。犠牲者を単なる「数」と見るのではなく、一人ひとりの人生に心を寄せて見てほしいものだ。
被爆地・長崎へ来てください。
原爆資料館を訪れ、今も多くの遺骨が埋もれている被爆の跡地に立ってみてください。1945年8月9日11時2分の長崎。強力な放射線と、数千度もの熱線と、猛烈な爆風で破壊され、凄まじい炎に焼き尽くされた廃墟の静寂。7万4千人の死者の沈黙の叫び。7万5千人もの負傷者の呻き。犠牲者の無念の思いに、だれもが心ふるえるでしょう。
かろうじて生き残った被爆者にも、みなさんは出会うはずです。高齢となった今も、放射線の後障害に苦しみながら、自らの経験を語り伝えようとする彼らの声を聞くでしょう。被爆の経験は共有できなくても、核兵器廃絶を目指す意識は共有できると信じて活動する若い世代の熱意にも心うごかされることでしょう。
長崎市民は、オバマ大統領に、被爆地・長崎の訪問を求める署名活動に取り組んでいます。歴史をつくる主役は、私たちひとりひとりです。指導者や政府だけに任せておいてはいけません。オバマの演説は確かに画期的なものであった。しかし、歴史を作るのは一部の指導者だけではない。やはり、社会を構成する一人ひとりの声と行動が、歴史を前に進めるための条件を作り出すのだと思う。
原子爆弾が投下されて64年の歳月が流れました。被爆者は高齢化しています。被爆者救済の立場から、実態に即した援護を急ぐように、あらためて日本政府に要望します。政府はどのような思いでこの声を聞くのだろうか。ムダ金としか思っていないのではないかと危惧せざるを得ない。少なくとも麻生首相にその気持ちが少しでもわかるとは思えないし、わかろうという気すらないであろう。結局、我々が政府を追い詰めていくしかないのだと思う。
核兵器が大量に存在するという現実を、ただ追認することをもって「現実的」と勘違いする人がいまだに多いが、ほうっておけば核兵器はどんどん拡散していき、ますます危険になるというのが「現実」である。時間がかかっても、核兵器を廃絶することの方が、人類の未来を開くという視点からははるかに現実的であろう。日本がその道を切り開く名誉ある地位を占めて欲しいものだと切に願う。