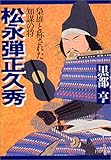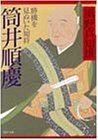最初の一歩。悲願!公慶上人の大勧進。大仏殿復興までのながい道 ~ 東大寺 大仏殿
「奈良の大仏炎上と再興」の公慶上人のエピソードについて追記です。
戦国時代。松永弾正久秀によって東大寺大仏殿が焼き払われます。
100年経った江戸時代まで大仏様は風雨に晒されていました。
その復興に公慶上人に尽力しました。
その公慶上人の最初の一歩のお話です。
・・・
公慶は東大寺・大仏殿建立の悲願を興し、諸国を勧進にまわります。
手始めに奈良から京都をぬけ、近江へとむかいます。
しかしなかなか帳はじめは、誰もが遠慮して寄進してくれません。
日暮れの頃、ひとりの物もらいの男と出会います。
なにを思ってか公慶は、男に大仏再興の寄付を話しかけます。
「そりゃ旦那、この乞食に寄付しろって無茶なはなしでっせ」
男に断られても、公慶は大仏様のご利益についてとうとうと説きます。
男がそそくさと立ち去ろうとしても、ついて歩いて話します。
とうとう男は、根負けします。
「ぼんさんには、負けましたわ。
そりゃ大事な一文じゃ。くれてやるわ」
呵々大笑し男は一文銭を公慶に投げてやりました。
ところが、勢いあまって一文銭は、田んぼへと落ちてしまいました。
「ああ、こりゃすまんこってで・・・」
「いえいえいえ。」
にっこりと公慶は微笑み、衣を脱いで田んぼに踏み込んでいきます。
脚がとられ、転んでも、泥まみれになっても一文銭を探し出します。
日がとっぷりと暮れたころ、ようやく見つけました。
水で洗い、男が去った後に合掌します。
矢立てを取り出し、勧進帳に
― 金壱文也 近江の乞食 某
と、筆太に認めました
大津の町にはいり、勧進をはじめると人々は、みな勧進帳のはじめに目をやり、
「ああ、乞食さえ寄進しとるなぁ。
こりゃ、わしらも寄進せんわけにはいかんわな。」
といって、こぞって寄進者が増えていきました。
公慶上人のはじめの一歩は乞食の寄進からでした。
そして後に、大仏復興へと実を結ぶのでした。
ランキングに参加しています。
ポチッとよろしくお願いします。
↓↓↓↓↓

>奈良の大仏炎上と再興
戦国時代。松永弾正久秀によって東大寺大仏殿が焼き払われます。
100年経った江戸時代まで大仏様は風雨に晒されていました。
その復興に公慶上人に尽力しました。
その公慶上人の最初の一歩のお話です。
・・・
公慶は東大寺・大仏殿建立の悲願を興し、諸国を勧進にまわります。
手始めに奈良から京都をぬけ、近江へとむかいます。
しかしなかなか帳はじめは、誰もが遠慮して寄進してくれません。
日暮れの頃、ひとりの物もらいの男と出会います。
なにを思ってか公慶は、男に大仏再興の寄付を話しかけます。
「そりゃ旦那、この乞食に寄付しろって無茶なはなしでっせ」
男に断られても、公慶は大仏様のご利益についてとうとうと説きます。
男がそそくさと立ち去ろうとしても、ついて歩いて話します。
とうとう男は、根負けします。
「ぼんさんには、負けましたわ。
そりゃ大事な一文じゃ。くれてやるわ」
呵々大笑し男は一文銭を公慶に投げてやりました。
ところが、勢いあまって一文銭は、田んぼへと落ちてしまいました。
「ああ、こりゃすまんこってで・・・」
「いえいえいえ。」
にっこりと公慶は微笑み、衣を脱いで田んぼに踏み込んでいきます。
脚がとられ、転んでも、泥まみれになっても一文銭を探し出します。
日がとっぷりと暮れたころ、ようやく見つけました。
水で洗い、男が去った後に合掌します。
矢立てを取り出し、勧進帳に
― 金壱文也 近江の乞食 某
と、筆太に認めました
大津の町にはいり、勧進をはじめると人々は、みな勧進帳のはじめに目をやり、
「ああ、乞食さえ寄進しとるなぁ。
こりゃ、わしらも寄進せんわけにはいかんわな。」
といって、こぞって寄進者が増えていきました。
公慶上人のはじめの一歩は乞食の寄進からでした。
そして後に、大仏復興へと実を結ぶのでした。
ポチッとよろしくお願いします。
↓↓↓↓↓
>奈良の大仏炎上と再興
- 河合敦先生と行く 歴史がよくわかる奈良の本 (単行本)/河合 敦
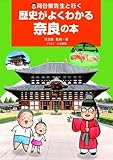
- ¥1,029
- Amazon.co.jp
奈良の大仏炎上と再興~戦国の鷹山氏と江戸時代の公慶上人。生駒・茶筅の里から東大寺 大仏殿の因縁
奈良では城が100以上も存在しています。
大半は”城跡”になっていますね。
それだけ、大和国には国主・豪族があふれかえっていたのですね。
さて、生駒市高山町は、かつて鷹山(たかやま)氏が治めていました。
そのお城は、今では高山城跡として残されています。
実は、私が住んでいるのが生駒市。
お隣の町なんですね。
生駒市高山町は茶筅の里として名を馳せております。
茶筅の全国シェア90%を占めています。
そもそも茶筅は室町時代に鷹山氏(たかやまし)が考案したものです。
鷹山氏が没落した後、家臣たちや、多くが武士は帰農します。
中には茶筅師に転じ、今にその伝統を伝えているということです。
鷹山氏は、清和源氏の流れを汲むとされる名家です。
応仁の乱から戦国時代にかけては、大和の一大勢力であった越智・古市氏に与していました。
さて”奈良の大仏”として親しまれる東大寺。
これを建立したのが平城京遷都し、平城京を治めていた聖武天皇です。
修学旅行でもみなさん、訪れたことがあるのではないでしょうか。
ところが戦国時代、松永久秀によって、奈良の大仏が、無残にも焼き払われてしまいました 。
・・・
永禄10年(1567)10月10日、深夜。
松永久秀と、三好三人衆と筒井順慶との戦いで、東大寺は炎上します。
大仏は猛火によって溶け崩れ、頭部は像の背後に落下しました。
松永久秀と組んでいたのがこの鷹山氏です。
天正5年(1577)10月10日。
松永久秀は、信貴山城で織田と筒井順慶の軍によって滅ぼされます。
鷹山氏もこのとき、筒井氏に攻められ滅亡します。
・・・
時は流れ・・・江戸時代。
鷹山氏を先祖とする「 公慶上人(こうけいしょうにん)」が現れます。
大仏殿の大仏は、江戸時代まで鎌倉の大仏のように雨ざらしの状態であったそうです。
それを再興したのが、この公慶上人でした。
・・・
東大寺が炎上して、およそ100年後のことです。
東大寺に修業にはいった13歳の公慶上人。
このとき強い雨が降っていました。
そこで公慶上人は、風雨にさらされた大仏さまを目の当たりにし涙したとあります。
そして、大仏殿再興を心に誓ったそうです。
貞享1年(1684)。
大願を心に秘めた公慶上人
幕府に大仏修復を願い出ましたが、幕府は協力を拒みます。
ただ一つ、東大寺が寄付をもとめ勧進するのは容認しただけでした。
公慶上人は、勧進を開始し、翌年には復興着手した。
1689年12月、松尾芭蕉が東大寺を訪れました。
このときの大仏の様子をこう俳句を詠みました。
「初雪やいつ大仏の柱立て」
いつになったら大仏殿は再興するのだろうと嘆いた歌でした。
芭蕉の心配をよそに、着々と大仏の修復が進められます。
元禄5年(1692)3月8日。
大仏開眼供養が盛大に営まれました。
いよいよ大仏殿の復興です。
公慶上人の熱い思いが将軍に伝わり、徳川綱吉公と桂昌院の支援を受けることがかないました。
宝永2年(1705)4月。
無事、大仏殿上棟式が執り行われ、ここに再興したのでした。
同年7月、公慶上人は疲労がたたり亡くなります。
焼き払ったのが松永久秀、そして加担した鷹山氏。
その業を、子孫の公慶上人が償うかのように再興する。
ちょっと因縁めいたものを感じますね。
ランキングに参加しています。
ポチッとよろしくお願いします。
↓↓↓↓↓

・・・
興味がありましたら、こちらもご覧ください。
ヽ(^o^)丿
★平城遷都と大仏造立のお話です。
「聖武天皇と光明皇后~世界初の夫婦物語」
1.聖武天皇と光明皇后
2.日本最初の福祉。光明皇后 法華寺
3.呪われた都・平城京。権力闘争の果てに
4.行基登場。世界初の黄金大仏を建立。
5.ガンダムを超える奇跡!大仏開眼!
★奈良の武将「筒井順慶」と観光のお話です。
「奈良・大和 王道の武将、筒井順慶」
その1
その2
その3
★もうひとりの奈良の武将、鷹山氏(たかやまし)についてのお話です。
生駒市高山町の観光と高山城跡について紹介しております。
1.茶せんの里、生駒市高山町。竹の名産地と茶道具の歴史
2.高山城跡を訪れました。
3.高山城跡と東大寺大仏殿との意外な関係
4.素朴な味のお菓子。 高山製菓 ~生駒市高山町
大半は”城跡”になっていますね。
それだけ、大和国には国主・豪族があふれかえっていたのですね。
さて、生駒市高山町は、かつて鷹山(たかやま)氏が治めていました。
そのお城は、今では高山城跡として残されています。
実は、私が住んでいるのが生駒市。
お隣の町なんですね。
生駒市高山町は茶筅の里として名を馳せております。
茶筅の全国シェア90%を占めています。
そもそも茶筅は室町時代に鷹山氏(たかやまし)が考案したものです。
鷹山氏が没落した後、家臣たちや、多くが武士は帰農します。
中には茶筅師に転じ、今にその伝統を伝えているということです。
鷹山氏は、清和源氏の流れを汲むとされる名家です。
応仁の乱から戦国時代にかけては、大和の一大勢力であった越智・古市氏に与していました。
さて”奈良の大仏”として親しまれる東大寺。
これを建立したのが平城京遷都し、平城京を治めていた聖武天皇です。
修学旅行でもみなさん、訪れたことがあるのではないでしょうか。
ところが戦国時代、松永久秀によって、奈良の大仏が、無残にも焼き払われてしまいました 。
・・・
永禄10年(1567)10月10日、深夜。
松永久秀と、三好三人衆と筒井順慶との戦いで、東大寺は炎上します。
大仏は猛火によって溶け崩れ、頭部は像の背後に落下しました。
松永久秀と組んでいたのがこの鷹山氏です。
天正5年(1577)10月10日。
松永久秀は、信貴山城で織田と筒井順慶の軍によって滅ぼされます。
鷹山氏もこのとき、筒井氏に攻められ滅亡します。
・・・
時は流れ・・・江戸時代。
鷹山氏を先祖とする「 公慶上人(こうけいしょうにん)」が現れます。
大仏殿の大仏は、江戸時代まで鎌倉の大仏のように雨ざらしの状態であったそうです。
それを再興したのが、この公慶上人でした。
・・・
東大寺が炎上して、およそ100年後のことです。
東大寺に修業にはいった13歳の公慶上人。
このとき強い雨が降っていました。
そこで公慶上人は、風雨にさらされた大仏さまを目の当たりにし涙したとあります。
そして、大仏殿再興を心に誓ったそうです。
貞享1年(1684)。
大願を心に秘めた公慶上人
幕府に大仏修復を願い出ましたが、幕府は協力を拒みます。
ただ一つ、東大寺が寄付をもとめ勧進するのは容認しただけでした。
公慶上人は、勧進を開始し、翌年には復興着手した。
1689年12月、松尾芭蕉が東大寺を訪れました。
このときの大仏の様子をこう俳句を詠みました。
「初雪やいつ大仏の柱立て」
いつになったら大仏殿は再興するのだろうと嘆いた歌でした。
芭蕉の心配をよそに、着々と大仏の修復が進められます。
元禄5年(1692)3月8日。
大仏開眼供養が盛大に営まれました。
いよいよ大仏殿の復興です。
公慶上人の熱い思いが将軍に伝わり、徳川綱吉公と桂昌院の支援を受けることがかないました。
宝永2年(1705)4月。
無事、大仏殿上棟式が執り行われ、ここに再興したのでした。
同年7月、公慶上人は疲労がたたり亡くなります。
焼き払ったのが松永久秀、そして加担した鷹山氏。
その業を、子孫の公慶上人が償うかのように再興する。
ちょっと因縁めいたものを感じますね。
- 大仏をめぐろう/坂原 弘康
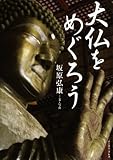
- ¥1,670
- Amazon.co.jp
ポチッとよろしくお願いします。
↓↓↓↓↓
・・・
興味がありましたら、こちらもご覧ください。
ヽ(^o^)丿
★平城遷都と大仏造立のお話です。
「聖武天皇と光明皇后~世界初の夫婦物語」
1.聖武天皇と光明皇后
2.日本最初の福祉。光明皇后 法華寺
3.呪われた都・平城京。権力闘争の果てに
4.行基登場。世界初の黄金大仏を建立。
5.ガンダムを超える奇跡!大仏開眼!
★奈良の武将「筒井順慶」と観光のお話です。
「奈良・大和 王道の武将、筒井順慶」
その1
その2
その3
★もうひとりの奈良の武将、鷹山氏(たかやまし)についてのお話です。
生駒市高山町の観光と高山城跡について紹介しております。
1.茶せんの里、生駒市高山町。竹の名産地と茶道具の歴史
2.高山城跡を訪れました。
3.高山城跡と東大寺大仏殿との意外な関係
4.素朴な味のお菓子。 高山製菓 ~生駒市高山町
戦国の梟雄・松永久秀の墓 ~ 達磨寺
戦国の梟雄といわれ、大和の武将・筒井順慶との死闘の果てに、大和信貴山城で倒されます。
松永久秀の首は、安土へ運ばれます。
遺体は北葛城郡王寺町の達磨寺に埋葬されました。
それが、こちら。
埋葬したのは、筒井順慶でした。
半生をかけた仇敵でしたが、武人として敬服する部分もあったのではないでしょうか。
小さなお墓です。
左から片岡新助春利(代二十七代)の墓。
中央が、片岡八郎公(第十七代)、
そして、右端が、松永久秀の墓です。
片岡春利は、片岡城(上牧町下牧)の城主でした。
永禄12年(1569)に、松永久秀が攻めてきたとき、片岡城で戦ったのでした。

ランキングに参加しています。
ポチッとよろしくお願いします。
↓↓↓↓↓

>だるまと聖徳太子の不思議な、ふしぎなおはなし。~臨済宗南禅寺 達磨寺
>戦国のメリークリスマス 松永久秀
~ 日本で最初にクリスマスの日を休暇にした人
>嗚呼、栄枯盛衰 足利義昭 と 興福寺
>「奈良・大和 王道の武将、筒井順慶 」
その1「宿敵襲来!」
その2「大仏炎上!」
その3「親友との決別!」
松永久秀の首は、安土へ運ばれます。
遺体は北葛城郡王寺町の達磨寺に埋葬されました。
それが、こちら。
埋葬したのは、筒井順慶でした。
半生をかけた仇敵でしたが、武人として敬服する部分もあったのではないでしょうか。
小さなお墓です。
左から片岡新助春利(代二十七代)の墓。
中央が、片岡八郎公(第十七代)、
そして、右端が、松永久秀の墓です。
片岡春利は、片岡城(上牧町下牧)の城主でした。
永禄12年(1569)に、松永久秀が攻めてきたとき、片岡城で戦ったのでした。

ポチッとよろしくお願いします。
↓↓↓↓↓
>だるまと聖徳太子の不思議な、ふしぎなおはなし。~臨済宗南禅寺 達磨寺
>戦国のメリークリスマス 松永久秀
~ 日本で最初にクリスマスの日を休暇にした人
>嗚呼、栄枯盛衰 足利義昭 と 興福寺
>「奈良・大和 王道の武将、筒井順慶 」
その1「宿敵襲来!」
その2「大仏炎上!」
その3「親友との決別!」