味酒 倭なす大物主の醸みし神酒 ~ 大物主神物語(5) 三輪山 大神神社
4.「タタリ神!?大田田根子命をさがせ!」
崇神天皇の時代に猛威をふるった疫病。
夢枕にたった大物主神のお告げから、天皇は大物主をはじめ神々にすがります。
大田田根子(意富多多泥古)を招き御諸山(みもろのやま:三輪山)の大物主神(意富美和之神(おおみわのおおかみ))を祀りました。
市磯長尾市(いちしのながおち)を招き倭大国魂神(やまとのおおくにたまのかみ)を祀りました。
また疫病の鬼が入ってこないように国の要所に鎮座する神々にも御祭しました。
大和の東入口の墨坂神(すみさかかみ)に、赤い楯と矛を奉納しました。
大和の西入口の大坂神(おおさかのかみ)に、黒い楯と矛を奉納しました。
大和の境界なす山々の神様、河の神様、すべての神々に御供え物を捧げ祀りました。
こうして神々の霊力によって疫病は終息し、国内は次第に平安になったのでした。
古代、人々は疫病や災害など人智のおよばぬことを、さまざまな霊の祟りと信じていました。
人の力ではどうしようもないときに、人は人を超越した力をもつ神や仏にすがろうとしたのですね。
― 現代。
様々な怪異とされていた現象が科学で解明されています。
空を飛び、何千里の海を、地を駆け、離れた人と意思を伝える機械。
まさに現代の人間は、神にも等しい力をもっています。
しかし社寺仏閣に訪れる人は後を絶ちません。
まだまだ神仏の力にすがることは多くあるのですね。
疫病が去り、平穏となり、そして国が富みます。
五穀豊穣を祝い、高橋邑の活日(いくひ)を大神神社の掌酒(さかびと:酒造りをする人)に任命し神酒をつくらせます。
その冬、活日はみごとな神酒を醸しました。
大神主神へ神酒を捧げ、天皇に献上するとき、こんな唄を詠みました。
此の神酒は 我が神酒ならず
倭なす 大物主の醸(か)みし神酒
幾久(いくひさ) 幾久
この神酒は 私が醸した神酒ではありません。
大和を御造りになった大物主神が醸された神酒です。
幾世までも久しく栄えませ 栄えませ
するとお供のものたちがこう詠みました。
味酒 三輪の殿の朝門にも出でて行かな 三輪の殿門を
味酒(うまさけ) 夜通し呑みあかし朝に大神神社の御殿の御門を出ていきたいものよ
これを聞いた天皇が返します。
味酒 三輪の殿の朝門にも押し開かね 三輪の殿門を
味酒(うまさけ) 夜通し呑みあかし朝に大神神社の御殿の御門を出ていきなさい
・・・
神様には、二つの顔をもっています。
和魂(にぎみたま)と荒魂(あらみたま)です。
荒魂は怒りの姿。
神霊の働きの強い面、不可思議な霊的作用をもって、疫病を蔓延させ、天災などを起こすと信じられていました。
また人智が及ばぬ難儀・難敵をうちはらいます。
和魂とは、神様の平素の穏やかな姿。
生きとし生けるものを守り、幸せな方向に導く心をもっています。
ランキングに参加しています。
ポチッとよろしくお願いします。
↓↓↓↓↓

 大物主神物語
大物主神物語
1:我は汝の幸魂奇魂なり。大国主神と大物主神。
2:大国主と武甕槌。国譲りの神話
3:天に等しき出雲大社 光と影 大物主神の登場
4:タタリ神!?大田田根子命をさがせ! 大物主神と崇神天皇
5:味酒 倭なす大物主の醸みし神酒
崇神天皇の時代に猛威をふるった疫病。
夢枕にたった大物主神のお告げから、天皇は大物主をはじめ神々にすがります。
大田田根子(意富多多泥古)を招き御諸山(みもろのやま:三輪山)の大物主神(意富美和之神(おおみわのおおかみ))を祀りました。
市磯長尾市(いちしのながおち)を招き倭大国魂神(やまとのおおくにたまのかみ)を祀りました。
また疫病の鬼が入ってこないように国の要所に鎮座する神々にも御祭しました。
大和の東入口の墨坂神(すみさかかみ)に、赤い楯と矛を奉納しました。
大和の西入口の大坂神(おおさかのかみ)に、黒い楯と矛を奉納しました。
大和の境界なす山々の神様、河の神様、すべての神々に御供え物を捧げ祀りました。
こうして神々の霊力によって疫病は終息し、国内は次第に平安になったのでした。
古代、人々は疫病や災害など人智のおよばぬことを、さまざまな霊の祟りと信じていました。
人の力ではどうしようもないときに、人は人を超越した力をもつ神や仏にすがろうとしたのですね。
― 現代。
様々な怪異とされていた現象が科学で解明されています。
空を飛び、何千里の海を、地を駆け、離れた人と意思を伝える機械。
まさに現代の人間は、神にも等しい力をもっています。
しかし社寺仏閣に訪れる人は後を絶ちません。
まだまだ神仏の力にすがることは多くあるのですね。
疫病が去り、平穏となり、そして国が富みます。
五穀豊穣を祝い、高橋邑の活日(いくひ)を大神神社の掌酒(さかびと:酒造りをする人)に任命し神酒をつくらせます。
その冬、活日はみごとな神酒を醸しました。
大神主神へ神酒を捧げ、天皇に献上するとき、こんな唄を詠みました。
此の神酒は 我が神酒ならず
倭なす 大物主の醸(か)みし神酒
幾久(いくひさ) 幾久
この神酒は 私が醸した神酒ではありません。
大和を御造りになった大物主神が醸された神酒です。
幾世までも久しく栄えませ 栄えませ
するとお供のものたちがこう詠みました。
味酒 三輪の殿の朝門にも出でて行かな 三輪の殿門を
味酒(うまさけ) 夜通し呑みあかし朝に大神神社の御殿の御門を出ていきたいものよ
これを聞いた天皇が返します。
味酒 三輪の殿の朝門にも押し開かね 三輪の殿門を
味酒(うまさけ) 夜通し呑みあかし朝に大神神社の御殿の御門を出ていきなさい
・・・
神様には、二つの顔をもっています。
和魂(にぎみたま)と荒魂(あらみたま)です。
荒魂は怒りの姿。
神霊の働きの強い面、不可思議な霊的作用をもって、疫病を蔓延させ、天災などを起こすと信じられていました。
また人智が及ばぬ難儀・難敵をうちはらいます。
和魂とは、神様の平素の穏やかな姿。
生きとし生けるものを守り、幸せな方向に導く心をもっています。
ポチッとよろしくお願いします。
↓↓↓↓↓
 大物主神物語
大物主神物語1:我は汝の幸魂奇魂なり。大国主神と大物主神。
2:大国主と武甕槌。国譲りの神話
3:天に等しき出雲大社 光と影 大物主神の登場
4:タタリ神!?大田田根子命をさがせ! 大物主神と崇神天皇
5:味酒 倭なす大物主の醸みし神酒
- 三輪山と卑弥呼・神武天皇/笠井 敏光

- ¥2,079
- Amazon.co.jp
- 三輪山の古代史―大和王権発祥の地から古代日本の謎を解く/著者不明
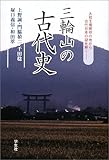
- ¥2,079
- Amazon.co.jp
タタリ神!?大田田根子命をさがせ! 大物主神と崇神天皇 ~ 大物主神物語(4) 三輪山 大神神社
御諸山(みもろやま:三輪山)に鎮座された大物主神。
山からながれる狭井川のほとりに、神武天皇と大神主の御子・伊須気余理比売(いすけよりひめ)の皇居があったと伝えられています。

「神武天皇聖跡狭井河之上顕彰碑」
それは伊須気余理比売が巫女として大物主神を祀り、奉仕するためではないかと思われます。
しかし―
時は流れ、天皇をはじめ人々の大物主神や神々への畏敬の念がうすれてきます。
崇神天皇7年(紀元前91)。
崇神天皇(すじんてんのう)の時代。
国中に疫病が猛威をふるい、大勢の人が亡くなりました。
手の施しようもなく天皇は嘆くばかりでした。
ある夜、高貴な方が夢の中に顕れました。
大物主神です。
「我が子を探し出すのだ。
さすれば疫病はおさまるだろう」
そこではたと天皇は気づきます。
大物主神をはじめ、八十万(やそろず)の神々への神祭りが疎かになっていたことを思い至りました。
この凶事は、もはや大物主神の怒りではないだろうかと、すっかり畏れ入ってしまったのです。
さっそく大物主の子なるものを探し出し連れてくるように、国中にふれをだしました。
・・・
果して宮中に一人の男が連れてこられました。
その男に問います。
「お前は、誰か。」
男は河内の美努村(大阪府八尾市近辺)の大田田根子(おおたたねこ)と名乗ります。
そして、
「父は大物主神と申します。
母は活玉依媛(いくたまよりびめ)と申します。
陶津耳の娘です。」といいました。
これこそが求めていた者だと天皇は大いに喜びました。
大田田根子を大物主神を祀る神主と迎え、御諸山の大物主神を御祭しました。
現在の三輪山を御神体とした大神神社の原型が、ここに成り立ったのでした。
この甲斐あって、やがて疫病が終息したのでした。
世の中に平穏が戻ります。
さらに翌年、五穀が豊かに稔ります。
人々の生活がやすらかになりました。
その後、大田田根子命を、大神神社の若宮・大直禰子神社で祀ったのでした。
・・・
一説では、大田田根子は、河内の美努村(大阪府八尾市付近)と、茅渟県(ちぬのあがたの陶邑(大阪市堺市付近)で見つかったとあります。
また、この災厄は大物主自身がひきおこしたとも伝えられています。
それは未知なる疫病への死の恐怖を、大物主神のタタリのせいとしたのではないでしょうか。
朝廷の信仰をあつめ、また畏れられていた大物主神のひとつのお話でした。
ランキングに参加しています。
ポチッとよろしくお願いします。
↓↓↓↓↓

 大物主神物語
大物主神物語
1:我は汝の幸魂奇魂なり。大国主神と大物主神。
2:大国主と武甕槌。国譲りの神話
3:天に等しき出雲大社 光と影 大物主神の登場
4:タタリ神!?大田田根子命をさがせ! 大物主神と崇神天皇
5:味酒 倭なす大物主の醸みし神酒
 三輪山と大神神社の目次はこちら
三輪山と大神神社の目次はこちら
「大神神社 古事記の山「 三輪山 」【総集編】」
山からながれる狭井川のほとりに、神武天皇と大神主の御子・伊須気余理比売(いすけよりひめ)の皇居があったと伝えられています。

「神武天皇聖跡狭井河之上顕彰碑」
それは伊須気余理比売が巫女として大物主神を祀り、奉仕するためではないかと思われます。
しかし―
時は流れ、天皇をはじめ人々の大物主神や神々への畏敬の念がうすれてきます。
崇神天皇7年(紀元前91)。
崇神天皇(すじんてんのう)の時代。
国中に疫病が猛威をふるい、大勢の人が亡くなりました。
手の施しようもなく天皇は嘆くばかりでした。
ある夜、高貴な方が夢の中に顕れました。
大物主神です。
「我が子を探し出すのだ。
さすれば疫病はおさまるだろう」
そこではたと天皇は気づきます。
大物主神をはじめ、八十万(やそろず)の神々への神祭りが疎かになっていたことを思い至りました。
この凶事は、もはや大物主神の怒りではないだろうかと、すっかり畏れ入ってしまったのです。
さっそく大物主の子なるものを探し出し連れてくるように、国中にふれをだしました。
・・・
果して宮中に一人の男が連れてこられました。
その男に問います。
「お前は、誰か。」
男は河内の美努村(大阪府八尾市近辺)の大田田根子(おおたたねこ)と名乗ります。
そして、
「父は大物主神と申します。
母は活玉依媛(いくたまよりびめ)と申します。
陶津耳の娘です。」といいました。
これこそが求めていた者だと天皇は大いに喜びました。
大田田根子を大物主神を祀る神主と迎え、御諸山の大物主神を御祭しました。
現在の三輪山を御神体とした大神神社の原型が、ここに成り立ったのでした。
この甲斐あって、やがて疫病が終息したのでした。
世の中に平穏が戻ります。
さらに翌年、五穀が豊かに稔ります。
人々の生活がやすらかになりました。
その後、大田田根子命を、大神神社の若宮・大直禰子神社で祀ったのでした。
・・・
一説では、大田田根子は、河内の美努村(大阪府八尾市付近)と、茅渟県(ちぬのあがたの陶邑(大阪市堺市付近)で見つかったとあります。
また、この災厄は大物主自身がひきおこしたとも伝えられています。
それは未知なる疫病への死の恐怖を、大物主神のタタリのせいとしたのではないでしょうか。
朝廷の信仰をあつめ、また畏れられていた大物主神のひとつのお話でした。
ポチッとよろしくお願いします。
↓↓↓↓↓
 大物主神物語
大物主神物語1:我は汝の幸魂奇魂なり。大国主神と大物主神。
2:大国主と武甕槌。国譲りの神話
3:天に等しき出雲大社 光と影 大物主神の登場
4:タタリ神!?大田田根子命をさがせ! 大物主神と崇神天皇
5:味酒 倭なす大物主の醸みし神酒
 三輪山と大神神社の目次はこちら
三輪山と大神神社の目次はこちら「大神神社 古事記の山「 三輪山 」【総集編】」
- 大神神社/中山 和敬

- ¥2,310
- Amazon.co.jp
