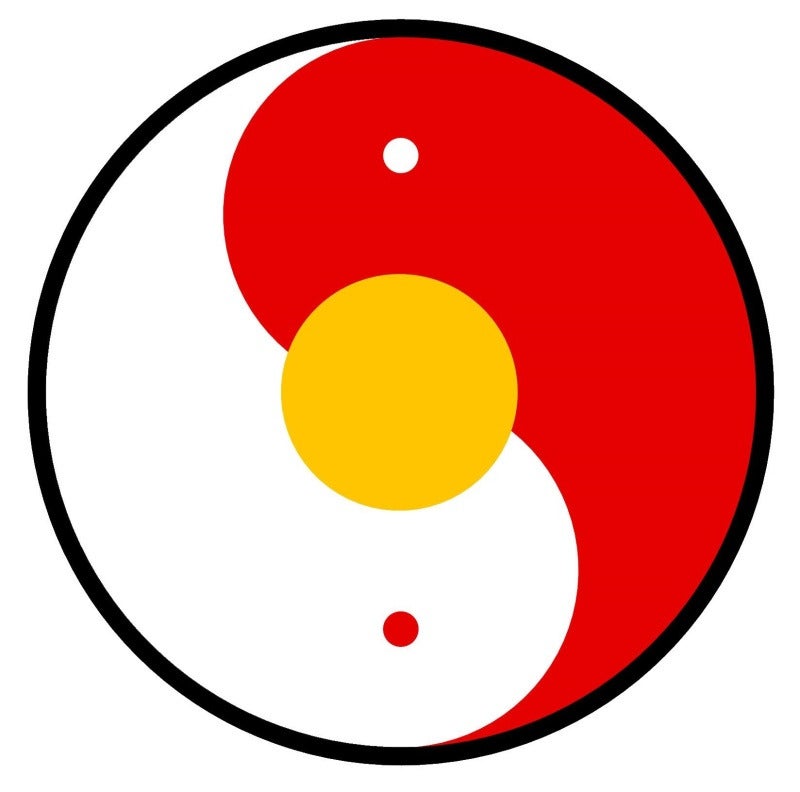“……真の神様への真剣な祈りの尊さを教えていただきましたのは昭和十七年のことでした。この年の八月に聖師さまは、第二次大本事件で検挙されて以来六年八ヶ月ぶりに亀岡にお帰りになられました。その頃私は母と一緒に亀岡に住んでいましたが、聖師さまが中矢田にお帰りになられまして三日目の夜のことでした。床に就いていた母が突然『聖師さまの足音がする』といって跳び起きたのです。私は『そんなアホーなことが』と思い、母が少しおかしくなったのではないかと心配したほどです。
ところが玄関の戸をたたいて入って来られましたのは、まさしく聖師さまでした。私たちはびっくりして早速にお部屋にお通りいただきました。この当時、聖師さまはどこにお出かけになられますにも、いちいち当局に届けなければならないというご状態でしたので、夜になって皆が寝しずまってから、破壊された天恩郷の状況をご覧になるために、中矢田農園から天恩郷へお出かけになり、その途中に私どもの家がありましたので、お帰りにご一服なさるためだったのでしょうか、それからのちもよくお立ち寄りくださいました。
聖師さまは開口一番、『ひどいことをしくさりよった、思うとったよりひどいことしくさりよった』と仰せになりまして、ひじょうにご憤慨のご様子でございました。それでもこのときすでに、聖師さまは大本再建のご構想をお練りになっていらっしゃったご様子で、その後も天恩郷におみ足をおはこびになる度に、私の家にお立ち寄りくださり、いろいろとお話をしていただきました。ある日母が不在で、家には姉と私の二人だけのところへ、聖師さまがお越しになられたことがございました。私はその日、大変にしょげていました。
というのは、その前日、タイピストとして軍属を志願しに京都に行きましたところ、ちょうど締め切ったところで、次回十月に志願せよとのことだったのです。私の家では誰一人軍隊に行く者もなく、そのことが娘心にはずかしく、男が奉公しないのならせめて私が……と思いまして、志願しに行ったようなわけだったのです。その思いが叶わず、私は残念でたまりませんでした。
今思いますと、もったいないことですが、私はついそのことを聖師さまにお話ししてしまったのです。聖師さまは、はじめ驚いたようなお顔をされておられましたが、「残念でございました。おしゅうございました」と興奮して語る私に向かい、次のように言われたのです。
『なにを言うとんじゃ。あのなあ、人には言われんけど、ガダルカナルも新聞では日本が勝っているように言うとるけどあれはなあ日本が負けよんやで。四分六なんや今は……。それが来年になったら七・三になって、そして結局は負けてしまうんやで』
そして、さらに次のようにおっしゃってくださったのです。
『どんなになってもやな、どんなことになっても、「かんながらたまちはへませ」を祈れよ。どんなときにも、「かんながらたまちはへませ」を祈るんや。祈ったならば……「かんながらたまちはへませ」という声が聞こえたならば、神様はどんなところに人間がおっても、すぐにお守りくださるんだ。救ってくださるんだ』
聖師さまは、こんこんと諭すようにお話くださるのでございました。
そして翌昭和十八年の四月になって私は結婚することになりました。当時、主人は新聞記者として中国で活動しておりました。その主人のもとへ私は単身、行くことになったのです。なにしろ戦争の第一線地帯に行くわけですから、内心、不安でいっぱいだったのを覚えています。結婚のお礼かたがた、私は聖師さまのところへ出発のご挨拶にまいらせていただきました。
聖師さまは、私の目の前で拇印を三つ押してくださって、それをお守りとしてお下げくださったのです。私は今もそのお守りを肌身はなさずいただいておりますが、その折りに聖師さまは次のようにおっしゃいました。
『いいか、この拇印を持って行けよ、そしてどんなことがあってもな「かんながらたまちはへませ」を忘れるでないぞ。いよいよのときは、「かんたま」でもいいから祈れよ』
このお言葉が、どれだけ私の励みになり、救いになったことでしょう。私は中国におきまして、今から思いましても、もう足がすくんでしまうほどの危ない目にもあいました。じわじわとあぶら汗がにじんできて、命が今なくなるのか、やられてしまうのかという状況の中で、私はひたすら「かんながらたまちはへませ、かんながらたまちはへませ」という祈りだけで、はかりしれないご神徳をちょうだいしたのです。
私たちが「かんながらたまちはへませ」という祈りの言葉を教えていただいているということは、なんと素晴らしくありがたく、幸せなことでしょうか。いつのまにか、この祈りの言葉に慣れてしまって、そこにどれほど大きい神様のおめぐみをいただいているかを、つい私たちは忘れがちでありますけれども、あのあたたかいお言葉のひとつひとつが、今も私の心をはなれず、とてつもなく大切なことを教えていただいたのだと、顧みては感謝させていただく毎日です。”
(「おほもと」昭和55年12月号 米川喜代子『「みろく」の家庭づくり』より)
*出口王仁三郎聖師によると、言霊の中で「カ」の言霊が一番よく響くのだそうです(「惟神霊幸倍坐世(かむながらたまちはへませ)が一番ひびく。カの言葉の言霊が一番響く。」(木庭次守編「新月のかけ 出口王仁三郎玉言集 霊界物語啓示の世界」)。
*この祈りの言葉「惟神霊幸倍坐世(かむながらたまちはへませ)」は、出口聖師が木の花姫命(このはなひめのみこと)から授かったもので、神様とつながる言葉とされています。「神ながら……」の「神」とは主神のことですが、特定の神霊の名前が含まれているわけではありませんので宗教宗派にかかわらず、誰でも唱えることができます。
・木の花姫命の託宣 (青年時代、高熊山での神秘体験を詠んだ歌)
つつしみて天津祝詞を宣りつれば忽然としてあらはる女神
われこそは富士の神山の守護神 木の花姫よと厳かに宣らす
木の花姫静かにわれに宣らすやう 祈る言葉は惟神霊幸倍坐世と
有難しかたじけなしと感謝しつ 此の神文をしきりに唱ふ
今までに此の神文は宣りつれど かく尊しとは思はずにゐし
(「歌集 霧の海」より)
*出口聖師は、木の花姫の『木の花』とは、梅の花であると示されています(「木の花とは梅の花の意なり。梅の花は花の兄と云ひ、兄をこのかみと云ふ。現代人は木の花と云へば、桜の花と思ひゐるなり。……」(「霊界物語」第六巻第二四章『富士鳴戸』))。とはいえ、桜の花が間違っているということではありません(「桜の花をかざして現われ給うた木の花姫は仮のみ姿」(出口和明「実録出口王仁三郎伝 大地の母」あいぜん出版))。ちなみに、冨士浅間神社で祀られる「木花咲耶姫命(このはなさくやひめのみこと)」は、木の花姫命のご分霊です。
“昭和六年の夏でしたか、海外宣教について出口聖師は、次のようにお話になりました。
「大本の宣伝使は先ず「惟神霊幸倍坐世(かむながらたまちはへませ)」と唱えあげる「神語」が含んでおり、かつ顕わすところの御神徳をひろめて行きさえすればよい。仏教は六字の称号をとなえてアレだけ多くの衆生を救った。大本の神語「惟神霊幸倍坐世」は、名は実の主なりというごとく、ことごとく有名有実であり、絶対権威がある。したがって神語は決して講釈してきかせたり、解釈を定めたり、説明を加えて内容を限定することは良くない。日本人たると外国人たるとを問わず、誰にも、「カムナガラタマチハヘマセ」とそのまま奏上するように知らせるとよい。外人にはローマ字で書いてそのままを覚えさせ、そのままに発声奏上するように知らせるとよい。そうすれば神語奏上によって、無限大の御神徳は、随時随所、唱うる人々の相違によって、それぞれの御神徳が現われ来たり、どんな人も必ずや何等かの体験を得させていただくことが出来るものである」と、‥‥‥”
(「おほもと」昭和31年12月号 竹山清『世界改造の経綸』より)
“祝部神(はふりべのかみ)は、事もなげに答へて云ふ。
『宇宙万有を創造し給うた全智全能の大神の経綸は、吾々凡夫の窺知する所ではない。吾らは唯々神の教示に随つて、霊主体従の行動を執ればよい。第一に吾々神人として、最も慎むべきは貪欲と瞋恚と愚痴である。また第一に日月の高恩を悟らねばならぬ。徒(いたずら)に小智浅才を以て、大神の聖霊体を分析し、研究せむとするなどは以ての外の僻事(ひがごと)である。すべて吾々の吉凶禍福は、神の命じたまふ所であつて、吾々凡夫の如何とも左右し難きものである。之を惟神(かむながら)といふ。諸神人らはわが唱ふる宣伝歌を高唱し、天津祝詞を朝夕に奏上し、かつ閑暇あらば「惟神霊幸倍坐世(かむながらたまちはへませ)」と繰返すのが、救ひの最大要務である。吾々はこれより外に、天下に向つて宣伝する言葉を知らない』
と云つた。”
(「霊界物語 第五巻 霊主体従 辰の巻」『波上の宣伝』より)
・倭姫命の託宣 (神習教・芳村正秉管長)
“正秉は伊勢神宮の出納課長に転身した。また、当然のことながら、禰宜として神事を行った。たとえば、福島県郡山市の開成山大神宮は、「東北のお伊勢さま」として崇敬されているが、これは明治九年九月に正秉が斎主となって、御霊代(みたましろ)遷座式が斎行されたものである。
彼は神官として、神事を行っていくうちに、だんだん神と交流することができるようになっていく。伊勢神宮に奉職中、その後の彼の人生にとって重要な出来事が起こる。それは同時に、古神道最大の秘儀を明かすものでもあった。
周知のように、伊勢神宮には内宮と外宮があり、内宮には正宮を中心に多くの社が鎮座している。その中で、特に古神道家に重要視されているのが、別名「荒祭宮(あらまつりのみや)」である。
別宮とは正宮に準じる宮で、正宮が天照大御神の和魂(ニギミタマ)を祭っているのに対し、荒祭宮の方は天照大御神の荒魂(アラミタマ)を祭っている。つまり、正宮と荒祭宮で陰陽セットになるのである。
伊勢内宮に参拝する時には、正宮に参拝した後で、その奥に鎮座する荒祭宮に参拝するのが‶通‶の参拝法である。
彼は時々、荒祭宮においてヤマトヒメノ(倭姫)命より、ありがたい御神諭をいただいた。ヤマトヒメノ命とは前述の通り、天照大御神の御杖代(みつえしろ)として、二〇〇〇年前に伊勢神宮を現在の地に定めた最初の斎主である。
ある時、正秉はヤマトヒメノ命との神人交流の中で、おうかがいを立てた。
「仏教ではナムアミダブツという念仏がありますが、神道ではそれに代わる言葉は何でしょうか?」
するとヤマトヒメノ命より、
「かみながら(加美奈賀良)という言葉である」
とのお答えがあった。
正秉はお答えがあまりにもシンプルなので、再びうかがった。
「それだけでよろしいのでしょうか?」
「よい。かみながらは神の大道の根本(帰宿)である」
とお諭しになられたという。”
(山田雅晴「大中臣神道の秘儀と神言 よみがえる古代朝廷祭祀」たま出版より)
・おそのさんの空念仏 (妙好人、三河のおその)
“このおそのが、あるとき田舎道をいつもの通り「南無阿弥陀仏」、南無阿弥陀仏」と言って歩いておった。すると一人の若い女が行き過ぎて、おそののその姿を見て大いに軽蔑して、「ああ、またおそのさんの空(から)念仏か」と申しました。するとおそのはそれを聞いてその女の方へ駈け出していきました。若い女は、空念仏かと悪口を言ったのですから、定めし怒って来たのだろうと思って、「そんなに怒らんでもいいが」というと、おそのは、「いやいや怒るのではない、実はあなたにお礼が言いたくてあとを追ったのだ。それはもしも私の言う念仏が充実した念仏であって、それが手柄となって救われるというのならば、私のような愚かなものは、何としても救われる値打はない。しかしあなたは空念仏ということをおっしゃった。自分の念仏ではなくて空念仏となってこそ、初めて救われるのだということをあなたが教えて下さったので、こんなありがたいことはない」。こう言って非常に厚く礼を述べたということです。これはやはり念仏の真意を、非常によくとらえた言葉だと思うのです。私が念仏するというのならば、もはや自力的な念仏なのでありまして、私がからっぽになっている念仏だと言えると思うのです。
法然上人に、沢山の人々が念仏とは何だということを繰り返し聞いたという話ですが、いつも法然上人は簡単に「ただ申すばかり」と言われたと申します。ただ南無阿弥陀仏と言えばいいのだ、こう教えられているのであります。この「ただ」ということに千鈞の重みがあるわけでして、何か意味あって言う念仏であるならば、それは本当の念仏ではないのであります。”
(「柳宗悦 妙好人論集」(岩波書店)より)
・「ありがとう」の力 (黒住教)
“備前藩士の一人で高禄のお家柄の人ですが、ハンセン病にかかり、顔にも表れてきました。で、かねてうわさに聞く上中野の先生のところへお参りして、おかげを受けたいものと、御宗家をたずねまして、教祖(黒住宗忠)様の御教えを受けました。
教祖様は、
「ご心配はありません。よくなります。が、この道では、何よりありがたいということが肝要です。とにかく、一日に百ぺんずつ「ありがたい」ということを熱心に唱えてごらんなさい!」
その人は、それはまことにたやすいことだと思って、さっそくそれを七日間実行しましたが、なんの効もありません。
そこで、また参りまして、そのことを申し上げますと「では、日に千べんずつ・・・」との仰せです。
今度は少し骨がおれますが、千べんずつ七日間実行しました。が、少しも病状は変わりません。
また、そのことを申しますと、
「・・・・どうか、日々一万べんずつ唱えなさい!きっとおかげがあります!!」
とのお言葉。
純真な人のことですから、またそのお言葉どおり一万べんずつ毎日々々唱えましたところ、ちょうど七日間目の日に、にわかに熱が出て、激しく吐血し、弱りきって倒れたまま寝たのでしたが、久しぶりになにもかも忘れて熟睡し、目が覚めると、たいへん気分がよく、不思議に手や足の腫れや、腐色が取れてしまって、きれいになっていました。
このひとは、それ以来、熱心にお道を信じて、生涯二、七の御会日を一回もかかさず参拝されたとのことです。”
(「教祖神の御逸話」(黒住教日新社発行)より)
*「ありがとう」を一日一万遍唱えたら奇跡が起きた、とか言う話はよく知られていますが、おそらくこの話を元にしたものだと思います。
・カバラー (ユダヤ神秘主義)
“人間は「聖なる言語」の「本質的な性質」を喚起しようという意図を持ってそれを発音すれば〈神〉をまねぶことができる、とコルドヴェロは信じていた。その発音された音はすべての思考の源へと上昇してそこに住む霊と合一し、「肉体のない霊的存在」に変容して人間を向上させる。
チュニジア版『千夜一夜物語』の一挿話に、カバラーの言語観がよく現われたものがある。カバラーの修行をしたパドマナバという婆羅門が、ヘブライ語のアルファベットの文字を適切な霊的意図を持って発音すればそれに対応する天使たちを召喚できる、と弟子に説くのである。
「各々の文字は一人ずつの天使に支配されている。その天使は〈全能〉の美徳と〈神〉の本質が流出した光である。この天使たちは地上にも天上にも住み、地上世界に住む者を治める。文字は言葉を作り、言葉は祈りを作る。文字が示す天使、書き言葉や話し言葉の中に潜む天使こそが、通常の人間の目には奇跡に見えるような作業を行うのである。」
カバリストにとって文字とは、物質的な叡智の宇宙を創る名辞と形態の組み合わせである。「クォーク」を透して最小の微粒子、物質の本源すなわち基礎性質を突き止めようとしている現代の物理学者と同様、カバリストは「御名」と「形態」(それは一種の絵文字であるヘブライ文字の中にうまく組み込まれており、文字はまた「数字」と「次元」をもあらわす)をある種の神聖な原子に変換するという方法で文字を通じてその本源に迫り、考え得るあらゆる置換を行うという方法で自然を超越して跳躍するのである。この目的のために彼は最初の〈神の御名〉、万物に浸透するかの第五元素の力を操作する。自らのエネルギーと、現在、過去、未来の万象の〈王冠〉を通じて放射するエネルギーを弛まぬ努力で合一させるのである。世界を根本的に支配する力を通じて、有限の中の無限、多の中の〈一者〉と向かい合うのだ。このように認識された文字はそれが表すものそのものなのである。—― それは肉体の器官によって発音されるがゆえに物質的なものであり、かつ天使の世界とつながっているがゆえに霊的なものである。それは無限に増殖して名辞とその対象の世界を形成するが、もともとの音に換言すると宇宙のハミングそのものとなり、慄然たる沈黙の中で光と音が溶け合うところで振動するのだ。
ツェルフと呼ばれる瞑想の技法、すなわち文字置換法は、言語を用いて言語そのものの構造を分解し、神秘家をやすやすと超自然的な領域に連れて行く。この驚くべき観照法はまず聖書の一句に徹底的に瞑想することから始まる。それを続ける内にその言葉は論理的な意味を喪失し、それでもなおその一句を繰り返し唱え続けると、カバリストは一種の失見当の状態に陥り、突如「意味を超えた意味」が稲妻のように閃くのである。特別の呼吸法および肉体の中枢への精神集中と組み合わせると、この瞑想法はほとんど直ちに法悦状態を招来する。
十三世紀のツェルフの実践家たちは理性を疑問視する観点から、より慎重な同時代人やタルムード学者、それに一般的なユダヤの支配階級などを批判した。『ゾハル』と共に栄えたスペイン学派の指導者アブラハム・アブラフィアは ――他のことに加えて―― 自分は眠れる物質主義者たちを「学問の虚栄」から救うために来た、と述べている。”(P114~P116)
“それぞれの者が、自分なりのやり方でバアル・シェム・トヴの観念……人間の祈りは〈神〉を完成させるものである。なぜなら人間こそ〈神〉の生ける火花なのだから……を実践していたのである。
「汝の唇を出るすべての言葉、すべての表現をもって、イクド(紐帯)を生じせしめることに専心せよ。あらゆる文字は宇宙、魂、善を包含する。上昇するにつれて、それは互いに結び付いてゆき、最後には統一されるのである。すると文字は統合され、結びついて単語を形成する。そうなればそれは実際に〈神の真の存在〉と結合する。そして以上のあらゆる局面において、汝が魂は文字の中に含まれる。」
バアル・シェム・トヴは、祈りと一体化することは〈神〉と一体化することである、と説いた。このような意識の高められた状態に至ると、ハシドはあらゆる肉体感覚を失ってしまう……外来の思考に妨げられることがなく、恐怖や緊張が喜びを妨害することもない。バアル・シェム・トヴは言う、その状態に至った者は「知性が発達しはじめたばかりの小さな子供の如くである」。祈りの言葉を通じて到達するハシドのデヴェクト(注:神への帰依)は愛によって強くなる。彼はそれを恋人のように堅く抱きしめ、手放したくないと願うからである。「それぞれの単語に執心するがゆえに」とバアル・シェム・トヴは義弟への手紙に書いている、「それを引き延ばして発音するのである」。このようにして自分自身と〈神〉のあいだの障壁を取り除いてしまえば、実は原初の状態においてはそこには障壁も悪もなく、ただ自分自身の思考が悪の幻影を構築しただけだったのだ、ということが判る。ハシディズムの解釈では、エゼキエルの見た「出たり戻ったりしていた」人のようなものの幻像は、源に向かって走りたいとは欲しながら、にもかかわらず肉体の中に住んで音を聞き、飲み、食いぶちを稼ぎ、そのためにその地上の領域に戻らなくてはならない人間の魂の寓意である。だが自我を滅却して感覚を消滅させてしまうと、魂は天使のように自由に高く飛翔する。とは言え、バアル・シェム・トヴによれば、高次世界の観念すら〈神〉を人間の世界から覆うもう一つの衝立に他ならない。ハシドは祈りに集中することで天使の群れすら消し去り、再び〈無〉の状態に戻る。アブラフィアのツェルフの師家たちと同様に、彼もまたヘブライ文字の生きた本質を前提とし、その真の実在を吸収すべく努めるのである。自らを〈神〉の道具として捧げるハシドは、〈神〉に即興的に語りかけるか、あるいは既定の祈祷書の語句をのみ用いて語る……いずれの場合においても、彼は意識的に〈言葉〉を操作しているのだ。その〈言葉〉こそ、彼を〈玉座〉の正しい位置に復活させる神聖なエネルギーを完璧な形で凝縮したものである。祈りにおいては、自我を滅却する方法は問わない。重要なのは、より高い位置に進むということなのである。”(P163~P164)
(パール・エプスタイン「カバラーの世界」(青土社)より)
*このカバラーの説は、「かんながらたまちはへませ」や念仏、光明真言などの真言陀羅尼にも当てはまることだと思います。なお、このような称名の行は、数珠を繰りながら行うのがよいようです。