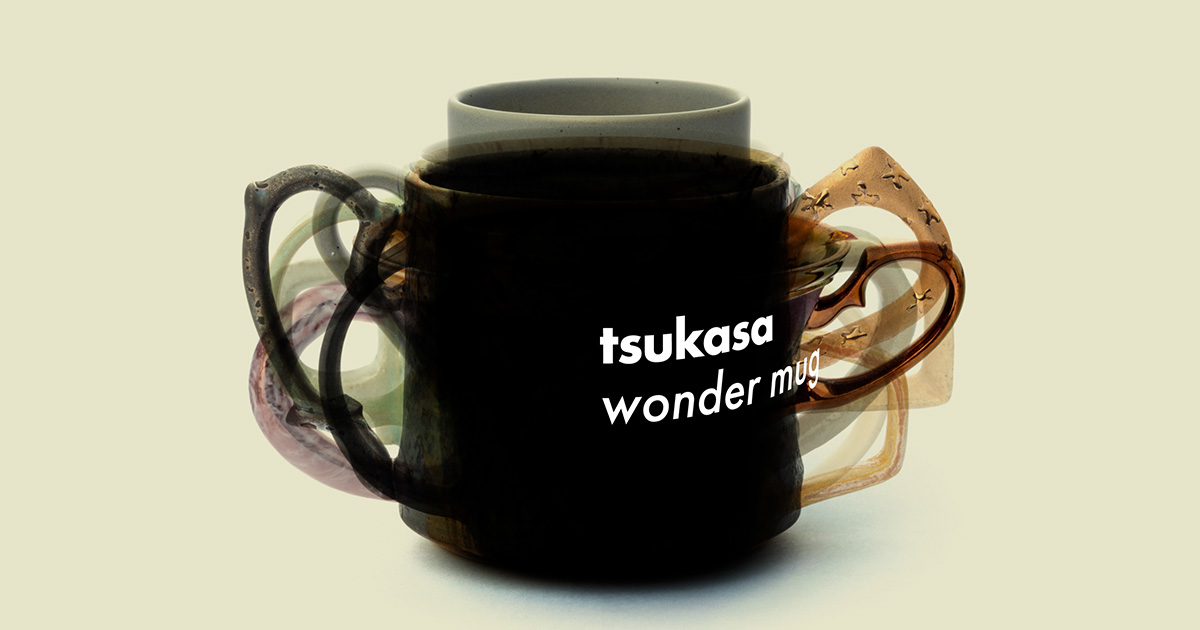前回に続き
かまわ庵茶会episode1の2/2後編です。
●点前座をつくる
点前座は茶席の華「叡知の場」です。
道具組、取り合わせは席主の茶道の知識・
センスの見せ所です。
担当は席主の貴也くん。
・升升皆さん一緒に成長しましょう!
酒屋の玉木さんのアイデア
・美しい点前、分かり易い半東の解説は特訓の賜物
「見立/みたて」は何でも良いわけではありません。
品・クオリティと自らのルーツや地縁です。
ゆえに一期一会が人との出会いに
限定しては浅はかです。
また単に買えばいい、何でも作ればいい、
奇想天外・奇抜がいいなんてのは
短絡的ではいけません。
・地元笠原の古のタイルが蓋で茶器は升
現在の茶道・茶道具作りは、新たな創造を
することに背徳感から古の道具を写すか、
知らなくて滅茶苦茶かどちらかです。
水指を作っても、美しい茶巾の載る姿も
荘り物をした姿もイメージしないで
水の容器バケツだと思って作っています。
塗り蓋、共蓋の意味も扱いも分かりません。
それは茶道の全てを知らないからです。
●美濃焼で全て揃う、茶碗も作る
茶会に使った茶碗は形も色も違いますが、
全て美濃焼です。
多治見工業高校の先輩の
人間国宝の先生方の茶碗から
若手作家の茶碗まで多種多様な
茶碗・茶道具を自足できてしまうのが
日本の6割以上の生産を担う
日本一の陶磁器の街・東濃・美濃焼の
実力だと思います。
陶芸家のケンタ、新作茶碗の初使いでおもてなし。
●床の間荘をつくる
床の間は茶会の精神の御柱
「魂の象徴の場」です!
担当したのは玉木さん。
・逃げも隠れもしない虚空に向かい伸びる漢武
一般的には軸を掛けますが、
まだ軸を持っていない場合
急に付焼刃に軸の買い物などもいけません。
ならば軸以上のもてなしの
自己表現を考えるべきです。
裏千家なら梶の葉用いて
葉蓋で七夕茶会と思っていたら。
「自然の物をなめるな!」
自然・天然の物が一番難しい。と
私は恩師に厳しく教わりました。
現実はまさにその通りです。
本当に読み通りになんか、なりゃしません。
理想的なモノは無いんです。
だから日々、葉や花の具合成長を
観察しなければ
「今この瞬間!」を捕らえて表舞台で
使う事なんてできません。
「自然を相手に、自然から學ぶ」
そこに至高と究極のもてなしの心が
あることを私達日本人は
學ばなければなりません。
茶会の後、玉木さんの奥様の手紙を
見せていただきました。
●茶道は「賓主互換/ひんしゅごかん」と
「一座建立/いちざこんりゅう」
そして、いつの間にか主客の境界が無くなり、
心が通い合う状態を一座建立と申します。
つまり、茶道・茶会はお客様との共働作業。
お客様と一緒に作り上げるものなのです。
・北村さんとお母さん
・山本さんご家族
小さな子供達は日本伝統文化が
珍しく、たった一度でも貴重な体験となります。
そんな老若男女が一緒に同じ場に参加して
作り上げる、楽しめる「もてなし文化」を
日本人は500年以上前に確立させてきたのです。
そんなん西洋にも
アフタヌーンティーとかあるでしょ!
と言われる方もいますが、
茶道、茶の湯は「ドリンク」ではないんです!
私たち日本人は
何故たかが「一服の茶」の為に
わざわざ茶室という場を作り、
準備し、飾り付け、人生を懸けて茶碗を作り、
仰々しい点前をするのでしょうか?
奥伝の点前だと「一服」点てるのに
一時間近くかかります。
茶道を知らない方は、CMやドラマの
薄茶のシーンだけ見て判断するので、
今年20周年を迎えるセラミックパークMINO
世界に誇る茶室ですが、初めて入った!
という方がほとんどでした。
あなたの街にも、あなたの街にも
素晴らしい茶室や茶会に相応しい場所は
日本全国、世界中にあります。
日本人ならそんな茶室や場所で匠の菓子と
一服の抹茶をいただきたいと思うのは当然です。
つまり今回のように私達と同じ茶会は
全国どの場所でも開催可能です。
茶会には行ってみたいけど
茶道をしてないから
気が引けて行けない方ばかり。
そんな方々は茶道をしている方よりも
圧倒的に多いのが今の日本の現実なのです。
日本人なのに、もったいない現実を
日本中で変えましょう!
・貴也君とハナタロウ商店 を経営される奥様、
みんなの笑顔
◼️「かまわ庵茶会 episode1」まとめ
岐阜県多治見市で開催した
小さな茶会ですが、いつかきっと皆さん
誰もが知る茶会になると、私は思っています。
理由は簡単です。
美濃守護、土岐氏の外護の宗とした禅宗から
命名されたこの地は、
利休居士や地元の古田織部公とともに、
桃山茶陶の聖地として
茶禅一味のわび茶の大成を担ってきました。
その華麗なる祖先の系譜を継承しているのが
かまわ庵社中のみなさんだからです。
その血潮が今ここに覚醒しました。
茶禅一味、歴史、武将、茶陶、
世界に唯一無二の場所が、ここ東濃の地です。
それはアニメの「ひょうげもの」ではなく、
これはリアルな現代のひょうげの
物語だからです。
故郷の岐阜県、美濃、東濃、多治見市にて
日本の伝統文化である茶道を通じた
町づくり・活性化を行う
私達の活動の輪を広げるご支援、
御協力をいただける個人様や企業様が
いましたらぜひご連絡をお待ちしております。