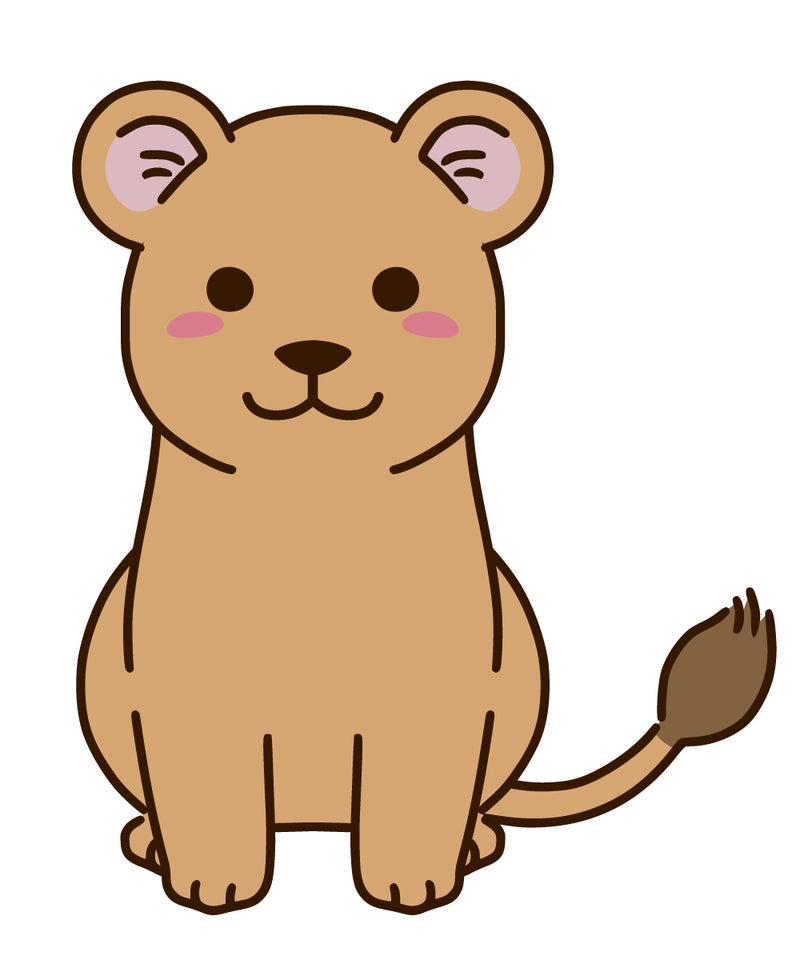少し前、猫についての記事で「ライオンがくしゃみをして、鼻の穴から猫が飛び出した」という伝承が、世界各地に存在することを取り上げました。
↓
また、猫が「養蚕」と関係があることも書きました。
↓
さらに「養蚕」について調べていたら、またまた興味深い民話に辿り着きました。
その民話、だいたいこんな内容です。
「犬頭絲(けんとうし)」
あるところに、蚕から絹糸をとって暮らしを立てている娘がおりました。
ある日、大切に飼っていた蚕を白い犬が食べてしまいます。
さびしく思って犬に向かって泣くと、犬はくしゃみをし、よく見ると鼻の穴から二筋の白い糸が伸びていました。
その糸を引くと、長々と続きどこまでも出てきます。
四、五千両ほど巻きとり、糸が尽きると犬も倒れて死んでしまいました。
犬を桑の木の下に埋めると、そこからたくさんの蚕が出て、娘はその繭からよい絹糸を作って幸せに暮らしました。
「白い犬が蚕を食べて、くしゃみをし、鼻の穴から糸を出す」
・・登場人物やストーリーに違いはありますが、このような民話が日本各地にあるようです。
=「鼻の穴」から重要な何かが出る?
「鼻」といえば・・
「安来節」の「どじょうすくい踊り」では、鼻に五円玉を付けるんですよね! (代わりに鼻の穴に割り箸をさす場合も)
(この五円玉、もともとは一文銭でした)
なぜ鼻にお金を付けているのでしょうか? 由来とされるのはこんなお話。
削がれた鼻を、隠すため・・!?
(ていうか、削がれるの?((;゚Д゚))))
・・でももしかしたら、一般的な由来の他に何か別の意味があるかもしれませんよね・・?
(鼻の奥にお金(=宝物)が隠れているとか・・?(・∀・))
このどじょうすくいにも用いられる「ひょっとこ」のお面には、「鼻毛」が長く描かれているものがあります。
毛が下に向かって長く伸びているので、これもさきほどの「鼻の穴に割り箸をさす」別の表現なのでしょうか?
「鼻毛を伸ばす」
「鼻毛を伸ばす」→「鼻気を伸ばす」→「鼻息を伸ばす」
→「呼吸を伸ばす」→「長い呼吸をする」?
・・というヨガの呼吸法「長息」の意味だったりして?
(違う? (・∀・))
ちなみに・・
「鼻毛を抜く」という言葉には「手玉に取る」という意味があるんですよね!(びっくりです!( ゚д゚))
「手玉に取る」の語源「お手玉」
「鼻の穴」にはどんな意味があるのでしょうか??
(鼻の奥に大切なものが潜んでいて、何かのきっかけで鼻の穴から飛び出てくる・・とか?)
・・なんだか気になるので、これからも考えていきたいです(・∀・)