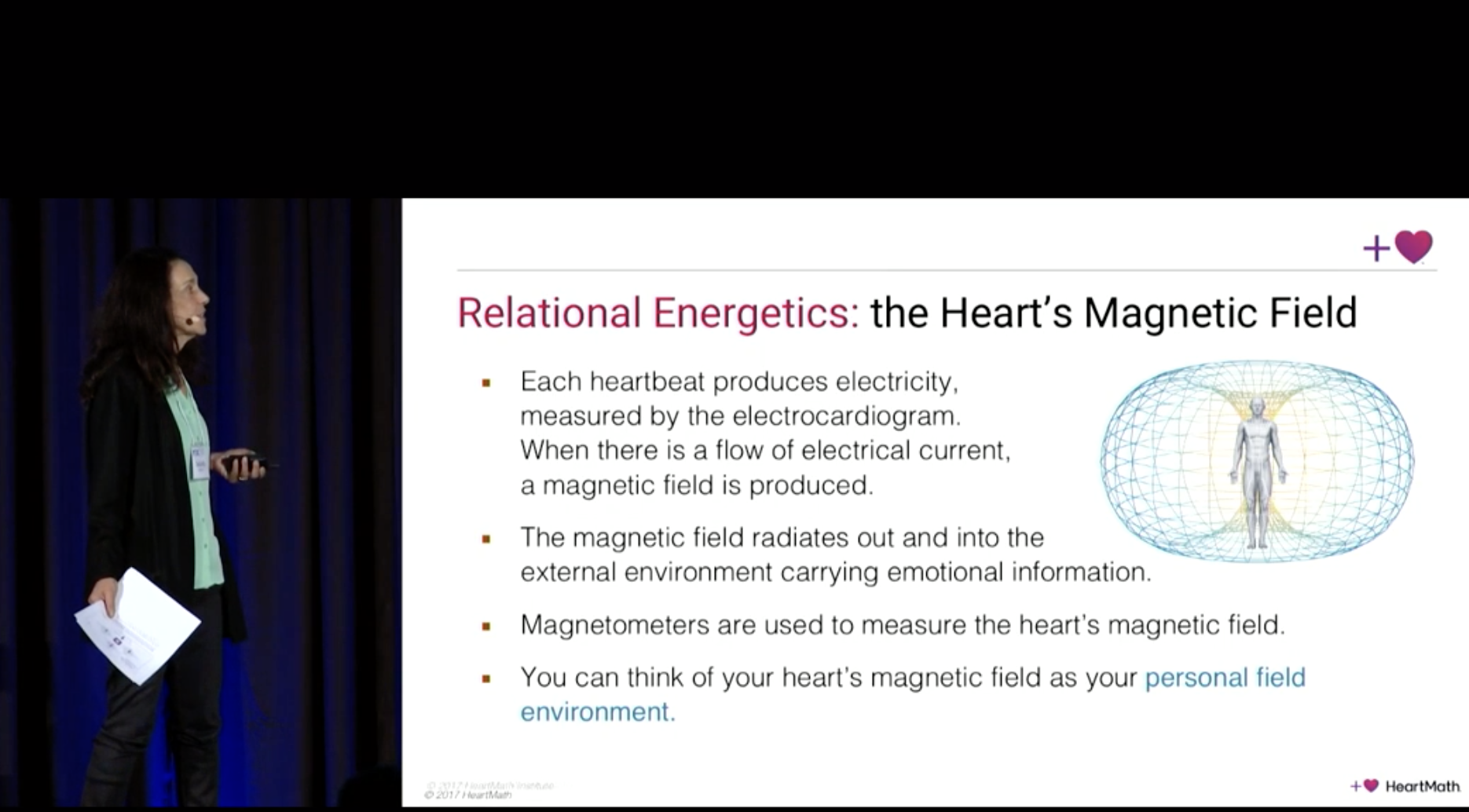公認心理師のふーこです![]()
今日は興味深いテストをご紹介したいと思います。
皆さんがご存じのマシュマロ。
ふわふわして美味しいですよね。
あのマシュマロを使ったテストをした心理学者がいました。
社会心理学者のウォルター・ミシェルらによって行われた「マシュマロテスト」です。
このテストは、4~5歳児の子どもを対象に、お皿の上に1つのマシュマロを置き
「食べずに待っていればもう1つマシュマロをあげるわ」と言い部屋から実験者が退出。
実験者が戻るまでマシュマロを食べずに我慢できるかどうか、はたまた我慢できずにパクっと食べてしまうかを弁別するテストでした。
ミシェルらがマシュマロテストに参加した子どもたちを数十年にわたって追跡調査したところ、色々なことが分かりました。
マシュマロを食べずに我慢した子は・・・
◎先のことを考えて計画や行動ができる
◎誘惑に負けにくい
◎入試では高い得点を叩き出した
◎肥満指数が低い
◎対人スキルが優れている
一方、我慢できなかった子は・・・
◎目先の誘惑に負けやすい
◎入試では悪い成績
◎肥満指数が高い
◎対人スキルに困難を抱える子が多い
一体この差はなんだろうかとfMRI(脳内の血液代謝を測定する)で調べたところ、我慢できた子どもの脳内の前頭前野と線条体の機能的結合が強いことが判明しました。
前頭前野はブレーキの役目をするもの、線条体は報酬系と呼ばれていて快楽に対して強く反応する領域です。
我慢できた子は、前頭前野によって線条体の活動を適切に制御することができていたということになります。
もしこの実験をしてみて、ご自身もしくはお子さんが我慢できなかった場合どうしたら良いのか。
心配はいりません![]()
自制能力(セルフコントロール)は後天的に身につけることが可能なのです。
重要なのは、自制の方略を身につけること!
例えば、自分の目の前にマシュマロを置くよりも、マシュマロを隠しておいた方が我慢できる時間が長くなる、などです![]()
行動や思考の抑制に適切な方略を学習することが後天的に人生を生き抜く秘訣になります。
親が子どもを過保護にコントロールするよりも、子どもの自主性に任せて育てた方が自制能力は高くなることが示されています。
私も子どもの自主性に任せる育児に舵を切った時には、ハラハラドキドキの連続で幾度眠れぬ夜を過ごしたか分かりません。
子どもの力を信じて任せることも時には必要なのだと、ハタチを過ぎた息子を見てそう思う今日この頃です。
私はマシュマロを隠してもっともっとセルフコントロールできるように頑張ります![]()
【参照】がまん強い子どもは将来成功する?(著:松本 昇)
【10/29】アドバイス禁止! 不登校・行きしぶりの子の保護者さんと心理師のお話し会
WEBサイトはこちら
不登校、登園・登校しぶりの子の「生きる力」を考える 親子心理研究所
教育に関するご相談、心理師との相談、アセスメントのコンサルテーションを受け付けています