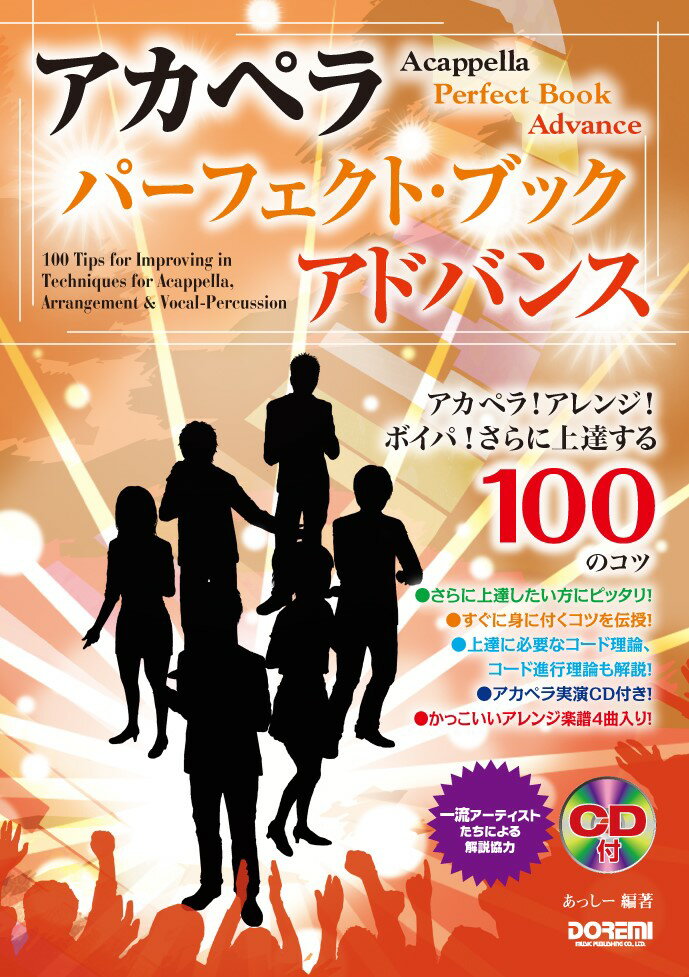- 今回は、どんなアカペラ楽譜を見てもすぐに歌える方法(移動ド歌唱)を紹介します!
- 「おっ、すごい!そんな方法があるのか!」と思われるかもしれませんが、すぐにマスターできるわけではありません。
- 少し時間をかければ、誰でもできるようになりますので、ぜひ挑戦してみてください。
-
移動ド歌唱とは?
すべての音(臨時記号や短調は今は考えない)を「ドレミファソラシ」のみで歌うことを移動ド歌唱と言います。
-
-
例えば、「レ・ミ・ファ#・ソ・ラ・シ・ド#」(スケール)をピアノで弾き、主音「レ」を「ド」と位置づけて「ド・レ・ミ・ファ・ソ・ラ・シ」に置き換えて歌うことです。これにより「ドレミファソラシ」の音の幅を覚えておけば、どのような曲もすぐに歌えるようになります。
-
-
ちなみに、楽譜通りの音階で歌うことを固定ド歌唱といいます。

実際の楽譜で例を示すと、「大きな古時計」を移動ドで音名を振ると以下のようになります。


-
移動ド歌唱を習得するために必要な知識
移動ド歌唱を学ぶ前に、キーとスケールの知識が必要です。
-
-
キーは調とも呼ばれ、楽譜などの一番左の音部記号(ト音記号やへ音記号)の横につく、♯や♭の数のことです。その中で主たる音を主音と呼び、主音から順番に音を並べていくとスケールとなります。
-
-
移動ド歌唱で歌うには、この2つの知識が必要になりますので、学んでおきましょう。
- 新アカペラパーフェクトブック、アカペラパーフェクトブック~アドバンス~で詳しく解説していますので、是非読んでみてください。
-
-
-
移動ド歌唱の前の基礎練習
移動ドを歌う前に必要なことは、「ドレミファソラシ」の各音の間隔を覚えることです。
-
-
実際の曲で移動ドを歌う際には、「ドレミファソラシ」の順不同で出てくるため、「ド~ソ~ミ~ファ」のようにメロディに従った順序で歌います。次の音への間隔を把握することが重要です。
-
-
まずは、「ド」⇒「ソ」、「ソ」⇒「ミ」などの音の幅を覚えていきます。
-
ボイトレの本では、「ドレドレ ドミドミ ドファドファ ドソドソ」と初心者には退屈な練習が出てきますが、これらは音の間隔を掴むためです。
練習教材として以下を紹介します。(移動ド歌唱ではシをティとするのが一般的です) -
是非、練習してみてください。
-
-
-
移動ド歌唱ができるようになるまで
移動ド歌唱を学ぶ手順をまとめましたので、その手順に従って挑戦してみてください。
-
-
①キーとスケールを勉強する
②「ドレミファソラシド」「ドシラソファミレド」を何度も練習する -
③固定ドで音の間隔を掴む(上記動画参照)
-
④過去に歌ったことがあるアカペラ楽譜を移動ド歌唱を歌う(歌い慣れているため、移動ド歌唱を行いやすい)
-
⑤歌ったことがないアカペラ楽譜で移動ド歌唱に挑戦する
-
-
今回はアカペラアレンジにおけるベース作成に関して、多くの質問が寄せられる点に焦点を当てます。
特に、楽器のベースと声によるベースの違いを理解していない方が多いため、この機会にしっかりと学んでおきましょう。
楽器のベースと声のベースの音域の違い
アカペラのベース(合唱のバスパートなど)も楽器のベースも同じへ音記号で表記されます。
しかし、実際の音の高さは楽器の方が1オクターブ低いのです。
楽器のベースは、見やすくするため、オクターブ上げて表記をしています。
例えば、「ミ(E3)」の場合以下のようになります。
①アカペラの楽譜の場合
②楽器のベースの楽譜の場合
③実際の楽器のベースの音を楽譜上に表記した場合
アカペラアレンジする際に意識すること
アカペラアレンジでは、ベースパートを作るときに、楽器ベースの楽譜を参考にする人が多いと思います。ここで気をつけるのは、ベース音域が高くなりすぎないようにすることです。
下の譜例は、楽器のベースをそのままアカペラ楽譜に起こしたものとします。
楽器のベースでは先ほど述べたのように、表記の1オクターブ下なので問題は発生しませんが、アカペラの場合、コーラスと音域が重なってしまうことがあります。譜例のように、瞬間的に高くなるであれば許容できることもありますが、度々このような音域が続くとベースらしさが失われてしまいます。
そうならないよう、1オクターブ下げたり、他の音に変えるなどの工夫が必要になります。
この点に注意しながらアカペラ楽譜を書いてみてください。
「アカペラパーフェクトブック」シリーズは、アカペラの練習法、アレンジ(楽譜作成)、ボイパの方法などをまとめた本で、アカペラ楽譜も何曲か掲載しています。この一冊で、アカペラに関する知識を身に付けることが可能ですので、是非読んでみてください。
アカペラアレンジに音楽理論は必要か?
結論から言うと必要です。
ただし、初心者の場合は全てを学ぶ必要はなく、初歩的なことのみでいいと思います。
よくアカペラアレンジにおいて、音楽理論は不要と書かれている記事もありますが、それは疑問に思うこともあります。
音楽理論不要と言いながら、記事の中で音楽理論用語を用いて解説しているのです(もしかしたら音楽理論の定義が私と認識が異なっているのかもしれません)。
初心者に必要なのは、以下の3つです。
- ・「コードの知識(ルート、コードトーン)」
- ・「コーラスの役割」
- ・「ベースの役割」
この3つを押さえておけば問題ありません。
それぞれ、アカペラパーフェクトブックシリーズで解説していますのでご参考ください。
そして、音楽理論で挫折しやすいのは、コードの「度」です。
「3度」「5度」とよく耳にする方も多いでしょう。
これらは、音楽理論の中でも特に重要とされる用語で、アカペラアレンジをする上でも重要です。
「度」を意識することで、綺麗なハモり、声部の少ないアレンジができるなど、幅が広がります。
ある程度アレンジをこなしてから(4、5曲ほど)、挑戦することをお勧めします。
「度」について学びたい方は、アカペラパーフェクトブックシリーズを読んでみてください。アカペラの練習方法、アレンジ(楽譜作成)、ボイパ方法など、アカペラを行う上で必要な情報が網羅されており、初心者向けのアカペラ楽譜も収載しています。
合唱楽譜の作り方(初心者向け)について解説します。
本記事での合唱楽譜とはピアノ伴奏+合唱
を指しますので、あらかじめご了承ください。
アカペラ楽譜と合唱楽譜の主な違い
■声部数
アカペラでは5声(ボイパは除く)が一般的ですが、合唱では3声または4声が一般的です。
■旋律
各パートに美しい旋律が求められます。特にソプラノパートは主旋律を担当することが多いですが、他のパートも旋律的な役割を果たします。アカペラでもコーラスやベースの旋律の美しさが求められますが、合唱ほどではありません。
■ベースパート
ピアノ伴奏の場合、楽器のベースがなく、楽器のベースを模写した声でのベースパートも基本的にありません(バスは低音を担当するパートですが、楽器のベースとは役割が異なります)。
■リズム
ポップスと比べると、合唱には比較的単純なリズムが多いですが、合唱らしいリズムで副旋律を作ります。
合唱楽譜の構成
合唱楽譜は基本的にアカペラ楽譜の作り方と同じ作り方です。
違うのは、旋律の美しさや合唱特有の表現方法ですので、まずはアカペラ楽譜の作り方に沿って作成してみることが大切になります。
①ピアノの伴奏
ピアノの伴奏は、コードに基づいて作られます。四分音符だけでも伴奏が成立するので、初めての方はコードの勉強をしてみてください。
もしくは、最初はピアノ伴奏だけの楽譜を購入し、そこに合わせて合唱部分のみを考えると良いでしょう。
②合唱部分
アカペラでいう「字ハモ」がよく使われます。
ただし、合唱楽譜は和声や対位法に従い、1つ1つのパートを丁寧に作り込む必要がありますが、初心者の場合には挫折してしまうかもしれません。まずはどんな形でもよいので、作ってみることが大切だと思います。
③必要な知識
楽譜を作る上で必要になるのがコードの知識です。
合唱楽譜もアカペラ楽譜もコードを用いてハーモニーを作り出します。
コードは基本的になことであれば学習ハードルは高くありません。
少しのコードの知識で楽譜を作ることが可能です。
これを機にコードについても学んでみてください。
合唱楽譜作成の学習方法
実際に楽譜を作成するには、書籍で学ぶのが最も効果的です。
しかし、合唱の楽譜作りについての情報は限られており、また敷居も高く、楽譜作りに不安を感じる方も多いかもしれません。
まずは、アカペラ楽譜の作り方を勉強し、基本を身につけることをお勧めします。
アカペラ楽譜の作り方で最も有名な書籍が「アカペラ・パーフェクト・ブック」シリーズです。
練習方法、アレンジ、ボイパ、コード理論など、幅広い知識を身に着けることができます。
音楽理論(コード)の知識を学ぶ書籍としても定評があります。
合唱楽譜としてのクオリティを求めるには、更なる勉強も必要ですが、
はじめの一歩としては参考になる書籍ですので、学んでみてください。
Amazonで購入
楽天で購入
今回はシンコペーションに焦点を当てて説明します。
シンコペーションとは、特定の音符を前にもってくる技法のことです。
例えば、譜例で見ると、2小節目と4小節目の最初の拍がタイで結ばれているのがわかります。
これは、最初の拍の音符を8分音符分だけ前にズラすことによって実現されています。
初級者がよく取り込むアレンジの1つとして、四分音符のみで構成されたものが挙げられます。
ただ、それだけではリズムが単調で面白みに欠けてしまいます。
シンコペーションを取り入れることで、リズムに変化を加え、魅力的な味わいを生み出すことができます。
「アレンジにジャズを取り入れる必要があるのはなぜ?」
「学んだことをどう生かすの?」と、疑問に思うかもしれません。
実は、多くの現代曲は過去の曲のリズムを取り入れており、特にジャズの和音やリズムは、
現代音楽においても頻繁に使用されています。
ぜひこの機会にジャズを聴いてみませんか?
今回の話題は、コーラスのリズムについてです。
アップテンポの曲では、しばしばコーラスがギターのリズムに合わせてラインを作ることがあります。
ただし、楽器のリズムをそのままアカペラに採用は適切ではありません。
それぞれの楽器は、その楽器らしい特性を持っているからこそ、効果的な演奏ができるのです。
声で奏でる場合も、声に合った魅力的なリズムに変えていくことが重要です。
特にアップテンポのリズム(例えばギターのバッキング)を「トゥ(tu)」という歌詞を使い
表現するのはあまり良くないと思っています。
その発音自体がやわらかいため、曲の雰囲気に合わないと感じることがあります。
これは倍音が少ないために起こりうるものだと考えています。
倍音が多ければ多いほど固い音になります。
ですので、
倍音の多い「a」「i」を子音にもつ歌詞に変える
のがおススメです。
リズムパターンにはよく使われるものがあり、
これらは様々なジャンルのリズムに触れることで理解を深めることができます。
特におすすめなのは、ファンクギターのリズム、ボサノバやサンバのパーカッションのリズム、そしてR&Bの鍵盤楽器のリズムです。
これらのリズムパターンを把握することで、さまざまな音楽のリズムに対する理解が深まるでしょう。
良いベースラインを作るためには、リズムと音選びの両方が重要です。
これをマスターするためには、耳コピ(耳で聞いて楽曲を譜面に起こすこと)が非常に役立ちます。これは最も効果的なベースラインを作る方法の一つです。最初は難しく感じるかもしれませんが、特に音感がない人にとっては特に有効です。
どんな曲を耳コピすれば良いかというと、FUNK、JAZZ、R&B、BOSSANOVA、FUSIONなどさまざまなジャンルのベースラインがおすすめです。
これらのジャンルはJ-POPにも大きな影響を与えており、例えばスピッツがR&B、ドリカムがFUNKやJAZZの要素を取り入れていることがあります。
ただし、ベースには基本的な法則や技巧的な要素もあります。例えば、ルート音や5度を担当する役割、ペダルポイント、クロマティックアプローチ、クリシェなどがあります。これらについてはベースの教則本(アカペラパーフェクトブックシリーズで解説しています)を読むことをお勧めします。
まずは耳コピに挑戦してみてください。少しずつ慣れてくると、どんなジャンルのベースラインでも自分のものにできるようになります。
累計1万部突破!アカペラの教則本の定番書です。練習方法、楽譜の書き方、ボイパまで分かりやすく解説しています。
今回は最も質問が多い字ハモの作り方です。2つのすぐにできる作り方について解説します。
字ハモについて詳しく学びたい方はアカペラパーフェクトブックシリーズ読んでみてください。
コードの音のみでコーラスを作る
最も一般的な字ハモはコーラスをコードのみで構成させることです。通常コーラスの使い方の定番はコードの構成音で構成します。字ハモも基本一緒です。コードの構成音をコーラスが歌いリードを支えることでハーモニーが安定します。このアレンジ方法については下記で解説しています。
【誰にも分かる】アカペラの定番アレンジ | アカペラ楽譜作成(アレンジ)、練習方法上達ブログ (ameblo.jp)
3度+コードの音の字ハモ
3声のコーラスにおけるもう一つの効果的な字ハモの作り方について説明します。
トップコーラスはリードボーカルとの3度のハーモニーを形成させます。
セカンドとサードコーラスは、すべての音符に対してコードの構成音を使用して作ります。
リードとトップが3度でハーモニーをとることで、リードが際立ち、セカンドとサードの低いコーラスが低音部分を歌うことで、和音がより安定します。
こうすることで、コーラスのみで字ハモを作るよりかっこいいアレンジに仕上がります。
発展した字ハモの作り方について
綺麗な字ハモを作るには、コードなどの音楽理論の知識が必要になります。
字ハモの基礎となるのは、リードがコードの中でどのような音を歌っているかです。
リードの音はコードの音だけでなく、それぞれが特定の役割を持っています。
例えば、ある音がテンションであり、別の音が経過音であるといった具合です。ハーモニーを作る際には、これらの役割を考慮すると良いでしょう。
興味がある方はアカペラパーフェクトブックシリーズを読んでみてください。
累計1万部突破!アカペラの教則本の定番書です。練習方法、楽譜の書き方、ボイパまで分かりやすく解説しています。
アカペラアレンジで大変なのが、リードとベースを楽譜作成ソフトに打ち込むことです。
そこでmidiを利用するとアレンジが楽になります。
midi(ミディ)は、Musical Instrument Digital Interfaceの略称で、電子楽器間で音楽データを通信するための規格です。
MIDIファイル(拡張子.mid)は様々な機器(パソコンもその一つ)で再生できるデータファイルです。楽譜作成ソフトに取り込むことで、楽譜(歌詞なし、音符のみ表示)として表示させることも可能になります。
ネット上では様々な楽曲のmidiファイルが販売されています。
- バンドスコアのmidi
- ピアノアレンジのmidi
- ボーカルのみのmidi
その中で、ボーカルとベースが含まれるmidiを購入します(もちろんボイパならドラムありのもでもよいでしょう)。
楽譜作成ソフトで購入したmidiファイルを開き(インポートもしくはファイルを開く)、必要なパート以外を削除し、ボーカルとベースのみを残します。
こうすることで、楽譜作成ソフトでコーラスを打ち込むだけとなり、アレンジが簡単になります。
ただし、midiは楽器のベースですので、声に合わせて音域を調整する必要がありますので注意してください。
midiを開く練習として、以下にアカペラ楽譜を挙げておくので読み込んでみてください。
是非midiを有効活用してみてください。
アカペラアレンジについて学びたい方は、アカペラパーフェクトブックシリーズを読んでみてください。アカペラの練習方法、アレンジ(楽譜作成)、ボイパ方法など、アカペラを行う上で必要な情報が網羅されており、初心者向けのアカペラ楽譜も収載しています。
アカペラーの間でもかつて人気があった楽譜作成ソフトのFinaleシリーズ、
現在は無料のMuse Scoreが人気ですが、綺麗で素早く楽譜を作成するには、有料の方が良いです。
Finaleは2024年8月下旬に開発・販売終了のアナウンスがされました。
出版業界では最も使われているソフトで、楽譜作成界隈にかなりの衝撃を与えました。
公式サイトより代替品としてSteinberg社のDoricoが推奨されています。新しい開発環境、ユーザ目線で作成されたので、非常に使い勝手が良いとのことです。
私も体験版(Dorico pro5)をインストールしてみました。
慣れは必要ですが、使い勝手がよく便利なので正式に購入する予定です。
Finaleと比べてよかった点をいくつか紹介します。
iPadで楽譜作成可能(無料)
Doricoは、iPadでも楽譜を無料で作成できます。今まで無料で使い勝手の良いタブレット端末向けの楽譜作成ソフトはほとんどありませんでした。iPad版のDoricoは浄書機能やパート数に制限はありますが、アカペラ楽譜を作成する上で必要な機能はほぼ網羅されています。慣れが必要ですが、操作も簡単で、すぐに楽譜作成に取り掛かれます。
また、MusicXMLファイルにも対応しており、MuseScoreで作成した楽譜をDoricoに取り込むことや、その逆も可能です。PCで操作するのが苦手な人にもおすすめです。
Dorico for iPad: 楽譜作成アプリ | Steinberg
レイアウトが簡単、綺麗
楽譜レイアウトが非常に簡単にできます。五線譜同士の間隔もmm単位で直接入力でき、均等に配置できます。さまざまな部分において細かく設定できます。
拍の途中から音符が配置可能
Finaleでは、小節の1拍目からしか音符を置くことができませんした。
Doricoの場合には、拍の途中から音符を置くことができます。
譜例では、4拍目に4分音符を置きました。オレンジ色の線に合わせることで、任意の拍に音符を配置することが可能です。それ以外の拍は休符が自動的に置かれます。
アカペラ楽譜を作る場合には1拍目に音符を置かないことも多く、この機能は非常に便利です。
違う音価の音符で上書き可能
Finaleでは音符を配置し終わった後に一度音符を消す必要がありましたが、Doricoではその必要はなく、音符を置きたい拍に配置するだけで上書きできます。非常に便利な機能ですが、誤って上書きすることもあるので注意が必要です。
ボイパ譜が簡単に作成可能
Finaleではボイパ譜を作るのが非常に面倒でした。バスドラ(音符が下向き)とそれ以外(音符が上向き)で声部を切り替えながら音符を配置していく必要があります。Doricoでは、音色ごとの設定をするだけで市販のドラム譜、ボイパ譜のような楽譜がすぐ作れます。
高速ステップのような操作も可能(要設定)
Dorico Ver5.1.60(Ver5の人は無料アップデート可)よりFinaleの高速ステップに近い形が可能となりました。「編集タブ」>「環境設定」「キーボードショートカット」>「シャドウノートをステップ上げ(下げ)」に対してショートカットキー(↑、↓)を割り当てることにより、音符入力時に、↑、↓ボタンで音高の操作ができるようになりました。
この万能ツールもメリットばかりではありません、デメリットもあります。
音符が書き換わる
Doricoでは、選択されている音符に対して変更を行います。
例えば、変更した音符をクリックし、音価(音の長さ)を選び変更します。
ところが、すでに音符が変更したい場所と違う箇所で選択されているとその音符が変更されてしまいます。
自分の気づかないところで音符が変更されていることもありえるのです。
ここは非常に気をつけることだと思います。
是非Doricoを使ってアカペラ楽譜に挑戦してみてください。
アカペラの練習方法、アレンジについてさらに学びたい方は、アカペラパーフェクトブックシリーズを読んでみてください。アカペラの練習方法、アレンジ(楽譜作成)、ボイパ方法など、アカペラを行う上で必要な情報が網羅されており、初心者向けのアカペラ楽譜も収載しています。
追記:Doricoを購入するとFinale27(英語版)がダウンロードできるとアナウンスされた件について、続報があったので、追記します。入手方法について、以下の記事でまとめています。
Finaleの英語版の入手方法(Doricoクロスグレード購入者) | アカペラ楽譜作成(アレンジ)、練習方法上達ブログ
MakeMusic社のeStoreにてDorico Proクロスグレードをご購入しなければ適用されない
ようなので、ご注意ください。以下添付されたメールです。
ーーーーーーーーーー
拝啓 MakeMusic製品ご登録ユーザー様各位
(本メールはFinale 27ユーザーの方にも念のためお送りしております)
8月28日に、楽譜作成ソフトウェアFinaleの開発/販売元であるMakeMusic社がFinaleの開発/販売終了をアナウンスしましたことをご案内させて頂きました。その後、MakeMusic社が8月30日(米国時間)に「MakeMusic社の英語WebページでMakeMusicアカウントの登録をされていて、MakeMusic社のeStoreでDorico Proクロスグレードの購入者にはFinale 27(英語版)のダウンロード版を提供する」との追加のアナウンスがありました。
2024年8月28日に弊社から日本の皆様へご紹介させて頂きました、株式会社ヤマハミュージックジャパンLM営業部様の日本語WebサイトでのDorico Proクロスグレード優待販売に関しまして、MakeMusic社の追加のアナウンスを受けてヤマハミュージックジャパン様に確認しましたところ、ヤマハミュージックジャパン様ではDorico Proクロスグレードを購入された方へのFinale 27(英語版)ダウンロード版の提供はできないとのご連絡を頂きました。
Dorico Proクロスグレードを検討されているFinale 27をお持ちでない日本のユーザーの皆様で、MakeMusic社からの追加のアナウンスにありますDorico Proクロスグレードの購入者にFinale 27(英語版)ダウンロード版の提供を希望される方は、MakeMusic社のeStoreにてDorico Proクロスグレードをご購入いただく必要があるということになります。このMakeMusic社の8月30日の追加措置は、Finale 27をお持ちでない日本のユーザーの皆様に対して、Finale 27に搭載されたMusicXMLの現行バージョンであるMusicXML 4.0を使用してFinaleファイルをXMLファイルでエクスポートし、そのファイルをDoricoでインポートすることを考慮されています。
ーーーーーーーーーーーーーーーー