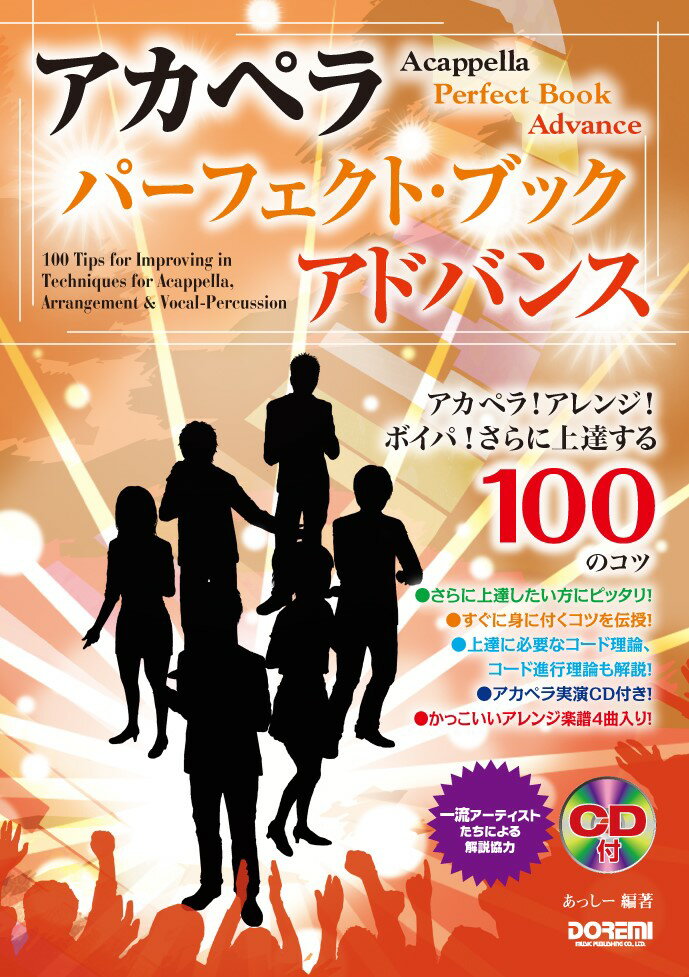アカペラアレンジにおいて難しい点は、原曲の楽器のリズムを声で再現する際に、他のアレンジと同じになってしまったり、単調で面白みに欠けることがあることです。
本記事では、原曲のリズムを活用しつつ、アカペラらしいアレンジを取り込むコツについて解説していきます。
解説は下記動画の晩餐歌/tuki.のアレンジを用いて行います。
晩餐歌は初級者向けのアレンジ楽譜です。3、4曲目に歌う楽譜としてピッタリです。
原曲のリズムはすべてを取り込まない
原曲のリズムを取り込む時には、すべてを取り込んでしまうと、アカペラとして面白みに欠け、他のアレンジャーと差がつかないので、印象的な部分だけを取り込むようにします。
晩餐歌の原曲では、イントロ、エンディングのギター部分が印象的であったのと、
2番目からベースが入るので、その部分は原曲に近い形で構成しています。
ただ、原曲のリズムや音をそのまま取り込むのではなく、
「アカペラ」として歌いやすい、聞きやすく、変更することをお勧めします。
特にギターソロなどの楽器を声で再現する時には注意が必要です。
楽器のソロは細かなメロディが低音から高音までをカバーしているため、声で忠実に再現しようとすると不自然になることがあります。
随所にアカペラらしいアレンジを取り込む
アカペラらしいアレンジとは、ベルトーンや字ハモなどを指します。
アカペラの醍醐味は声だけで様々な奏法を真似することだけではなく、アカペラらしい旋律を奏でられるところです。
特に、ベルトーンや字ハモはよく用いられる技法で、この晩餐歌にも様々なところで使われます。様々なアカペラアレンジを見聞きしながら、良いと思った部分を自分のアレンジ取り込みましょう。
休符を使いこなす
単調にならないためには休符を使うことが大切です。
1番はボイパを入れない想定でいます。そのため、休符を多く使い、静かなアレンジとなっています。逆に、2番はベースが動くので、コーラスにも動きを与えています。これにより、2番がより盛り上がるようになっています。
今回は1番と2番で盛り上げ方を休符によって変えていますが、サビやBメロを盛り上げたい場合には、その前のセクションに休符を活用し、相対的に前のセクションが静かなアレンジとなるように工夫してみましょう。
自分たちのアカペラグループの楽譜は、自分でアレンジできるようになりましょう!
ぜひ、アカペラアレンジに挑戦してみてください。
アカペラの練習方法、アレンジについてさらに学びたい方は、アカペラパーフェクトブックシリーズを読んでみてください。アカペラの練習方法、アレンジ(楽譜作成)、ボイパ方法など、アカペラを行う上で必要な情報が網羅されており、アカペラ楽譜も収載しています。