・ジュンク堂書店が防犯カメラで来店者の顔認証データを撮っていることについて

とくに、NEWS PICKSというサイトで私のブログ記事を取り上げていただき、多くの方にコメントをいただいているようです。
・NEWS PICKSのジュンク堂書店に関する記事(閲覧には登録が必要)
そのなかで私が感じたことをいくつか書かせていただきます。
■関連するブログ記事
・プライバシー権からジュンク堂書店が来店者に無断で顔認証データを取得していることを考える
まず、コメント欄のトップで、成毛眞という方が、経営論の観点から、さまざまな数字を列挙して、ジュンク堂書店が断りなくすべての顧客から顔認証データを取得していることを擁護されいます。
しかし、成毛氏は、すべての顧客に断りをいれることは「めんどうくさい」と書かれていることには驚きます。成毛氏はプロフィール欄をみると、銀行の取締役などを歴任されている方のようですが、そのような社会的地位の方が、「法律なんかどうでもいい」というスタンスなのは驚きます。
企業が市場で生き残ってゆくために利潤を追求するのは当然ですが、企業市民としてコンプライアンスを遵守するのはその前提条件です。
法令違反による不祥事を起こすと、企業は行政処分や刑事罰などを受けるだけでなく、商品の不買運動、取引先・投資家からの信頼失墜などの企業の存亡に関わるリスクを負いかねません。
逆にコンプライアンスに真摯に取り組む企業はブランド価値が向上し、人材が集まり、従業員の士気が高まります(高巌『コンプライアンスの知識』37頁)。
たとえば2014年7月のベネッセの事件だけでなく、2012年11月の三菱東京UFJ銀行の560万件の個人情報漏洩事件など、金融業界も個人情報保護法に関連する事件と無縁ではありません。
成毛氏は、「顔認証がキライな来店客が10%減っても、万引きロスが半分の0.7%になるほうがはるかに合理的」と試算されています。
しかしそれがもし、「めんどくさい」として、個人情報保護法18条に基づく、「顔認証データを取得している」という利用目的の通知を行わないまま違法に実施されるのなら、ジュンク堂はワタミやすき家、ホリエモン氏の頃のライブドアのように、コンプライアンス意識の無いブラック企業の烙印を押され、より多くの顧客が離れてゆくのではないでしょうか。
現に、ネットで調べると、顔認証の問題に関しては、冤罪被害者の会が設立されており、それらの被害者を支援する弁護士による弁護団も結成されているようです。
・顔認証万引冤罪被害者の会
・顔認証万引冤罪被害者の弁護団
被害者の会と弁護団が結成されている以上、もしジュンク堂書店が利潤至上主義の経営を続けるのであれば、訴訟を提起されるリスクがあります。訴訟が提起されたという事実がマスコミにより報道されれば、大きな風評リスクが現実化するでしょう。
ジュンク堂書店や顔認証システム推進論者は、このような顔認証システムの冤罪被害者も企業の経済的効率性の観点から見て見ぬふりをするのでしょうか。
成毛氏は、顔認証がキライで去ってゆく客は10%と試算していますが、去ってゆく客は10%にとどまらず、ジュンク堂書店は市場からの退場を命じられる可能性があります。
なお、成毛氏は、顔認証システムよりもむしろ警察のNシステムを検討すべきだと主張しておられます。
しかし、Nシステムについては、刑事訴訟法と憲法13条(肖像権・プライバシー権)との調整が争点であったところ、合憲との最高裁判決がすでに出されています(最高裁平成15年11月27日判決)。
このようにNシステムについては司法的な結論が出ており、また、民間部門のジュンク堂の、しかも一般の防犯カメラでなく顔認証システムの問題に、公の機関の警察のNシステムの話を持ち出すのは、議論のすり替えです。争点となる法令もまったく異なるのですから。
つぎに、うえから2番目に荘司雅彦という弁護士の方のコメントがありました。要約すると、“そもそも防犯カメラは街中にあるし、そのデータを買い取っている「名簿屋」もいるかもしれないから、別にいいじゃないか”というものでした。
これは率直なところ驚いてしまいました。この方は本当に弁護士の方なのでしょうか?大ざっぱにいえば、「世の中には犯罪者は多いから、別にジュンク堂も犯罪しちゃっていいじゃん」と言っているように読めます。
なお、たしかに従来より名簿屋は問題視されてきたところであり、2015年9月に成立した改正個人情報保護法では、名簿屋対策として、①事業者が個人情報を第三者提供する際に記録を作成し保管すること(25条)、②受領する事業者も記録を作成し保管し、提供者による取得の経緯を確認しその記録を作成・保管すること(26条)、③直接的な罰則の創設(83条)、という制度が新設されました(日置巴美・板倉陽一郎『平成27年改正個人情報保護法のしくみ』80頁)。
この荘司氏は、弁護士なのに、ひょっとしてこのような法改正もご存じないのだろうかと思いました。
なお、先般のブログ記事でも追記しましたが、12月29日付で読売新聞に、このジュンク堂書店やワークマンの顔認証データ取得の問題をくわしく取り上げた記事が掲載されました。
・客に知らせず顔データ化…客層把握や万引き防止|読売新聞
この読売新聞の記事においては、個人情報保護法の改正のたたき台となった、内閣府IT総合戦略本部の「パーソナルデータに関する検討会」の委員を務められた森亮二弁護士はつぎのようなコメントをしておられました。
森亮二弁護士のコメント
『(通常の防犯カメラに比べて、)特定の個人を追跡する機能をもつ顔認識システムの方が肖像権やプライバシー侵害の度合いが強く、両者は区別する必要がある』
『(そのため、)顔認識システムを採用していることを明記し、嫌だと感じた人はその店を利用しないで済むようにするなど、透明性を確保することが大事だ』
『(通常の防犯カメラに比べて、)特定の個人を追跡する機能をもつ顔認識システムの方が肖像権やプライバシー侵害の度合いが強く、両者は区別する必要がある』
『(そのため、)顔認識システムを採用していることを明記し、嫌だと感じた人はその店を利用しないで済むようにするなど、透明性を確保することが大事だ』
成毛氏や荘司弁護士等は今一度この記事を読み直すべきです。
■関連するブログ記事
・全国の防犯カメラに映った万引き犯の映像を共有化するデータベースの構築は許されるのか?
・防犯カメラ・ウェブカメラの映像が「丸見え」な問題について/安全管理措置・保管期間
・【解説】個人情報保護法の改正法案について/ビッグデータ・匿名加工情報
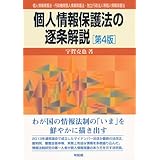 |
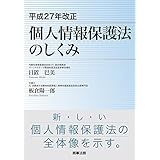 |
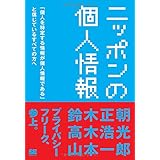 |
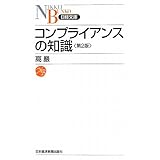 |
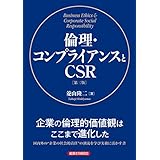 |
法律・法学 ブログランキングへ
にほんブログ村
