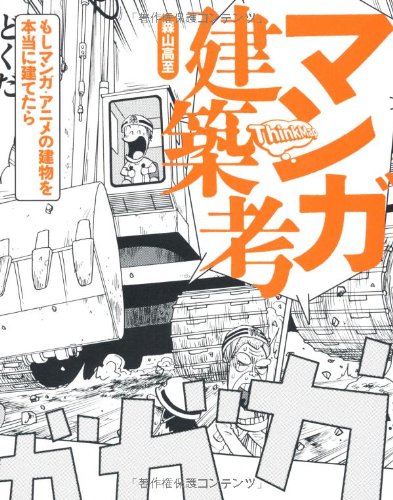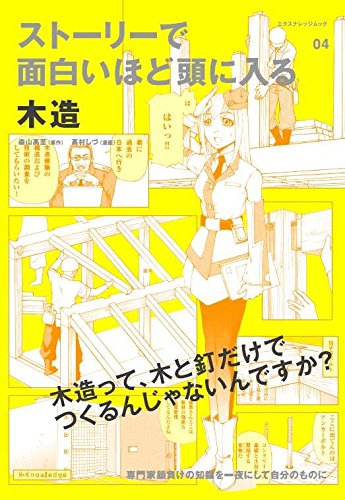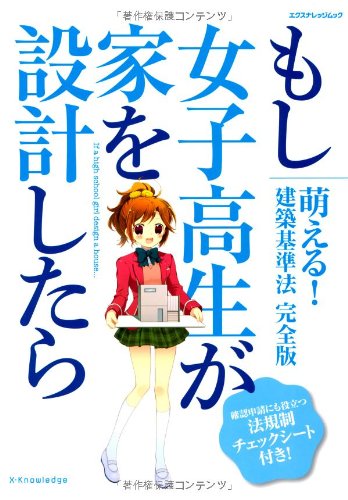東京中央卸売市場、「築地魚河岸」とはどういったものであるのか?の続きです。
「築地魚河岸三代目」というマンガ作品があります。
豊洲にはそれがないんです。
これまで見てきたように、築地市場というのは、ただ単に土地を指すとか建物を指すとかというものではありません。
魚河岸というのは長い間の先人の努力により魚の流通の仕組みを作り出した人的ネットワークのことです。
なぜ、そのような人的ネットワークが生まれたかというと、むろん「美味しい魚を楽しく食べるため」です。
それが、目に見えるカタチになったものが築地市場です。
かつては1400社、現在でも600社以上という、なぜ、いろんな仲卸さんが築地に居るのだと思います?
それは、我々の食文化と関係があります。
魚をいかに美味しく楽しく皆に届けるか、の追求の結果が築地にたくさんの魚を集め
美味しく、楽しいから、世界中からたくさんの人が集まるようになったんです。
築地には「おさかな普及センター」「おさかな資料館」という施設もありますが
http://www.osakana-center.com/top.html
活魚水槽のシムラさんのHPには晴らしいお魚情報のページがあります。ぜひ一度見てみましょう。
http://shimura.moo.jp
水産庁によれば、世界には25000種類の魚がいて、そのうち食用魚は3000種以上といわれています。外国では食用魚は700種、日本は2500種以上も食用としているのです。
海外に行くとすぐわかりますが、魚料理のレベルの違いです。
種類だけでなく、調理法や加工方法も多種多様であり、その包丁さばきや味加減で日本にかなう国はありません。
それだけ、魚の知識も豊富、料理も豊富というわけです。
それを支えているのが、築地の仲卸さんたちなんです!
大事なことなんでもう一回いいますよ。
日本の食文化を支えているのは、仲卸さんを中心とする魚食文化の知識と、人的ネットワークなんです!
だから、漁業生産者も卸会社も仲卸業者もスーパーや小売り、割烹、居酒屋、飲食店、最終消費者は仲違いしてはいけません。
豊洲の問題で互いが喧嘩してはいけません。
このネットワークの循環が切れたときに、日本の食文化は死にます。
それを断ち切り続けてきたのが、たかが数年前に見識も品性も低い一部の政治家と一部議員と不動産屋と建築屋による豊洲計画なんです。
まさにそういったテーマに取り組んだマンガ作品が「築地魚河岸三代目」なのです。
「築地魚河岸三代目」を見ながら解説していきたいと思います。
第1巻の口絵ですが、築地の雰囲気がよく出ていますよね。
仲卸の店が並び、ところ狭しと発泡が積み重なっている。
この作品の連載が始まったのはちょうど2000年、今から16年前ですが、この頃から仲卸しさん減り始めていましたが、まだ1000社もありました。
このスーツをねじりはちまきに変えた男が三代目、旬太郎です。
旬太郎が飛び込んだ築地仲卸の世界はとっても厳しいものなのですが、それなりに頑張って素直さがあれば、一方とても暖かいところでもある。
同世代の先輩にいつも小言を言われています。
ところが、彼は築地でも一二を争う、魚の目利きなのです。
「特殊物」といって、寿司屋さん向けの魚を販売しています。
それも、厳選された商品を、違いの分かる人にだけ売るような。
主人公のライバル三代目なのです。
サケ専門の仲卸さんも出てきます。
カニ専門、マグロの切り身のサク(柵と書きます)専門
乾物の専門目利き
貝は貝専門の貝屋さんが居ます。
フグ専門の仲卸さんなんか、すっごく厳しいです。
数寄屋や茶室の大工の棟梁と同じですねえ。
食品を扱うことは、食べる方にも食べられる方にも命を扱うことだ!と、気が抜けねえんんだ、このフグの仲卸さんはおっしゃっています。
あと、魚河岸がただの流通倉庫ではないんだ、というのがお客さんに合わせて、魚の準備をしていることです。
魚河岸はいってみれば調理場の延長線上にあるのです。
同時に漁場ともつながっている。
豊洲の施設では、そういった配慮が圧倒的に欠けています。
だから!豊洲では「マグロが切れねえ」なんて間抜け話になるのです。
TV取材でマグロ屋さんが怒ってらっしゃいましたよね。
マグロが置けない
マグロが切れない
なんということでしょう。
マグロはデカい
解体包丁は日本刀みたいなもの
3人、4人がかり
この切り方ひとつでマグロの価値が変わる。
銘木の丸太の製材は、どこでどう切るかによって,
木目が活かせるかどうかによって、
せっかくの丸太の樹の価値が変わるのですが、
それと同じか、それ以上、一発勝負の真剣勝負なのです。
大変な作業です。
で、これが豊洲市場で準備したとか言ってる、仲卸さんの部屋。
絶対無理です。
わかっていない。
机上、
現場を見もしないで、パソコンの上でライン引いただけ。
この詰め込み感、マンガ喫茶かよ!マンガ喫茶のブースかよ!
あのなあ、オフィスブースの机の上にパソコン置くようなわけにはいかないんだよ。
豊洲施設を設計した日建設計の実力とやらを見せてもらった気がします。
このままいくと、英二さんも廃業です。
なぜなら、バカ設計によるスペースだけの問題じゃないんです。
⑬に続く
「築地魚河岸三代目」というマンガ作品があります。
築地で働く人達と魚を美味しく食べることをテーマにした作品です。
主人公の赤城旬太郎は銀行マン。妻の実家が築地の仲卸「魚辰」を、銀行を辞め継ぐことになりました。食いしん坊であること以外、魚について取り柄が無い、魚のことなんてなんにも知らない旬太郎が、持ち前の食い意地と、人への優しさから、立派な仲卸として成長していくことを通じ、日本の魚や料理について学ぶことが出来るという作品です。
いろんな巻がありますが、その中で描かれているのは、作者の一種一種、一尾一尾の魚に対する愛と漁業への造詣の深さ、働く方々への尊敬と誇りです。
この作品を読めば
豊洲施設には圧倒的に抜けている部分。
抜けているどころか初めから入れていなかった、考慮していなかった、魚河岸へのリスペクト
豊洲市場計画の失敗は必然だということが理解できるでしょう。
今から80年前の日本橋から築地の移転にはそれが在った。
主人公の赤城旬太郎は銀行マン。妻の実家が築地の仲卸「魚辰」を、銀行を辞め継ぐことになりました。食いしん坊であること以外、魚について取り柄が無い、魚のことなんてなんにも知らない旬太郎が、持ち前の食い意地と、人への優しさから、立派な仲卸として成長していくことを通じ、日本の魚や料理について学ぶことが出来るという作品です。
いろんな巻がありますが、その中で描かれているのは、作者の一種一種、一尾一尾の魚に対する愛と漁業への造詣の深さ、働く方々への尊敬と誇りです。
この作品を読めば
豊洲施設には圧倒的に抜けている部分。
抜けているどころか初めから入れていなかった、考慮していなかった、魚河岸へのリスペクト
豊洲市場計画の失敗は必然だということが理解できるでしょう。
今から80年前の日本橋から築地の移転にはそれが在った。
豊洲にはそれがないんです。
魚河岸というのは長い間の先人の努力により魚の流通の仕組みを作り出した人的ネットワークのことです。
なぜ、そのような人的ネットワークが生まれたかというと、むろん「美味しい魚を楽しく食べるため」です。
それが、目に見えるカタチになったものが築地市場です。
かつては1400社、現在でも600社以上という、なぜ、いろんな仲卸さんが築地に居るのだと思います?
それは、我々の食文化と関係があります。
魚をいかに美味しく楽しく皆に届けるか、の追求の結果が築地にたくさんの魚を集め
美味しく、楽しいから、世界中からたくさんの人が集まるようになったんです。
築地には「おさかな普及センター」「おさかな資料館」という施設もありますが
http://www.osakana-center.com/top.html
活魚水槽のシムラさんのHPには晴らしいお魚情報のページがあります。ぜひ一度見てみましょう。
http://shimura.moo.jp
水産庁によれば、世界には25000種類の魚がいて、そのうち食用魚は3000種以上といわれています。外国では食用魚は700種、日本は2500種以上も食用としているのです。
海外に行くとすぐわかりますが、魚料理のレベルの違いです。
種類だけでなく、調理法や加工方法も多種多様であり、その包丁さばきや味加減で日本にかなう国はありません。
それだけ、魚の知識も豊富、料理も豊富というわけです。
日本が育み、伝え残してきた文化はたくさんありますが、その中でも圧倒的に突出しているのが、魚料理です。
それを支えているのが、築地の仲卸さんたちなんです!
大事なことなんでもう一回いいますよ。
日本の食文化を支えているのは、仲卸さんを中心とする魚食文化の知識と、人的ネットワークなんです!
だから、漁業生産者も卸会社も仲卸業者もスーパーや小売り、割烹、居酒屋、飲食店、最終消費者は仲違いしてはいけません。
豊洲の問題で互いが喧嘩してはいけません。
このネットワークの循環が切れたときに、日本の食文化は死にます。
それを断ち切り続けてきたのが、たかが数年前に見識も品性も低い一部の政治家と一部議員と不動産屋と建築屋による豊洲計画なんです。
まさにそういったテーマに取り組んだマンガ作品が「築地魚河岸三代目」なのです。
「築地魚河岸三代目」を見ながら解説していきたいと思います。
第1巻の口絵ですが、築地の雰囲気がよく出ていますよね。
仲卸の店が並び、ところ狭しと発泡が積み重なっている。
この作品の連載が始まったのはちょうど2000年、今から16年前ですが、この頃から仲卸しさん減り始めていましたが、まだ1000社もありました。
このスーツをねじりはちまきに変えた男が三代目、旬太郎です。
旬太郎が飛び込んだ築地仲卸の世界はとっても厳しいものなのですが、それなりに頑張って素直さがあれば、一方とても暖かいところでもある。
同世代の先輩にいつも小言を言われています。
ところが、彼は築地でも一二を争う、魚の目利きなのです。
「特殊物」といって、寿司屋さん向けの魚を販売しています。
それも、厳選された商品を、違いの分かる人にだけ売るような。
主人公のライバル三代目なのです。
サケ専門の仲卸さんも出てきます。
カニ専門、マグロの切り身のサク(柵と書きます)専門
乾物の専門目利き
貝は貝専門の貝屋さんが居ます。
築地は都営ですから、当然東京都の職員さんも居ます。
フグ専門の仲卸さんなんか、すっごく厳しいです。
数寄屋や茶室の大工の棟梁と同じですねえ。
食品を扱うことは、食べる方にも食べられる方にも命を扱うことだ!と、気が抜けねえんんだ、このフグの仲卸さんはおっしゃっています。
あと、魚河岸がただの流通倉庫ではないんだ、というのがお客さんに合わせて、魚の準備をしていることです。
魚河岸はいってみれば調理場の延長線上にあるのです。
同時に漁場ともつながっている。
豊洲の施設では、そういった配慮が圧倒的に欠けています。
だから!豊洲では「マグロが切れねえ」なんて間抜け話になるのです。
TV取材でマグロ屋さんが怒ってらっしゃいましたよね。
マグロが置けない
マグロが切れない
なんということでしょう。
マグロはデカい
解体包丁は日本刀みたいなもの
3人、4人がかり
この切り方ひとつでマグロの価値が変わる。
銘木の丸太の製材は、どこでどう切るかによって,
木目が活かせるかどうかによって、
せっかくの丸太の樹の価値が変わるのですが、
それと同じか、それ以上、一発勝負の真剣勝負なのです。
大変な作業です。
で、これが豊洲市場で準備したとか言ってる、仲卸さんの部屋。
絶対無理です。
わかっていない。
机上、
現場を見もしないで、パソコンの上でライン引いただけ。
この詰め込み感、マンガ喫茶かよ!マンガ喫茶のブースかよ!
あのなあ、オフィスブースの机の上にパソコン置くようなわけにはいかないんだよ。
豊洲施設を設計した日建設計の実力とやらを見せてもらった気がします。
このままいくと、英二さんも廃業です。
なぜなら、バカ設計によるスペースだけの問題じゃないんです。
⑬に続く