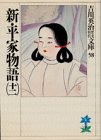讃岐屋島の合戦でも追い詰められた平家。頼みにしていた援軍にも裏切られ、源氏に囲まれて孤立する中、平教経はつぶやきます。
「おもしろい。おもしろいほど、事ごとに食い違ってくる。不運とは、こうしたものか。どこまで、人と運とがもつれあうか、もてあそばれて行くものか、あまんじて不運と闘ってみるのも愉しくないことはない。どうせ落ち目の運命ならば、この落日のように、荘厳でありたいものだ。」
(吉川英治、『新・平家物語(十三)』より)
昔、大学生の時、物理がちんぷんかんぷんで苦しんでいたことがありました。
友達が、毎回、平然と講義を受けていたので、聞いてみたことがありました。
「講義の内容、分かるん?」
「全然。」
「でも、あんまり、あせってないよね。」
「分からないことを楽しむんよ。」
「分からないことを楽しむ」…。分かったような分からないような、なんだか騙されたような受け答えをされましたが、もしかしたら、教経の「あまんじて不運と闘ってみるのも愉しくないことはない」に通じるところがあるのかもしれません。
分からないことも、不運も、長い人生にはつきものです。それを楽しむような余裕をもちたいなあ。