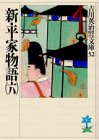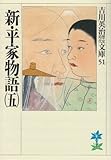これほどな人びとが、これほど心をいためても、一個の人間の死を、どうにもならぬ
(吉川英治、『新・平家物語(六)』より)
世の医師がさじを投げてしまった平清盛の容態。おびただしいほどの平家人が、その安否を案じ、見守っていても、それでも清盛一人の命を救うことができません。
ディズニーのアニメ「アラジン」には、何でも願いを叶えてくれる魔法のランプの精が出てきますが、その力をもっても叶えられないことが3つあるそうです。
ひとつは、「人を殺めること」。ひとつは「死んだ人を生き返らせること」。ひとつは「人の心を変えること」。
どんな力をもってしても、人の生き死にを自由にはできない。言い換えれば、それほど命は崇高なものなのです。一世を風靡した平家ではあるけれども、人の力が絶対とはならない。これも、「おごれる者も久しからず」を表しているように思えます。
 |
新・平家物語(八) (吉川英治歴史時代文庫)
850円
Amazon |