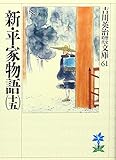『新・平家物語』のもう一人の主人公、それは一人の庶民・麻鳥だと思います。
清盛、義経、頼朝と、名だたる者たちが活躍し、そして消えていきました。
しかし、無力な麻鳥と蓬(よもぎ)の夫婦は争いの世に踏み殺されもせず、今、吉野山の桜を見ながら、若草の上に腰をおろし、静かにゆっくりと時を楽しんでいました。
「何が人間の、幸福かといえば、つきつめたところ、まあこの辺が、人間のたどりつける、いちばんの幸福だろうよ。これなら人もゆるすし、神のとがめもあるわけはない。そして、たれにも望めることだから」
(吉川英治、『新・平家物語(十六)』より)
貧しいながらも人と人とが思い合って暮らす尊さ。
主人公の一人、義経は、それを望みながらも、世がそれを妨げました。そこに哀しさがありました。
麻鳥は、位階や権力とは無縁の中で、自分らしく生き、そこにあたたかさがありました。
立場も人生も全く異なる二人が、この軍記物語を、ただの権力争いの物語ではなく、喜びも哀しみも、愚かさも尊さも伝える人間の物語に高めている、そう感じました。
 |
新・平家物語(十六) (吉川英治歴史時代文庫)
850円
Amazon |