中学英語を完成させる(1)
高卒認定までの話を書いてきましたが、ここからは“その後”のお話。
その後、どんな勉強をすればいいか?
たとえばいきなり予備校に行って、ついていけるのだろうか?
高認を終えた人は、喜びもつかの間、そんな悩みの中に放り込まれます。
そもそも同じ『高卒認定に合格した』という人でも
小・中とずっと不登校だった人が、15歳で全教科受けた(認定されるのは18歳でも、受けて単位を取得することは可能)場合
と
高三になって高校をやめた人が、1教科だけ受けた場合
と
高校をやめて何年もたつ人が、数教科受けた場合
では、モトの学力に大きな差があるはずです。
合格ラインが低いので、ただ『受かった』という人の学力が横並びなはずもなく、
『ギリギリ、たまたま受かった』
『ほぼパーフェクトだった』
という人の差はとても大きいです(そういう試験なので)。
ここでは、『高校にそもそも(ほとんど)行っていない』人や、『学業からかなりの間離れていて、ほとんど忘れてしまった』人が、『ギリギリ、たまたま受かった』あと、
どうやってスタートラインまで学力を持っていくか?
に焦点を当て(何故なら、私がその立場だったからです)、書いていきたいと思います。
特に英語は“出来ない人は本当に出来ず、それを『出来る人』には理解しにくい”ので、スタートのスタートから躓きやすく、『どうやって勉強したらいいかわからない』というパターンに陥りがちです。
まずはこの『英語をどうしたらいいか』を、複数回に分けて書きたいと思います。
ただし特殊な事情で学力が低い場合(LDなどの発達障害を持つ等)は想定していないので、もしそういった事情で学力に不安がある場合は、既成の“勉強の仕方”に囚われず、塾や予備校よりも先に専門機関に相談した方が良いと思われます。
こういった教育相談は子供のものと思われがちですが、16歳以上でも受け入れている機関が多くあります(東京都であればTOSCAなど)。
目安としては、偏差値30以下~50の、基礎学力(読み・書き・聞く・話す)に大きな問題のない人、が対象になります。
あるいはそれ以上でも、『読めないことも無いんだけど、詳しいことを問われるとわからない』人です。(私がこれでしたが、ぶっちゃけ、読めてる気がしているだけで全然読めてません。笑)
高認の勉強とかなり被りますが、最終的に“志望校の過去問が解ける”まで持っていく必要があるため、少し低いところから始めても最終的にはもっと高いところを目指す勉強になります。高認勉強法で書いていたような“数日から一か月ぐらいでとりあえず受かる”ものではありません。
手っ取り早い方法では無く、堅実で地味な勉強をすることになります。
中学英語を完成させる(2)に続きます。

にほんブログ村
その後、どんな勉強をすればいいか?
たとえばいきなり予備校に行って、ついていけるのだろうか?
高認を終えた人は、喜びもつかの間、そんな悩みの中に放り込まれます。
そもそも同じ『高卒認定に合格した』という人でも
小・中とずっと不登校だった人が、15歳で全教科受けた(認定されるのは18歳でも、受けて単位を取得することは可能)場合
と
高三になって高校をやめた人が、1教科だけ受けた場合
と
高校をやめて何年もたつ人が、数教科受けた場合
では、モトの学力に大きな差があるはずです。
合格ラインが低いので、ただ『受かった』という人の学力が横並びなはずもなく、
『ギリギリ、たまたま受かった』
『ほぼパーフェクトだった』
という人の差はとても大きいです(そういう試験なので)。
ここでは、『高校にそもそも(ほとんど)行っていない』人や、『学業からかなりの間離れていて、ほとんど忘れてしまった』人が、『ギリギリ、たまたま受かった』あと、
どうやってスタートラインまで学力を持っていくか?
に焦点を当て(何故なら、私がその立場だったからです)、書いていきたいと思います。
特に英語は“出来ない人は本当に出来ず、それを『出来る人』には理解しにくい”ので、スタートのスタートから躓きやすく、『どうやって勉強したらいいかわからない』というパターンに陥りがちです。
まずはこの『英語をどうしたらいいか』を、複数回に分けて書きたいと思います。
ただし特殊な事情で学力が低い場合(LDなどの発達障害を持つ等)は想定していないので、もしそういった事情で学力に不安がある場合は、既成の“勉強の仕方”に囚われず、塾や予備校よりも先に専門機関に相談した方が良いと思われます。
こういった教育相談は子供のものと思われがちですが、16歳以上でも受け入れている機関が多くあります(東京都であればTOSCAなど)。
目安としては、偏差値30以下~50の、基礎学力(読み・書き・聞く・話す)に大きな問題のない人、が対象になります。
あるいはそれ以上でも、『読めないことも無いんだけど、詳しいことを問われるとわからない』人です。(私がこれでしたが、ぶっちゃけ、読めてる気がしているだけで全然読めてません。笑)
高認の勉強とかなり被りますが、最終的に“志望校の過去問が解ける”まで持っていく必要があるため、少し低いところから始めても最終的にはもっと高いところを目指す勉強になります。高認勉強法で書いていたような“数日から一か月ぐらいでとりあえず受かる”ものではありません。
手っ取り早い方法では無く、堅実で地味な勉強をすることになります。
中学英語を完成させる(2)に続きます。
にほんブログ村
『かいじゅうたちのいるところ』実写映画化
えええええ
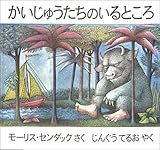
この絵本、読んだことが無くてもどこかで見かけたことはある方が多いと思うのですが、2010年1月開始で映画化するんですね。びっくり。(→映画公式HP※予告編ムービーが始まります)
子供のころ大好きだった絵本の一つなので、これはどんな評価でも中身でも観に行かないと。。
やさいのようせいみたいなCGムービーになったらいいなあと思っていたのだけど、実写かー。予告編見たら思ったより違和感が無かったし、私の森好き(海より山的な意味で)はたぶんこのへんから来てるので、そのあたりも楽しみです。
しかし1月か……いや、でも、きっと元気がもらえる筈。前売りストラップほしいし!
でもこういうのに限らず、ストラップってつい集めちゃうんだけど実際には使い道に困るんだよなー。
1つのものにジャラジャラつけるのは苦手なので、ペンケースにつけたりパスケースにつけたり、手帳につけたりしてるけど、こう他に何かいい使い道は無いものか。
とか悩むのはわかってるけど、でも、ほしい……。
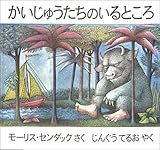
この絵本、読んだことが無くてもどこかで見かけたことはある方が多いと思うのですが、2010年1月開始で映画化するんですね。びっくり。(→映画公式HP※予告編ムービーが始まります)
子供のころ大好きだった絵本の一つなので、これはどんな評価でも中身でも観に行かないと。。
やさいのようせいみたいなCGムービーになったらいいなあと思っていたのだけど、実写かー。予告編見たら思ったより違和感が無かったし、私の森好き(海より山的な意味で)はたぶんこのへんから来てるので、そのあたりも楽しみです。
しかし1月か……いや、でも、きっと元気がもらえる筈。前売りストラップほしいし!
でもこういうのに限らず、ストラップってつい集めちゃうんだけど実際には使い道に困るんだよなー。
1つのものにジャラジャラつけるのは苦手なので、ペンケースにつけたりパスケースにつけたり、手帳につけたりしてるけど、こう他に何かいい使い道は無いものか。
とか悩むのはわかってるけど、でも、ほしい……。
記憶療法の可能性
昨日、ためしてガッテンで記憶についてやっていた。
正確には『記憶脳を刺激する!最新科学ワザ』というタイトルで、主に高齢者の「物忘れ」「ど忘れ」という現象に焦点をあてている。が、記憶のメカニズムはヒトである以上老若男女同じなので、子供だろうと大人だろうと関係なく同じことが言えるのだろう。
さて、この番組を見ていて思い出したのが記憶療法だった。
大まかにいえば記憶術や記憶法を使い、脳(記憶機能)のリハビリと、自己評価の向上・精神の安定を得るのが目的の心理療法だ。
※抑圧され忘れていた記憶を取り戻す類のものとは、名称が似ているがかなり性質を異にする
私がどんな経緯でこれを知ったのかよく覚えていないが、時系列で考えると、自分なりに当時の状況から抜け出したくて調べたのかもしれない。
それはともかく、今調べても記憶療法についてはこの勝俣氏しかヒットせず、氏の消息はともかく現在記憶療法そのものがどうなっているのかはよくわからない。恐らく“脳トレ”ブームに吸収されたのだろうと思うが、これはただの憶測である。
何故突然『記憶療法』を思い出したのかと言うと、ガッテンの“記憶力を取り戻した”という人々の顔が、本当に嬉しそうで晴れやかだったからだ。
憶えておきたいことを憶え、思い出したいものを思い出す。
ただそれだけで人生に光が差すということは、確かにあるのかもしれない。
私も現在この方のblog記事や本を読んだり記憶法セミナーを受講したり、他色々な書物に手を出したり、自身で試行錯誤して下手すると勉強そのものよりも『記憶とは何か』に触れているが、『勉強する』行為そのものではなく『アタマの使い方を知り、使う』という行為がいかに快体験なのかを、身をもって実感している。
私は“アタマがいい”という現象を(何故現象と呼ぶかはここではおいておく)、以前は“元からアタマを使える”ということだと、思い込んでいた。
私自身はIQテストなどでは比較的高数値を出していたが、“アタマがいい”と自分のことを思ったことは一度もなく、どちらかといえば、愚鈍で無知蒙昧な底辺の人間だというセルフイメージが強かったのである。
おかげで、稀に「君はアタマが良いから」と言われると、“お前はアタマがおかしくて理解できない”と拒絶されたようでいたく傷ついたものだ(要するに、皮肉に聞こえていた)。何というか、これこそアタマの悪い話である。
さすがに今現在は、「まあ、マシなほうだろう」ぐらいにはなっている。少なくとも学力に関してはある程度の自信(ポテンシャルに対するものだが)を持ち、アタマの良い悪いは考えもしなくなった。
今はどちらかと言えば、アタマの使い方について考える日々だ。
アタマの“使い方”に必要なのはテクニックであり、ツールなのだと思う。
そのうちの一つが(あるいはかなりの領域をカバーしているのが)“記憶”の分野だろう。
先の記憶療法で、一番効果が出るのは恐らく『自分は頭が悪い』といったような自己評価の低い人で、後は努力するしかないと悲壮な覚悟により頑張り過ぎて疲弊したり、あるいは色々と諦めてしまった人なのかもしれない。
『記憶』し『テスト』する。点数はあくまでも結果だが、思い出せた!ということそのものが成功体験なのだから、日常的に積み重ねやすい。成功体験を積み重ねることで自己評価は上がり、それは自信と安定に繋がるだろう。
塾や学校で同じような効果を結果として得る事もあるかもしれないが、通う人(通わせる親)はそれだけを求めているわけではあるまい。
その効果のみを求め、“療法”として確立することに何らかの可能性を感じている。
……それにしても、このガッテン、たまに見ているしHPもチェックすることが多いものの、進行がどうしても“タルい”ので集中して見るのが少し辛い。バラエティとしての体裁と、幅広い層に合わせてある作りなのだから仕方ないが。
まあ還暦の母や90近い祖母すら早回しで見ていることが多いので、ひょっとしたらただじっと座って見ていられない血筋なだけかもしれないが……。
正確には『記憶脳を刺激する!最新科学ワザ』というタイトルで、主に高齢者の「物忘れ」「ど忘れ」という現象に焦点をあてている。が、記憶のメカニズムはヒトである以上老若男女同じなので、子供だろうと大人だろうと関係なく同じことが言えるのだろう。
さて、この番組を見ていて思い出したのが記憶療法だった。
大まかにいえば記憶術や記憶法を使い、脳(記憶機能)のリハビリと、自己評価の向上・精神の安定を得るのが目的の心理療法だ。
※抑圧され忘れていた記憶を取り戻す類のものとは、名称が似ているがかなり性質を異にする
私がどんな経緯でこれを知ったのかよく覚えていないが、時系列で考えると、自分なりに当時の状況から抜け出したくて調べたのかもしれない。
それはともかく、今調べても記憶療法についてはこの勝俣氏しかヒットせず、氏の消息はともかく現在記憶療法そのものがどうなっているのかはよくわからない。恐らく“脳トレ”ブームに吸収されたのだろうと思うが、これはただの憶測である。
何故突然『記憶療法』を思い出したのかと言うと、ガッテンの“記憶力を取り戻した”という人々の顔が、本当に嬉しそうで晴れやかだったからだ。
憶えておきたいことを憶え、思い出したいものを思い出す。
ただそれだけで人生に光が差すということは、確かにあるのかもしれない。
私も現在この方のblog記事や本を読んだり記憶法セミナーを受講したり、他色々な書物に手を出したり、自身で試行錯誤して下手すると勉強そのものよりも『記憶とは何か』に触れているが、『勉強する』行為そのものではなく『アタマの使い方を知り、使う』という行為がいかに快体験なのかを、身をもって実感している。
私は“アタマがいい”という現象を(何故現象と呼ぶかはここではおいておく)、以前は“元からアタマを使える”ということだと、思い込んでいた。
私自身はIQテストなどでは比較的高数値を出していたが、“アタマがいい”と自分のことを思ったことは一度もなく、どちらかといえば、愚鈍で無知蒙昧な底辺の人間だというセルフイメージが強かったのである。
おかげで、稀に「君はアタマが良いから」と言われると、“お前はアタマがおかしくて理解できない”と拒絶されたようでいたく傷ついたものだ(要するに、皮肉に聞こえていた)。何というか、これこそアタマの悪い話である。
さすがに今現在は、「まあ、マシなほうだろう」ぐらいにはなっている。少なくとも学力に関してはある程度の自信(ポテンシャルに対するものだが)を持ち、アタマの良い悪いは考えもしなくなった。
今はどちらかと言えば、アタマの使い方について考える日々だ。
アタマの“使い方”に必要なのはテクニックであり、ツールなのだと思う。
そのうちの一つが(あるいはかなりの領域をカバーしているのが)“記憶”の分野だろう。
先の記憶療法で、一番効果が出るのは恐らく『自分は頭が悪い』といったような自己評価の低い人で、後は努力するしかないと悲壮な覚悟により頑張り過ぎて疲弊したり、あるいは色々と諦めてしまった人なのかもしれない。
『記憶』し『テスト』する。点数はあくまでも結果だが、思い出せた!ということそのものが成功体験なのだから、日常的に積み重ねやすい。成功体験を積み重ねることで自己評価は上がり、それは自信と安定に繋がるだろう。
塾や学校で同じような効果を結果として得る事もあるかもしれないが、通う人(通わせる親)はそれだけを求めているわけではあるまい。
その効果のみを求め、“療法”として確立することに何らかの可能性を感じている。
……それにしても、このガッテン、たまに見ているしHPもチェックすることが多いものの、進行がどうしても“タルい”ので集中して見るのが少し辛い。バラエティとしての体裁と、幅広い層に合わせてある作りなのだから仕方ないが。
まあ還暦の母や90近い祖母すら早回しで見ていることが多いので、ひょっとしたらただじっと座って見ていられない血筋なだけかもしれないが……。