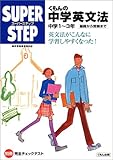インフルエンザ疑惑
結論から言えば、家族は陰性でした。
良かったーという思いと、ただの風邪でもかなりの熱を出して苦しんでいたので、特効薬も何もないのが逆に困ったものでもあります。
今は薬で症状が落ち着いているみたいだけど、風邪薬って基本的にただ症状を和らげるだけだからなあ。
数日経ってからやっぱりインフルエンザでしたー!ということもあるので、油断できません。
今日明日はグッと冷え込むみたいだから気をつけないといけません。
ようやく加湿器を出しました。ちょっと遅かったかなー。
良かったーという思いと、ただの風邪でもかなりの熱を出して苦しんでいたので、特効薬も何もないのが逆に困ったものでもあります。
今は薬で症状が落ち着いているみたいだけど、風邪薬って基本的にただ症状を和らげるだけだからなあ。
数日経ってからやっぱりインフルエンザでしたー!ということもあるので、油断できません。
今日明日はグッと冷え込むみたいだから気をつけないといけません。
ようやく加湿器を出しました。ちょっと遅かったかなー。
中学英語を完成させる(4)
中学英語を完成させる(3)の続きです。
前回
白紙の紙・参考書・辞書
を用意してくださいと書きましたが、準備するものは、実は他にもあります。
それは『勉強する環境』であり、『やる気』です。
家でやるなら、自分の机周りを。
外でやるなら、どこでやるか等。
“集中して出来る勉強場所の確保”が必要です。
特に気が散りやすい人は、どうしたら自分が集中できるか?を、自分で知る必要があります。
視覚的な刺激に弱い人は、『前』と『左右』を模様が何もないもの(ボール紙など)で塞ぐ等をします。コの字型の屏風のようなものを、机の上に立てるわけです。
※こういったものは市販もされていたと思うのですが、それなりに高かったと記憶しています。
これ以上のことは今回の範疇ではないので避けますが、ADHDなどの人に向けたノウハウなどが、実は多数の人の集中力向上になる、ということはよくあるので興味ある人は調べてみるといいかもしれません。
特定の刺激に対する過敏さ、というのは人それぞれなので、蛍光灯やコントラストがまぶしいという人は遮光眼鏡(サングラスのようなものです)を使用することもあります。
私は先天的に目が弱いこともあり、緑色の物を勉強用に使用しています。さすがに人前では怪しいので家でのみの使用ですが、この眼鏡を利用することで一部の余計な光をカットし、視覚情報が取りこみやすくなるので、学習効率が格段に向上したと感じています。
それでは、勉強の中身に入ります。
まず『最初の一歩』として、この『一冊の参考書』を完璧にします。
何故たった一冊なのかと言えば、勉強したいけど勉強に慣れていない、という人の特徴として
参考書を買ったはいいものの、最初の数Pしか手をつけないまま、ほったらかし
で、そのちょっとしかやっていない本が何冊もあったりします。必要な部分しかやらない、と決めて買った本ならそれでいいのですが、大体の参考書は『全部やる』ことではじめて身に付くものなので、「ちょっとやっただけ」ではピンポンダッシュするようなものです。
中身(学力)が「はーい」と出てくる頃に、その場から離れてしまっているのです。
一冊目をせっかく選んだのだし、たった一冊なのだから(しかも中学生用!)、ちゃっちゃと全部やっちゃいましょう。
参考書は、最初のstep(または章)から始めます。
ちゃんとした『中学生用』なら、アルファベットから始まるはずです。ここは飛ばし――ません。
稀にアルファベットが間違っている人がいるので、大文字小文字も一応確認してください。
バカじゃないの?というぐらい簡単かもしれませんが、5秒で終わってもいいのでとにかく『やってから次に進む』ことが大切です。
筆記体が書けない人は、無理に筆記体で書かなくても大丈夫です。
例えばアルファベットなら、とりあえず書いてみて(えーびーしーでーと歌いながらでも)、書き終わったら次に進みます。
白い紙には、出てきた単語・例文を全部書きます。
何故全部かというと、これまで英語を殆どやってこなかった人は
『英語を書く力』と『日本語を書く力』
が圧倒的に足りていないので、答案を書くのにすごーく時間がかかります。
単語を一つ書くのにモタモタ、綴りに自信がなくてモタモタ、書き間違えて消してモタモタ……これではいくら問題を解く力があっても、時間が足りなくなります。
『でもマークシートだし……』という人は、ちょっと甘いです。
単語も熟語も“見るだけでいい”という段階の人は、もう既にかなり学力がついているからこそ“見るだけでいい”んです。既に蓄積があるのです。
とにかく、最終的には一分一秒を争わなくてはならないので、『手』を作らなければいけません。
そしてそのためには結局、『沢山書く』しかなく、そのためだけの時間を作るのはもったいないので『書きながら』勉強した方が効率が良い、ということになります。
なので
『読みやすい字をなるべく速く書く』練習
だと思って書いてください。この『読みやすい』が大事なところで、『読めない字を速く書く』のでは駄目です。採点者に読めない字は“採点不能”となり、たとえ本人なりに合っていても不正解になります。
※自分でかなり後になってから復習する時もチョー困ります
また、英文(または英単語)を書くときは一度しっかり見たら、例文から目を離して、白い紙と自分の字だけを見て書いてください。(このあたりは茂木健一郎氏の脳を活かす勉強法に詳しかった気がしますが、この本が今手元に無いので詳しいことは不明…)
さて、出てきた英文が白い紙に書いてあると思いますが、その中からとりあえず
『新しい単語』
『わからない単語』
『わかっているはずなのに、その文での役割(意味)がわからなかった単語』
を
『紙』から『ノート』に
書き写して下さい。(この時も『一度見て憶え、何も見ないで書く』というのを忘れずに)
これでこのノートが“マイ単語帳”になります。
単語の勉強がしたくなったら、この段階ではこの“マイ単語帳”から学ぶようにしてください。
ある程度勉強が進んでいる人は書く単語も少ないので、すぐ終わるはずです。
その時点の内容が曖昧だったり、初めて触れる場合、ページの単語がほとんど載っているはずです。
中学の時点で出てくる単語は全て重要なので、安心して憶えてください。
単語の“憶え方”には色々あるので、自分に合う方法を探し、良さそうなものはどんどん試してみてください。
単語を憶えるときに注意することは、発音も大事だということです。
どう発音したらいいかわからないものは、すぐ調べてください。
『音』がわからない『コトバ』を憶えるのは、すごくすごく大変です。
もちろん適当に読んでゴロ合わせしてもいいのだけど、さすがに中学英語の段階では、たとえゴロで憶えていても一緒に発音も憶えてください。
えーと、
Student
を
「スツデント学生でんねん」
と憶えてもいいんだけど、正しい発音も一緒に憶える、ということです。
これは“出来れば”ではなく“絶対に”です。
綺麗な発音が実際には出来なくてもいいのだけど(口の構造を英語の発音用に変えるのは、手を作るより時間がかかります)、頭の中で音を再生するときは、正確な発音にしてください。
このとき、発音記号にも注目してください。
出来れば発音記号については別に時間を取り、これだけを学習してみてください。
最初は、綴りと発音だけを憶える(綴りながら言う、綴りを見て言う、言ってから綴る)
次は、発音と意味
意味と綴り
最終的には
日本語からもパッと英語(音)が出るし、書ける。
英語からパッと和訳が出る。
ここが目標ラインです。
次にの目標ラインには、自動詞か他動詞ではどうか、数えられるかどうか、ヒトに使われるものか、という分類を覚えたり、活用、類義語、反対語、言い換え、語源など色々とあるのですが、それらは文法を学習する過程で
『何故そんな分類があるのか?』
が理解できてからでOKです。
自動詞&他動詞というものがわからない段階で、この単語は自動詞ではこう、他動詞ではこういう意味になる、なんて憶えるのは厳しいです。
○○の時は××になる、というものについては、○○の部分を先に学習して、理解出来たらそういう視点を持って新しい単語・今までの単語にあたって下さい。
逆にいえば、『新しい視点』が出来たら、すぐに今までの単語を復習するようにしてください。
(5)に続きます
前回
白紙の紙・参考書・辞書
を用意してくださいと書きましたが、準備するものは、実は他にもあります。
それは『勉強する環境』であり、『やる気』です。
家でやるなら、自分の机周りを。
外でやるなら、どこでやるか等。
“集中して出来る勉強場所の確保”が必要です。
特に気が散りやすい人は、どうしたら自分が集中できるか?を、自分で知る必要があります。
視覚的な刺激に弱い人は、『前』と『左右』を模様が何もないもの(ボール紙など)で塞ぐ等をします。コの字型の屏風のようなものを、机の上に立てるわけです。
※こういったものは市販もされていたと思うのですが、それなりに高かったと記憶しています。
これ以上のことは今回の範疇ではないので避けますが、ADHDなどの人に向けたノウハウなどが、実は多数の人の集中力向上になる、ということはよくあるので興味ある人は調べてみるといいかもしれません。
特定の刺激に対する過敏さ、というのは人それぞれなので、蛍光灯やコントラストがまぶしいという人は遮光眼鏡(サングラスのようなものです)を使用することもあります。
私は先天的に目が弱いこともあり、緑色の物を勉強用に使用しています。さすがに人前では怪しいので家でのみの使用ですが、この眼鏡を利用することで一部の余計な光をカットし、視覚情報が取りこみやすくなるので、学習効率が格段に向上したと感じています。
それでは、勉強の中身に入ります。
まず『最初の一歩』として、この『一冊の参考書』を完璧にします。
何故たった一冊なのかと言えば、勉強したいけど勉強に慣れていない、という人の特徴として
参考書を買ったはいいものの、最初の数Pしか手をつけないまま、ほったらかし
で、そのちょっとしかやっていない本が何冊もあったりします。必要な部分しかやらない、と決めて買った本ならそれでいいのですが、大体の参考書は『全部やる』ことではじめて身に付くものなので、「ちょっとやっただけ」ではピンポンダッシュするようなものです。
中身(学力)が「はーい」と出てくる頃に、その場から離れてしまっているのです。
一冊目をせっかく選んだのだし、たった一冊なのだから(しかも中学生用!)、ちゃっちゃと全部やっちゃいましょう。
参考書は、最初のstep(または章)から始めます。
ちゃんとした『中学生用』なら、アルファベットから始まるはずです。ここは飛ばし――ません。
稀にアルファベットが間違っている人がいるので、大文字小文字も一応確認してください。
バカじゃないの?というぐらい簡単かもしれませんが、5秒で終わってもいいのでとにかく『やってから次に進む』ことが大切です。
筆記体が書けない人は、無理に筆記体で書かなくても大丈夫です。
例えばアルファベットなら、とりあえず書いてみて(えーびーしーでーと歌いながらでも)、書き終わったら次に進みます。
白い紙には、出てきた単語・例文を全部書きます。
何故全部かというと、これまで英語を殆どやってこなかった人は
『英語を書く力』と『日本語を書く力』
が圧倒的に足りていないので、答案を書くのにすごーく時間がかかります。
単語を一つ書くのにモタモタ、綴りに自信がなくてモタモタ、書き間違えて消してモタモタ……これではいくら問題を解く力があっても、時間が足りなくなります。
『でもマークシートだし……』という人は、ちょっと甘いです。
単語も熟語も“見るだけでいい”という段階の人は、もう既にかなり学力がついているからこそ“見るだけでいい”んです。既に蓄積があるのです。
とにかく、最終的には一分一秒を争わなくてはならないので、『手』を作らなければいけません。
そしてそのためには結局、『沢山書く』しかなく、そのためだけの時間を作るのはもったいないので『書きながら』勉強した方が効率が良い、ということになります。
なので
『読みやすい字をなるべく速く書く』練習
だと思って書いてください。この『読みやすい』が大事なところで、『読めない字を速く書く』のでは駄目です。採点者に読めない字は“採点不能”となり、たとえ本人なりに合っていても不正解になります。
※自分でかなり後になってから復習する時もチョー困ります
また、英文(または英単語)を書くときは一度しっかり見たら、例文から目を離して、白い紙と自分の字だけを見て書いてください。(このあたりは茂木健一郎氏の脳を活かす勉強法に詳しかった気がしますが、この本が今手元に無いので詳しいことは不明…)
さて、出てきた英文が白い紙に書いてあると思いますが、その中からとりあえず
『新しい単語』
『わからない単語』
『わかっているはずなのに、その文での役割(意味)がわからなかった単語』
を
『紙』から『ノート』に
書き写して下さい。(この時も『一度見て憶え、何も見ないで書く』というのを忘れずに)
これでこのノートが“マイ単語帳”になります。
単語の勉強がしたくなったら、この段階ではこの“マイ単語帳”から学ぶようにしてください。
ある程度勉強が進んでいる人は書く単語も少ないので、すぐ終わるはずです。
その時点の内容が曖昧だったり、初めて触れる場合、ページの単語がほとんど載っているはずです。
中学の時点で出てくる単語は全て重要なので、安心して憶えてください。
単語の“憶え方”には色々あるので、自分に合う方法を探し、良さそうなものはどんどん試してみてください。
単語を憶えるときに注意することは、発音も大事だということです。
どう発音したらいいかわからないものは、すぐ調べてください。
『音』がわからない『コトバ』を憶えるのは、すごくすごく大変です。
もちろん適当に読んでゴロ合わせしてもいいのだけど、さすがに中学英語の段階では、たとえゴロで憶えていても一緒に発音も憶えてください。
えーと、
Student
を
「スツデント学生でんねん」
と憶えてもいいんだけど、正しい発音も一緒に憶える、ということです。
これは“出来れば”ではなく“絶対に”です。
綺麗な発音が実際には出来なくてもいいのだけど(口の構造を英語の発音用に変えるのは、手を作るより時間がかかります)、頭の中で音を再生するときは、正確な発音にしてください。
このとき、発音記号にも注目してください。
出来れば発音記号については別に時間を取り、これだけを学習してみてください。
最初は、綴りと発音だけを憶える(綴りながら言う、綴りを見て言う、言ってから綴る)
次は、発音と意味
意味と綴り
最終的には
日本語からもパッと英語(音)が出るし、書ける。
英語からパッと和訳が出る。
ここが目標ラインです。
次にの目標ラインには、自動詞か他動詞ではどうか、数えられるかどうか、ヒトに使われるものか、という分類を覚えたり、活用、類義語、反対語、言い換え、語源など色々とあるのですが、それらは文法を学習する過程で
『何故そんな分類があるのか?』
が理解できてからでOKです。
自動詞&他動詞というものがわからない段階で、この単語は自動詞ではこう、他動詞ではこういう意味になる、なんて憶えるのは厳しいです。
○○の時は××になる、というものについては、○○の部分を先に学習して、理解出来たらそういう視点を持って新しい単語・今までの単語にあたって下さい。
逆にいえば、『新しい視点』が出来たら、すぐに今までの単語を復習するようにしてください。
(5)に続きます
中学英語を完成させる(3)
中学英語を完成させる(2)の続きです。
『そりゃ、日本語で書いてあったら解けるに決まってる』
という人は、そこまでの読解能力には問題が無いはずなので、いよいよ『英語の勉強』を始めます。
やり方に悩み過ぎて“やり方マニア”になっては本末転倒なので、もし今ある程度勉強を進めている場合はそのままそれを信じてやっても問題ないかもしれません。
私のはただの『提案』です。
ですが、勉強は“しない”よりは遥かに“する”方が良いし、「ああしよう、こうしよう」と悩んでいるよりは“一つの方法を信じて、やれるところまでやってみる”方が、結果としては良いのだと思います。
なので途中で“あ、これ明らかに合ってないな”と思ったら変えればいいのですが
「とりあえず、ゼロよりは1のほうがいい」
と、『やってみる』ことから始めてみてください。
今回は“何からやっていいかわからなくて、なにもできない”という状態から始めます。
まず
白紙の紙(コピー用紙でもメモ用紙でも藁半紙でも、無地の紙ならなんでもOKです)
中学英語の参考書
辞書(英和辞典)
ノート・筆記用具(自分の使いやすいもの。何が使いやすいかまだわからない場合、オーソドックスなものを)
を用意します。
辞書は『いらない』という説もありますが、“付録”含め最近のものは機能・内容的に優れているものが増えているので、大学受験を志しているのなら買って損はないと思います。
出来ればあるといいものは
音声の出る電子辞書
中学~大学受験までの単語・熟語集
ですが、これらはいきなり用意するにはお金がかかるのと、自分に合ったものを見つけるのがこの段階では少し難しいので『あったら』で構いません。
※最初の一冊が選べない場合はこれを勧めます。
くもんの中学英文法―中学1‾3年 基礎から受験まで (スーパーステップ)
posted with amazlet at 09.10.31
くもん出版
売り上げランキング: 956
(これが難しいと感じる人は、スタートでつまずかない中学英語 (くもんのベイシックドリル)から始めてください)
何故中学英語をしっかりやる必要があるかと言えば、高校英語は中学英語をマスターしていることが前提だからであり、更に言えば
中学英語が完璧になるだけで、偏差値30~40の世界からは脱出できる
からです。
中学英語というのは、英文法、単語(綴り・発音)、熟語、全てを含みます。
「中学時代英語の成績は良かったけど、高校に入ったら全然できなかったよ?」
という人は、『テストで点が取れていただけ』ではないでしょうか?
本当に英文法も完璧でしたか?
発音記号は読めていましたか?
単語も熟語も完全に覚えていますか?
それを使って英作文が出来ましたか?
“まあ、だいたいYES”
“もちろんYES!”
と言える人は、恐らくここを読んですらいないと思います。
もちろん、これらが完全にできないまま高校に進み、そのまま“なんとなく”英語が出来るようになり、大学受験まで進める人は沢山います。
“なんとなく”出来る人は、それでいいんです。
『本当にできないけど、本当にできるようになる!』
そういう人は、中学英語から始めよう、というお話です。
※英会話はまた別の次元(口からのアウトプット)なので、この場合の“英語が出来るようになる”というものにはすべて“受験”というコトバがつきます。『受験英語』と『英語が話せる能力』、は『現代文』と『円滑なコミュニケーション』と同じぐらい違うモノです。お互いリンクする部分はありますし、両方出来るようになる人もいますが、まずは身近なところ(受験勉強への第一歩)に目標を設定します。
中学英語を完成させる(4)に続きます。
にほんブログ村