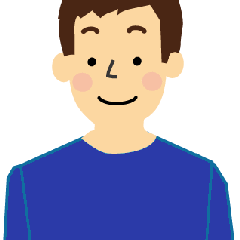こんにちは。藤井です。
今日はVision1の
「すべての日本国民が安心して暮らせる国家の実現」
の6つの政策・改革
①社会保障対策
②災害・環境対策
③地方活性化対策
④外交・国防対策
⑤働き方改革
⑥財政健全化対策
その中の⑤働き方改革について述べていきたい。
⑤働き方改革
今、まさしく、与党・野党ともにこのテーマについては多く議論されている。既存のアイディアとも重複することもあると思うが、私が考える働き方改革を述べていきたい。
働き方改革の影響は、少子高齢化問題や労働関連法規の改正問題のみならず、それこそ、これからの国民のキャリア、生き方を左右する重要なテーマである。したがって、それを推進するためには、労働関連法規は基より、社会保障分野、税制分野、教育分野を一体として、かつ大胆に改正するとともに、今までの「働き方」のパラダイムシフトを巻き起こすような改革が必要であると考える。ここでは主な政策として、高齢者の働き方改革、若年層の働き方改革と教育改革、企業に対する諸制度、大きくこの3つのテーマで示していきたい。
1)高齢者の働き方改革
現在でも60歳定年以降の雇用延長は国の制度としても推進されているが、実際のところ定年後は同じ仕事をしていても、雇用形態は契約社員になり、基本給は半額、ボーナスは無し、というケースも決して珍しくない。私が提案したいのは定年制の廃止と、完全な同一労働同一賃金の実施である。それから後述する企業に対する諸制度とも重複するが、採用における、年齢制限の完全撤廃である。いまでも求人広告などでは限定的に年齢を制限する求人の記載が認めれられている。(例:35歳まで 長期的なキャリア形成のため・・・など)
まず、正社員とは期間の定めのない雇用契約であるので、労働者自身が自分の引退年齢を決定すべきであると考える。しかし、この制度を法律で定めるにあたっても、年金の支給開始は65歳から延長すべきではない。あくまでも国民一人一人が自分自身の意志により、いつまで働くかを決めるべきである。また、年齢だけを条件にした賃金差別もしてはならない。これから、産業の自動化による労働における肉体的な負担の軽減や、情報通信技術を活用した在宅勤務などで年齢に関係なく高齢者が活躍できる領域はどんどん広がってくるであろう。
また、採用における年齢制限の完全撤廃を法律で定め、年齢に関わらずどのような分野にも再チャレンジできる仕組みも重要である。
「年上の新人なんてマネジメント出来ない。」
このような偏見があると、日本が危機に直面している少子高齢化問題を根本的に解決することはできない。このように使用者である企業の意識も根本的に変えていくことが、高齢者の働き方改革には重要である。
2)若年層の働き方改革と教育改革
現在、奨学金返済に苦しむ若者や、経済的事情から大学への進学を諦めざるを得ない若者など、20代の若年層における「働き方」にも大きな問題がある。ここでは、教育分野にも言及し、若年層の働き方改革への提言を述べたい。
まず、企業による学歴による採用差別の撤廃である。誤解の恐れがあるため「学歴」という言葉の定義を明確にしておきたい。一般的には「学歴」という言葉は
「あの会社は旧帝大クラスか、上位私大以外は書類選考で落とされてしまう・・・ これは学歴差別だ!」
というように、大学のランクや偏差値などを基準とした序列を意味する事が多いが、厳密に言うとこれは「学校歴」というべきであろう。(もちろん大学のレベルによる採用差別も禁止すべきだと考えているが。)
ここで私が言いたい「学歴」とは、高卒とか、大卒という、どの過程まで修了たかを示す意味である。
世の中には、別にわざわざ大学を出なくてもできる仕事は山ほどあるのに、大卒しか受け入れない、大卒の初任給と高卒の初任給が違う、大卒はホワイトカラー、高卒はブルーカラーと採用や賃金、その後の昇給まで差別している実態がまだ多く存在している。これは法律で禁止する。あくまでも能力で評価するべきである。合わせて義務教育を高校までに引き上げる。(もちろん、どの高校に進学するかという受験制度は残す必要はある。)優秀な若者は高校からでも社会に出て働き、今の大卒と同じように評価されれば、家計の学費負担も減り、奨学金の返済に苦しむことも無い。その際、企業側も若年層の研修・教育には力を入れる必要があり、国もそれを支援する仕組みは必要となるであろう。この政策は国としても労働人口を増やす一助になるであろう。
また、同じ考えで、小学校~大学における飛び級も大いに推進すべきである。教育の機会は全国民共通に与えられるべきであるが、その進度まで同じにするべきでは無い。優秀な生徒はどんどん飛び級を行い、若くして世界と勝負する人材を輩出することも、日本の産業界の発展に大きな活力を与えるであろう。
しかし、エンジニアや企業法務や経理など、専門的な知識が求められる仕事に関しては、いくら優秀でも、高卒の人材が不利になることは否めない。実情としては現在の工業高校、商業高校には成績優秀な生徒は平均的に見て、進学していないのが現状であろう。したがって、まずは各県内のいわゆる、進学校にトライアル的に工業科、商業科を併設し、特別なカリキュラムを編成し、優秀な学生が若くして、開発分野や商学、法学分野の知識を身につけられる制度も考えていきたい。
また、大学と高校との中間的な位置付けとして高等専門学校の増設も検討したい。現在は各都道府県に1~2校で、ほぼ全て工業高専である。これを商学、法学、経済学、経営学等、文科系の学科も新設していく。
ただ、大学で学ぶという意味は専門的技術を身に付けるという意味だけではない。真理を追究するために学びたいという人が経済的な問題で大学へ進学できない状況はやはり解決すべき問題であることには変わりがない。そこで、大学にはすべて夜間部の設置を義務付け、働きながら学べる環境を作る。(学生の負担を考え、6年制にして1日の講義時間を短縮するなど議論の余地はたくさんある)企業にも、働きながら学べる環境を支援を求める法整備も必要となるだろう。
このように、「働き方」だけでなく、「学び方」大胆な改革を行うことにより、全国民に様々な選択肢を示し、チャンスを掴める環境を整備することが重要である。
3)企業に対する諸制度
現在、働き方改革として議論されているのはこのテーマであろう。労働基準法の36協定の見直しや派遣法の改正などが具体的な例である。しかし、制度を見直すのは結構であるが、企業に対して強制力を働かせることが重要である。
現在でも、労働基準法において違反した使用者に対し、懲役刑を伴う罰則も存在する。しかしそれは「強制労働」に関する罪である。明治や大正期は炭坑などで強制的に働かされている悪しき慣習があったため、それを防止するため定められた刑罰であるが、それ以外の罰則規定はあまり見当たらない。もちろん違反した企業は行政的な処分は発生すると思うが、労働者の身分的な拘束の防止を主眼に置いている、現在の労働基準法は使用者に対する強制力、罰則も含めて、根本から見直すべきである。
ちなみに余談となるが、労働基準法上、いわゆる「正社員」であることの唯一の権利は「いつでも辞めれる」ことである。(民法上の規定で退職の意志表示をしてから2週間は退職できないが・・・)もちろん不当な解雇はある程度法律で規制されているが、かなり限定的であると言わざるを得ない。最近は改正も多くあり、多少改善はされているが同法ではむしろ有期的な労働契約が身分的拘束に繋がることの方を規制する趣のほうがはるかに強い。
話を元に戻すと、いくら法律を改正し、制度を改めたとしても、そこに強制力が働かなければ意味が無く、絵に描いた餅である。
私は、前述のVision1①社会保障対策でも言及した通り、「税と社会保障の一体改革」と合わせて、働き方改革における企業に対するある種の強制力を高めていくべきと考える。
①でも述べたが、今までの、年金制度、健康保険制度を全て廃し、全て税金で社会保障費を賄い、国庫から直接社会保障費を負担する制度に改めるべきだと考える。
その際には、消費税、法人税の増税は避けられないだろう。しかしながら企業にとっては、同時に年金や健康保険の企業負担分もなくなるので、単純に企業負担が増えるとは言えないが、現状の少子高齢化問題、消費の低迷を考えたときには、実質的な企業の負担増も必要である。ただ、法人税のみでは、赤字企業にはその負担義務が無いことから、一部の企業のみ社会保障の負担を強いることにもなるので、赤字企業に対しても、一定の社会保障負担分の納税を求めることも必要となる。
しかし、ただいたずらに企業に対して負担を求め続けることは産業の活力を損なう恐れがあるため、労災保険のメリット制と同じように、採用の年齢差別、学歴差別、各働き方改革に
貢献している会社には減税措置を、逆に違反する企業には税率の引き上げや追徴金を課すことを提案したい。
また、雇用形態は原則「正社員」と規制し、労働者派遣も派遣会社にいままで登録型であったスタッフは派遣会社の「正社員」とし、いわゆる登録型派遣は全面禁止にすべきと考える。
派遣先への転籍を希望する社員に関しては派遣元、派遣先双方で転籍に向けた努力をすることも法令で整備したい。派遣会社は自身の福利厚生、給与面などの労働条件や研修環境を整備することにより、その所属する社員の支持を得て、派遣という働き方にメリットを感じる社員を引き留める企業努力をすべきである。
そして、最低賃金も時給換算ではなく、月給の固定給の最低額を定め、順次経済環境に合わせて、引き上げていく事によって、富の再分配を図りたい。
私は、この「働き方改革」密接に繋がっている少子高齢化問題の本質は労働人口の減少よりむしろ、消費人口の減少による日本の市場規模縮小の方がより深刻であると思う。労働人口の減少は技術革新による自動化や人工知能の開発による解決策があると思うが、そのサービスやモノを買う購買力を持った人口減少はそもそもの人口を増やすことと、一人当たりの所得を増やす以外に解決方法は無い。
上記のような税と社会保障の一体改革を行えば、今まで社員が増えれば確実に負担となっていた社会保険料等の労務費がなくなり、労働関係法令を重視し社員のモチベーションを高め、社員一人当たりの生産性を高めれば、たとえ法人税率が上がったとしても、諸制度に対する優良企業の減税措置があるため、経営次第でメリットのある制度とすることができる。また国全体としても過労等による疾病の発生の低減が期待でき、医療費の高騰を抑える効果が期待できる。そして社員の給与を高め、購買力のある市場を日本に作れれば良いサイクルでの経済成長を実現することができる。
労働時間を減らし、本人の希望により、専業主婦・専業主夫も増え、より少ない労働力で生産効率を高めることにより、多くの経済効果を国民が実感できる制度を是非目指していきたい。そうすることにより国民一人一人が余裕を持って暮らし、人口の増加、幸福の実現を目指せる国家を作っていきたい。