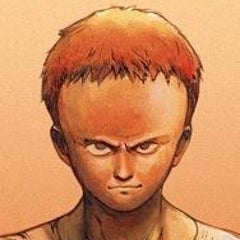【ネタバレあり】
「荒木飛呂彦の奇妙なホラー映画論」で「後半の大どんでん返しがルール違反スレスレ」と紹介されていたので、観ました。
確かにルール違反スレスレで、皆さん賛否両論あるようですが、私的には良しです。
最後の最後にアッと言わせるどんでん返しを狙った映画でこのオチを持ってきてたら「ふざけんな!」って思ったでしょう。
しかし、この作品は明らかに後半から観客にオチに気付く要素を提示していきます。
なので、徐々に気付くのを楽しむべきでしょう。
ただ、この徐々にが難しいところで、観客の洞察力は様々なため、かなり早めに確信してしまう人は、ちょっとつまらなくなってしまうかも。
徐々に気付かせるポイントをピックアップすると、
・モーテルにたまたま居合わせた人全員の誕生日が一緒
・死体が消える
・囚人への審問シーンの挿入
前半はしっかりと伏線を張り、ミスリードを誘いながらも引き込んでいく脚本。
例をあげると、
・囚人は解離性同一性障害であるという弁護団医師の見解。(伏線)
・囚人は過去モーテルに母親に捨てられたという事情聴取記録。(伏線)
・囚人は母が売春婦であったという事情聴取記録。(伏線)
・冒頭、囚人移送中という説明があり、当然モーテルの囚人がそうだと思う。(ミスリード)
・囚人を連れてきた刑事が上着を脱いだ時の背中の血。(伏線・ミスリード)
・子供は前夫から虐待を受けていたというセリフ。(伏線)
・モーテル主人の異常な売春婦に対する敵対心。(伏線)
で、脚本としては先に述べた、誕生日が一緒とか、死体が消えるなんてあまりにも非現実的な要素を出さずに最後まで引っ張って大どんでん返し!って話にも当然持っていけるところをそれをせず、後半徐々に観客へオチが読める要素を提示していく。
推理サスペンスとして、成立してると思いました。
(物語が多重人格の囚人の妄想の出来事でした!なんて最後の最後に明かしていたら、それは「ルール違反スレスレ」ではなく「ルール違反」で観客怒る(^^; )
最後の最後に大どんでん返しで、どうだ!という映画は、シックスセンス以降、狙ってる作品が多かったので、なんとなく、こういう徐々にひっくり返すのもありだよね、という感想です。
ちなみに私はかなり早い段階で少年が囚人の幼い頃だと思ってしまいました。
ぽっちゃりとした少年だった故にすぐに太った囚人とオーバラップしてしまったのです。
で、モーテルの出来事は過去のことで、囚人が殺人鬼になるきっかけと思いながら観てました。
囚人の罪はアパート住人6人の殺害だし、モーテルに捨てられたという過去が最初に提示されていたし、囚人が刑事に護送されてモーテルにやってくるところで、現在の話と思わせようとしてるけど、冒頭に囚人の写真が出てて、囚人の顔が違うからやはり現在進行形の話ではないと。
惜しいけど、ずれた読みでした。
振り返ると最初に沢山情報を与えてくれてるんですよね。
囚人の写真、解離性同一性障害まで最初っから明かさなくても良さそうなのに。
それだけ情報を与えても観客は混乱してくれると読んでいたのか、逆にその情報によって混乱すると読んでいたのか。。。
ちょっと残念に思ったところを追記。
物語が囚人の多重人格による妄想の出来事だった。というのがこの映画のオチではあるが、最後にもう一度、オチを作ってる。
妄想の中で各キャラクターが死んでいくことによって、人格も消滅していく。そして最後に生き残った元売春婦の女性の人格だけになったということで、殺人の人格はなくなったと弁護団医師は説明し、死刑執行は免れる。しかし、その後、囚人を移送している際に、本当の殺人人格である少年の人格が現れ、移送する運転手の首を絞めて、終わる。
ここがちょっと。囚人は男性だし、元売春婦の女性の人格だけが残るって、医師は疑問を抱かないのか?女性の人格が残って、安定すると思うか?
それに、囚人の妄想の出来事をどれだけ詳細に聴きとっていたのか分からないけど、父親に虐待されていたという少年の人格を怪しく思わないのか?
異様に売春婦に敵対心を持つモーテル主人の人格の存在から、売春婦であった母親に対して囚人が複雑な感情を持っているだろうことも明らか。
元売春婦の人格が最後に残るわけがない。
そもそも解離性同一障害で人格は簡単に消えるものではない。障害の重さで様々ではあるが半年、数年現れなかった人格が突如現れたりする。
このオチのためにだろうけど、少年が殺されるシーンは描かれていない。
そして少年は一言も喋らない。(だからといって両親は話しかけているので聴取で子供の存在に気付いていなかったというのは無理があると思う)
死体が消えるという状況において曖昧に居なくなる。
ちょっと最後のダメ押しオチには無理があると思う。