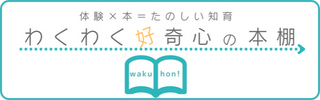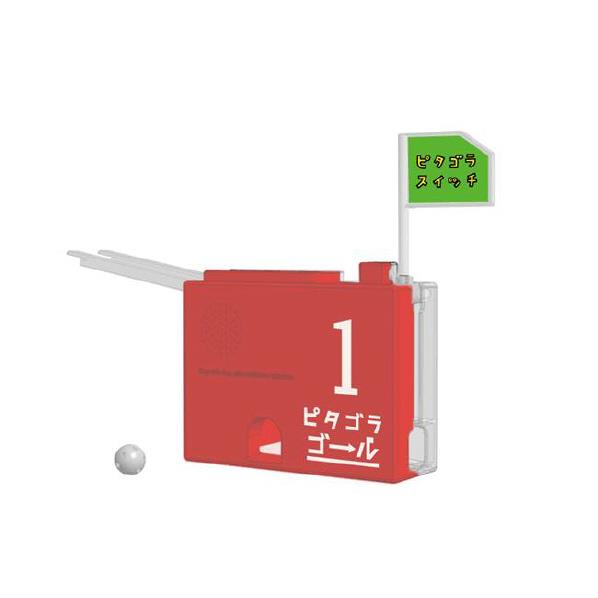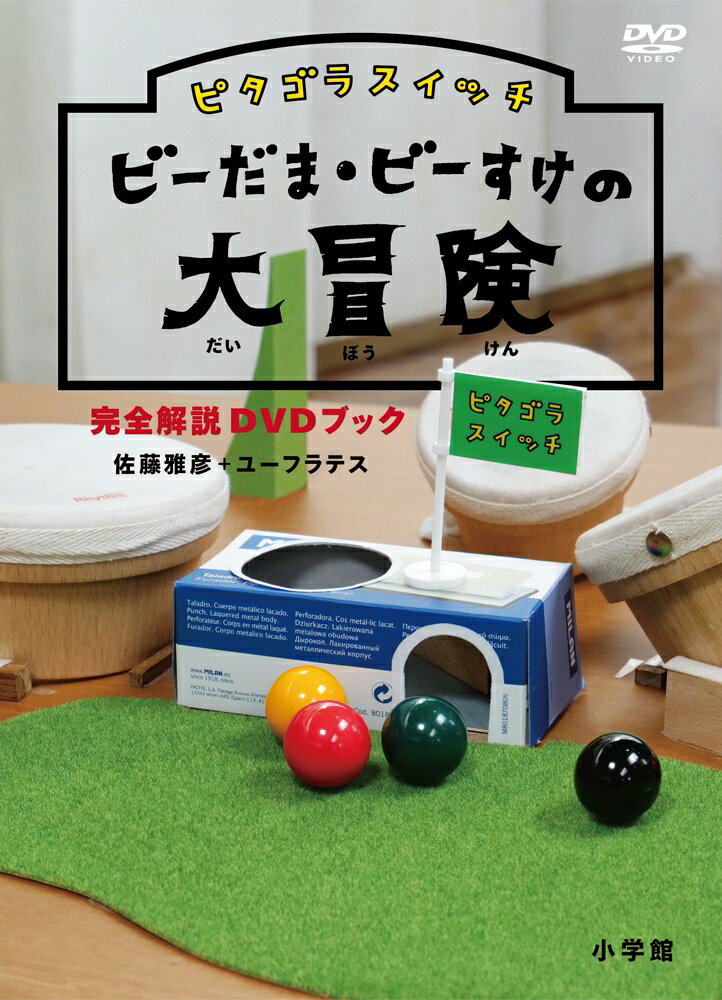↑オススメ絵本などを紹介している個人ブログです。
↑最近のブログはこちら
ガウディ展、めちゃくちゃオススメ!!
雪――!!
さむ―――ッ!!
そして雪――――!!!!
想像以上に雪だった……。
あ、うちの子たちですか?
元気に朝5時起きで外に飛び出していきました……寒い……。
まだ誰もいない公園でソリ遊び!
朝には雪がやんですぐに溶けると思って、早朝からめいっぱい雪遊びをしたんですが、
おかしいな……??
昼を過ぎても降っている……だと???
そしてまだ雪で遊ぶ……だと???
家の裏手にそりのすべり台を作ろうと、せっせと雪を運んで固めているみたいです。
ちょうど北側で日が全然当たらない場所なので、たぶん当分、溶けずに残るだろうなと。
そして当分、毎日遊ぶつもりなんだろうなと。(笑)
この地域はほとんど雪が積もらないので、
近所の子どもたち、みんな朝から大喜びで飛び出してくるかと思ったんですが、
意外に(?)あまり遊びに出てこなくて、うちの子たちだけずっと遊んでいるっていう。
夫が、「(うちの子たちは)苦労を買って出るタイプだから」って言っていて、
それってそういう意味だっけ!?(笑)
とりあえず本人たちは、苦労しているつもりはないと思いますが、
結果的に家の近所が雪かきされてよい感じです。ええ。
幼児期のおもちゃたち
さて前日の土曜日も、寒いし、いつ雪が降ってくるかわからないので、
あまり遠方には出かけず、図書館に行ったくらい。
で、あとは何をしていたかというと、
コレ。
この年になってもまだプラレール!!
しかも、作り始めが「こたつの上」っていうあたりで、いろいろおかしい!
いや、別にいくつになってもプラレールで遊んでいいんですよ。
それは全然!
ただうちの子たち、別に電車好きというわけでもないのに、まだ出番があるプラレールっていう。
しかもその横にあるのは、幼児が遊ぶボール転がし積み木だし、
一番左の手前、
なんなら、赤ちゃんが遊ぶおもちゃも持ってきたんですが!?
電車がジェンガを倒すと小さなベルが倒れて、
その中からビー玉が出てきて転がってジェンガを倒して、
すると赤ちゃんおもちゃの上から、ストッパーが外れたボールが転がってくる……っていう流れらしい。
最近、さすがに幼児期のおもちゃを整理しようかなって思ったんですが、
こういうことがあるからなかなか捨てられなくて!
長男に聞いても「まだ使うかもしれないからとっておく」って言うし、
で、実際にこうやって出番があったりするから(有言実行)、ホント、なかなか処分できない!
小学生兄弟の家で、まだこの赤ちゃんおもちゃを使ってる家って、けっこうレアじゃないかと思う……。
次男はプラレールの箱の中から「500円玉のおもちゃ見つけた!」って言って、
ホワイトボードに貼り付けられるタイプのレールで、
ころころ500円玉おもちゃを転がしていました。
……が、やがてそれも長男のピタゴラ装置に吸収された!
あ、我が家のドミノは常にジェンガです。
狭いリビングが埋まっていくううううううう!
で、これをですね。
最初から最後まで成功させたい長男!
ラストはこれを置いて、準備万端な長男!
だが、ここは簡単には問屋が卸さないのがピタゴラスイッチですよ。
も――こっちが成功すればあっちが止まり、
あっちがクリアできれば今度はこっちがうまくいかず!
絶望。(笑)
「もうこれでOKってことにしたら?」ってつい言っちゃったんですけれど、
「やだ! ぜったい成功させる!」って長男が言い張り、
なんだかんだで50回くらいはリトライして、ついに成功―――!!!
長い長い戦いだった……リビングの占領時間も長かった……
そんなわけで、プラレールも、赤ちゃんのコロコロおもちゃも、
なんならこの前買ったアシックスの靴の箱も、
当分現役で我が家にありそうです。
ちなみにアシックスの箱は、
↑ココ。
こたつのすぐ横です。
長男の足元にある黒い箱は、たぶん、次男の入学前に買った水筒の箱じゃないかな……。
家に物が多すぎる!!!!!(笑)
↑この部屋の足元が写せない理由。
つまり、そういうことです。(察して)
本人たちがこういう「遊び」を卒業した暁には、
いろいろ断捨離してすっきりさせたいなーと思うんですが、
それっていったい何歳なんだろう……???
気長に待とうと思います。うん。
余談
で、まだせっせと子どもたちは雪のすべり台を作っているわけですが!
朝、雪に埋もれた梅の写真を撮っていたら、
メジロがひょっこりと顔を出しました。
同じ木にはヒヨドリの姿も!
鳥たちもいきなりの寒さで大変だろうなぁ……
で、問いたいのはうちの子たちですよ。
ねぇ、君たちは寒くないの?? ねぇ????
ここまでブログを書いた後、
手伝いに行った夫が寒さに負けて帰ってきたので、バトンタッチで私が代わりに行ったんですが、
ちょうど家の裏手のおばあちゃんにお会いして、
おばあちゃんが選挙に行って帰ってくるまで、お庭の雪で遊ばせてもらってしまった…!!!
ありがたや―――!
冷え切ってもはや一歩も動きたくない私です。
昼ご飯にカレーを作った数時間前の私を褒めたい。
夕飯? もちろんカレーです。(笑)
***
↑ピタゴラ好きにはたまらない!
↑寒いけれど春ニットが欲しくなるー!