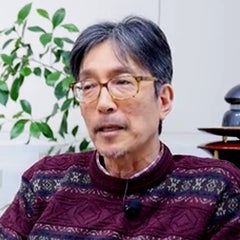先日、Tom's labのクリスタルダイヤモンドスピーカーBG031を購入して下さった浜松市のMさんが、使用していたONKYO D-200Ⅱと比較視聴され、BG031の音の良さに惹かれ購入を決めたという話を聞いた。
そこで、D-200ⅡとBG031の音響特性を測定して出音の違いを解明し、更には、D-200Ⅱを改造して満足できる音が出るスピーカーに蘇らせることが出来ないかを探ってみた。
D-200Ⅱは、振動版の素材改革などが盛んに行われていた1989年にONKYOから発売された16cm2wayの低価格ながら高音質のスピーカーとして評価された名器だ。しかし、このD-200Ⅱは知人からの頂き物ということで、かなり老朽化していると思われる。
ちなみに、BG031は8cmフルレンジ無指向性スピーカーの吸音材が綿わたの基本モデル。
まずは音響特性の比較
(1)周波数音圧特性
黒:BG031 赤:D-200Ⅱ
1/3オクターブ・スペアナ風測定では、D-200ⅡはBG031に対し、50Hz、64Hz辺りの音圧が6dB程度落ち込んでいる。これにより、低音の量感が全く違って聞こえる。
また、BG031の高域がほぼ平坦であるのに対し、D-200Ⅱは3.2kHz以上が5dB程度高くなっている。ネットでの評価でも高域が強すぎることが投稿されている。
D-200Ⅱの仕様書では再生周波数は38Hz~45,000Hzとなっているが、リアポートであるため、壁際に設置すればある程度の低音の量感は得られると思われるが、壁から離してしまうとその効果は半減する。
(2)インピーダンス特性
BG031のバスレフポートの共振周波数(fr)が60Hzであるのに対し、D-200Ⅱは55Hzとほぼ同じであるが、WOユニットの特質から最低共振先鋭度(Q0)がかなり低くブロードな特性となっている。また、中音域ではNWの特性で4Ω位まで落ち込んでいる。
(3)歪特性

中音量での測定では1~3kHzの歪が若干気になるものの、特に問題となるレベルではない。事前に行った試聴でも素直に聴けた。(データの2次歪、3次歪、ノイズレベルはレスポンスに対して+40dBシフトされており、4次歪以上はノイズレベルに含まれる)
しかし、WOのコーン紙を軽く叩いてみたところ、ある位置でボイスコイルがこすれる音がする。永年の使用により振動系のゆがみが発生していると思われる。大音量時には大きな歪が発生している可能性がある。
次にD-200Ⅱの改造を目論み、WO、TW、NW、キャビネットの素の特性を評価
WO
黒:NWに繋いだ特性 赤:素の特性
コーン紙の裏の一部に白い塗料が塗られている。
これは、カーボンコーン独特の共振を和らげるためと思われる。
更には、0.5g(10×10×5mm)程度の重りが接着されている。
軽量なカーボンコーンのみではf0が上がり、十分な低音が得られにくいので振動系の等価質量(m0)を増し、f0とQ0を下げるためと推測する。
重りは、リード線の位置の反対側に付けられているので、ある程度はバランスが取れていると思われるが、重りの方がはるかに質量が大きいと思われるので、永年使用による振動系のバタつきが心配される。
コーン紙を押してゆがみを矯正してみたが、こすれる感触は改善されない。
その後、キャビネットに取り付けて歪特性を測ってみたところ、最悪な特性に変貌していた。
細かく観察してみたところ、コーン紙とエッジの接着の一部が剥がれている。無理にコーン紙を押したことが原因であるが、もともと剥がれかかっていた様だ。
TW
振動板の裏には、WOと同じ様にゴム状の小さい重りが貼り付けられている。これもプラズマカーボナイトの癖を取ることが目的と思われる。
また、磁気回路ギャップの中にゴム状のごみの様なものが付着していることも判明した。
NW
写真はWO用、別基板でTW用もあり
回路構成は、WO側TW側とも-18dB/octの変形型である。
回路シミュレーターで特性を予測してみたところ、WO側はスピーカーユニットのインピーダンスカーブを考慮すれば、ほぼカットオフ周波数Fc=2400Hzの良好な特性を持っているのに対し、TW側は、中域を5dBほど減衰させる、言い換えれば、高域を5dBほど上昇させる特性になっている。この特性がトータルでの高域上がりの特性に貢献している。
キャビネット
板厚が18mm~20mmのパーチクル合板が使われており、隅木で補強され十分な強度を持っている。
吸音材は薄いウレタンフォームが数枚付けられ、一般的なブックシェルフ型と比べると極端に少ない。
バスレフポートはφ25mm×50mm程度で、同等のスピーカーユニットでシミュレーションしてみると、fb=45Hzであったが、インピーダンスカーブから推測すると55Hz位か。
改造目的
(1)低音の増強
(2)高域の平準化
(3)歪特性の復元正常化
改造方法
(1)リアポートからフロントポートに変更し、出来る限り理想的なポートの音圧を得る。
このスピーカーシステムは当時流行の小型ブックシェルフタイプ(9.9リットル)であるため、理想的なバスレフ効果は得られにくい。
シミュレーションにより、バスレフポートの共振周波数(fr)を55Hzに設定し,
φ22mm×55mmのポート2本をWOの下に追加する。
(2)本来ならば、NWの回路構成を以下の「更新NW回路例」の様に変更し、更に使用している素子をグレードアップしたいところだが、ここはONKYOの技術者が導き出した構成を尊重し、出来る限り現状のNWを利用することにした。
一般的には、BPケミコンは音質上好ましくないと言われるが、コストダウン以外にも音をまろやかにするメリットもありそうなので、カーボンやプラズマカーボナイトなどの硬い音が得意な振動板を使用しているシステムなので、理に適っているかもしれない。
また、プリント基板による配線も、オーディオマニアからは敬遠されるが、小出力ではほぼ問題無いと考える。

更新NW回路例(Fc=2400Hz,-12dB/oct,TWAT=5dB)
回路シミュレータ上で検討してみたところ、TWoutに3Ω程度の抵抗を直列に追加することにより、中域はそのままで高域のみを下げることが出来そうだ。

NWボードの使われていないパターンを切断し、3Ωのセメント抵抗の半田付に利用する。
(3)WOのコーン紙とエッジの接着部が剥がれていた部分を接着剤で補修する。
この補修は表側からだけでなく、裏からの補修も必要。
また、TWの磁気回路ギャップの中のゴム状のごみの様なものを取り除く。
結果
(1)により、50、64Hzの音圧が6dB程度向上し、低音が増強された。
(2)により、高域もほぼシミュレーション通りの特性が得られた。
黒:改造後 赤:改造前
(3)により、ほぼ元の歪特性に復元できた。
補足
スピーカーユニットの取り外しや取り付けで、WOのねじ穴が1か所つぶれてしまったが、ねじ下穴を開けた丸棒を詰めて無事補強完了。
改造後の外観