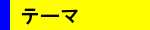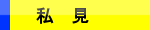「危機の時代」を乗り越える新しい統率力
小学館101新書 2011年9月25日 初版第1刷発行

<目次>
はじめに 能力なきリーダーしかいない日本の不幸
第1章(現状認識)
東日本大震災でわかった「危機に克つリーダー」の条件
[スピード]
1週間でできない「緊急対策」は、1年かけてもできない
[危機管理力]
組織のイメージを最小限にする工夫と判断が必要だ
[行動力と交渉力]
次世代の国家リーダーに求められる「3つの条件」
第2章(対策)
組織を元気にするリーダーシップの育て方
[ビジョナリー・リーダー]
世界で勝つ企業は人材育成に毎年1000億円かけている
[中間管理職“再生術”]
組織を動かすには「“揺らぎ”のシステム」を使いこなせ
[新・人材教育カリキュラム]
リーダーシップは“天与”のものではない
第3章(比較研究)
日本が学ぶべき世界のリーダーシップ
[イギリス・キャメロン首相①]
弱冠43歳にしてトップに立ったリーダーはどこが凄いのか?
[イギリス・キャメロン首相②]
「グレート・ソサエティ」構想で活かすべき「民の力」
[ロシア・メドベージェフ大統領]
「結果を出す指導者」の驚くべき決断力と行動力
[日本vs中国リーダー比較]
国民の差ではなくリーダーの差が国家の関係を規定する
第4章(提言)
私が「リーダー」だったら日本の諸課題をこう乗り越える
【震災復興】
「緊急度の掌握」ができなければ非常時のリーダー失格だ
【電力インフラの再構築】
原発と送電網は国有化、電力会社は分割して市場開放せよ
【食料価格の高騰】
世界の農地に日本の農業技術・ノウハウを売り込め
【水資源争奪戦】
水道事業を民営化して「水メジャー」並の競争力をつけよ
【エコカー開発競争】
劇的な低価格を実現し、世界市場で優位に立つ「新EV革命」
【財政危機】
所得税・法人税ゼロの「日本タックスヘイブン化」で経済は蘇る
おわりに 「強いリーダー」は強い反対意見の中から生まれる
[ビジョナリー・リーダー]
世界で勝つ企業は人材育成に毎年1000億円かけている
リーダー不在の背景には、議員連盟という
弊害もある。私はこれまで何度も議員連盟
が主催する「勉強会」なるものに講師として
呼ばれているが、勉強すべき議員のセンセイ
たちはいつも“受け身”だ。
遅刻してきて、メモも取らず適当に話を聞き、
終了間際に席をたって、次の勉強会に行くの
である。
こういうことを一日中繰り返す国会議員の
勉強会は、カフェテリアでつまみ食いをして
いるようなものだ。
将来のトップを育てるというコンセプトを
持っていないのは政界だけではない。
経済界も同様である。
今の日本企業の中に「リーダーシップ教育」
はない。あるのは「職能教育」だけだ。
たとえば、企業に入社すると、社内文書の
書き方から始まり、入社1年目、2年目の
教育メニューが決まっている。
営業の部署に配属されれば、「相手と話す
時は顔より少し下のネクタイの結び目辺りを
見るとよい」と、ロボットでも作っているか
のような画一的な営業教育が待っている。
アメリカのGE(ゼネラル・エレクトリック)
では「我々の将来はGEのリーダーが何人
育つかにかかっている」という考えに基づき、
リーダーを創る教育を徹底している。
この人材育成のためだけにGEは毎年1000
億円をかけている。
売上高10兆円余の1%に相当する金額だ。
そういう時間と労力とコストを費やして、
次代を担うリーダーを育てているのである。
韓国のサムスングループも毎年、売上高10兆円
余の1%近くに当たる1000億円を人材育成
のために費やしている。
若い社員を毎年数百人、アジアや中東、ブラジル
などに送り込み、現地で人脈づくりや語学力の
向上、歴史・文化の勉強などに励ませるのだ。
GEは、御存知の通り発明王エジソンが作った会社です。
GEがすごい会社であることは、100数十年の歴史を
持つダウ工業株30種平均の銘柄から一度も外された
ことがないことからも分かります。
新しい会社が出ては消えるという栄枯盛衰が常である中で、
GEはどのような時代であっても輝き続けているのです。
名経営者として名高い、前GE会長ジャック・ウェルチ氏は、
世界でシェア1位か2位になれる事業しか行わない、
という方針を貫き通しました。
GEの現在のCEOはジェフ・イメルト氏ですが、
ジャック・ウェルチ氏が数百人の候補者の中から選び抜いた、
優れた経営者です。
韓国のサムスングループを率いるのは、イ・ゴンヒ氏です。
イ・ゴンヒ氏は日本で生活し、日本に学んだことを著書の
中で述べています。
サムスングループは日本に学び、日本の製造業を凌駕する
ようになりました。
サムスングループの中核企業であるサムスン電子は、
投資額は、日本企業と比べ、一桁多いと言われています。
日本企業が数百億円の投資なら、その10倍以上の数千億円
相当の投資を行なっているので、日本企業が太刀打ちできる
はずがありません。
GEもサムスングループもリーダー育成のために1000億円
という大金を費やしていることを見ると、R&D(研究開発費)
に投資しているだけではなく、次世代のための先行投資を
行なっていることが分かります。
パナソニックやソニー、シャープなどのかつて日本を代表
する世界的な企業が凋落してしまったことに、日本人として、
とても悲しく思います。
昔の輝きをもう一度取り戻してもらいたい、と切望するのは
私だけではないでしょう。
日本企業はもうダメになってしまったのでしょうか?
以上の記事は、2013年5月18日のものです。
過去2年間で変わったことは、サムスングループの勢いが
衰えたことです。サムスングループの中核企業である
サムスン電子の主力製品、ギャラクシーシリーズが奮い
ません。
アップルのiPhone6 に大きく水を開けられています。
最新機種ギャラクシーS6は、地元韓国でも不人気で、
販売店には閑古鳥が鳴いている、という報道がなされ
ました。
ギャラクシーシリーズの販売が目標を下回っているため、
部品を供給している日本企業も苦戦を強いられています。
一方、ソニーはアップルの軍門に下り、アップルの下請け
に成り下がっていると伝えられました。
日本企業はどうしてしまったのでしょうか?
もう一度書きます。
昔の輝きをもう一度取り戻してもらいたい、と切望するの
は私だけではないでしょう。
日本企業はもうダメになってしまったのでしょうか?
藤巻隆(ふじまき・たかし)オフィシャルブログ-
人気のブログランキング
こちらのブログやサイトもご覧ください!
こんなランキング知りたくないですか?
中高年のためのパソコン入門講座(1)
藤巻隆のアーカイブ
本当に役に立つビジネス書