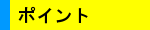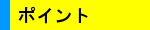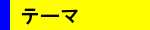<このページでは、『日経ビジネス』の特集記事の
概要紹介と、管理人のコメントを掲載しています>日経ビジネスの特集記事(114)外弁慶企業
HITACHI
世界から壊す成長の壁2015.07.06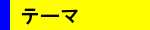
今週号の特集のテーマは
「安定感はあるが、革新性がない」
「技術はあるが、商売下手」──。
1910年に創業し、戦後の日本経済をけん引し
続けてきた日立製作所は、偉大な功績の割に
市場や消費者からの評価がいまひとつ、
という不思議な企業だ。
足元の状況を見ても、2009年度以降の構造改革
でV字回復に成功したものの、2015年度を最終と
する中期経営計画では、未達に終わる見通し
の目標も。
「成長の壁に直面している企業」というイメージが
鮮明になっている。
だが、海の向こうでは今、そんな日立の評判が
すこぶる高い。
開発から人事まで、国内では進めにくい様々な
改革をここ数年、海外で先行的に実施。
その多くがここへきて、成果を上げ始めているからだ。
海外拠点の変貌は、国内の日立の風土も変えつつある。
過去四半世紀、抜本的な体質転換を果たせなかった日立。
しかし、「外圧による改革」は、その歴史を塗り替える
可能性を秘めている。
(『日経ビジネス』 2015.07.06 号 P.025)
ということです。
外弁慶企業
HITACHI
世界から壊す成長の壁
(『日経ビジネス』 2015.07.06 号 表紙)
「日経ビジネスDigital」 2015.07.06
今特集のスタートページ
(『日経ビジネス』 2015.07.06号 PP.024-025)
「日経ビジネスDigital」 2015.07.06
第1回は、
「PROLOGUE 『海の向こう』では別の顔
海外では重くも暗くもダサくもない」
を取り上げました。
第2回は、
「PART1 海外で今、注目される理由」
を取り上げました。
最終回は、
「PART2 “外圧”で国内も変える」
をご紹介します。
今特集のキーワードは次の5つです。

外弁慶企業
総合力
権限委譲
社会イノベーション
外圧
今週号の特集のスタートページに掲載されている
画像がとても面白いですね。
「公家集団」と「弁慶」です。
画像を拡大してみましょう。
日本でのイメージ
頭でっかちの「公家集団」
(『日経ビジネス』 2015.07.06号 P.024)
「日経ビジネスDigital」 2015.07.06
世界でのイメージ
開拓魂に富む「野武士軍団」
(『日経ビジネス』 2015.07.06号 P.025)
「日経ビジネスDigital」 2015.07.06
日立製作所は、国内のイメージ「公家集団」と海外での
イメージ「野武士軍団」とまるで異なるイメージを共有する、
類まれな日本企業であることを、『日経ビジネス』取材班
は提示しました。
私たちは日常会話の中で、しばしば、「内弁慶(家の中で
威張っているが、一歩外に出ると小さくなっている)」、
と批判することがあります。
日立製作所は、海外では存在感が増していますが、
国内ではマイナスイメージがつきまとってきました。
国内と海外で対照的なイメージを抱かれた企業が、
日立製作所だ、というのが書き出しです。
では、本題に入りましょう!
PART2 “外圧”で国内も変える
日立製作所は、1980年代から改革に取り組んで
きましたが、思うように進みませんでした。
現場の抵抗が予想外に強かったからです。
現在進行中の改革の方向性が打ち出されたのは、
2009年に川村 隆氏(現・相談役)が会長県社長に
就任した後のことでした。
下の年表は、日立の改革の動きを当時の経営陣の
施策と照らし合わせて、作成されたものです。
企業規模が拡大するにつれ、改革の断行が困難
になることが理解できます。
セクショナリズムが横行し、全体最適よりも部分最適
が優先されるようになります。
こうした現況を破壊し、ベクトルを合わせるためには、
方向性を的確に示す有能なナビゲーターが欠かせ
ません。
そして、そのナビゲーターは方向性を示すだけでなく、
構造改革を何としてでも断行する人物でなければなり
ません。
日立には、そうした有能なナビゲーターが複数存在
したということです。
川村氏の登場以降、構造改革が加速
・日立製作所の歴代会長・社長と
主な構造改革や組織改革、事業買収や売却など
(『日経ビジネス』 2015.07.06号 P.040)
「日経ビジネスDigital」 2015.07.06
(『日経ビジネス』 2015.07.06号 P.041)
「日経ビジネスDigital」 2015.07.06
直近の改革の内容については、『日経ビジネス』の記者
による深堀りしたリポートをお読みください。
それまで「聖域」となっていた研究所にも改革のメスが
入ることになりました。
「研究所に入った時は、営業担当者と顧客訪問を
繰り返すことになるとは思ってもいなかった」。
日立製作所の中堅研究員、佐藤暁子氏は率直に
こう話す。
佐藤氏は入社以来、中央研究所などに勤務。
特許を10件以上出願した実績を持ち、
近年は交通渋滞や人の流れを解析するための
技術などを開発していた。
そんな佐藤氏の生活が変わり始めたのは2013年
頃から。長年、聖域とされてきた研究所の改革が
始まってからだ。2015年4月に研究所の大幅な
組織改編が実施されると、その働き方は一段と
様変わりした。
従来のように研究所で研究開発に没頭するの
ではなく、顧客先に出向き、先方と議論しながら
ソリューション創出を目指すことが仕事の9割を
占めるようになった。
(PP.040-041)
研究員は、研究のための研究ではなく、
顧客との接触を通じ、顧客のニーズを掘り起こし、
何を提供したら良いのかを考えることが求められ
るようになった、と私は考えています。
「カスタマー・ファースト(顧客第一)」をお題目で
終わらせず、実際に成果を上げることに集中する
ことが仕事になったのです。
表現を変えれば、日立のすべての社員が、
顧客のいろいろな問題を解決する営業マンになる
ことを求められるようになった、と言えます。
名称は異なるかもしれませんが、官僚的縦割り組織
から横断的組織(クロスファンクショナルチーム)への
移行は必然となり、目標に向かってベクトルを合わせ、
全体最適を目指すことになります。
ですが、経営陣の思惑通りに進まないのが国内の組織
改革です。
IoT時代に合わせた部門間を越えての技術の統合、
国境をまたいでの次世代型企業管理、「消極的」
「リスク回避思考」という評判を覆す大胆投資──。
PART1で見た、海外で進めてきたグローバル化の
実験は、国内にも着実に影響を及ぼし始めている。
「グローバル化が目的なのではなく、主戦場となる
市場がグローバル化しているから、適合しないと
生きていけないということ。この事実を直視し組織や
事業などを組み替えて対応していかないと死ぬだけ」
過激な言葉を使い、こう話す中西会長が、海外とは
対照的に改革が進まぬ国内の状況に強い不満を
抱いているのは明らかだ。
(P.041)
日立で特徴的なことは、グローバルな視点から、
米州、中国、欧州など、アジアなどの4地域に分け、
地域ごとに総代表を据え、権限委譲し、日本本社
の責任と権限を減らしていることです。
日本本社の責任と権限も減る
・2015年4月から移行した、地域総代表制による
グローバル自律分散経営
(『日経ビジネス』 2015.07.06号 P.042)
「日経ビジネスDigital」 2015.07.06
日立全体をグローバルな視点で捉え直すと、必然的に
人事体系も変わらざるを得ません。
人事情報の巨大データベースが稼働しているそうです。
2011年から「グローバル人財マネジメント戦略」と
呼ばれる取り組みを進め、2012年度に国内外の
日立グループ社員約25万人分の人事情報を
データベース(DB)化。
2013年度に、国内外の管理職約5万ポジション分の
役割の大きさなどをグローバル共通の尺度で
格付けする仕組みを整えた。
「数十万人規模の人事DB化は一部のグローバル
企業では実施されているが、日本企業ではまだ
珍しい」と、人事を担当する中畑英信・執行役常務
は説明する。
人事体系が世界共通化されたことで、今後は、
日本本社の管理職のライバルは世界に広がる。
国籍や年齢を問わず優れた人材の抜擢もしやすく
なり、国内もやがて英国の鉄道セクションのように
(HITACHIの魅力 2 参照)、社歴や実績に関係なく
「最も市場が分かる人間に任せる」方向に向かうの
は間違いない。
(P.042)
日立社内のライバルは国内にとどまらず、海外にも
存在することになったのです。
いやが上にも社員の競争心を煽る仕組み、と言える
でしょう。
上昇志向の強い人にとっては良い環境に変わりました
が、今まで安定志向で大きな船に乗っていれば安泰
と感じていた社員には、尻に火が付いた状況です。
構造改革には必ず、軋轢が生じ、組織から弾き飛ば
される人たちが出てくるのは間違いありません。
それでも改革を断行しなければならない、と経営陣が
考える理由は次のとおりです。
グローバル日立の形に加えて、国内日立の形も
着実に変えていく。例えば、従来にない事業横断型
の組織の創設。
縦割り組織のデメリットを解消し、従来は事業ごとに
バラバラだった顧客への対応を一元化するのが狙いだ。
その一例が、2015年4月、社長直轄の戦略組織として
設立されたエネルギーソリューション社。
社名通り、発電に関する顧客ソリューションを一手に
請け負う。
(P.042)
日立が、シュンペーターが創造的破壊(creative destruction)
と表現した、イノベーションを起こそうとしていることは
明らかです。
東原敏昭・社長兼COO(最高執行責任者)は、
次のように語っています。
グローバルで勝つために、グループ内で統合可能
なものは、できるだけ一緒にしていくべきだと考えている。
事業やカンパニーごとに設立してきた販社も、
近隣地域にあるのであれば間接コストを下げるために、
大胆に統合していく発想が当然必要になる。
地域単位で統合や再編を進めていくなら、
販社や工場という拠点だけではなく、それに付随する
輸送ルートや販売ルートなどのサプライチェーンも、
統合効果があるものは一緒にしていく考え方が重要だ。
「One HITACHI」というメッセージを社内外で言い始めた
のは、社員に横の連携を意識させ、グループの総合力
をグローバルで存分に発揮してもらうためだ。
(P.043)
東原敏昭・社長兼COO(最高執行責任者)
(『日経ビジネス』 2015.07.06号 P.043)
「日経ビジネスDigital」 2015.07.06
企業文化(社風)を解体し、作り直すのは容易では
ありません。
日立は100年以上続いている会社です。
改革が一気に進むほど柔軟な組織ではないことは、
想像に難くありません。
もちろん、100年以上続いた文化の解体は容易でない。
日立の取引先の多くは今も、社内の人間同士が顧客
の目の前で躊躇なく名刺交換するなど、“古い日立”を
目の当たりにする。
それでも、中西改革によって、日立を包んでいた改革を
阻む膜は一つひとつ剥がれつつある。
(P.044)
川村隆・相談役はかなり大胆で、厳しい発言を
しています。日立の近未来像を述べています。
日立の社内が、ちょっと緩んでいる気はする。
もう少しびしっとやらないと。
マスコミなどから過去最高益更新と騒がれて
いい気になっていてはだめだ。
「何も変えずに今まで通りに仕事をやっていれば、
うまくいく」という考えでビジネスをしていたのが
昔の日立。
副社長をしていたころの私も含めてそうだった。
日立の社外取締役をしてくれているジョージ・
バックリー氏がCEOを務めていた米スリーエムでは、
米国に本社があるとはいえ経営陣の中で米国人は
少数派。国籍は様々だが、みな英語を使って議論
する。
日立もそのようになっていき、いずれ小さい本社が
各地に散らばっているような組織体でグローバル経営
を進めるのだろう。
そう考えるとスリーエムのように、日立の本社が創業
の地の日本にあったとしても、経営陣の人種は多様化し、
仕事で使う言葉も英語が普通になっていくのではないか。
いずれにせよ、今は英語を使わないとグローバルでは
ビジネスにならない。グローバル企業として存続していくなら、
そのくらいにならないと。
本社が日本にあっても、経営陣は日本人とは限らず
多国籍、使われる言語は英語。
これが永続していくグローバル企業の姿ではないか。
いずれ、日立の本社でも英語が当たり前のように
使われるようになるだろう。
(P.045)
川村隆・相談役
(『日経ビジネス』 2015.07.06号 P.045)
「日経ビジネスDigital」 2015.07.06
『日経ビジネス』特集班は、「外圧」をキーワードに
次のようにまとめています。
“外圧”によって古い国内を変え、既に「外弁慶企業」
である日立を、国内外を問わず強さと影響力を発揮
する「両弁慶企業=真のグローバル企業」にする──。
これが、中西改革が目指す最終目標なのだろう。
もっともGEを追い続ける日立の旅はそこがゴールでは
ない。GEの売上高は約18兆円、日立は約9兆7000億円。
営業利益率も約2倍の差がある。
仮に中西改革が成功したとして、その後も、GEに大差を
付けられたまま“普通のグローバル企業”の座に甘んじる
のか。それとも、あくまでGEに肩を並べるスーパーメジャー
を目指すのか──。
昭和の焼け野原で米国の最新の経営を必死に学び、
礎を築いた先人たちが、いずれの道を望んでいるかは
言うまでもないだろう。
日立は、GEに追い付き、追い越す。中西改革はスタート
ラインにすぎない。
(P.045)
ライバルとなる欧米勢の重電大手と比較すると・・・
・GEとシーメンス、日立の売上高と営業利益、営業利益率
(『日経ビジネス』 2015.07.06号 P.037)
「日経ビジネスDigital」 2015.07.06
もう一度、中西宏明会長兼CEO(最高経営責任者)の
インタビューをご覧ください。
特集で扱った内容と、中西会長の言葉が呼応し、
改革をなんとしても成功させてみせる、という意気込み
が伝わってきます。
日経ビジネスのインタビュー(178)
安心している暇はない

日立の改革はこれからも続く
日立が目指すゴールは、ずっと先にあります。
GEに追い付き、追い越すことです。
その日はいつになるのか?
当事者の日立でさえ断言できないでしょう。
ですが、ターゲットが明確になれば、
この先何年、いや何十年かけても実現できる、
と経営陣以下、末端の社員に至るまでもが、
本気になって継続的に事業に取り組めば、
実現できないことはない、と確信しています。
その時、日立は「日本の日立」ではなく、
名実ともに「世界のHITACHI」となるのです。
その日が来るのを自分の目で確かめたい、
と思います。
今特集のキーワードを確認しておきましょう。

外弁慶企業
総合力
権限委譲
社会イノベーション
外圧
藤巻隆(ふじまき・たかし)オフィシャルブログ-
人気のブログランキングこちらのブログやサイトもご覧ください!こんなランキング知りたくないですか?中高年のためのパソコン入門講座(1)藤巻隆のアーカイブ本当に役に立つビジネス書