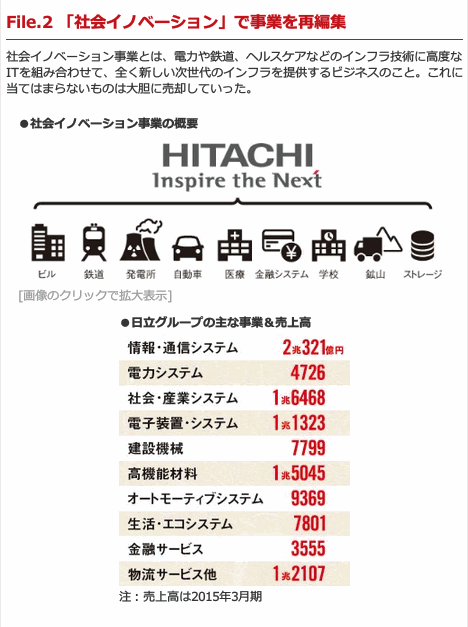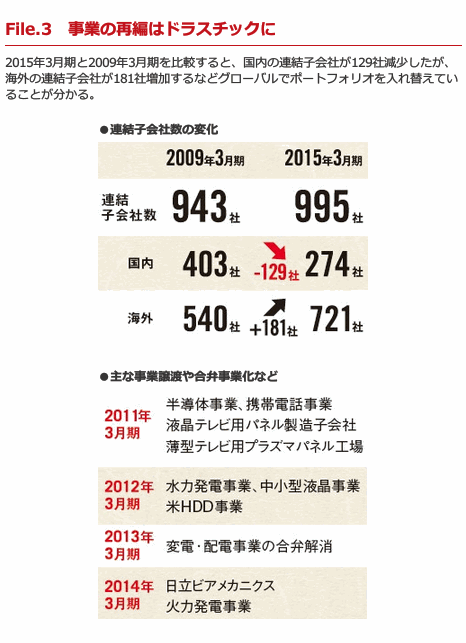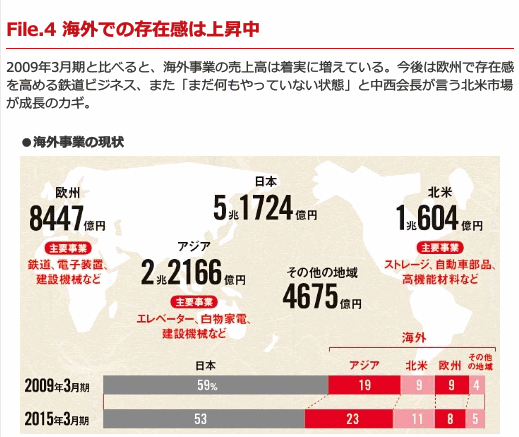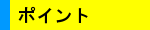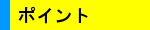概要紹介と、管理人のコメントを掲載しています>
日経ビジネスの特集記事(114)
外弁慶企業
HITACHI
世界から壊す成長の壁
2015.07.06
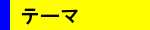
今週号の特集のテーマは
「安定感はあるが、革新性がない」
「技術はあるが、商売下手」──。
1910年に創業し、戦後の日本経済をけん引し
続けてきた日立製作所は、偉大な功績の割に
市場や消費者からの評価がいまひとつ、
という不思議な企業だ。
足元の状況を見ても、2009年度以降の構造改革
でV字回復に成功したものの、2015年度を最終と
する中期経営計画では、未達に終わる見通し
の目標も。
「成長の壁に直面している企業」というイメージが
鮮明になっている。
だが、海の向こうでは今、そんな日立の評判が
すこぶる高い。
開発から人事まで、国内では進めにくい様々な
改革をここ数年、海外で先行的に実施。
その多くがここへきて、成果を上げ始めているからだ。
海外拠点の変貌は、国内の日立の風土も変えつつある。
過去四半世紀、抜本的な体質転換を果たせなかった日立。
しかし、「外圧による改革」は、その歴史を塗り替える
可能性を秘めている。
(『日経ビジネス』 2015.07.06 号 P.025)
ということです。

HITACHI
世界から壊す成長の壁
「日経ビジネスDigital」 2015.07.06

「日経ビジネスDigital」 2015.07.06
第1回は、
「PROLOGUE 『海の向こう』では別の顔
海外では重くも暗くもダサくもない」
を取り上げました。
第2回は、
「PART1 海外で今、注目される理由」
を取り上げます。
最終回は、
「PART2 “外圧”で国内も変える」
をご紹介します。
今特集のキーワードは次の5つです。

外弁慶企業
総合力
権限委譲
社会イノベーション
外圧
今週号の特集のスタートページに掲載されている
画像がとても面白いですね。
「公家集団」と「弁慶」です。
画像を拡大してみましょう。

頭でっかちの「公家集団」
「日経ビジネスDigital」 2015.07.06

開拓魂に富む「野武士軍団」
「日経ビジネスDigital」 2015.07.06
日立製作所は、国内のイメージ「公家集団」と海外での
イメージ「野武士軍団」とまるで異なるイメージを共有する、
類まれな日本企業であることを、『日経ビジネス』取材班
は提示しました。
私たちは日常会話の中で、しばしば、「内弁慶(家の中で
威張っているが、一歩外に出ると小さくなっている)」、
と批判することがあります。
日立製作所は、海外では存在感が増していますが、
国内ではマイナスイメージがつきまとってきました。
国内と海外で対照的なイメージを抱かれた企業が、
日立製作所だ、というのが書き出しです。
では、本題に入りましょう!
PART1 海外で今、注目される理由
前回、日立製作所には国内(内)と海外(外)で
2つの異なる顔がある、というお話しをしました。
現在の日立は「外弁慶企業」であるというのが、
『日経ビジネス』の見方です。
今回は、「外弁慶企業」の面目躍如たる勇姿を
ご覧いただこうと思っています。
日立が海外ではこんなに存在感(プレゼンス)が
あるとは知らなかったな、と私を含め多くの読者の
方が感じると思います。
換言しますと、なかなか構造改革できなかった日立
が「外圧」によって変わってきたということです。
『日経ビジネス』によれば、日立には6つの魅力が
あるということです。

博士号を取得した社員が1000人以上在籍して
いることは驚きですし、「宝の持ち腐れ」と揶揄
され続けた所以でもあります。
ところが、IoT(モノのインターネット)の時代、
あるいは第4次産業革命が起こりつつある今、
長年蓄積されてきた技術力や研究、ノウハウ
が結集された「総合力」が重要な鍵となります。
日立には、宝の持ち腐れと言われ続けてきた
「総合力」があります。
その象徴ともいうべき、高速鉄道車両と鉄道
システムが海外で脚光を浴びています。

英国における日立の存在感がどの程度のもの
なのか、記事を読んでみましょう。
納得できるかもしれません。
(P.030)
ファー・イースト(極東)の車両メーカーが
シェア首位に──。
年間20兆円規模に達する世界の鉄道市場。
その約5割を占める主戦場の欧州で今、
異変が起きている。
震源地は英国。鉄道発祥の地であるこの市場で、
日立製作所が2019年までに車両の受注シェアで
トップに立つ。
見込みも含めると、2014~19年の間で新たに
1273両を受注。
競合の独シーメンスや加ボンバルディアを抜き、
英国で最も多い受注車両を抱えるメーカーになる。
全ての納入が完了すると、現在174両が走る日立
製列車の数は約8倍の1447両に増加する。
日本企業では初の快挙だ。
「今、欧州鉄道メーカーで最も勢いに乗る企業」
(鉄道運行会社、ヴァージン・トレインズ幹部)である。
先に掲載した写真の鉄道車両「Class800」シリーズが、
英国に納入されましたが、注目すべき点は、
優れているのは、この車両製造だけではない、
ということです。
英国の鉄道事情に適応した総合的な技術力がものを
言ったのです。
(PP.031-032)
2017年から商用サービスが始まるIEP(都市間高速
鉄道計画)で採用される「Class800」シリーズは、
英国の鉄道特有の条件を克服する様々な機能を
搭載した高性能車両だ。
英国の鉄道事情は欧州でも特殊で、例えば、
車両の空間容量を決める英国鉄道の車両幅は2.7m。
欧州の3mや日本の3.3mに比べて短く、その分全てを
コンパクトに設計しなければならない。
しかも、鉄道区間の一部は、いまだに電化されて
いないため、この狭い空間に、Class800はディーゼル
エンジンを積む必要があった。
古い陸橋などを走行する際に車両が一定の重量を
超えていると、安全確保のために減速を求められる。
その分、鉄道の輸送効率は落ち、収益計画に響いて
しまうのだ。
技術的な難題をいくつも抱えた車両開発だったが、
日立は結果的にこれらを見事に解消した。
DAS(運転支援システム)と呼ばれる運転士用
ナビゲーションも開発したそうです。
(P.032)
英鉄道会社の間では、運転士の能力の差によって、
列車の燃費が大きく変わることが問題となっている。
燃費に2倍ほどの開きがある場合もあるといい、
燃費効率の悪い運転士「ジョイ・ライダー」(運転を
楽しんでいる=enjoyから取った揶揄)をいかに減らす
かが、鉄道会社の課題となっていた。
DASはこの問題を解決するための仕組みだ。
「時速150kmに加速」「ここからブレーキを踏み始めて」
といった具合に、運転士に指示を与え、走行ルートの
電力消費を最小に抑える。
説明文を読めば簡単なシステムのような気がしますが、
実は、これはなかなか制御が難しいシステムだそうです。
(P.032)
単純なシステムに見えるが、現実の運行状況は天気や
故障などのイベントによって次々と変わる。
的確なナビをするためには、列車の状況や運行情報と
常に連携して速度の指示を出す必要がある。
つまり、鉄道の位置情報、運行情報、信号制御といった
システムが、互いに連動していなければならない。
こんなシステムが作れるのは、車両、運行情報、信号
制御といった鉄道インフラを構築するリソースに加えて、
情報技術のノウハウを持っている日立だからこそ。
他の鉄道車両メーカーにはおよそできない芸当と言える。
「Class800」シリーズの製造と、鉄道システムに対する
絶対的な自信は、次の言葉に表れています。
(P.032)
「安全、効率、コスト競争力を兼ね備えた鉄道システムを
作るうえで、日立ほど幅広いリソースを持つ企業はない」と、
日立レールヨーロッパの光冨眞哉CSO(最高戦略責任者)
は話す。

・鉄道関連ビジネスにおける日立のカバー領域
「日経ビジネスDigital」 2015.07.06
解説は下記をご覧ください。

・鉄道関連ビジネスにおける日立のカバー領域
「日経ビジネスDigital」 2015.07.06

・日立と世界大手の鉄道ビジネス比較
「日経ビジネスDigital」 2015.07.06

HITACHIの魅力①で見たように、高速鉄道車両と
鉄道システムが英国に受け入れられた理由は、
英国の鉄道事情に精通した人物に「本気」で権限
委譲したからでもあります。

「日経ビジネスDigital」 2015.07.06
(P.034)
「アジアや南米など、欧州以外にも大きいビジネス
チャンスが広がっている。我々は挑戦者だが、
他社にない強みで自信を持って攻めていく」。
こう意欲を燃やすドーマーCEO。
最近では、この「欧州で最も勢いのある鉄道メーカー」
で働こうと、アルストムやシーメンスなど競合他社から
転職を希望する人材も後を絶たないという。
社歴や実績に関係なく、それぞれのエリア・事業で、
「最も市場が分かる人間」に権限を持たせる──。
グローバル経営では当たり前の鉄則だが、
国内の日立は長年、当たり前のこの権限委譲が
なかなかできず、苦労を重ねた。

バーチャルカンパニーという実験をしているそうです。
成果が上がってきているということで、強固な構造を
壊す働きをしています。
一言で言えば、部分最適から全体最適への移行の
ため、権限や経営資源を集中させたということに
なります。
(P.035)
バーチャルカンパニーとは、日米欧で別々の会社を、
あたかも1つの会社のように運営する仕組みのことだ。
実際に2014年秋以降、製品開発についてはITプラット
フォーム事業本部の開発トップを兼務するHDS(日立
データシステムズ 註:藤巻隆)のジョン・マンスフィー
ルド上級副社長を頂点に、チームの組成から実際の
開発まで完全に一体運営されている。
HDSはもともと、メーンフレームやストレージ(外部記憶
装置)を米国内で売る販売子会社だったが、
2000年代後半以降、M&Aでストレージ周辺のソフト
ウエア開発力を強化。
ストレージ製品の管理やメンテナンスなどサービス・
ソリューションビジネスにシフトした。
今では年間約2兆円を売り上げる情報・通信システム
事業の中でも、特に重要な子会社の一つだ。
バーチャルカンパニーを通じて実現したいこととは、
何でしょうか?
(P.036)
「真に実現したいのは、セールスのオファーを
ワンストップで開発陣に伝えることと、
1つの目標に向かってスピード感のある開発体制
を実現すること。組織の統合も検討したが、
これは法的に別の会社でも実現できると考えた」
と熊﨑(裕之)氏(現サービスイノベーション統括
本部長兼社会イノベーション事業推進本部・
共生自律分散推進本部本部長 註:藤巻隆)は
振り返る。

日立が抱えていた問題とは何だったのでしょうか?
中西宏明会長兼CEO(最高経営責任者)は、
次のように語っています。
(P.037)
「モラル(規律)とモラール(やる気)の問題を
抱えていた」。
中西CEOがこう振り返るように、HDSは実績
こそ上げていたが、独立心が強く、
日立グループの一員として協調していこうと
考えるような会社ではなかった。
そんなHDSの雰囲気が2009年、中西CEOなど
の社会イノベーション宣言を機にがらりと変わる。
ストレージ技術はセンサー技術と並んで、
スマートシティーやスマートグリッド、ヘルスケア
など日立が言う社会イノベーション事業を進める
上で不可欠な要素。グループ全体がそこへ突き
進むなら、日本本社と手を組んだ方がストレージ
単体を売るより、自社の将来は確実に開ける。
多くの社員がそう考えるようになったのだ。
一方、HDSを率いるジョン・ドメCEOはこう語っています。
(P.037)
HDSを率いるジョン・ドメCEOは、
「我々は社会イノベーションという共通の目標に
向けて再結集した」と振り返る。
社内をまとめ上げたという点ではドメCEOの功績
も大きい。
社員とのコミュニケーションを絶やさず、
部門や個人の数字ではなく、会社共通の目標達成
を重視する社風を作り上げた。
働きがいなどに関わる表彰を受けているのもその
ためだ。

・GEとシーメンス、日立の売上高と営業利益、営業利益率
「日経ビジネスDigital」 2015.07.06

中国では超高層ビルの建設ラッシュが起こっている
そうです。
超高層ビルに欠かせないものといえば、
高速エレベーターがあります。
その高速エレベーターで日立は抜きん出た存在
となっている、というのが趣旨です。
(P.038)
超高層ビルが次々と建設されている中国は、
世界最大のエレベーター市場。
2014年時点で年間約50万台と世界需要の
約6割を占めるとされる。
そんな市場で14.8%(日立調べ)と最大受注
シェアを抱えるとされるのが日立だ。
成功している最大の理由は、チャンスと分かれ
ば躊躇なくリスクを取り、大きな投資をしてきた
こと。その結果、現地での存在感が高まり、
多くの優秀な中国人社員が入社し、
さらにビジネスが拡大するという好循環も生まれ
ている。
日立グループにおける中国地域の売上高は
1兆2400億円に上り、全売上高の12%を占める
見通しだが、エレベーターはその大きなけん引役
となっている。
問題は、広大な中国全土をカバーするため、
社員教育のための研修センターと、
保守拠点をどこにどれだけ設置するかという
ことです。
日立はその点でもぬかりはありません。
(P.038)
2015年中に、天津と成都の工場にも研修センター
を建設し、中国全土に約600カ所もある保守拠点
の人員拡充と技能向上につなげる構想だ。

・日立グループの中国におけるエレベーター工場
などの主要拠点と、中国での売上高推移
「日経ビジネスDigital」 2015.07.06
国家レベルで、中国と日本の関係はギクシャク
していますが、日立(私企業)と中国政府は、
どうなっているでしょうか?
良好な関係を維持していると思いますが。
(P.039)
今やエレベーター事業会社の日立電梯を含め、
中国における日立グループは約5万人の従業員
を抱えるまでになった。
その結果、中国におけるビジネスで重要な中国
政府とも、良好な関係が構築されているという。
中国の政府関係者なども「すぐに撤退するような
会社ではなく、本腰を入れて中国でビジネスしよう
としていると信頼してくれる」。
こう話すのは小久保憲一・日立グループ中国総
代表だ。

HITACHIの魅力⑤に関連して、中国ビジネスで
重要な点は、現地中国人を採用するだけでなく、
経営も任せることです。
つまり、「現地化」が大きなポイントとなります。
(P.039)
象徴が日立電梯。
つい数カ月前まで、社長から部長級まで約60人超が、
すべて中国人で占められていた。
現在は、社長と部長の合計2人は日本人となっているが、
幹部クラスでの現地人比率は圧倒的に高い。
このような、現地人材を大胆に登用するという日本企業
らしからぬ人事戦略が、中国におけるエレベーター事業
の急成長につながったとも言える。
「中国人社員は特に上昇志向が強い。部長級のみならず、
いずれ社長にもなれる可能性があるのだから、
自然に現地従業員のモチベーションは上がる」
(日立電梯の中国人幹部)。
加えて、中国人幹部が、欧米や日本など中国以外の海外
拠点で活躍できるようになるグローバル共通の人事制度
も日立グループで始まっており、現地人材の意欲はさらに
高まっているという。
日立は海外で着々と実績を積み上げてきた、
グローバルで戦うための施策を国内でも導入
しようとしています。
(P.039)
日立が海外で進める改革の最終目標は、
その成果を日本に持ち込み、“外圧”によって
日本の日立を変えることだ。
その試みは既に、実践に移され始めている。

日本は昔から“外圧”に弱いと言われてきた
日立はグローバルな世界での実績を引っさげて、
“外圧”によって、日立本体を変革しようとしています。
むしろ、海外よりも国内のほうが変革に対して抵抗
が強いと考えられます。
グローバルスタンダードに適応させるべく、
日立は自ら脱皮しようとしています。
硬い皮を剥ぐには大きな軋轢が伴いますが、
放っておけば死を招くことを、日立のトップは
十分に自覚しています。
「脱皮できない蛇は死ぬ」
という格言があります。
好むと好まざるとにかかわらず、国内も変えること
が現経営陣の使命です。
今特集のキーワードを確認しておきましょう。

外弁慶企業
総合力
権限委譲
社会イノベーション
外圧
最終回は、
「PART2 “外圧”で国内も変える」
をお伝えします。
ご期待下さい!
藤巻隆(ふじまき・たかし)オフィシャルブログ-
人気のブログランキング
こちらのブログやサイトもご覧ください!
こんなランキング知りたくないですか?
中高年のためのパソコン入門講座(1)
藤巻隆のアーカイブ
本当に役に立つビジネス書