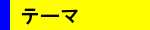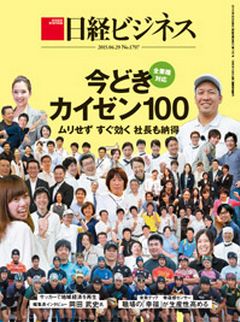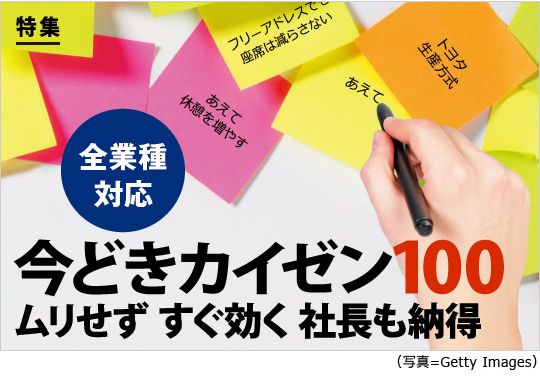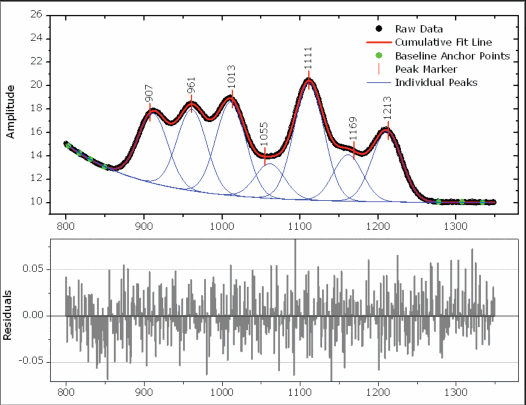「危機の時代」を乗り越える新しい統率力
小学館101新書 2011年9月25日 初版第1刷発行

<目次>
はじめに 能力なきリーダーしかいない日本の不幸
第1章(現状認識)
東日本大震災でわかった「危機に克つリーダー」の条件
[スピード]
1週間でできない「緊急対策」は、1年かけてもできない
[危機管理力]
組織のイメージを最小限にする工夫と判断が必要だ
[行動力と交渉力]
次世代の国家リーダーに求められる「3つの条件」
第2章(対策)
組織を元気にするリーダーシップの育て方
[ビジョナリー・リーダー]
世界で勝つ企業は人材育成に毎年1000億円かけている
[中間管理職“再生術”]
組織を動かすには「“揺らぎ”のシステム」を使いこなせ
[新・人材教育カリキュラム]
リーダーシップは“天与”のものではない
第3章(比較研究)
日本が学ぶべき世界のリーダーシップ
[イギリス・キャメロン首相①]
弱冠43歳にしてトップに立ったリーダーはどこが凄いのか?
[イギリス・キャメロン首相②]
「グレート・ソサエティ」構想で活かすべき「民の力」
[ロシア・メドベージェフ大統領]
「結果を出す指導者」の驚くべき決断力と行動力
[日本vs中国リーダー比較]
国民の差ではなくリーダーの差が国家の関係を規定する
第4章(提言)
私が「リーダー」だったら日本の諸課題をこう乗り越える
【震災復興】
「緊急度の掌握」ができなければ非常時のリーダー失格だ
【電力インフラの再構築】
原発と送電網は国有化、電力会社は分割して市場開放せよ
【食料価格の高騰】
世界の農地に日本の農業技術・ノウハウを売り込め
【水資源争奪戦】
水道事業を民営化して「水メジャー」並の競争力をつけよ
【エコカー開発競争】
劇的な低価格を実現し、世界市場で優位に立つ「新EV革命」
【財政危機】
所得税・法人税ゼロの「日本タックスヘイブン化」で経済は蘇る
おわりに 「強いリーダー」は強い反対意見の中から生まれる
[スピード]
1週間でできない「緊急対策」は、1年かけてもできない
未曾有の危機に際しては、復旧や調整という発想
ではなく、大胆に新しいものを生み出すくらいの
オプションを考えて真に有効な対策を打ち出す。
それが有事のリーダーの役割というものである。
優れた経営者というのは、普段から「ビジネス・
コンティニュイティ(BC/事業継続性)」を
どう確保するのかを考えていなくてはならない。
そういうことを24時間考えていなかったら、
もう経営者を辞めるべきなのである。
問題解決のためのチームを結成したら、
1週間以内に現状分析と今後の対策、
そして工程表を作らねばならない。
これまでの40年間、経営コンサルタント
として多数の企業の危機に対処してきた
私の経験からすれば、1週間かけても
それができないような組織なら、
1年かけたってろくな対策はできない。
その集中力とスピードがなくては、
有事のリーダーは務まらないのだ。
今月(3月)11日、あの東日本大震災が発生してから、
ちょうど2年になります。
あれほど、毎日何時間にもわたって現地の状況を
報道してきたマスコミは、取り上げる機会が激減
しました。
被災地の現況は、現地に行って確かめない限り、
十分に把握できません。
私は、これまでに一度も被災地を訪問したことは
ありません。
ですから、評論家のように上から目線でコメント
することはできません。
今、現地の状況を知ることができるのは、
一部の雑誌かインターネットだけです。
情報は遮断され、「陸の孤島」となっています。
そうした限られた情報を集約して分かってきたことは、
大震災発生直後と現況はほとんど変わっていない、
ということです。
民主党から自民党へ政権が変わっても、
復興どころか復旧さえ行われていません。
安倍政権の政策の目玉は「金融」「財政」「成長」
の3つの矢です。
とりわけ成長戦略を強調していますが、
はなはだ疑問です。
自民党の得意な公共事業への取り組みは、
目先の景気テコ入れ策に過ぎません。
成長戦略というのであれば、ICT(Information and
Communication Technology=情報通信技術)や
最先端医療などへの取り組みがあってしかるべき
ですが、残念ながら確認できません。
大前研一さんが、この本で指摘しているような、
あるべきリーダーに安倍首相は相応しい人物なのか、
いまだに見えてきません。
リーダーの条件が変わった、とはどういうことなのか?
次回以降も、大前さんの発言に耳を傾けてみましょう。
私たちにも、できることはあるかもしれません。
以上の記事は、2013年3月7日のものです。
東日本大震災からまもなく4年4カ月、
この記事を書いてから2年4カ月が経とうと
しています。
最近では、憲法がらみの報道はされても、
東日本大震災の被災地の現況や、
東電福島第一原子力発電所の状況は、
ほとんど報道されなくなっています。
復興庁が何をしているか、最近聞いたことが
ありますか?
決して「風化」させてはならないことですが、
大震災の現況が報道されず、見聞きしなく
なってくると、私たちもこの大惨事を忘れがち
になります。
「喉元過ぎれば熱さを忘れる」
これはいけないな、と自省しています。
被災者にとっては「大震災」は終わっていない
のです。
日本のリーダーであるべき安倍首相は、
憲法改正や憲法の勝手な解釈に血道を上げ、
東日本大震災のことは「過去」の出来事という
認識なのか、触れようともしません。
ごく一部のボランティア団体や個人は、
今でも大惨事が発生した当初と変わらぬ
気持ちで、被災者に寄り添い、ボランティア
活動に従事しています。
この人たちのひたむきさに頭が下がります。
私は何もできませんでしたし、現在でも、
何一つできません。
批判されても反論する資格はありません。
ですが、日本のリーダーある安倍首相が、
議員数が圧倒的に多いことに驕り、
国会で強気な答弁を繰り返していると、
国民からしっぺ返しを喰らうのはそう遠い
ことではない、と思います。
藤巻隆(ふじまき・たかし)オフィシャルブログ-
人気のブログランキング
こちらのブログやサイトもご覧ください!
こんなランキング知りたくないですか?
中高年のためのパソコン入門講座(1)
藤巻隆のアーカイブ
本当に役に立つビジネス書