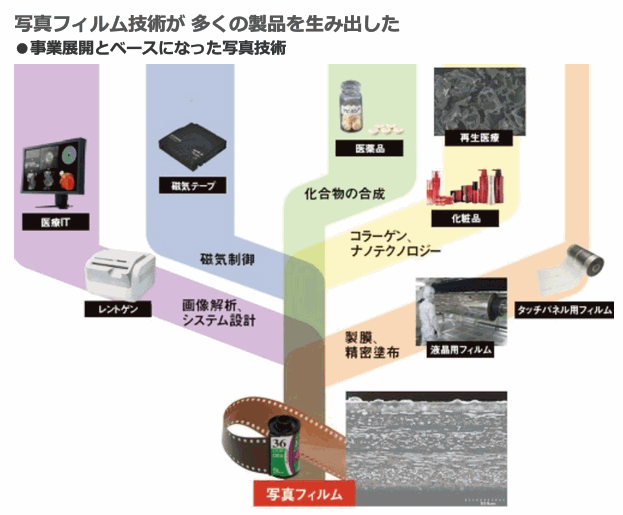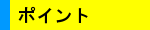概要紹介と、管理人のコメントを掲載しています>
日経ビジネスの特集記事(116)
次はiPS
富士フイルム
古森重隆、本業を培養する
2015.07.20
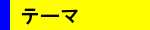
今週号の特集のテーマは
富士フイルムホールディングスの総帥、
古森重隆が最後の大勝負に打って出た。
見据えるのは、医薬業界の秩序を根底から覆すiPS 細胞。
100兆円市場の覇権を握るためなら、ノーベル賞学者とも
別の道を行く。
次々と新たな事業を創出し、本業喪失の苦境から復活した
富士フイルムは、競合ひしめく医薬・医療業界で新たな本業を
「培養」できるか。
先駆者の新たな挑戦は、日本企業にとって指針となる
(『日経ビジネス』 2015.07.20 号 P.024)
ということです。
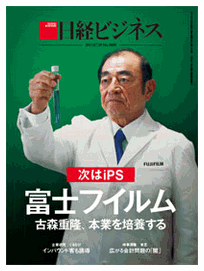
富士フイルム
古森重隆、本業を培養する
「日経ビジネスDigital」 2015.07.20

「日経ビジネスDigital」 2015.07.20
第1回は、
「PROLOGUE 勝算は見えている
古森重隆、最後の大勝負」
「PART.1 iPS創薬の覇権を握れ
京大を抜き去り 狙う100兆円市場」
を取り上げました。
第2回は、
「PART.2 異分野攻略の決め手
革新生み出すフィルム進化論」
を取り上げました。
最終回は、
「PART.3 中嶋社長が見せた意地
古森が去っても大丈夫なのか」
をご紹介します。
今特集のキーワードは次の5つです。

iPS細胞
再生医療
革新
異分野攻略
古森以後
今週号の編集長インタビューは、特集のPART.4
「次に次まで読む 6割の勝算で十分」のタイトルで、
古森重隆富士フイルムホールディングス会長兼
CEO(最高経営責任者)でした。
インタビューの詳細は下記をご覧ください。
日経ビジネスのインタビュー(180)
次の次まで読む 6割の勝算で十分
では、本題に入りましょう!
PART.3 中嶋社長が見せた意地
古森が去っても大丈夫なのか
古森重隆会長兼CEOは15年間経営の中枢に
君臨してきました。
そのため、後継者が古森会長と同等、あるいは
それ以上に事業を拡大していくことができるか
どうか、が注目されています。
(P.038)
「大丈夫ですって」
富士フイルムの社長兼COO(最高執行責任者)、
中嶋成博(66歳)は、同じ言葉を2度も繰り返した。
そして、こう続けた。
「1人の経営者だけで会社が動くわけじゃない」。
「古森さんがいなくなったら富士フイルムはどう
なってしまうのか」という記者の質問に、少しばかり
いら立ったようにも見えた。そこには、2012年の
社長就任以来、会長の古森重隆の陰に隠れがち
になりながらも、会社の成長を支え続けてきたという
中嶋の意地がにじむ。

代表取締役社長兼COO(最高執行責任者)
中嶋 成博 氏
「日経ビジネスDigital」 2015.07.20
中嶋氏は社長兼COO(最高執行責任者)としての自負
と危機感を抱いているそうです。
(PP.038-039)
実は、冒頭の「大丈夫ですって」という言葉
とは裏腹に、中嶋は強い危機感を募らせている。
今の時代は「どんな製品も10年から15年のスパン
で衰退期を迎える。だから、常に次を考え続け
ないといけない」という切迫した思いだ。
下のグラフをご覧ください。
写真フィルムの消滅とリーマンショックに見舞われながら、
2つの危機を乗り越えてきました。
このことからも富士フイルムは強靭で柔軟な企業である
ことが分かります。危機の時、企業の実力が試されます。

2つの危機を乗り越えた
・富士フイルムの業績推移
「日経ビジネスDigital」 2015.07.20
将来を見据え、中嶋社長が考えていることは
どういうことでしょうか?
(P.039)
これからも成長を続けるために、中嶋が考えて
いるのが、業態転換の新たなモデルだ。
それを象徴するのが、「小さく」「速く」「多く」と
いう3つのキーワードである。
これだけではなかなかイメージが湧きませんね。
そこで、もう少し詳しい説明を読んでみましょう。
(P.039)
まずは、自社で育成してきたオンリーワン技術
を生かせるような小さい事業を速く、しかも数多く
生み出す。それらを育てながら、新しい経営の柱
になるような事業が見えてきたら、一気に経営
資源を集中させて、さらに大きく育て上げる。
つまり、小さく産んで大きく育てるということです。
そうしますと、経営トップの目利きが重要になって
きます。
(P.039)
中嶋は言う。「ホームランばかり狙っても空振り
だらけになる。ヒットを打つからホームランも
出てくる」。
目指しているのは、単なる多角化ではない。
今経営を支えている本業が、いずれは喪失する
という危機感を持ち続けながら、「未来の本業」
をコンスタントに生み出し続ける新しい仕組みだ。
新しい仕組みの実現を目指す組織があります。
高機能材料開発本部(高開本)です。
(PP.039-040)
それを実現させるための組織が、2013年に立ち
上がった。高機能材料開発本部、略して「高開本」だ。
専任は4人で、ほとんどが兼務。
例えるならば、正規軍が攻めきれない領域をカバー
する「ゲリラ部隊」である。
ここで手掛ける高機能材料は、医薬品などのヘルス
ケアや、グループ会社の富士ゼロックスと並ぶコア
事業の一つ。各事業部から精鋭を集めてチームを組み、
とにかく短時間で、これまで足場がなかったような全く
新しい市場へ果敢に参入する。
もちろん、多少の失敗は覚悟の上だ。
組織横断的チーム(クロスファンクショナルチーム)と
同様なもの、と考えています。
高開本の特徴は次のように解説されています。
(P.040)
高開本の特徴は、製品ごとに立ち上げる
チームの構成にある。
技術、営業担当者のほか、事業の経営を
つかさどる「プロモーター」の最少3人で構成
する。プロモーターが、未来の本業を育てる
ための「小さな社長」と言えるだろう。
プロモーターの責任と権限についてもう少し
詳細に見てみましょう。
(P.040)
プロモーターは、自分のチームが手掛ける事業が、
富士フイルムの強みを生かして大きく育てられるか
どうかを、全社的な視点から常に考える。
必要であれば、経営資源を一気に集中させるため、
社内調整に走る。
実際の「経営」で鍛えられたプロモーターたちが、
「未来の本業」を支える人材の柱になっていく。
一方、富士フイルムの強みを発揮できないと判断
した場合は、見切りを付けるのもプロモーターの
役目になる。足元で、ある程度の売り上げがあった
としても、次の事業へ経営資源を素早くシフトする
ことが今後の課題だ。
富士フイルムに未解決の課題はないのだろうか、
という疑問が湧いてきますね。
長年の課題がありました!
富士ゼロックスとの相乗効果です。
(P.041)
9954億円──。
2001年に富士フイルムが連結子会社化して以降、
富士ゼロックスが担当する「ドキュメント」部門が
稼いだ営業利益の累計だ。
一方、富士ゼロックス「以外」の累計営業利益は
9482億円にとどまる(全社・消去などは除く)。
富士ゼロックスが本業喪失を乗り切る上で重要な
スポンサーだったことが、数字から浮き彫りになる。
富士ゼロックスは富士フイルムが75%を出資し、
複合機などを手掛ける子会社。
2015年3月期の売上高は1兆1780億円と、連結の
約半分を占める。
セブンイレブン店舗に導入した複合機には、
両社の最先端技術が詰まっているという。
だが両社は14年経っても、微妙な距離感を埋めきれて
いない。インターネットを使った遠隔保守サービスでは、
複合機と医療機器で連携が取れていない。
中嶋社長は次のように語っています。
古森会長と中嶋社長の違いを鮮明にしたものと
考えられます。
(P.041)
「古森さんは並外れたリーダーシップを持っている。
これから、同じような経営者が登場するかどうか、
私には分かりません」。
中嶋はこう述べた一方で、自らを鼓舞するかのように
続けた。「言葉は悪いけど、立場が人を作ることもある」。
確かに、古森は剛腕で瀕死の企業を再生させた
「有事のカリスマ」だ。
しかし、これからはカリスマに頼らなくても、本業創出を
続けられるよう、富士フイルムを生まれ変わらせる。
もう古森がいなくても──。
「大丈夫ですって」、と繰り返した中嶋は、心の中で
自分にこう言い聞かせていたに違いない。

古森会長以後
「有事のカリスマ」として富士フイルムを牽引してきた
古森会長兼CEO(最高経営責任者)が勇退した後、
誰が後継者となるのか、またどのような変革を目指す
のか、は衆目の一致するところです。
今特集のキーワードを確認しておきましょう。

iPS細胞
再生医療
革新
異分野攻略
古森以後
藤巻隆(ふじまき・たかし)オフィシャルブログ-
人気のブログランキング
こちらのブログやサイトもご覧ください!
こんなランキング知りたくないですか?
中高年のためのパソコン入門講座(1)
藤巻隆のアーカイブ
本当に役に立つビジネス書