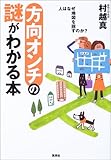ブログネタ:あなたに不足してる栄養素は?
参加中
ブログネタ:あなたに不足してる栄養素は?
参加中人々の交流を促進するデザインもあれば、阻害するデザインもある。
前者をソシオペタルといい、後者をソシオフーガルという。
例えば、内向きで円状に配置された椅子はソシオペタルである。
これによって座っている人々の顔が見渡せ、自然と会話がはずむ。
一方、互いに同じ向きを向かなければ座れないベンチはソシオフーガルである。
これによって、視線は交わることなく会話が阻害される。
家族で食卓を囲むと、なぜか幸せな気分になる。
自然と笑みがこぼれ、会話も弾む。
食卓は、ソシオペタルである。
特に円卓は、四角い食卓よりもデザイン的に優しい感じがする。
角が立たないということだろうか。
アーサー王伝説に登場する円卓の騎士は、王に最大限の忠誠を誓ったという。
彼らは、ソシオペタルである円卓を囲むことによって、互いの絆を確かめ、
前者をソシオペタルといい、後者をソシオフーガルという。
例えば、内向きで円状に配置された椅子はソシオペタルである。
これによって座っている人々の顔が見渡せ、自然と会話がはずむ。
一方、互いに同じ向きを向かなければ座れないベンチはソシオフーガルである。
これによって、視線は交わることなく会話が阻害される。
家族で食卓を囲むと、なぜか幸せな気分になる。
自然と笑みがこぼれ、会話も弾む。
食卓は、ソシオペタルである。
特に円卓は、四角い食卓よりもデザイン的に優しい感じがする。
角が立たないということだろうか。
アーサー王伝説に登場する円卓の騎士は、王に最大限の忠誠を誓ったという。
彼らは、ソシオペタルである円卓を囲むことによって、互いの絆を確かめ、
王への忠義を深めていったのだろう。
家族で顔を突き合わせて食卓で食事をするたびに、そんなことを考える。
やはり、食卓は円卓に限る。
家族で顔を突き合わせて食卓で食事をするたびに、そんなことを考える。
やはり、食卓は円卓に限る。
食卓にはもう1つ役割がある。
それは、お互いの顔や態度から異変を察知するということだ。
顔色や会話の雰囲気などから体調や精神を慮るのである。
つまり食卓は人間の肉体と精神の安定上にとっても必要ということだ。
ということで、現在の私に足りない栄養素は家族で顔を突き合わせる『食卓』だろう。
自分の肉体と精神の安定のためには、食卓を囲んでくれる家族が必要のようだ。
[参考文献]
¥3,885
Amazon.co.jp
- 経済は感情で動く―― はじめての行動経済学/マッテオ モッテルリーニ

- ¥1,680
- Amazon.co.jp
PHP+MySQLであなたもウェブアプリが作れる!/川井 義治

¥2,709
Amazon.co.jp