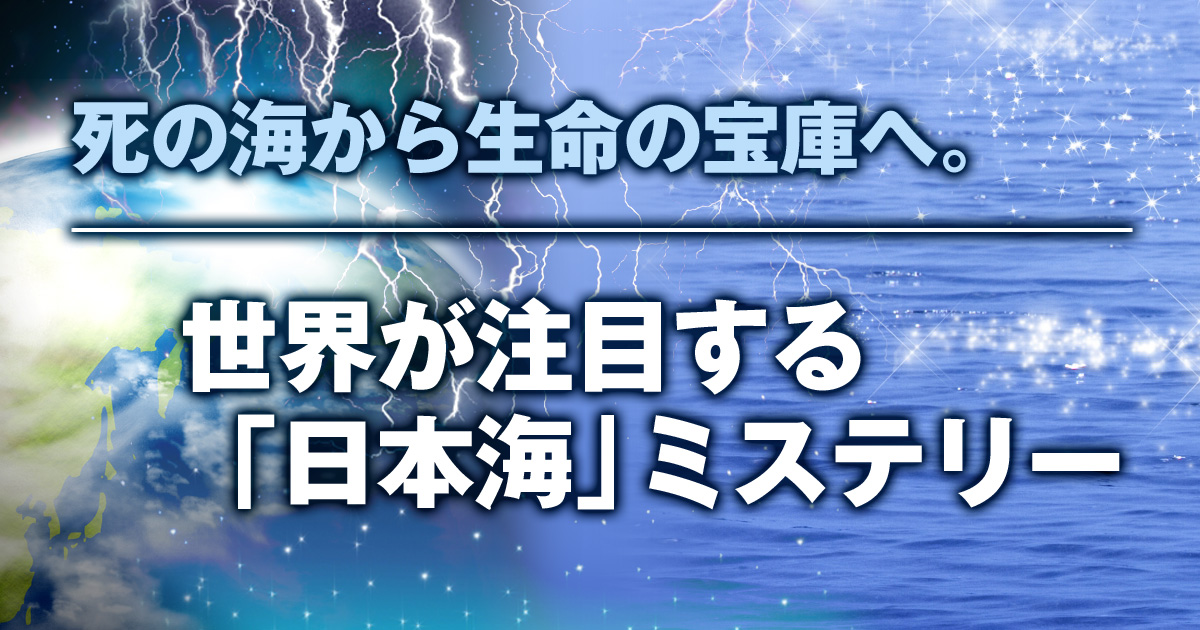現在、対馬海峡の水深約130mであるが、後期旧石器時代の最終氷期最寒冷期には120〜130mくらい海水面が低下したと考えられている。ちなみに津軽海峡は水深140mもあり、最寒冷期でも水路が残った。
すなわち、日本列島の九州島と本州島が最寒冷期に大陸と繋がって、徒歩で移動出来るか否かの瀬戸際にあった。
参考①-1では、対馬海峡は海水面が後退して幅10~15km、深さ10mの水路状に残り、出土する石器は地域として一体となった文化圏をなしていなかったと指摘されている。また、参考④では、後期旧石器時代の香坂山遺跡で出土した石刃について、ユーラシア大陸の東に向かうほど2千〜3千年ずつ新しい年代のものが出土しているが、朝鮮半島から日本列島へは約6千年を要している。
すなわち、現生人類が日本列島に最初に到達した後期旧石器時代の当時、日本列島はユーラシア大陸に繋がることは無かったことになり、当時の人々は適当な舟を用いて渡海したことになる。わざわざ、ユーラシア大陸から切り離された日本列島に渡って来たことになる。
やはり、初めて東の端に到達した現生人類である後期旧石器時代の日本人は日本列島が大陸からの敵や伝染病の侵入が難しい離島であることを認識して、わざわざ渡海したと考えられる。
現在、太平洋の島々に住む人々も、同様な理由で海洋を渡って拡散したのであろう。
寒冷化による人類の南下の結果であることが想定される(中川和哉)との説もあるが、同時期、台湾から海を渡って琉球列島の孤島にアクセスした事例もあり、寒冷化が大きな理由にはならない。
参考
①-1 最終氷期最寒冷期の対馬海峡
後期旧石器時代における日本と朝鮮半島 (中川 和哉、参考)
MIS2の時期には世界的な規模での寒冷化が進み、最終氷期最寒冷期(LGM)には120~130mの海水面低下が報告されている(菅2004)。対馬海峡西水道はその最深部が240mの深さをもっているが、130m前後の海面低下で朝鮮半島と陸続きになる。日本海の隠岐堆から採取されたピストンコア(KH-79-3,m-2、L-3 )をもとに分析がおこなわれ、最寒冷期には日本海の塩分濃度が低下する現象を、黄海が陸化し黄河の河口が済州島の東側にあったとし、黄河水で希釈された海水が開口していた対馬海峡を通じて日本海に流入していたと解釈した(大場1983)。
しかしながら、氷期の日本海への海水の流入量の計算の結果、津軽海峡からの海水流入でも説明することができ、短期間の海峡の存在を完全に否定することはできないという考え(松井・多田・大場1998)もある。
Parkほか(2000)は、対馬海峡の大陸棚が鮮新世から中期更新世までは構造的な傾斜と沈降を経験していたが、それ以外は安定していたという説(Yoo1997)を受け、対馬海峡の音響調査による堆積物や地形、ピストンコアによって採集された貝などの14C年代をもと に第5図に見られるように最終氷期最寒冷期の対馬海峡は幅10~15km、深さ10mの水路状に残ったと結論付けた。
MIS2のうち最寒冷期の年代については、33,000年から26,500年まで氷床の拡大が始ま り、LGMは26,500~20000年頃とされている。(P.U.Clarket.al 2009)。
朝鮮半島と九州本島の間には大小の旧石器時代遺跡のある島が散在する。まとまった発掘調査の事例は少ないが、五島列島の宇久島、小値賀島などの遺跡では、漁労などを行わないと現在の島嶼部の領域では生活できなかったと考えられる。漁労をもっぱらにしないという前提であれば、海水面が低下し、旧石器人の狩猟に必要なテリトリーが十分に確保できる時期に遺跡が形成されたと考えられる。それを示すように剝片尖頭器や原の辻方台形石器などが島嶼部で発見されている。この2種の石器は長崎県百花台東遺跡で共伴して おり、AT降灰直後から2番目の文化様相を示している。これらの状況的証拠や年代から剝片尖頭器の拡散時期はLGM前後であると想定できる。また石材には九州本島からもたらされた黒曜石があり、出土物も九州本島の内容に近い。対馬からの旧石器時代遺跡の報告はないが、他の島嶼部の遺跡では九州的な文化内容を示す遺物が主で、朝鮮半島の石材の嗜好性や石器組成を反映していない。このことは、川状の海峡が非常に狭くなっていたが、地域として一体の文化圏を形成していなかったことを示している。
①-2 日本列島の海峡の現在の水深(講談社BOOK倶楽部、参考)
間宮海峡、宗谷海峡、津軽海峡、および対馬海峡の水深は、それぞれ約10メートル、50メートル、130メートル、および130メートルです。
①-3 津軽海峡の水深(wikiより)
最も浅い所でも140mの水深がある津軽海峡は、中央に大河のような水路部が残った。両岸の生物相が異なる結果となった。
② 3万年前の航海、徹底再現プロジェクト(参考)
後期旧石器時代(5万年前から1万年前に遡る)にあたる3万年前の日本人は、しなくても良い危険な渡海をして絶海の小さな孤島に渡っている。
③ 現在の日本列島は海に囲まれて、大陸からの敵や伝染病の侵入の心配が少なく、安心して生活出来る(参考)