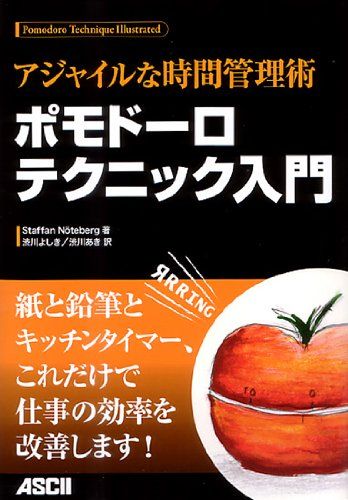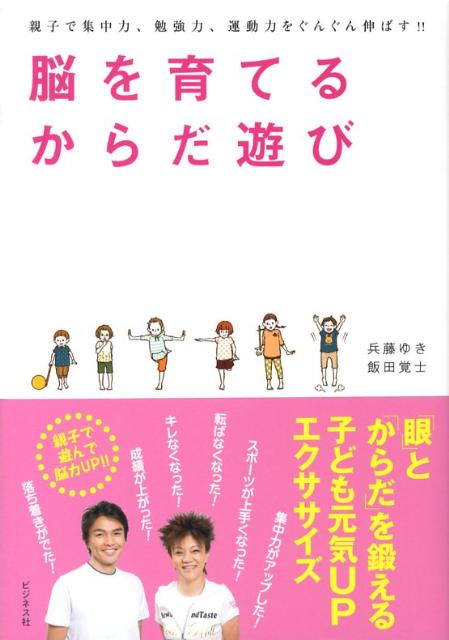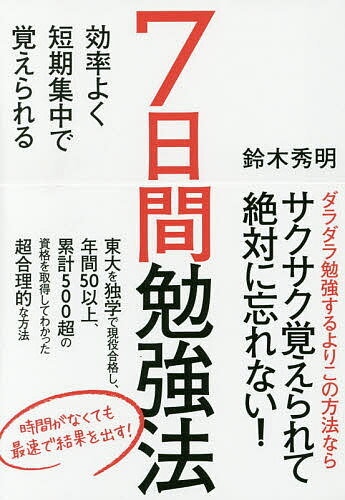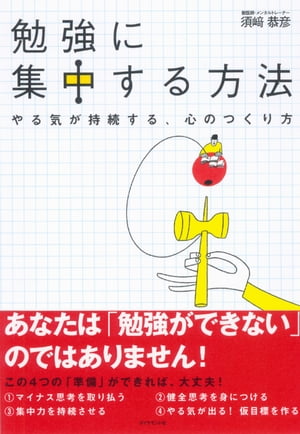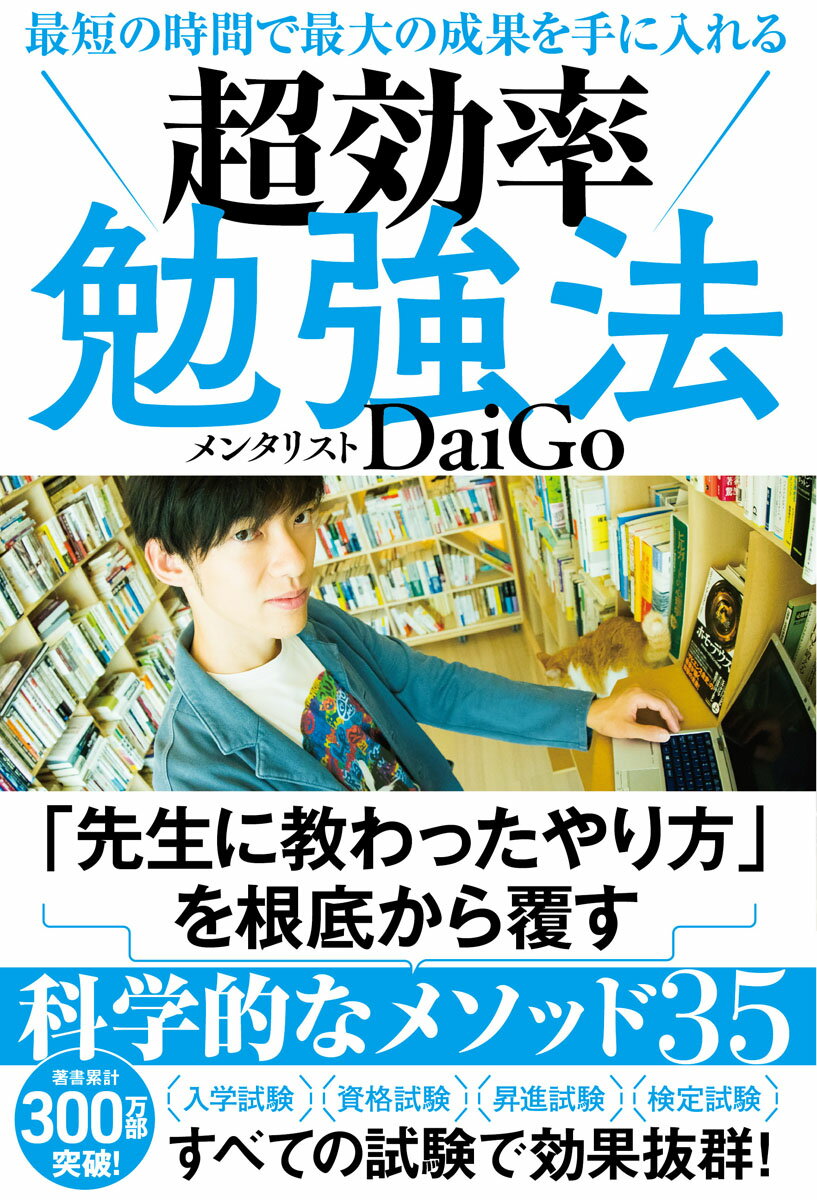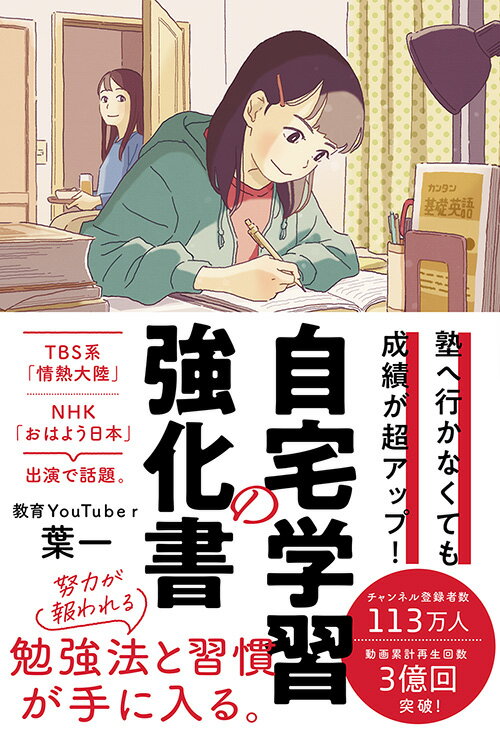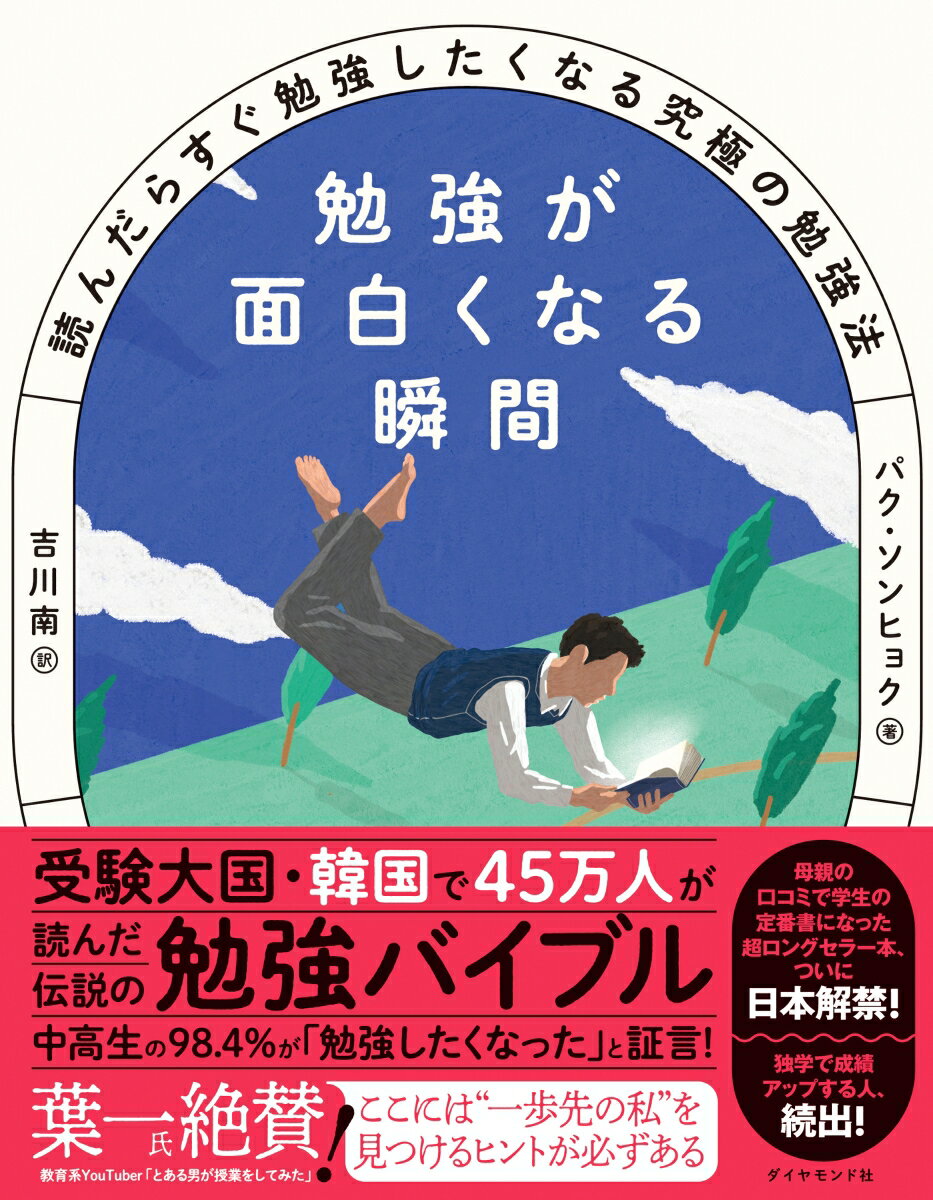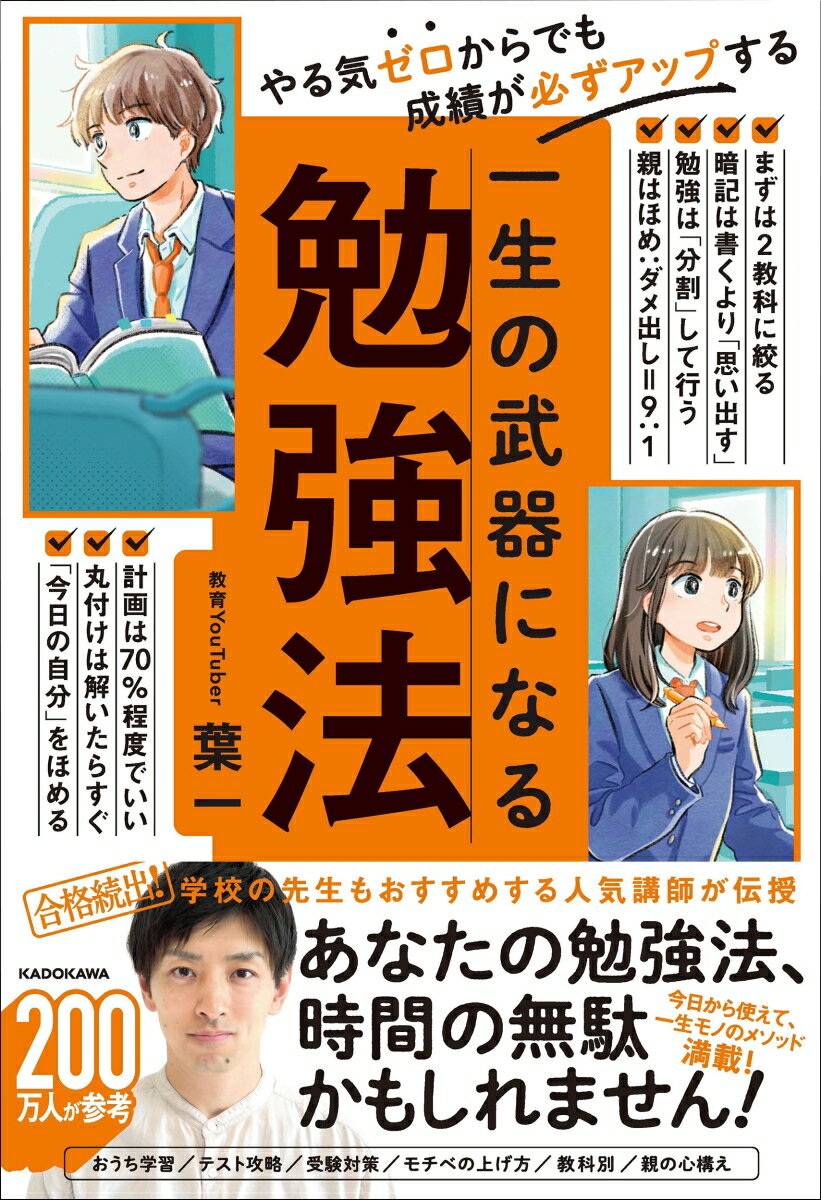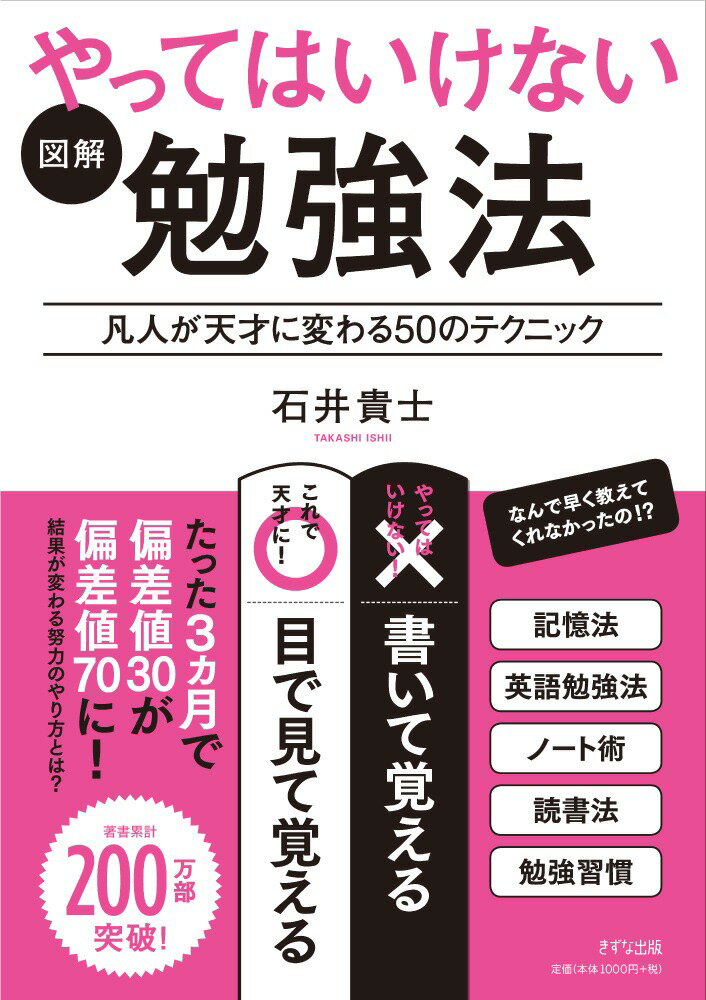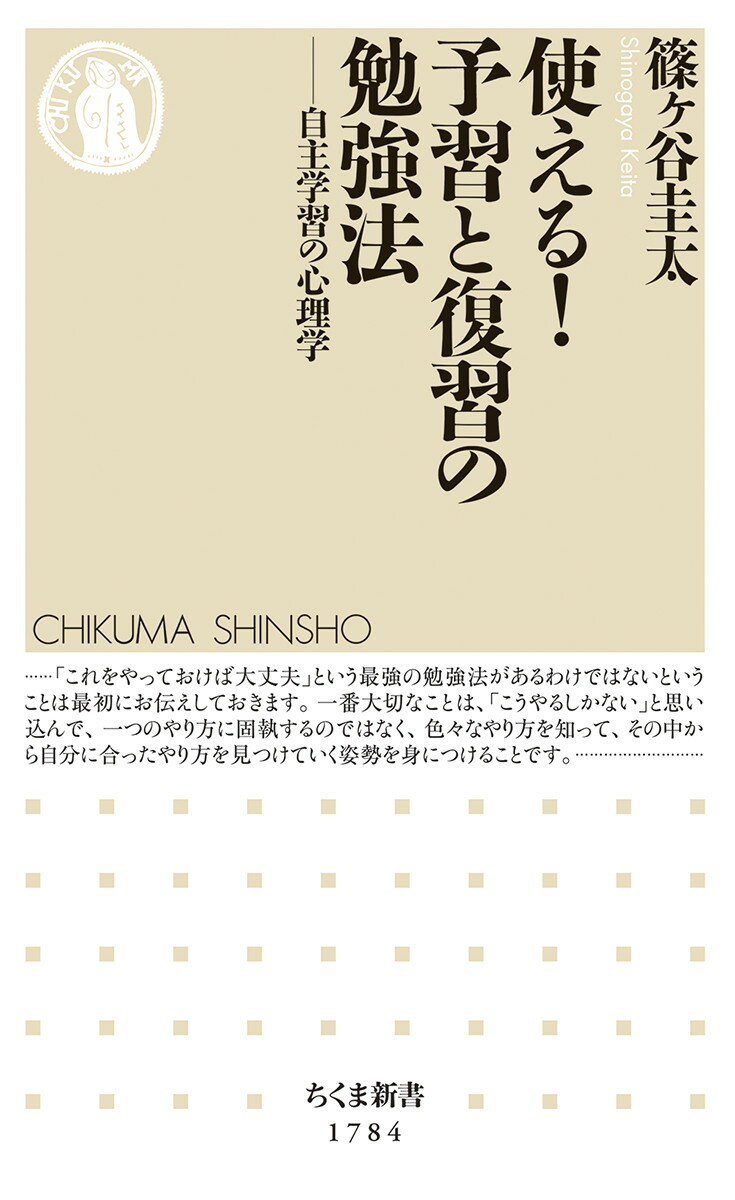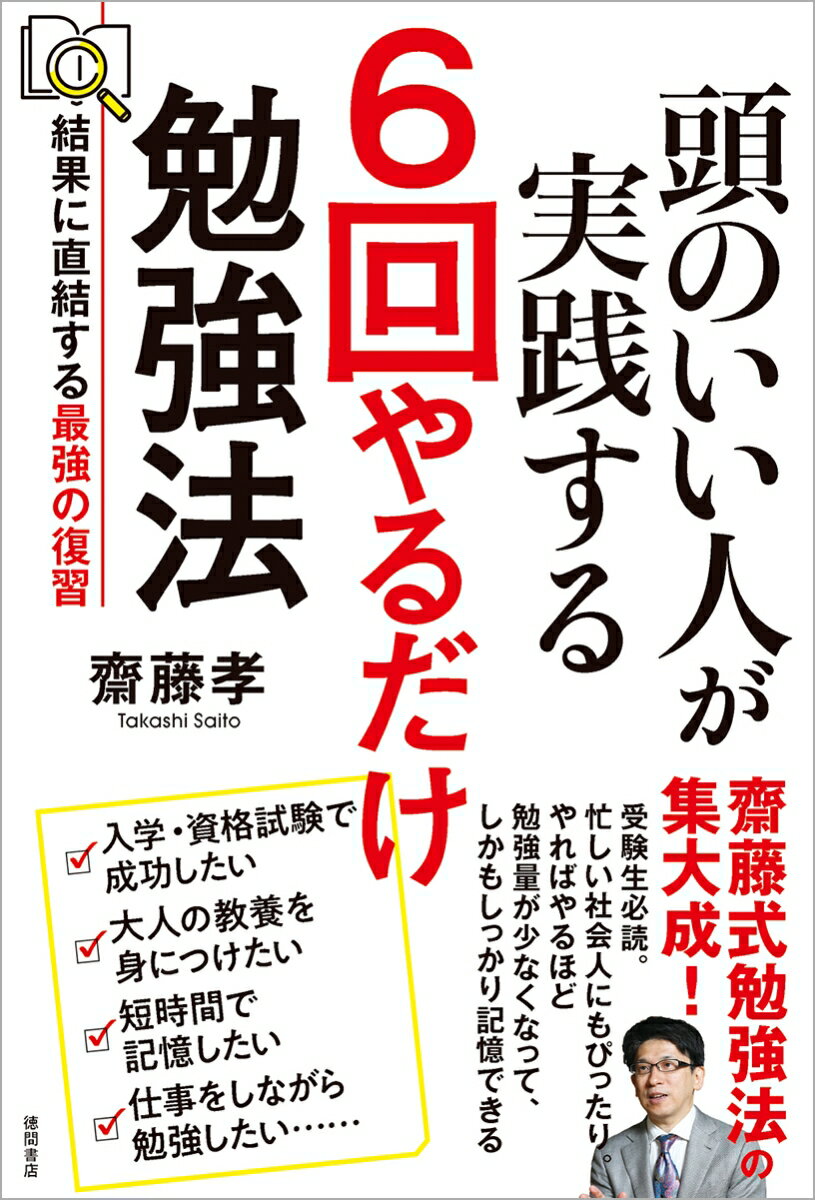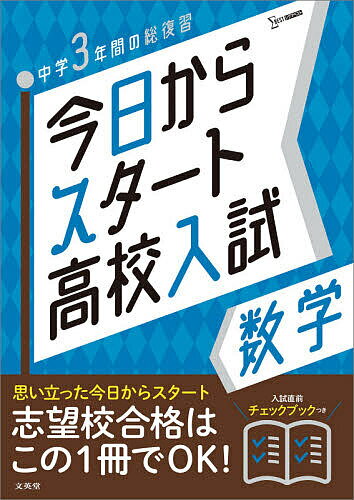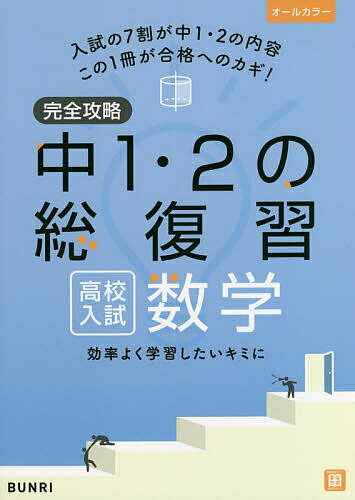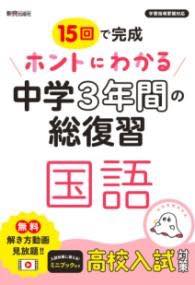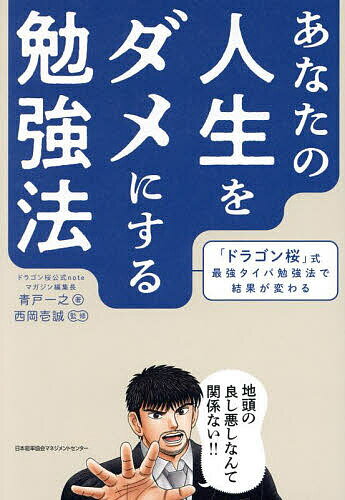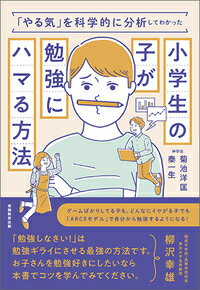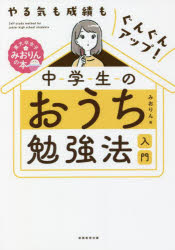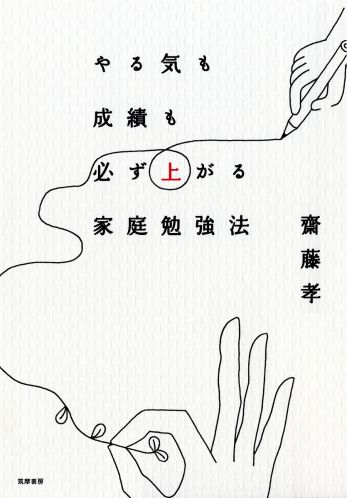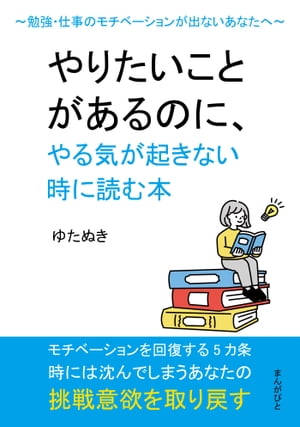もう私立試験が始まってしまいましたね。汗
今日、結果が判る生徒たちがいます。
無事、合格できていますように!
----------------------
さて、今回は、
・新しい教材の使用を避ける
・短時間集中学習(ポモドーロテクニック)
について書いてみます。
■高校受験日までに行うこと(1)
■高校受験日までに行うこと(2):過去問演習
■高校受験日までに行うこと(3):参考書の見直し
これは前回の「参考書の見直し」でも若干触れましたが、この時期から新しい教材は避けましょう。
新しい教材は、内容が難しかったり、見慣れていないせいもあり理解に時間がかかることが多いため、逆に焦りを生む原因となります。
既に学習した内容だと、どこにどんな風に書かれているかが判りますし、安心感が大きいほど、知識を確実に定着させることができます。
特に、過去に学習した内容を復習することで記憶を強化し、試験当日に自信を持って臨むことができます。また、既存の教材を使って、問題集や演習問題を解くことで、実践的な力を養うことができます。

▼短時間集中学習で行ってみる
ポモドーロテクニックで学習をする。
これは25分間集中して勉強し、5分間の休憩を挟むことで効率的に学習が進みます。
この方法は、集中力を持続させるために非常に効果的です。
短時間で集中することで、脳が疲れにくくなり、学習効率が向上します。
また、休憩時間には軽いストレッチやリフレッシュを行うことで、次の学習に向けての準備が整います。さらに、学習の合間に自分の進捗を確認することで、モチベーションを維持することができます。
もし集中が続かない場合は、若干時間を短くしても良いので、一定の時間で回すようにしましょう。
思ったより効果があるはずです。
-------------------------