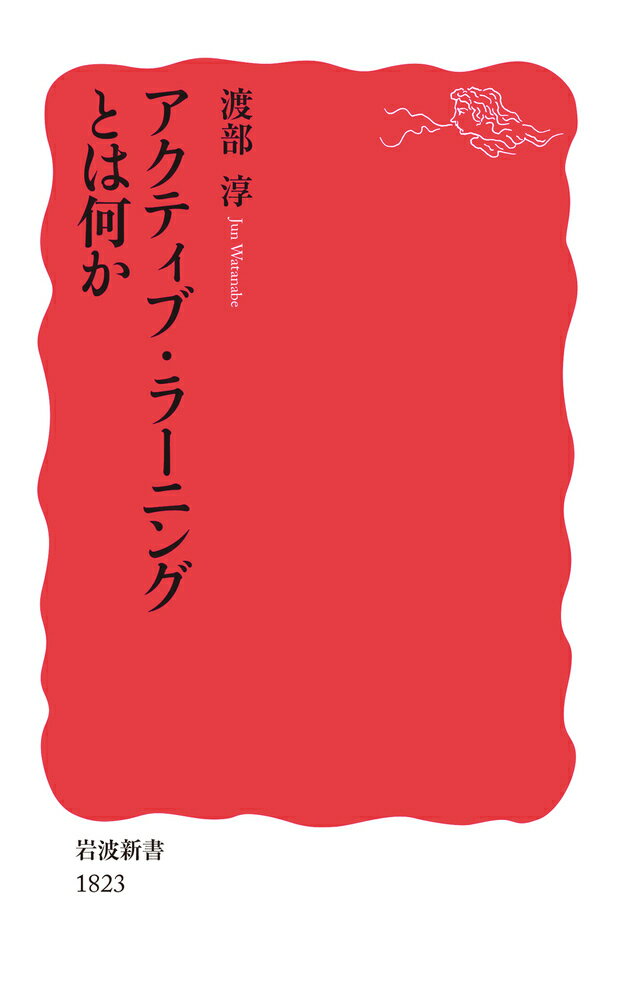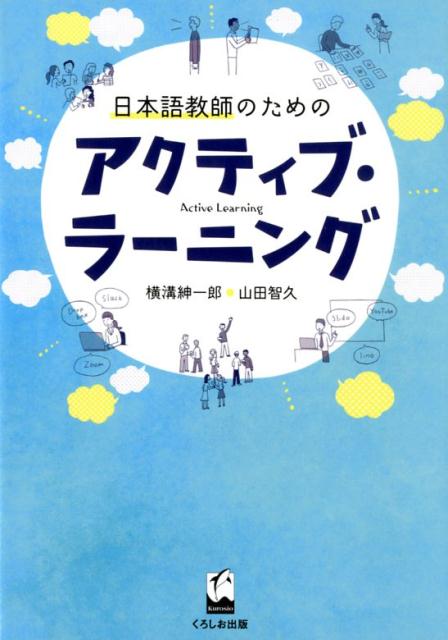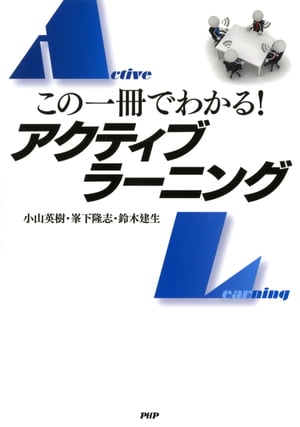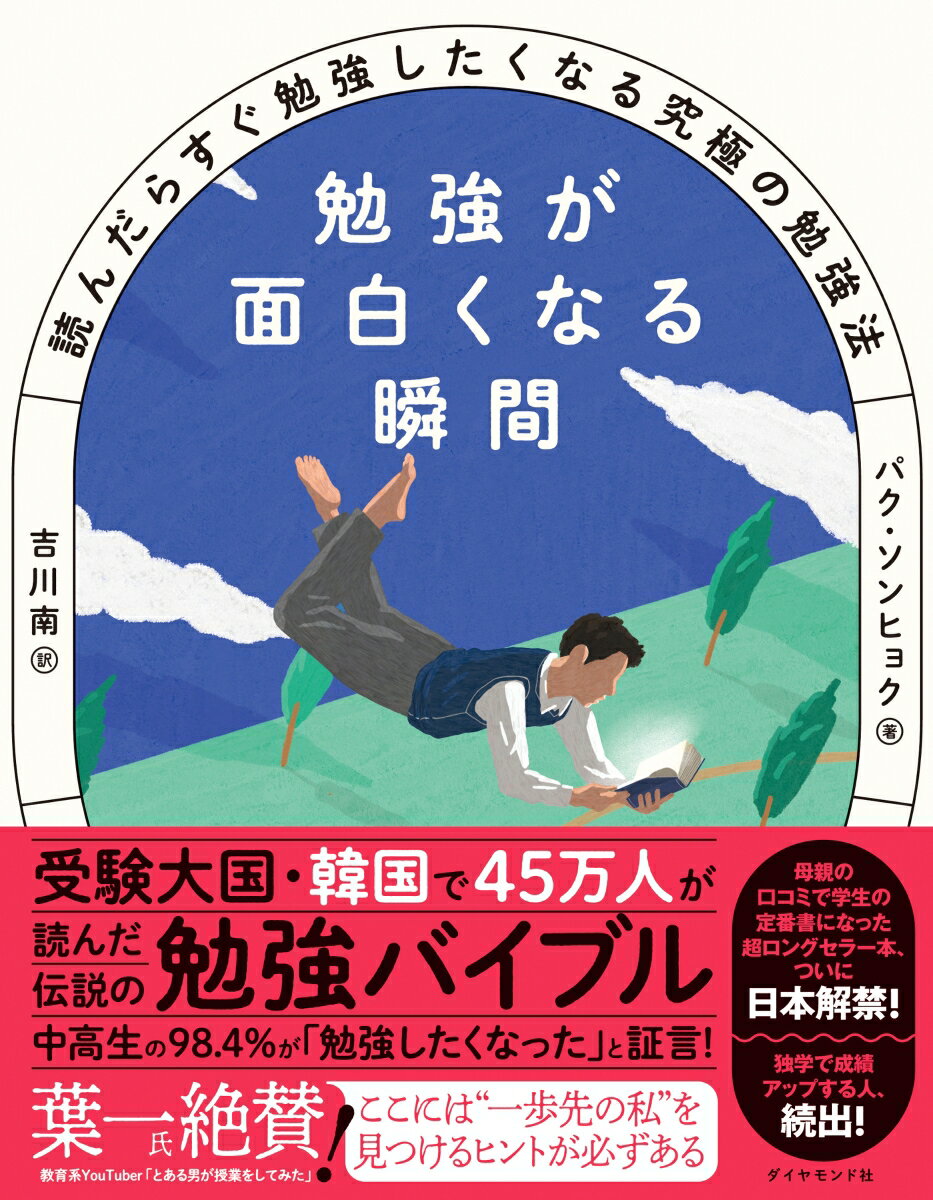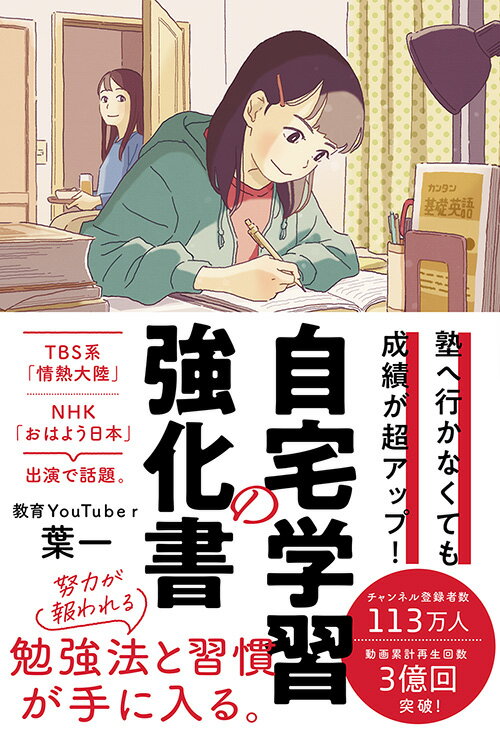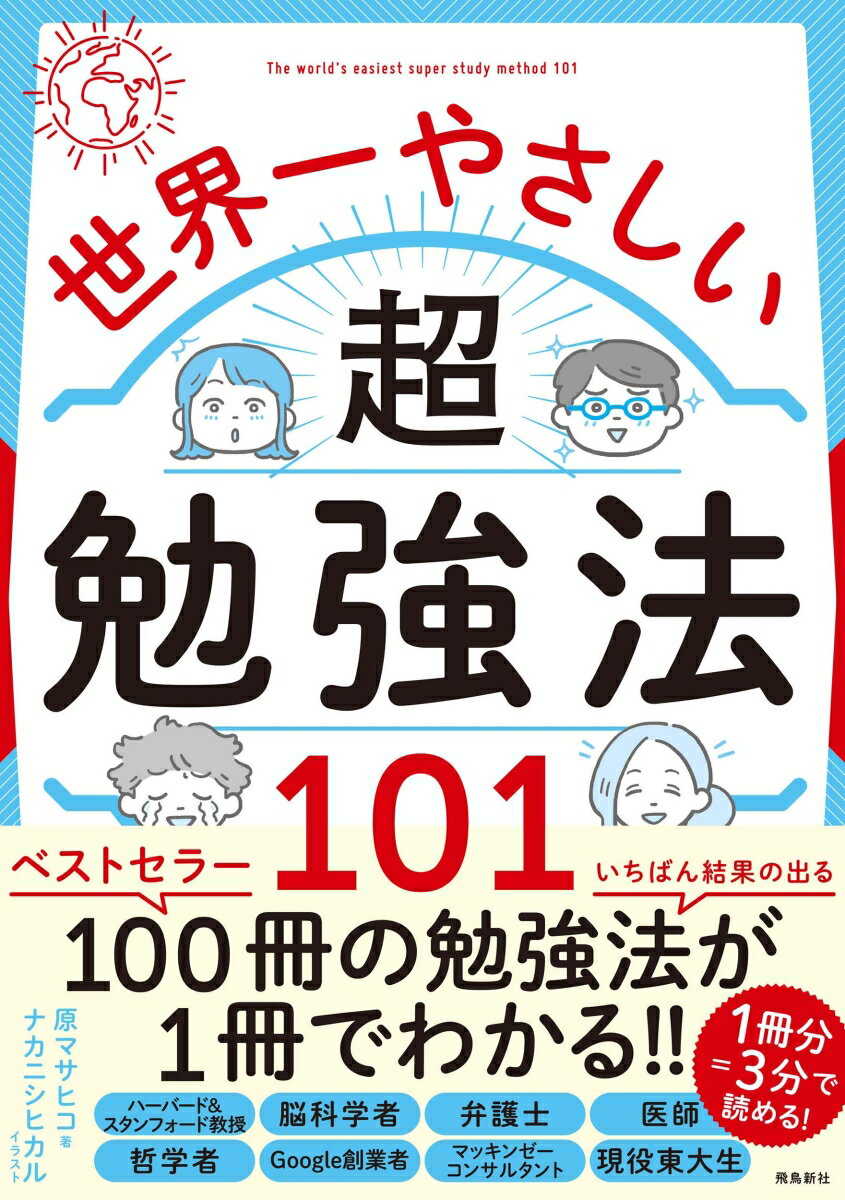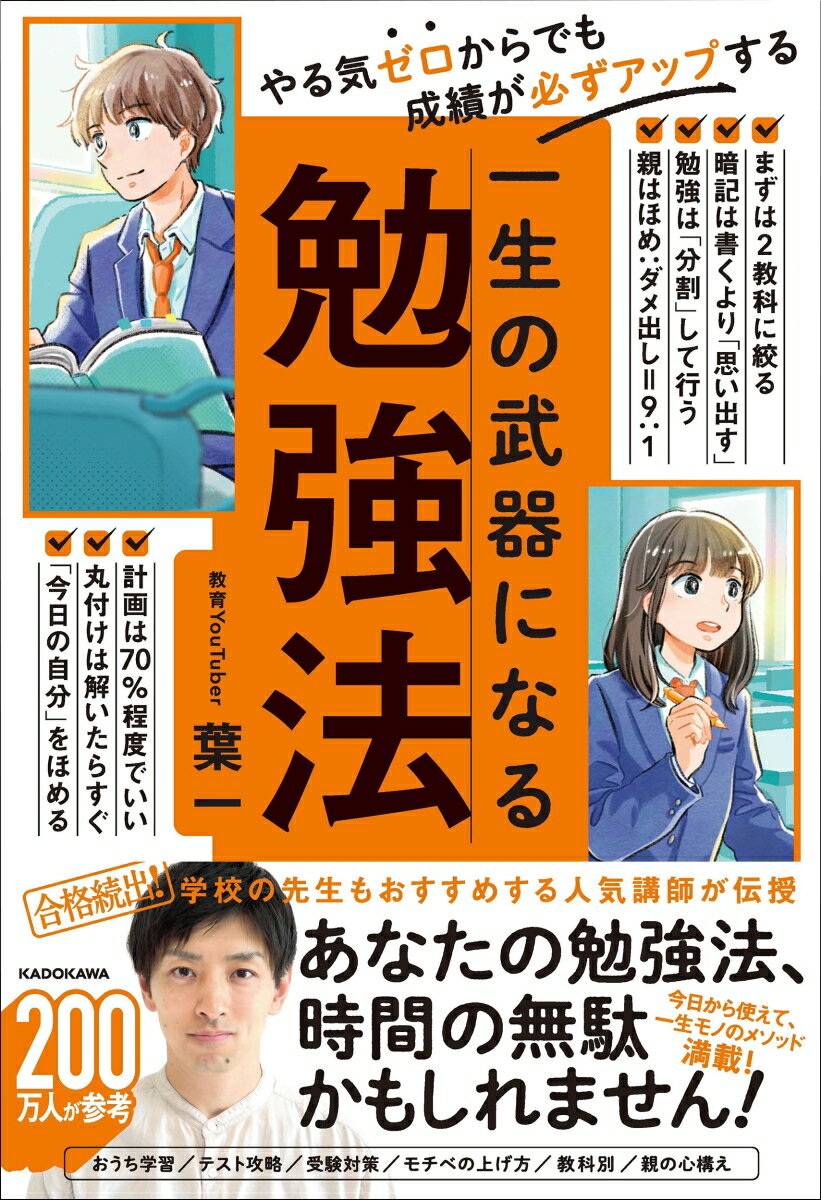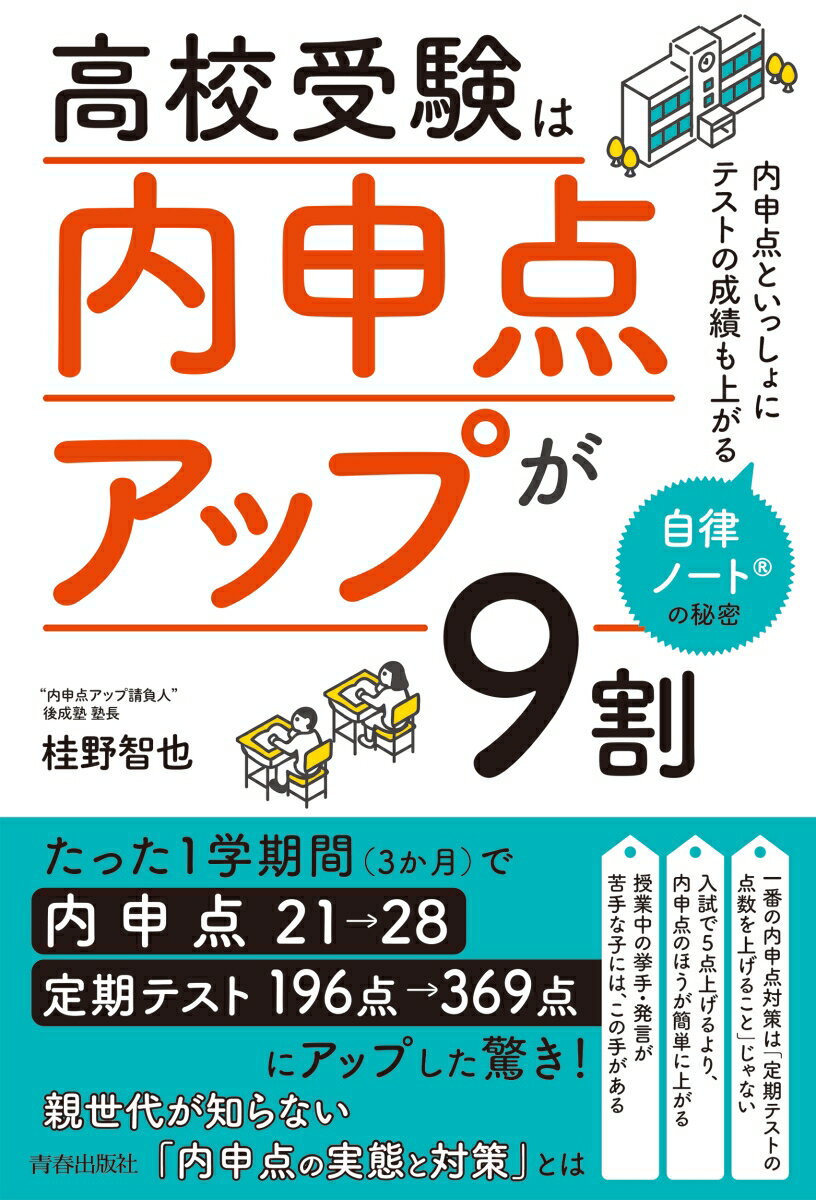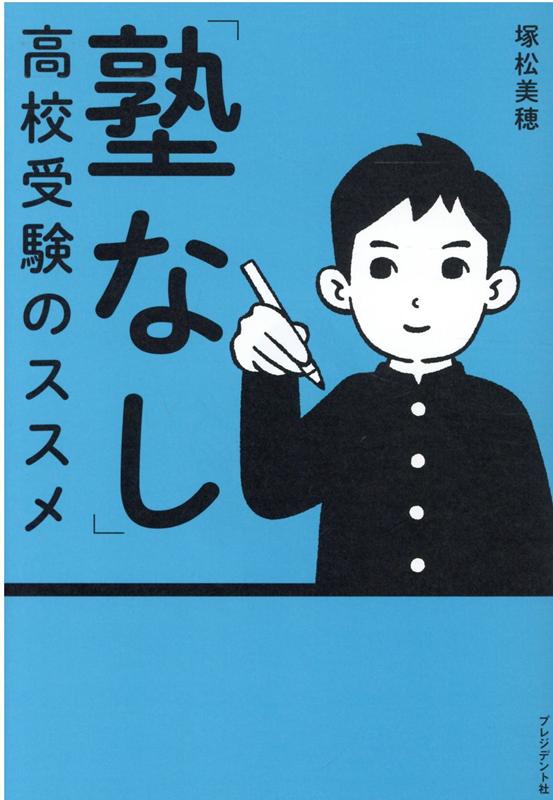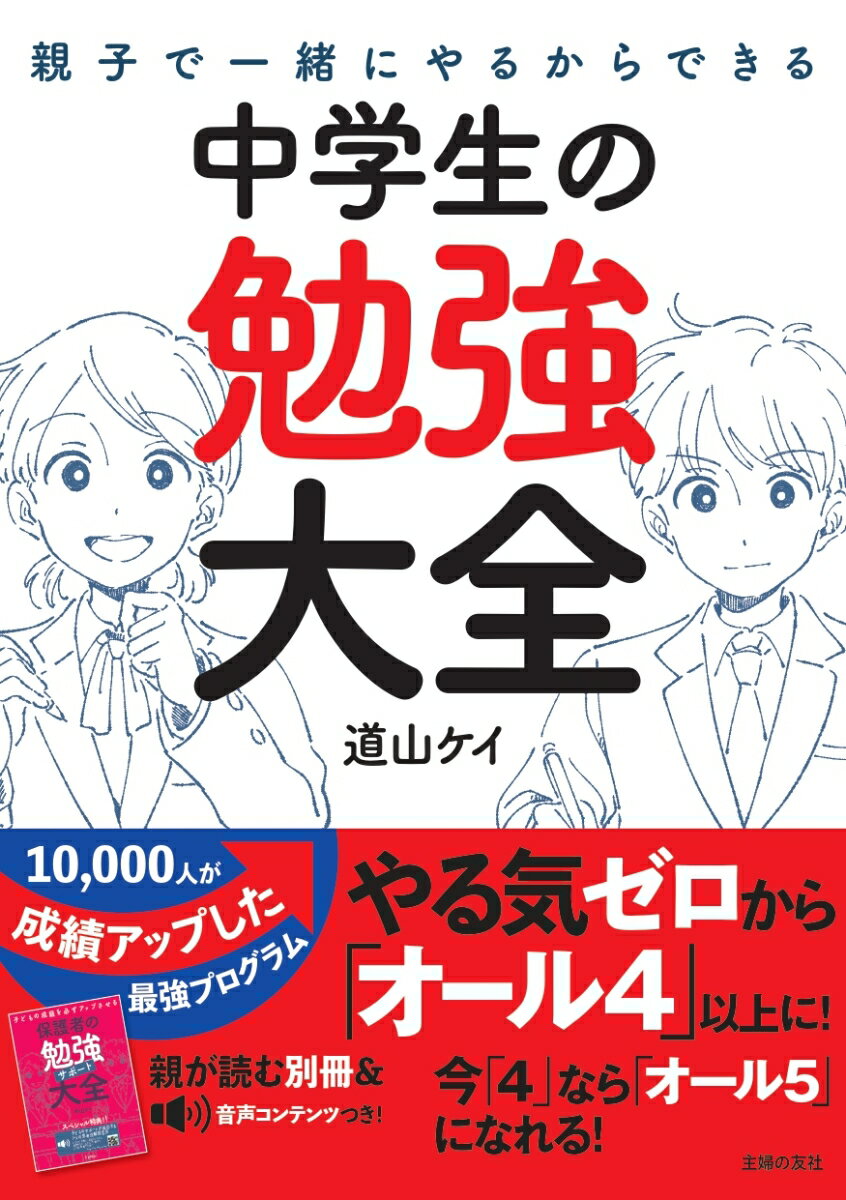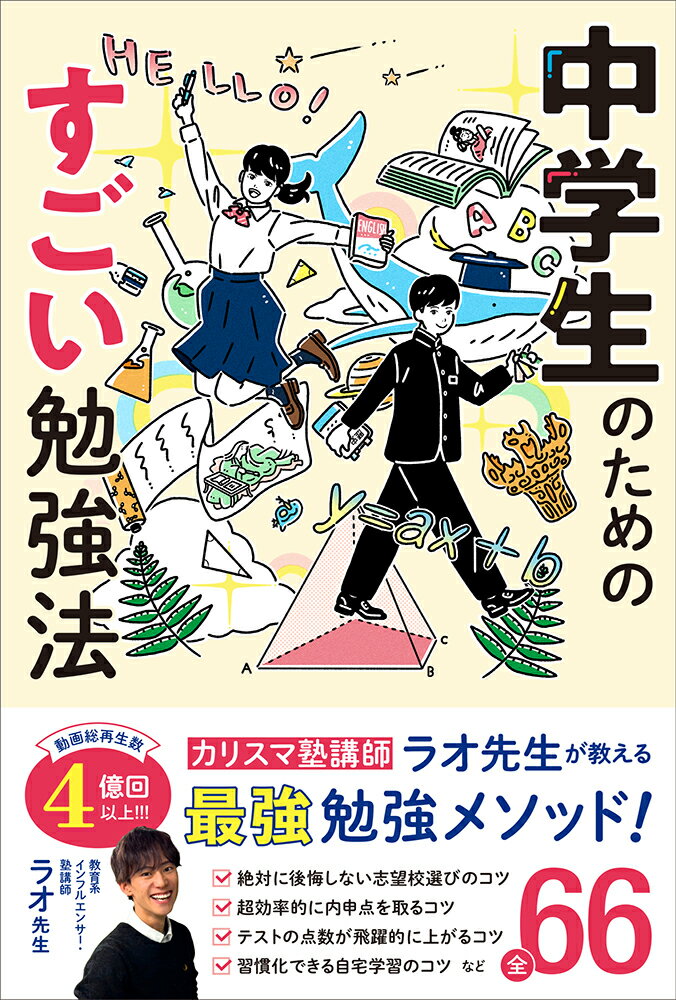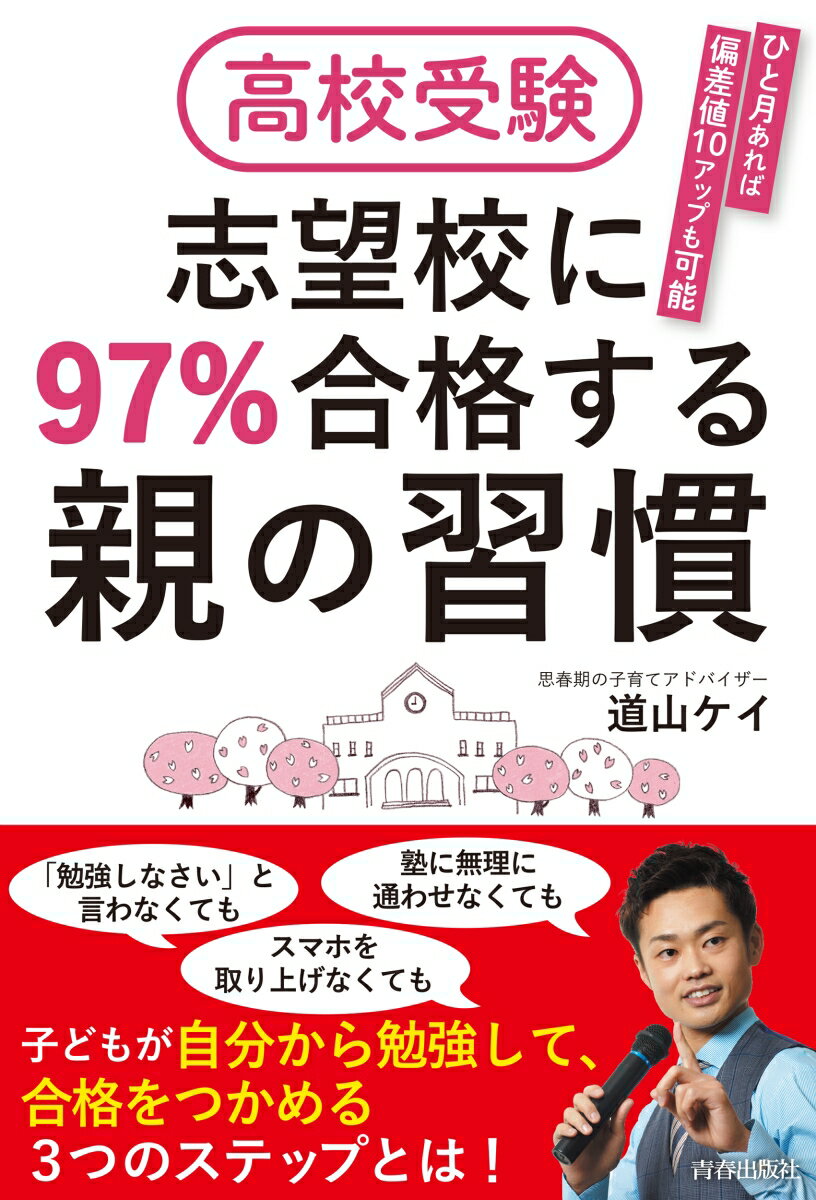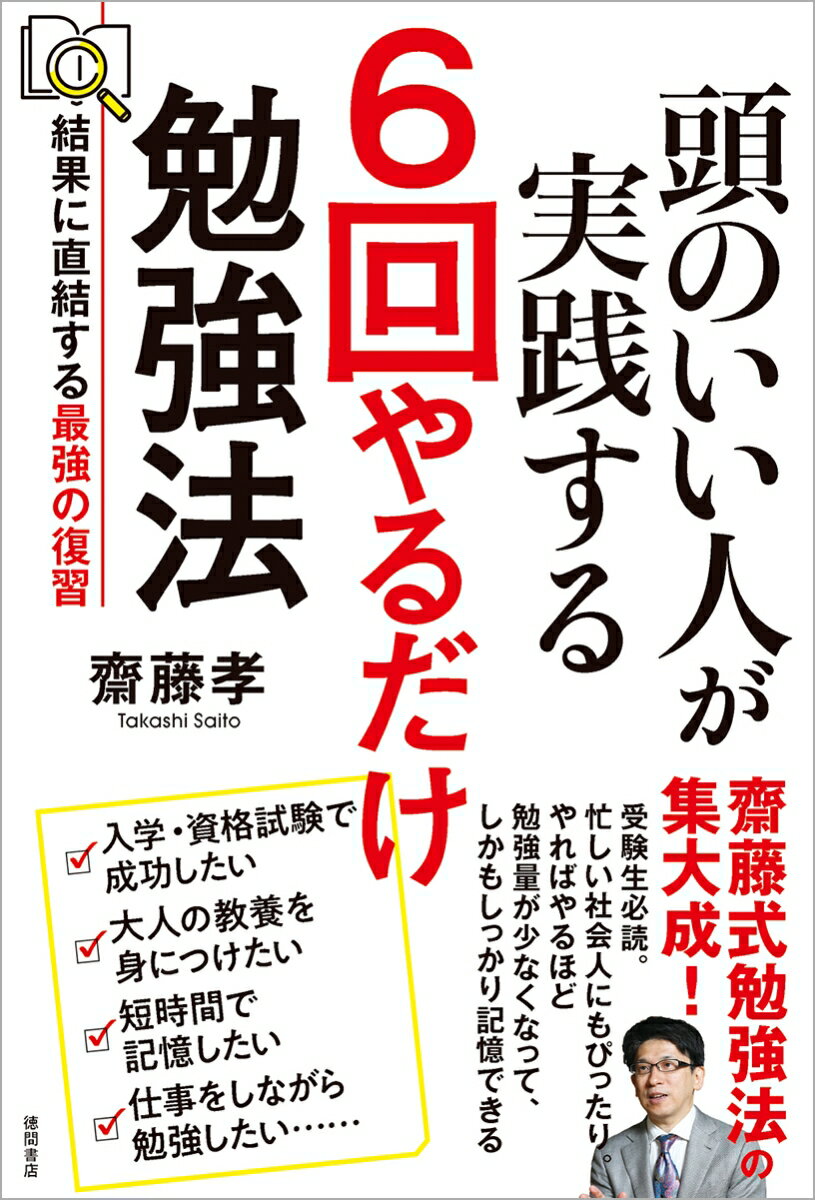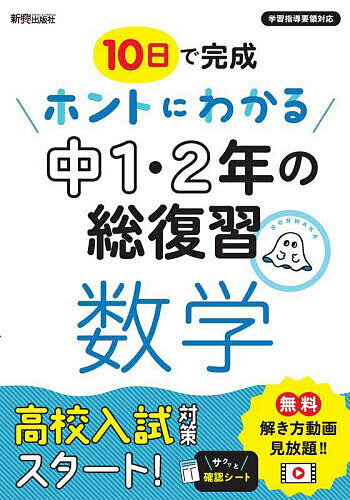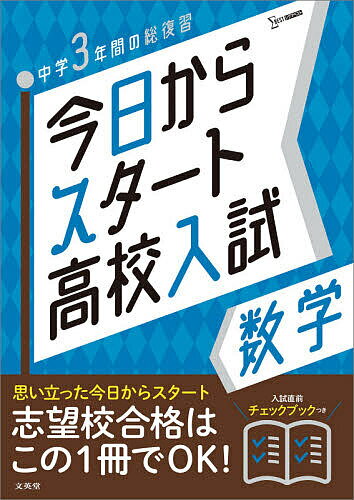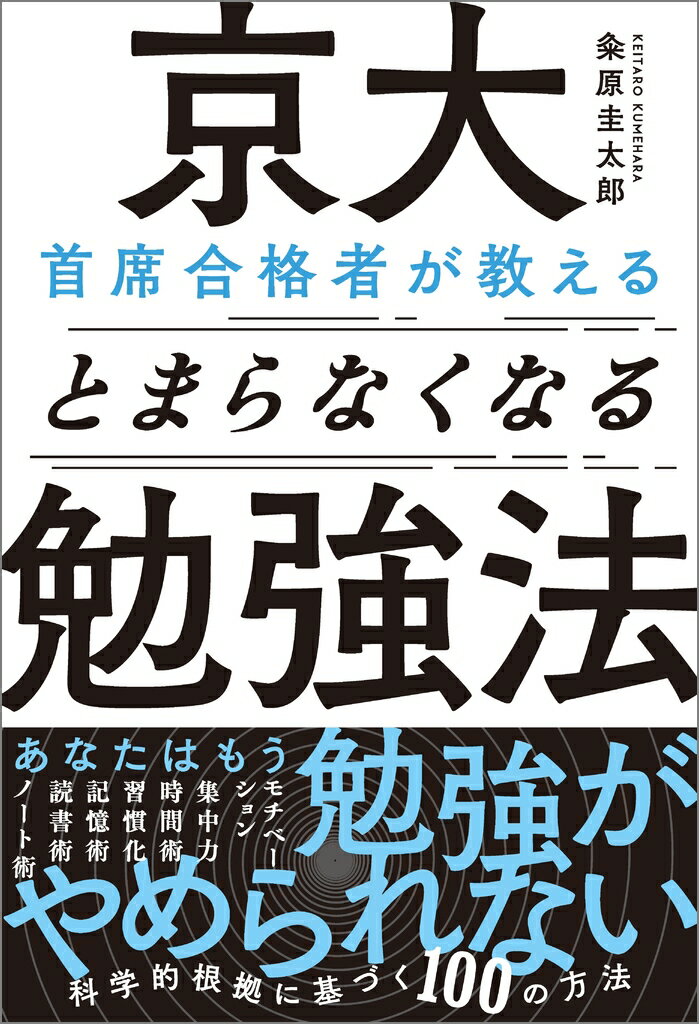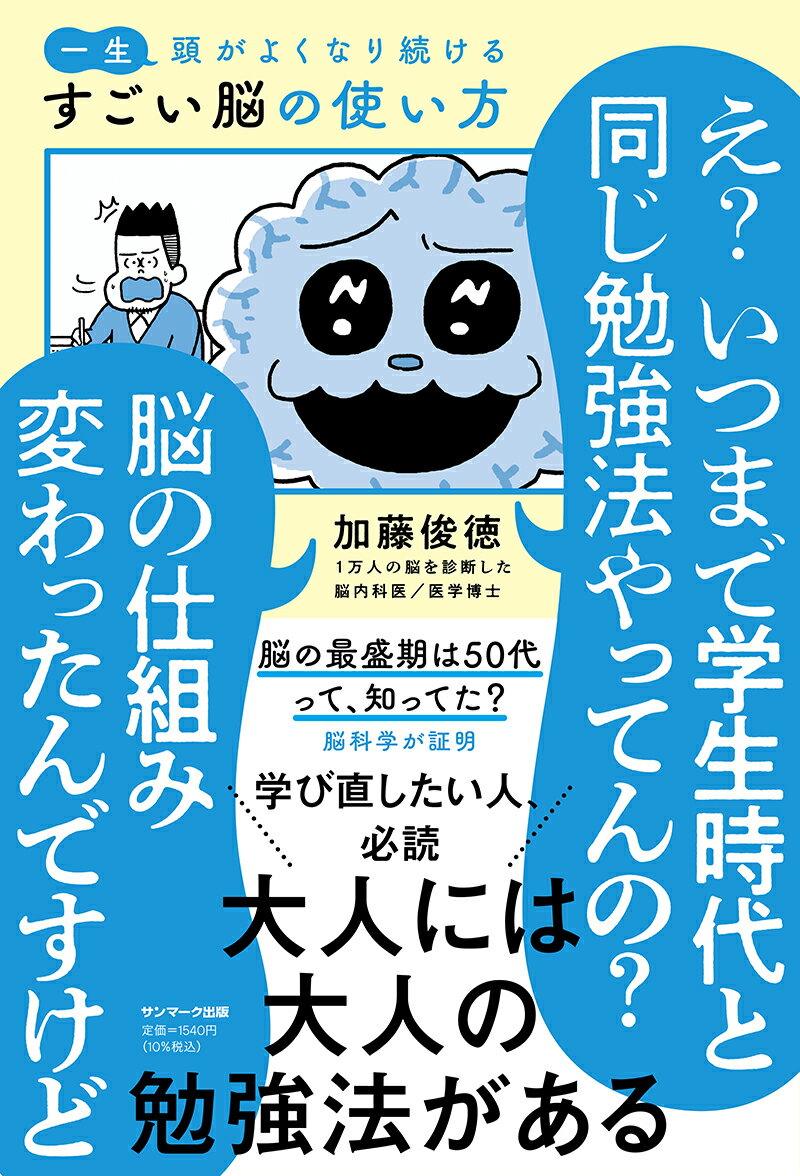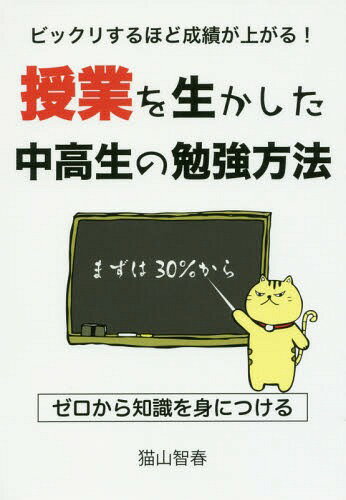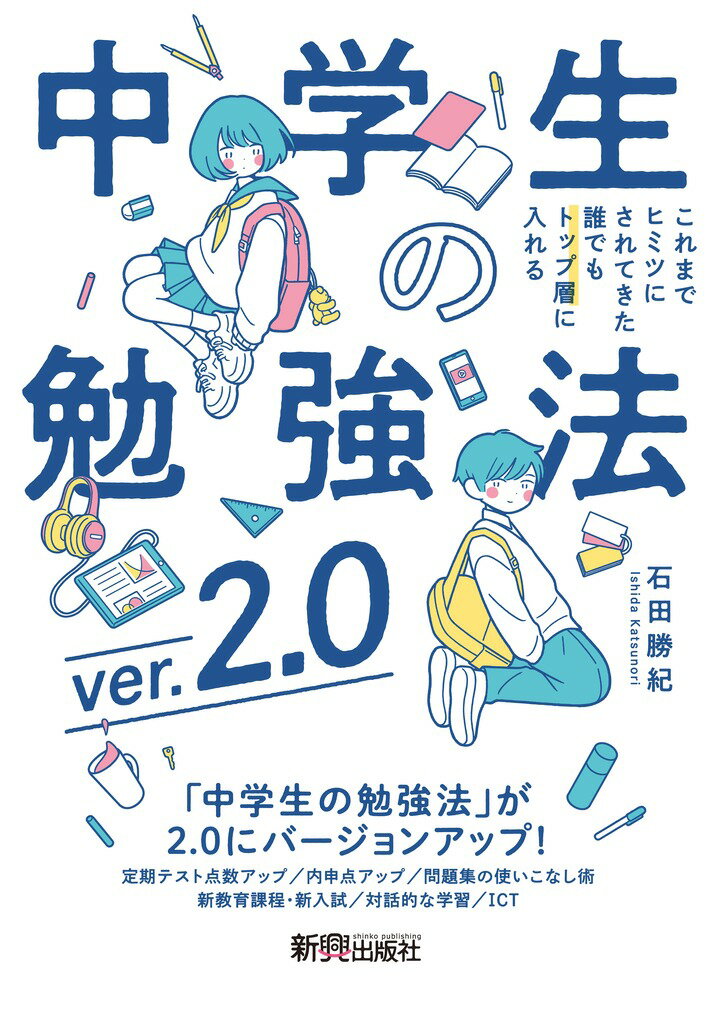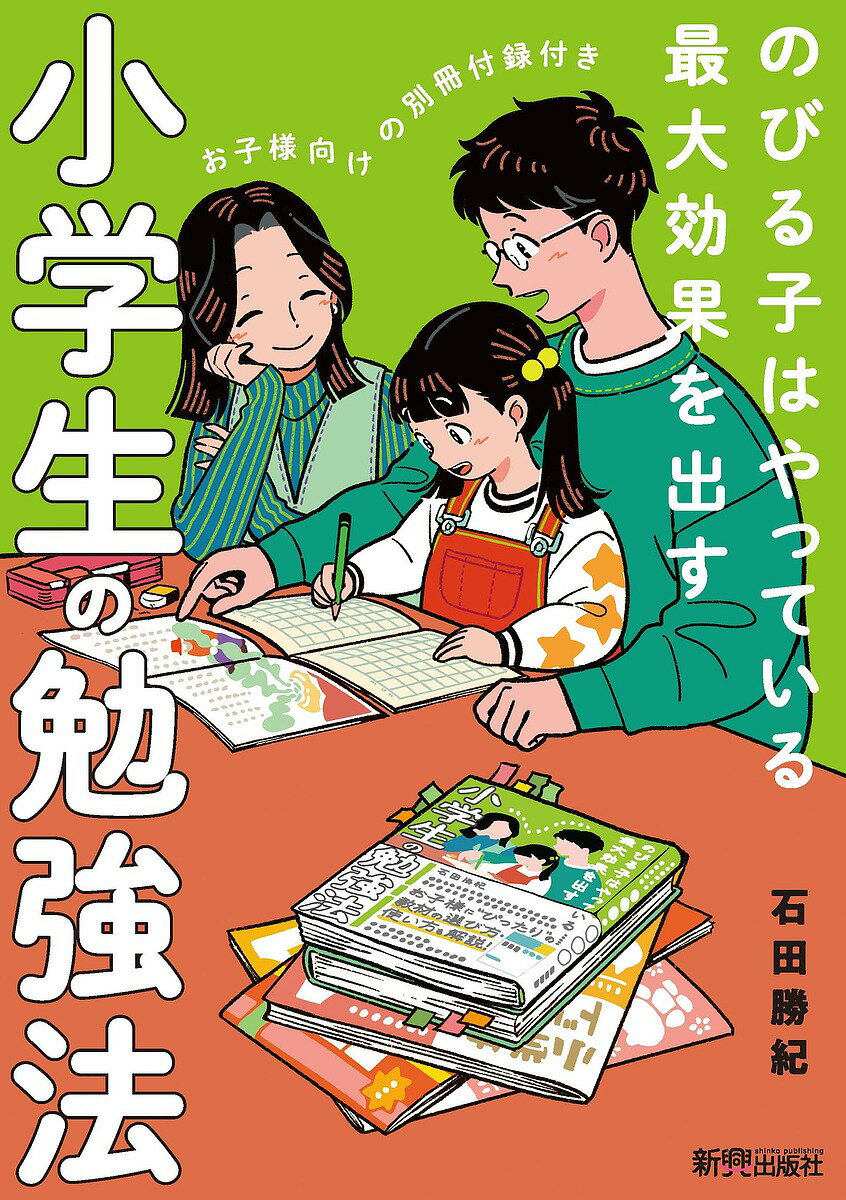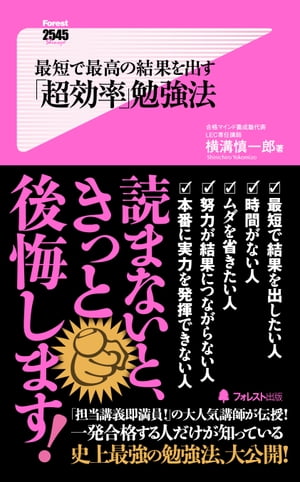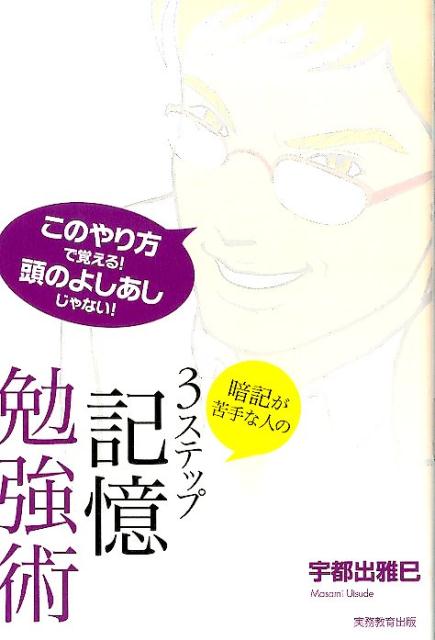まだ気持ちが乗らない?(1)
まだ気持ちが乗らない?(2)
先日、塾生が友達を連れてきました。
中学生の友達ということでしたが、学力が足りていない感じでしたが、本人、
「ちょっと勉強してみても良いかな…」的な雰囲気がありましたので、少しプリントをやらせてみようかと。
レベルを聞いてみると、やはり小学生の復習をしないと厳しそうでしたので、
「判る所からやろう!」ということにしました。
低学年からのスタートです。苦笑
進んでいる子は、先の学年の所をやったりしていますが、とにかくその子に会ったレベルからやらないと、絶対支障をきたすので、一つずつ積み上げようという話にしました。
色々な中学で、きっとこのような現象が起きているのでしょうね。
以前に来た子も、同様な感じでしたので、先生としては大変だったのではないでしょうかね?苦笑
↓↓
■多分、満点を取ったことが無い?苦笑
自分の学力を、周りの友達も理解をしてくれて、一緒に勉強してくれると良いかもと思っています。

教える側にとっても、凄く良い経験になりますし。
(アクティブラーニングをやっている都合上、この形は継続したいと思っています)
多分、進学塾などではなかなか味わう事ができない感じかと思いますし、うちの卒塾メンバーで指導側になる子が多いのはそんな経験が多いからなのかもしれません。
教えるというのは、言語能力を含め、コーチング力、相手の見極め、相手の現在の感情(EQ)など、さまざまなことに気を配ることが大切かと思います。
簡単な言葉で言い換えたり、判っているかを確認したり、相手の立場を理解できるようになります!(^^)v

教師、インストラクター、講師、コーチなど、様々な呼び方がありますが、教える事が楽しくなって来るのかもしれません。
有名スポーツジム、学校、Jリーグ(サッカー)、塾など指導をする現場も様々あるので、才能が開花してくれればと思っています。
----------------------------