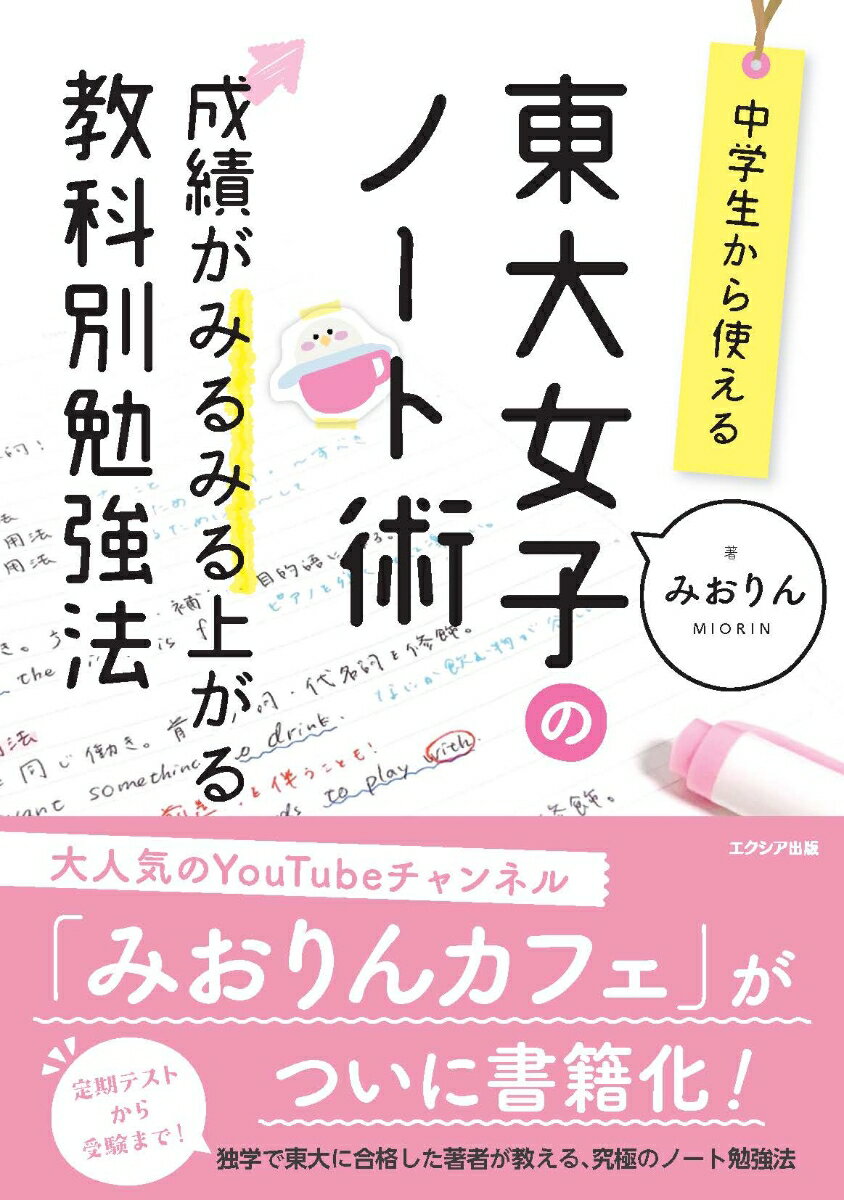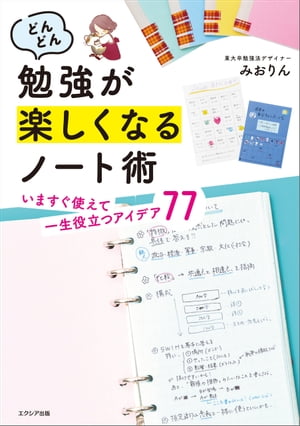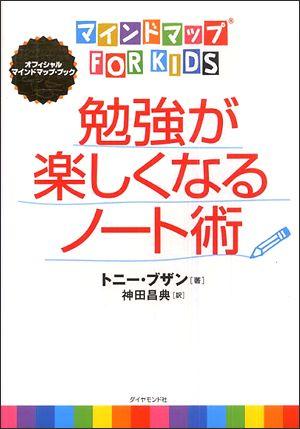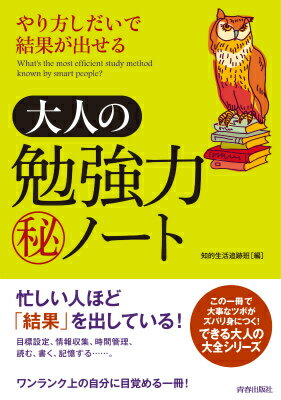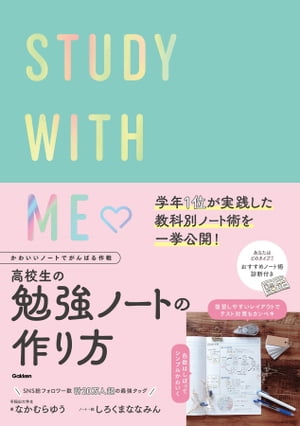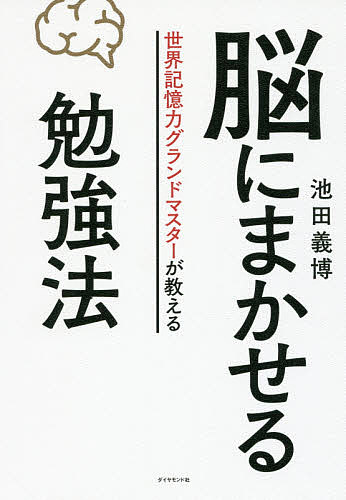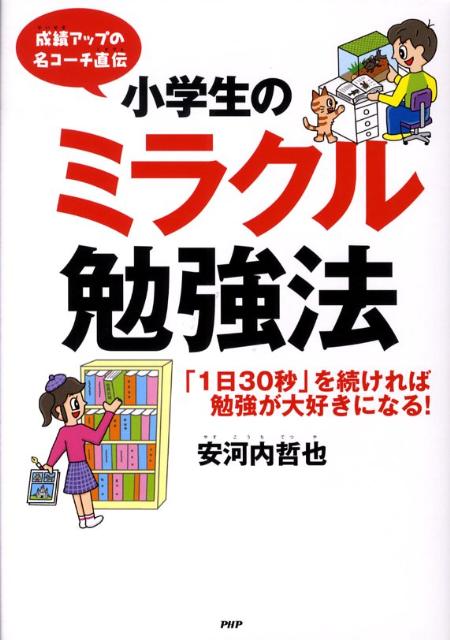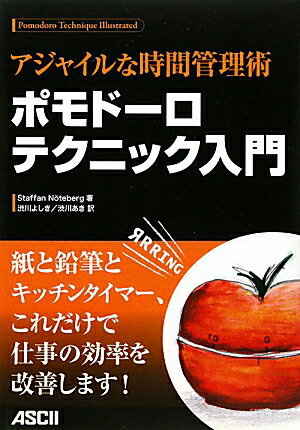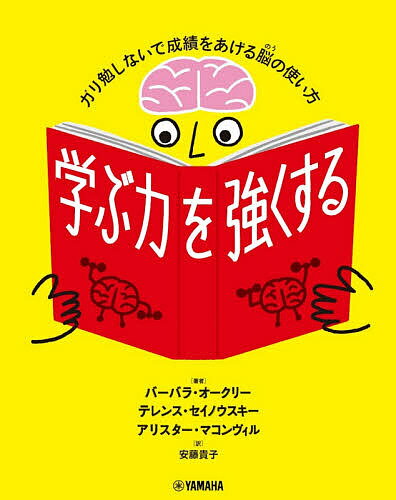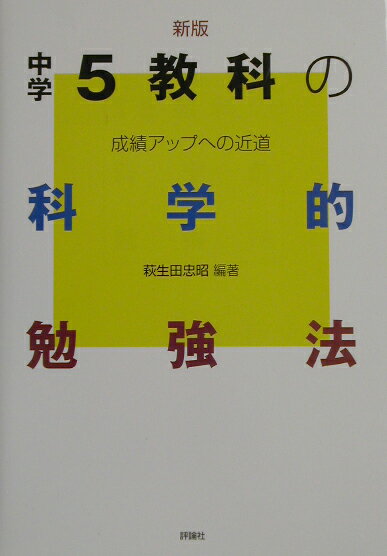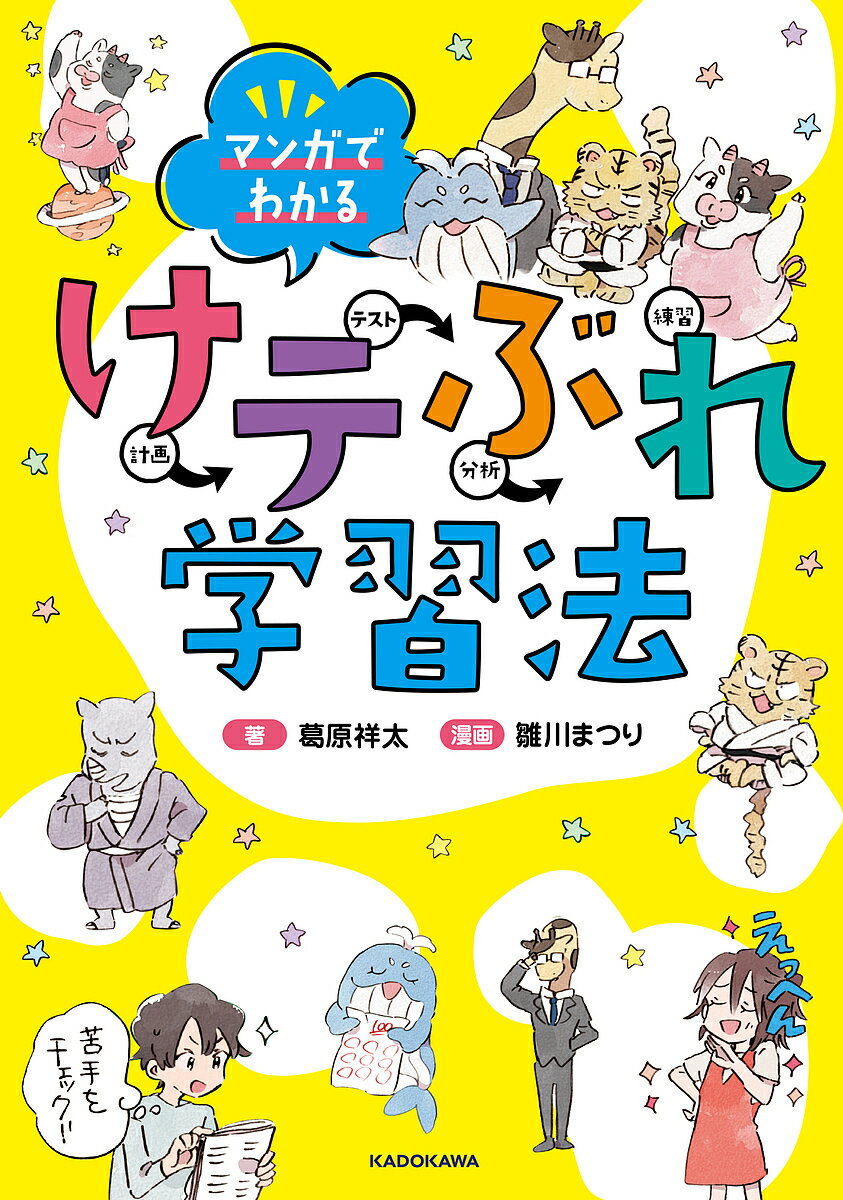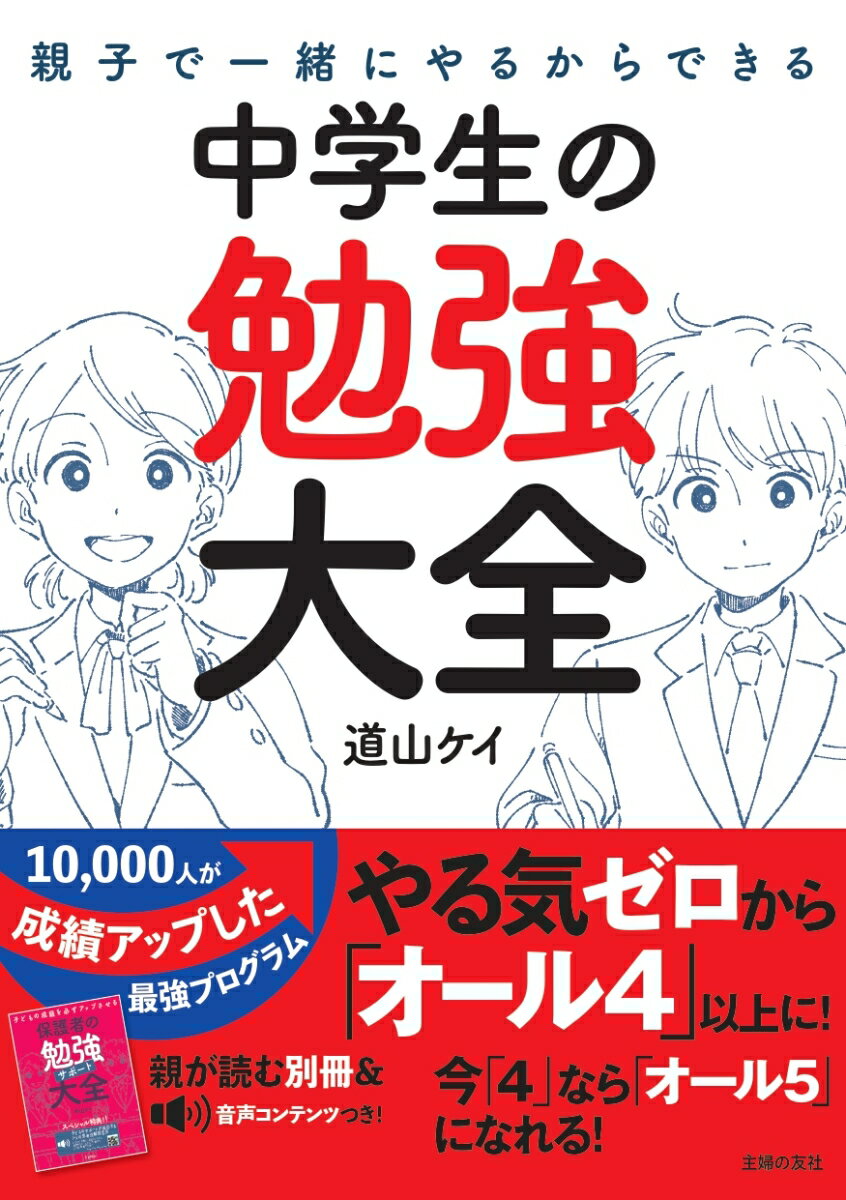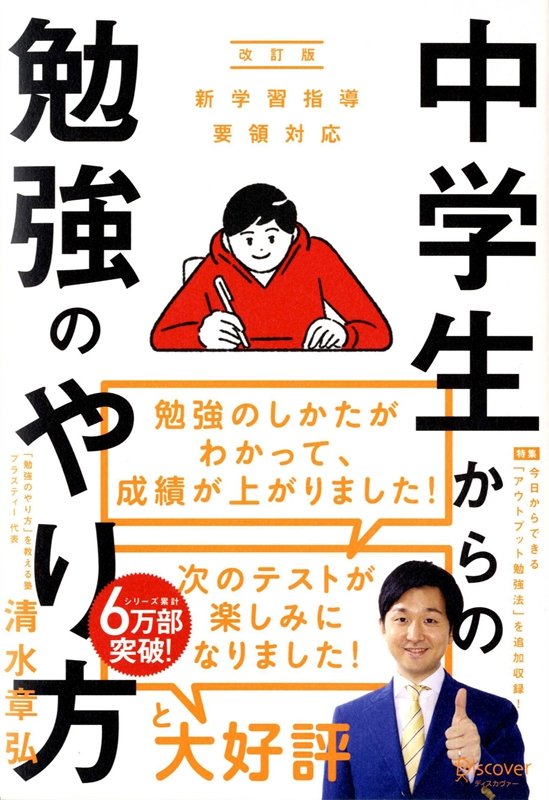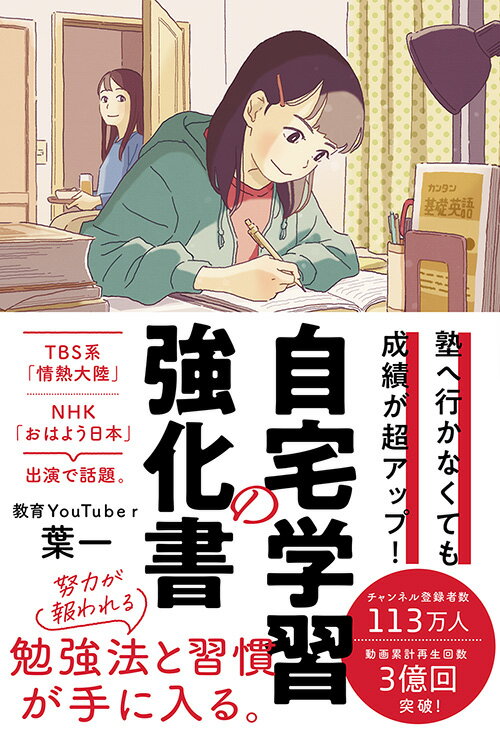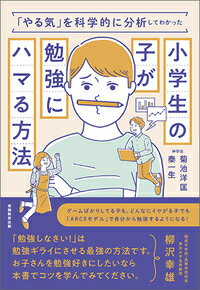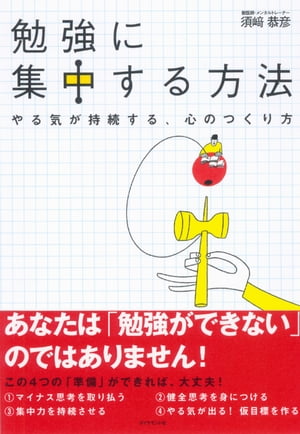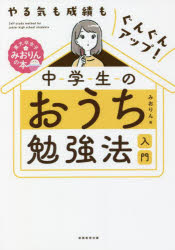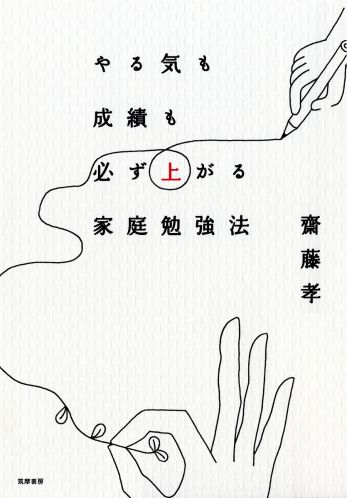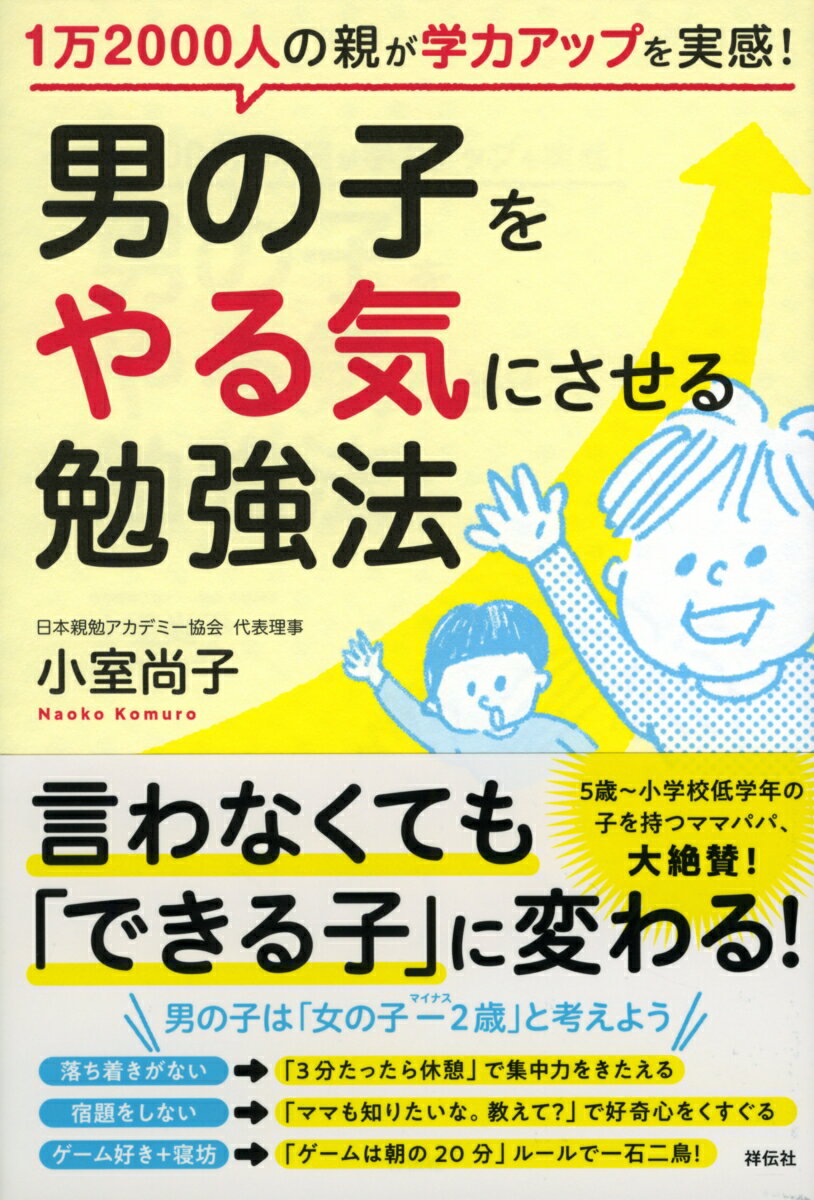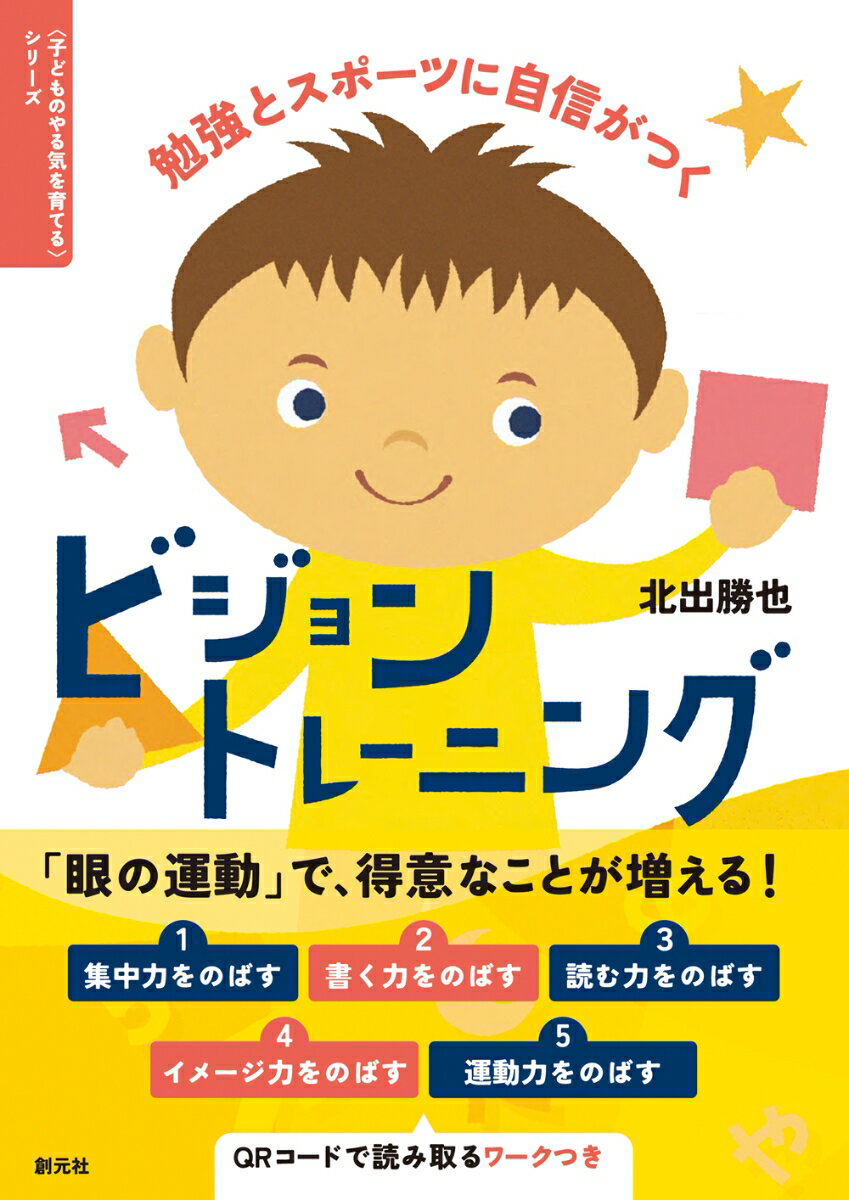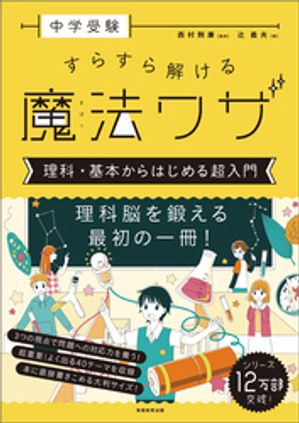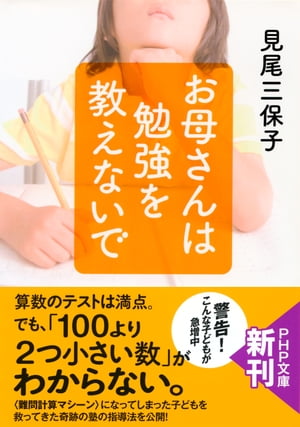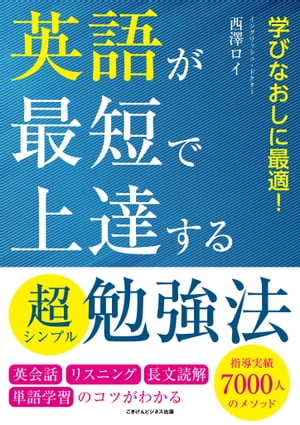と、中1の女子が友達女子に言っていました!(笑)
ま、正確には、
「もう試験前だから、ノートにまとめる時間より、覚える方が絶対良い!」
『お~~~、確かに!!』(正論だわ(笑)!)
そのきっかけになったのは私の一言!苦笑
「わぉ!凄く字を丁寧に綺麗に書いているね。でも時間掛かるんじゃない??」
「そうなんです!」
というやり取りの後にさっきの言葉が出てきた感じなのです。
<出来なかった所、判らない所をノートにまとめて覚える!>
というのは、普段の勉強の中で行うことで、いま、この切羽詰まった時間の無い時に、のんびりノートをまとめるというのが勿体ないという至極、判りやすい考え方です。

この彼女も、入塾当初はノートの書き方とか、普段勉強で行うことなどを結構細かくレクチャーをして、ママも巻き込んで普段勉強を頑張ってきただけに、余計に気になったのでしょう!(笑)
とにかく「試験に出るぞ!」と先生が言った箇所や範囲は100%覚えるようにして下さい!
100%です。
だって、覚えれば点数が貰えるのですよ!(笑)
だったら覚えないということは絶対に許されないですよね!?爆
みんなができて、自分が出来なかったら当然平均点でも離されてしまう訳ですから、頑張ってチャレンジして欲しいと思います。
-----------------------------