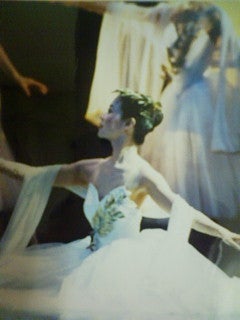私とバレエのお話↓↓
◇
1回目の記事はこちら↓↓
前回の記事はこちら↓↓
前回は、大人がバレエを習う上で大切な、生徒同士の人間関係でのONとOFFの切り替えについてお話させて頂きました。
今回は教師と生徒についてです。
大人からのバレエでむずかしいのが、この先生との距離感です。
子供がバレエを習っている場合、先生は『大人』ですので、『子供』と『大人』の関係です。
ところが、大人がバレエを習っている場合、『大人同士』の関係になります。
特に、先生と年齢が近かったり、自分の方が年上である場合や、
皆の仲が良い、アットホームなバレエ教室などの場合は、『先生』と『生徒』の距離が近くなりすぎる場合があります。
仲が良いのは、悪いことではありませんが、そうなってしまうと、よほどONとOFFの切り替えが上手な人でないと、バレエのレッスン中も先生のことをまるで“お友達”か“お母さん”のように思ってしまうようになります。
(先生ともっと仲良くなりたい)(先生に近づきたい)と思ってもらえることは、とても嬉しいのですが、子供の頃、“お母さん”に勉強やピアノなどを教えてもらった経験がある人ならわかると思いますが、あまりに身近な人にものごとを教わると、距離が近すぎて、すぐケンカになってしまったりして、なかなか上手くいかないことが多いものです。
すると、レッスン中に先生に“直し”を受けても、「ハイ、ハイ。わかりましたよ~。やればいいんでしょ?やれば。」といった感じになって、アドバイスを素直に聞けなかったり、「出来てないけど、まぁいいか。」「間違えちゃったけど、まあいいか。」と甘えてしまうようになってしまいます。
すると、バレエが上手になるために必要な『緊張感』がレッスンする上でなくなってしまい、その人の上達はそこで止まってしまいます。
それだけではなく、距離が近くなるとどうしても出てきてしまう、相手への“甘え”がさらにエスカレートしていってしまいます。
(先生にもっと認めて欲しい)からはじまった甘えは(もっと褒めて欲しい)(もっとかまってほしい)(もっと注目して欲しい)という風に連鎖しながらエスカレートしていきます。
これは、お酒が好きな人が毎日のようにお酒を飲みだすと、自制しないと、だんだん量が増えていってしまうのに似ています。
これが良い方向へ進むと、(先生に認めて欲しいから頑張る)(先生に褒めて欲しいから頑張る)という風に、バレエ上達への近道になるのですが、バレエというものは、いつもいつも順調という訳にはいきませんから、頑張っても思うように上達出来なかったり、先生に褒めてもらえなかったり、認めてもらえなかったりすると、(なんでもいいから注目して欲しい)(とにかくかまって欲しい)という少し間違えた方向に行ってしまいます。そしてバレエで注目を集めたり、かまってもらえないことがわかると、今度はあまり良くない方向で注目を集めたり、かまってもらおうとし始めてしまうことが多いです。
レッスン中も、バレエの約束やルールを破るようになり、周囲から見ると、まるで“先生やバレエをなめたり、バカにしているような態度”に見えてしまうこともあります。
それでもかまってもらえなければ、スタジオで自分だけを特別扱いするように駄々をこねたり、先生に注目してもらうためにわざと踊りを間違えたりする人もいます。かまって欲しくて、プライベートな用事で深夜に先生に電話をかけたり、先生の家まで訪ねて行ってしまったりするケースもあります。
また、発表会などの舞台に、突然出ないと駄々をこねて先生を困らせたり、踊りをわざと変えたり間違えたりしてしまうケースもあります。
甘えと言うものは、エスカレートすると自分でもびっくりしてしまうくらい、子供っぽい行動をしてしまうものなんですね。
そこまでいってしまうと、どんなバレエ教師でもそれを良しとはしてあげられませんので、NOを言わなくてはいけなくなりますが、そうなると、どっぷり甘えるモードに入っている人は、「どうして私を特別扱いしてくれないの!」「どうして私の言うことを聞いてくれないの!」と癇癪をおこしてしまい、やがて、「先生のバカ!」と、その教室を飛び出してしまうことになります。
そうやって甘える対象から遠ざかることで冷静さと、距離感を取り戻したその人は、しばらくしてから
(・・・あれ?私は一体なにをしていたんでしょう・・・)と我にかえるのです。
けれど、気がついた時に、その人はもう教室をやめてしまっています。
自分にとって大好きな先生と、大切だったあの場所にはもう戻れなくなってしまうのです。
もちろん、そこまで行く前に声をかけることによって、我にかえって踏みとどまる人もいます。
ただ、いずれにしろ、自分が距離をつめすぎて、甘えすぎてしまった結果は、自分で引き受けなくてはいけません。
もちろん、やめてしまったからといって、やり直せないわけではありません。
自分が、変わりたいと強く願えば、変わることができますし、もう一度教室に戻ることも出来ると思います。
先生の方は慣れていますし、教え子はみんな可愛いので、全然気にしていなかったりするのですが、なにしろ結構派手にやめてしまっているので、本人が恥ずかしくて、気まずいので、戻るにはかなり勇気が必要です。
さらに、その頃に一緒に習っていた人達は、自分が休んでいた間もレッスンを続けて上手になっていますので、そこのハードルも越える必要がありますので、自分の中で、しっかりと区切りをつけて再出発することが必要になります。
だから、世界中のバレエの先生は皆、生徒に厳しいのです。
生徒が自分で自分を甘やかさないために、先生に近づきすぎないために、厳しく接して生徒が自然に距離をとれるようにしてあげているのです。
だから、バレエの先生は皆、ピーンと張り詰めた緊張感を持っていたり、人を気軽に寄せ付けない雰囲気やオーラを出しているのです。先生も好きで威張っている訳ではないのです。
バレエの先生が生徒へ厳しくするのは、実は先生からのサービスなのです。
自分で頑張らなくても、スタジオに来たら自動的に緊張感を持ってレッスン出来るように考えられたシステムなのです。
バレエは毎日レッスンするものですし、一人前になるまでに10年かかるもの。
となると、教師と生徒は気をつけていないと自然に近い距離感になってしまう。
それを防ぐために、バレエの教師というのは、皆生徒に厳しいのです。
教師は生徒をめったに褒めませんし、生徒を近づかせません。
自分のプライベートも話しませんし、ONとOFFをはっきりと分けています。
ただ、このシステムにはデメリットもあります。
例えば、生徒が先生に自分の気持ちや意見を言えなくなってしまうこと。先生は絶対的で怖い存在になるので、先生に対してYESしか言えなくなってしまい、先生が見ているところと、見ていないところで態度を変えるようになってしまいます。
やがて生徒は裏表がある振る舞いをするようになります。
子供の頃に厳しい家庭やバレエ教室などで育った場合、バレエは踊れるけれど、裏表があって、人が見ていないところでは頑張れず、先生やお友達の悪口を本人がいないところでしきりに言うようになってしまうことがあります。
さらに、頑張っても褒めたり認めたりしてもらえないので、自信のない人になるというリスクがあります。
これは、生徒の問題というよりは、システムの問題なのですが、サクラバレエでは、生徒には自信を持ってもらいたいですし、どんな人にも自分の意見をきちんと伝えたり、裏表なく立ち居振る舞える、素直で真っ直ぐで信頼される人になって欲しいという想いから、このシステムを採用していません。
また、サクラバレエでは生徒が先生とのコミニケーションを取りやすくするために、普通のバレエ教室よりも生徒と先生との距離を近めに保っているため、生徒は先生に対して緊張感や怖いという感情を持たずに自由にのびのびとレッスン出来ていると思いますし、先生に対しても身近に感じてくれていると思います。このため、サクラバレエの生徒は、自由に自分の意見を述べること出来ますし、そういった機会も多いと思います。また、たとえ先生に対してでもハッキリと「NO」をいうことが出来ます。その代わり、誰も厳しくはしてくれませんし、緊張もさせてくれませんので、バレエが上手になりたければ、そして自分自身を成長させたければ、レッスンに来た際には、自分を甘やかさずに、自分で意識して緊張感や目的意識を持つ必要があります。
これが出来ないと、(先生はいつになったら私を上手にしてくれるのかな~?)(先生はいつになったら私に良い役をくれるのかな~?)と相手に甘えきってしまい、自分を甘やかしてしまい、次第にレッスンを休みがちになり、やがてレッスンに通うこともやめてしまうことになりかねません。それではバレエが上手になることはおろか、バレエを続けること自体が難しくなってしまいます。
そう聞くと、ほとんどの人が
(いやいや、大人なのに、そんな子供みたいになってしまう人がいるの?)と思うかもしれないのですが、これは大人なら誰でもそう成りえるお話なんです。
もともと甘え体質な人はもちろんですが、普段は自立している人でも、大人になると、自分が責任ある立場に置かれるようになり、だんだん周囲に甘えられる対象が少なくなってきます。
職場では責任ある仕事を任されるようになり、家庭では子供や親に頼られるようになり、バレエも経験が長くなると、他人に頼られたり甘えられたりする機会が増えて、その分、自分が甘えたり頼ったりする相手が少なくなっていきます。10代の頃に比べると、友達との距離もグッと遠くなり、そうすると、普段押さえている依存心が、(この人は頼りになる!)(この人になら甘えられる!)と思える相手に出会うと、そこに一点集中して出てしまうのです。
特に、小さい頃に親が少し厳しかったり、親が忙しくてあまりかまってもらえなかったり、バレエなどの厳しい習い事をしていて甘える経験が少ない人は、距離が近くて頼りになりそうで、信頼出来て甘えさせてくれそうな相手を見つけると、自分ではどうにもならないほど、そこに甘えが出てしまいます。
友達や恋人など、誰か一人に集中して甘えてしまう人や、
恋人や配偶者に何度も「別れる」「別れる」と言って相手をためしてしまうのも、同じパターンですね。
こういうタイプの人は、出来ればお付き合いする人の幅を広くして、特定の人に一点集中せずに、色々な人と交流して、普段から自分の弱みを周囲の人に少しずつ見せたり、甘えられる相手には甘えたりして、自分の中にある、普段は封じ込めている甘え心を分散させてあげて、上手につきあっていくよう心がけてみると良いかもしれません。
バレエの先生以外にも、心を許せて、信頼出来て、甘えられる相手が複数出来ると、そこに集中しなくてすむようになります。
また、このタイプの人には頑張り屋さんが多く、普段から頑張りすぎてしまう傾向にありますので、日頃のスケジュールに余裕を持ったり、好きなことをほどよく楽しんだりして、自分で自分を甘えさせてあげるようにすると良いかもしれません。
ともかく、バレエの先生との関係は、自分にとってはプライベートで関わりのある相手ですが、相手にとってはオフィシャルで関わりがある相手であることを忘れてはいけないということと、
先生との間にいつもいつも距離をとる必要はありませんし、レッスン中とレッスン前後とではまた違った距離感で良いと思いますが、大人同士だからこそ、自分の意志で先生との間に距離をとることが大切であることをお伝えしておきたいと思います。
とはいえ、私自身も入会したばかりの人や、どちらかというと人見知りの人や頑張りすぎるタイプの人にはスタジオでリラックス出来るようにと、あえて少しプライベートな質問をすることもありますので、ケースバイケースですし、意識しすぎると疲れてしまうので、ほどほどで良いと思うのですが、自分が人との距離をとることが難しいと感じている人は、“バレエの先生とはレッスンと関係のない話はしない”、という、昔からのバレエの世界の伝統にのっとって、先生のプライベートなことを聞いたり、自分のプライベートなことを必要以上に話しすぎないようにすると、やりやすいかもしれません。何事も練習だと思って、あれこれためしてみて下さい。
ちなみに、余談ですが、私の場合はスタジオでは常にオンモードですが、その中でもオンとオフの切り替えは、服装で表現していることが多いです。
例えばタイツの色。
ピンクの時はON。
ブラックの時は少しOFF。
例えばボトムスの種類。
スパッツの時はON。
巻スカートの時はややOFF。
例えばウォームアップウェア。
レオタードだけの時はON。
上にTシャツやニットを着ている時は少しOFF。
例えばバレエシューズ。
履いている時はON。
脱いでいる時はややOFF。
つまり、ピンクタイツにレオタード、スパッツでバレエシューズを履いている時はMAXにONです。
クラスレッスン中などがこのバージョンですね。
逆にTシャツに巻スカート、黒のオーバータイツでバレエシューズを脱いでいる時は、スタジオの中でもOFFな時です。
《ステップアップクラス》や《Crazy day!》では、こんな格好をして、普段よりものびのびと、自由に楽しみましょうね!と、ひそかにウェアで語っています。
また、レッスンが終わって、控室などに「昨日TVでローザンヌバレエコンクール観た人~?」なんて話しかけに行く時はレオタードの上にTシャツを着てバレエシューズを脱いで行くことが多いです。
ONとOFFの切り替えが苦手な人は他人のONとOFFを見分けるのも苦手だったりするので、今はちょっとふざけても良いところですよ、とか、ここは真剣にやるほうがオススメですよ、というのを生徒が目で見てわかるように、こっそりと発信していたりします。
もちろん、ただ寒いから上にウェアを着ている場合もありますし、黒いタイツでもONモードのこともありますので、一概には言えないのですが、一番わかりやすいのは、バレエシューズを履いているかどうかですね。
バレエシューズを履いている時にモードがOFFになっているバレエ教師はまずいませんので、そこが一番わかりやすいモードの切り替えかもしれません。
(先生がONとOFFを切り換えるタイミングがよくわからない・・・)(先生にいつ話しかければ良いのかわからない・・・)という人は、よければ参考にしてみて下さい。
◇
一年近く続いたこの『大人がバレエを習うということ』シリーズですが、基本的なことは一通り書かせてもらったように思いますので、今回をもって、一旦終わりとさせてもらいたいと思います。
しばらく充電して、いつか続編が書ければ・・・と思っていますが、ここで一区切りとさせてもらいたいと思います。
長い間、読んで下さってありがとうございました。
◇
新シリーズ『サクラバレエの歩き方』
1回目の記事はこちら↓↓