頬を刺すような冷たい夜風が、君の前髪をなぶって過ぎた。
ダウンジャケットのポケットに両手を突っ込んだまま俯いて歩く君は、身震いでもするように頭を左右に振った。
しかしその目だけは、20メートルほど先を歩く少女から外さない。標的となったその少女の後ろ姿は闇に溶け、時に街灯の下に姿を灯しながら急ぐ様子もなく歩を進める。
なぜそんな衝動に駆られたのか、君のその心の内にわき起こる感情が何なのか、自分でも計りかねているようにみえた。
わずか13年しか生きていない少年の君にとっては、初めて味わう狂おしさなのかもしれない。
そんな君が選んだたったひとつの方法は、かつては地上で一番愛らしく見え、今は憎悪の対象となったその影をこの世から消し去ること。
標的の少女がひとつ先の十字路を左に曲がるのと同時に、君は左への道を小走りになった。十字路をひとつ越え、息と足音を殺して次の角を右に入る。
民家の脇に立つ電信柱の影に隠れ、歩いてくる少女を待つ。静かな住宅地に足音が響いてきた。

「うんうん」スマホを手にした少女の声が聞こえる。あこがれ続けて、ようやくそばにいることが許されたと思った少女の声が。
─────────────────────────────
君はなんであの日、あそこ、そう、神社の境内に腰なんて下ろしていたんだろう。そこにいなければ、こんなことにはならなかったのに。
「美咲すごいなぁ」
「なんでぇ? キスなんて簡単よぉ、結衣だってできるよ」
彼女は、いたずらに鳴らすインターフォンのように、人差し指をこめかみの辺りでトントンと叩いた。
「で、どんな味がするの?」
「決まってるじゃない」その人差し指を、愛くるしい顔の横で立てた。
「その前に食べてたものの味よ」何も食べていない口をもごもごと動かす。
「俊君はどんな味がしたの?」
「ガムね。それも多分キシリッシュ」
「そこまで分かるの? すごーい! でもさ、お情けでキスなんてできるの?」
「お情けだからできるのよ」
そっと立ち上がった君は、逃げるように、足音を殺してその場を立ち去った。
─────────────────────────────
「それいいねぇ! クリスマスに4人で行けたら最高だね。でもさ、その前にゆいが何とかしなくちゃ」声が近づいてくる。
4人って誰だ……許さない、絶対許さない。君は憎悪の炎を燃やす。
「あーなるほどね。誘うだけだったらあたしが言ってもいいよ。後はゆいがするんだよ。うんう……え? いやだぁ、ゆいが言ってよ。あたしまだ言えないから。お誘いの交換交換」
誰だ、いったい誰に4人でクリスマスなどと誘いかけるのだ……そんなことは絶対させないから。
君は、手首のスナップを利かせて開いた4インチのバタフライナイフを逆手(さかて)に持ち替えた。
ナイフを持つ手が、寒さなのか怯えなのかブルブルと震えている。きっと君は、夢を見ているような浮遊感の中でそれを実行しようとしている。
引き返すなら今だ。自分の中の正気が頭をもたげているかもしれない。それを憎しみで噛み殺すのか。
息をひそめた君の前を、少女が通り過ぎた。
「うんう」少女が、んを言い終わる前に、君は躍りかかった。
背後から左腕を首に巻き付け、右手に握ったバタフライナイフを少女の右脇腹に突き立てた。
膝から崩れるように落ち込む少女の口を左手で覆い、耳元に口を寄せた。
「馬鹿女!」
少女が、幼子のような哀れな声をかすかに上げた。
尻餅をついた少女の口から手を外した君は膝をつき、血で滑る右手のバタフライナイフをきつく握りしめ、脇腹の中でぐりぐりと回した。
「ホント、馬鹿女だよ」
「ふぅんくぅん?」呟くような少女の声。
「痛いよぉ……なん、れぇ?」
君は右手をナイフから外し、ジーンズの尻でごしごしと拭いた。
「なんでかは自分で考えろよ」
声とともに、脇腹から抜いたナイフを少女の首筋に突き立てた。
ナイフは君が思った以上に刺さらなかった。それを抜き、今度は斜めに突き立てた。
拍動に合わせて噴出する血は制御弁を失ったポンプのように顔に降りかかり、君はさながら泣き狂う鬼のようだった。
遠くに見えるコンビニの看板、雲に見え隠れする月、温かな血を吸って、額にべったりと張り付いた前髪は、もう風になびかない。
君にも少女にも13歳のクリスマスはやってこない。
君が目に浮かべた涙は、悔しさだったのか、しでかしたことへの恐れだったのか、それとも悲しみだったのか、おそらくは誰にも分からないだろう。
─────────────────────────────
勇気を振り絞って愛を告白したのは君だった。実は彼女だって、小学校の頃から君が好きだった。けれど君には自信がなかった。
自信というのは誰かに与えられるものではなく、自ら獲得するもの。自信過剰は滑稽だけれど、自信を持つことは大事だ。
だから、君の告白を受け入れた彼女を信じて最後まで聞くべきだった。
「なぁんてね、ウソウソ」
「だよねぇ」
「もうさ、膝ががくがくでさ、もうさ、倒れそうだった。でも、俊君をかすみが狙ってるって噂があったりしてさ、諦めてたんだよねぇ」
「で、俊君のコクリで、キシリッシュの味ね」
「味なんて覚えてるわけないじゃない。あぁーでも幸せ。見て見て背中に羽根が生えてるっしょ」
「生えてない」
「そ? あれからさ、鏡の前でキス顔の練習してるんだ。けなげって言って、健気って」
「はい、けーなーげ」
─────────────────────────────
どこかの家から、聞き覚えのある歌が聞こえる。
心臓は左にあると思い込んでいた君は、あぁぁ、あぁぁ、と息とともに小さな声をあげながら何度も何度も自分の左胸を刺した。
でもそれは肋骨に阻まれうまくいかなかったのだろうか、泣き声に変わっていく。
そんな君が、刺したナイフをつかんだまま膝でにじり寄ったのは、血まみれで地に伏す操り手を失ったマリオネットみたいな少女の隣だった。
ばたりと倒れた君は、苦し気に何度も大きく息を吸う。おそらくは、ナイフの先が肺に達したのだろう。
横たわる君たちの横を、警戒感たっぷりに振り返る茶トラの猫が横切った。
やがて遠くからサイレンの音が近づいてくる。そして再び、冷たい空気を震わせて「ラスト・クリスマス」が流れる。
けれど、もうふたりにはなにも聞こえない。
─FIN─
Wham! - Last Christmas
ポチポチッとクリックお願いします。
 短編小説 ブログランキングへ
短編小説 ブログランキングへ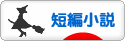 にほんブログ村
にほんブログ村これを書いた印象はとても強くて、さかのぼってみたら2012年の11月のアップだった。もう6年も経っていたのかと驚いた。
テレビ番組を見ていてふと思いつき、ささっと書いたのだけれど、読んでみたらあまり面白くはなくて、大幅に手をくわえました。神の視点が変わっていないのはご愛敬で。
1984年に発売された「ラスト・クリスマス」の作詞作曲者である、ワムのジョージ・マイケルが死んだのは2016年の12月25日でしたね。53歳でした。
クリスマスの定番曲でしたけど、最近は耳にしないような気がします。











