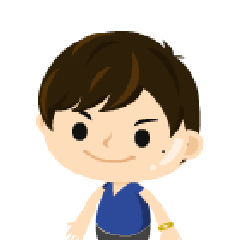こんにちは!たっくです!
車椅子ユーザーの方が賃貸住宅を選ぶ際に、どんな住宅を選んだらいいのか迷うことはありませんか?
そのようなお悩みをお持ちの方に対して、たっくが借りている住宅環境を例に、使いやすい、使いにくい部分をご紹介させていただきます。
今回は、たっく宅の「玄関」は、車椅子ユーザーにとって使用しやすいのか?
についてご紹介します!
結論から言うと、車椅子ユーザーにとって、少し使用しにくい場所になっているのではないかと思っております…
ではなぜ使用しにくい場所なのかを、たっくの個人的な意見としてご紹介させていただきます!
今回の記事を読んで、車椅子ユーザーが賃貸住宅を選ぶ際に、少しでもご参考にしていただけると幸いです!
目次:
・たっく宅の玄関環境
・車椅子の種類
・自走用車椅子を使用した場合はどうか?
・介助用車椅子を使用した場合はどうか?
・最後に
たっく宅の玄関環境
・玄関の内装
まずは、玄関の環境をご覧ください。
白を基調とした明るい空間となっております。
天井には照明が1つ設置されており、落ち着きのある夕日の色のような光が照らしてくれています!
見た感じは3000〜3500Kほどの色味があり、白い壁に反射して温かみのある空間で、おしゃれだなと思っています!
※ K(ケルビン):色温度の単位です。 単位数が大きくなると、より明るく青みがかった色となります。
3000〜3500Kは、夕日のような温かみのある色です。
5000Kは、日光のような白い色です。
6500Kは、青みがかった色で眩しいと感じる色です。
収納は、右側にあるウォークインクローゼット(以下、WIC)が設置されており、ドアは折れ戸(取手を手前に引くと扉が折り畳まれて開くドア)となっております。
・玄関の寸法
土間の広さは、縦幅1170mm、横幅730mmの空間で、横幅が少し狭いなといった印象です…
上り框の段差は10mmあり、土間・踏み面(土間とフローリングの間にある、鼠色の部分)・フローリングで色の変化があります。
車椅子ユーザーの方がこの玄関を使用すると、どのような使いにくさがあるのでしょうか?
それを知るには、まず車椅子の種類や大きさについてご説明させていただきます。
車椅子の種類
そもそも車椅子は、どんな種類があるのか、どれくらい大きいのでしょうか?
実は車椅子は、大きく分けて二種類あります!
それは、「自走用」と「介助用」です。
・自走用の車椅子
「自走用」は、車椅子に乗っている方が両手を使用して自分で車椅子を漕ぐことができる車椅子です。
(引用元:ac-illust.com)
のちに出てくる介助用と比べると、後輪が大きいことがイラストを見て分かります。
これは、両手で車輪を持ち漕ぐことができるために、大きくなっています。
・介助用の車椅子
次に「介助用」は、介護者に車椅子を押してもらって移動する用の車椅子です。
(引用元:ac-illust.com.介助用車椅子)
自走用と比べると、車輪が小さいですよね。
これは、ご自身で車椅子を漕ぐことができない方のために、介助者が車椅子の後ろ側についているハンドルを押して操作するタイプのものです。
また中には、手が不自由で自走用を操作することができない方が、両足で床を蹴って漕ぐために使用する方もいらっしゃいます。
・自走用と介助用の「幅」の違い
「自走用」と「介助用」の車椅子を比較すると、一つ大きな特徴があります。
それは、車椅子の幅です。
|
自走用車椅子幅 |
介助用車椅子幅 |
|
620〜630mm + 両肘のスペース
|
530〜570mm |
⇨介助用の方が、100mmほど幅が狭いことが分かります。
これらのことを考慮すると、果たして車椅子がたっく宅の玄関を通ることは可能でしょうか?
「自走用」と「介助用」を分けて説明させていただきます。
自走用車椅子の場合
自走用車椅子は、玄関に入ることは可能です。
しかし、玄関の幅は730mmなので、両側の空間が50mmしか残らない状態となります。
自走用の場合、両肘のスペースのことも考慮する必要があるため、結果かなり狭いと感じるのではないでしょうか。
玄関を通るたびに、両肘が壁に擦りむいて怪我をしてしまっては、元も子もないですよね…
そんな現状だと、外に出たいと言う気持ちが失せてしまいます…
車椅子と壁との間が50mmしかないが、W I Cから靴を取り出すことは可能か?
こちらのW I Cのドアは手前開きの折れ戸となっているため、戸が車椅子に当たってしまい開け閉めが困難となります。
その対策として、靴を普段から土間に置いたとしても、靴が邪魔で車椅子がスムーズに通ることが困難となります。
そのため、自走用車椅子を使用する方は、こちらの玄関はかなり使用しにくくなるのではないかと考えます。
介助用車椅子の場合
では、介助用の車椅子はどうでしょうか?
廊下と車椅子の幅を考慮しても、自走用と比べてももう少しゆとりがあります。
自走用車椅子の幅を530mmと仮定すると、200mmほどのゆとり空間が生まれます。
また自走用とは違い、肘のスペースも考慮しなくても良いです。
であれば、介助用であれば使いやすいのか?
実は、車椅子使用者よりも、介助者が大変になる可能性があります。
自走用で問題視されていたW I Cの開け閉め問題ですが、車椅子に乗車している方が扉を開け閉めする必要なないので、介助者が靴の取り出しを行えば問題ないかと思われます。
ただ、靴の脱着を介助で行うとなるとどうでしょうか?
介助者は車椅子を押すために後ろ側にいましたが、靴を履く介助を行うときは車椅子の前へ移動する必要があります。
車椅子の前へいく際に、200mmしか空間がないため、移動するにはかなり狭い空間となってしまいます。
そのため介助者もかなりバランス能力が高い方でないと、車椅子を横切る際にバランスを崩して転倒するリスクがあるため、とても注意が必要です。
対応策としては、玄関から外に出て広い空間で靴の脱着を行えば良いと思います。
実際に靴の脱着は、玄関が狭いため自然と外でおこなっている介助者をたくさんみてきました!
これらのことから、自走用車椅子にとってはかなり狭い環境になってしまいますが、介助用であれば工夫次第で住みやすい空間になるのではないかと感じました!
最後に
これらのことを考えると、車椅子を使用する場合は玄関の幅って大切ですよね。
車椅子ユーザーが使用する玄関環境は、玄関の土間が奥行き1200mm以上必要と言われています。
また玄関幅は、自走用を使用する方は1650mm、介助用を使用する方は介助者のことも考慮して2100mmの幅が必要と言われています。
(福祉住環境コーディネーター検定試験2級 テキスト&問題集)
これだけ広い玄関を推奨している理由として、玄関で車椅子の方向転換が必要であったり、介助者が楽に靴を脱ぎ履きさせるなどの介助を行いやすいように設定されているようにも思えます。
要するに、玄関は広いに越したことはないです。
でも玄関という空間だけで、それだけ広い賃貸住宅もなかなか見つけにくいですよね…
過去に、玄関が狭くてなかなか賃貸を選ぶことができなかった方にお会いしました。
その方は最終的に、玄関とリビングが直接つながっている間取りを選択されたようです。
車椅子や介護者のための空間が広々と使用できるため、不自由なく過ごされているみたいです。
これらのことから賃貸住宅を選ぶ際は、ぜひ広い玄関を選択することを強くお勧めします。
また、これからご自宅を建てる方は、将来のことを考えて広い玄関を設計されることをお勧めします。
たっくの先輩(リハビリ職)は、ご自宅を建てられる際に、将来車椅子生活になっても家に帰ることができるようにと、とても広い玄関を設計されていました!
今回はここで終わりにします。
次回も玄関編の続きをご紹介させていただきます。