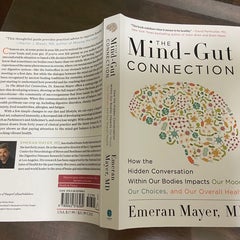Q: A of Bの場合、Aが「部分」であり、Bが「全体」であるということで、
・Some of the students(A=some, B=the students)
・a student of Keio University(A=a student, B=Keio University)
・a member of the tennis club(A=a member, B=the tennis club)
・a house of wood(A=a house, B=wood)
等の用例は理解しやすく感じます。次の例も、名詞of 名詞ではないですが、ある感情がBの出所から出るということで考えれば 理解できます。
・I'm afraid of snakes(A=I'm afraid, B=snakes)
次の用例はどうでしょうか。
・She accused me of telling a lie.
これはA=me, B=telling a lieという理解では失敗してしまいます。これまでのA of Bの理解では、accused telling a lie of me、
つまり、「私という出所から嘘をつくことを責める」と解釈してしまう可能性があります。
また、
・The man robbed him of his wallet.(その男は彼から財布を奪った)
これも、A=him, B=his walletだと失敗してしまいます。生徒はよく整序問題で、robbed his wallet of himのようにしてしまいがちです。これは「彼という出所(全体)から、財布(部分)を取り出す」イメージで考えてしまったことによる誤答例だと考えられます。
The man robbed me=A, the wallet=Bという理解がここでは大切なのですが、動詞の性質によってこの事例が生じていると言えそうです。
この構文について、田中先生より、以下のご指摘がありました。
A:
動詞 + A + of + Bの構文のof を読み解くカギはやはりof の出所性と帰属性です。帰属性は関連化と関係し、出所性は分離と関係します。そこで以下の4つを見てみましょう
accuse A of B ([doing] something) AをBをしたことで告発する
remind A of B AにBのことを思い出させる
deprive A of B AからBを奪う
rob A of B AからBを 強奪する
accuseとremindは関連化がはたらき、例えばaccuseだとAを告発する行為とBとを関連づけるということになります。一方、robの場合はAを襲ってBをAから引き離すということですが、clear A of Bと解釈上は同じです。They came to clear the highway of debris. だと「彼らは高速道路のがれきを取り除きにきた」ということですが、このof debris は取り除くもの(clear するもの)が何であるかを示していると考えることができます。rob A of Bでもrobは「何かを奪う目的で襲う」という動詞なのでrob Aは「Aを何かを奪う目的で襲う」ということを、そしてof Bは「奪い取るものが何であるか」を示していると考えることができるます。日本語にすれば「AからBを奪う」となるかもしれませんが、英語は「Aを襲って、Bを奪った」という流れです。「AからBを奪った」とはしないことです。robは人や銀行などを襲うという意味なので、何を奪うかはof Bで表現すると教えておくのがよいと思います。accuseとremindではA of BでAとBを結びつける(関連づける)意味合いが強くなるのに対して、robとclearではA of BでAとBを引き離す(分類)の意味合いが強調されますが、生徒に指導する際には、いずれも「Aに対してある行為を行う、どうしてかといえばof B」と教える手もあります。
The man robbed himで「その男は彼を襲った」、どうしてかといえばof his wallet(財布のことで)と情報処理するということです。She accused me of telling a lie. も「彼女は僕を責めた、どうしてかといえばof telling a lie(嘘をついたことで)」と解釈することができます。
このように、日本語に引きずられると、語の本質を見失ってしまうことがよくわかりました。rob A of Bも「何かを奪う」ことに焦点のある動詞ではなく、「誰かを襲う」というところに焦点がある動詞と考えることで、ストンと納得がいきますね。clearも「取り除く」と考えると、「高速道路を取り除く?」になってしまいますが、「きれいにする」というところに焦点があって、その関連性をofで示すわけですね。チャンクで理解すると有効な例であることもわかりました。
Q: accuseはblameとよく対比されますが、accuseはA of Bで、blameはA for Bですが、これはaccuseとblameの動詞の性質による違いで説明する必要があるのでしょうか。同じような動詞の意味のネットワークで考えてしまうと、前置詞の選択で少し迷ってしまいそうな例です。
A: accuse A of Bと blame A for Bは意味的に似ているように思えますが、実は動詞の働きが違います。blame A for Bはpunish A for B、praise A for B、thank A for B, scold A for Bと構文的には仲間で、共通項は、for Bがなくても文法的には問題ないということです。このfor Bは行為の理由・根拠を示しています。一方、accuse A of B でof Bは構文上必須です。そこでThey accused the manだけでは不十分で、The police accused the man of theft (murder).のようにaccuse Aとof Bは切っても切れない関係ということになります。Don't blame me.はOKですが、 Don't accuse me.とはいわないですね。
「AをBのことで責める」という日本語で考えると違いがわかりませんが、forなのかofなのかということに気を配れば、blame A for Bは「責める」というAに焦点があり、accuse A of BはAが行ったBの行為に焦点がある語だということがわかるのですね。構文の違いに目を向けることが大切だということがよくわかりました。
このように、こうした動詞構文は、日本語を介在させると理解がしずらくなってしまう事例が多々あるように思いました。
日本語ではなく、動詞のコアと、情報処理との関連から、動詞構文と前置詞の関係を整理しておく必要があると思います。(中村)