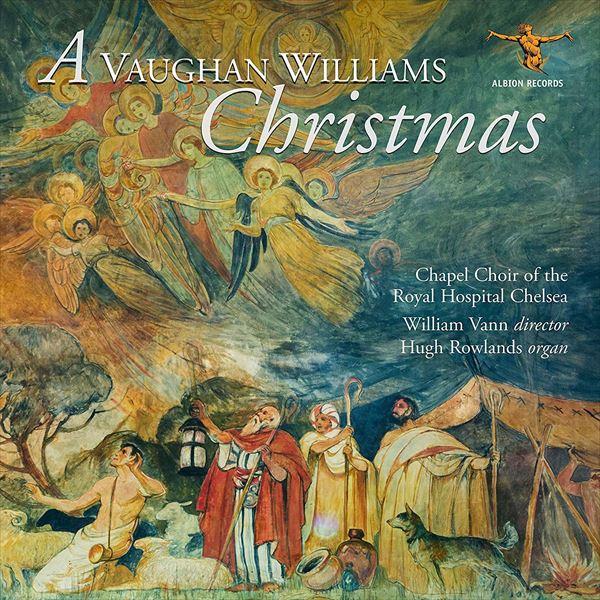今週の火曜日
横浜での塾の会議のために
出かけた際のこと。
バス停から鉄道の駅まで
歩いて行く途中のお宅の庭に
小さな白い花が咲いているのが
目にとまりました。
(2025年6月24日撮影。以下同じ)
帰宅後に
ハナノナで調べてみると
クレソン、オランダガラシ(88%)
オオカワヂシャ(3%)
アリッサム(3%)
と出ましたが
形状や色がそれらとは
明らかに違います。
アップで撮った写真で調べてみると
トウバナ(77%)
セイヨウジュウニヒトエ、アジュガ・レプタンス(10%)
イヌゴマ、チョロギダマシ(7%)
と出ましたけれど
やはり違う感じ。
お馴染みの
「おさんぽ花ずかん」を見ても
それらしきものは見当たらず。
そこでふと
スマートフォンで撮った写真を
直接、インターネットで検索できる
という話を以前、聞いたことを思い出し
試しにやり方を調べてみて
やってみたところ
「調べる:植物>」と出ました。( ̄▽ ̄)
「植物」が太字になっていたので
タップしてみると
「Siri の知識」として出たのが
Broad-Leaved Thyme とタイムです。
Broad-Leaved Thyme を
タップしても
「コンテンツがありません」
と表示されるので
タイムの方をタップすると
Wikipedia のページが表示され
これか、と思ったんですが……。
Wikipedia の冒頭の説明に
タイムはシソ科イブキジャコウソウ属の植物の総称で(略)ハーブとしてよく知られる代表種にタチジャコウソウがあり、日本ではこの種を一般にタイムと呼んでいる。
と書かれており
タチジャコウソウの文字が色変して
リンクが張られていたので
そちらに飛んでみると
「名称」という項目に曰く。
和名タチジャコウソウは、茎が立ち上がり、麝香のようなよい香りがするので、漢字で「立麝香草」と書く。和名の由来は、日本にも自生する近縁種のイブキジャコウソウが地を這うのに対して、本種は先端が立ち上がることから名付けられたものである。
今回見かけた種も
茎が立ち上がっていますので
ぴったりの説明だと思われました。
ただ
立麝香草の項目に載っている
「開花期の茎葉」の写真を見たら
葉っぱが肉厚で
雰囲気が違うんですよね。
近縁種である伊吹麝香草
[イブキジャコウソウ]の
ページに飛んでみると
こちらの方が
葉っぱの雰囲気は似てますけど
花の感じが違います。
というサイトを見てみても
明らかに花の
つき方の雰囲気が違う。
その一方
「タイム(植物)」で
検索した際にヒットした
「みんなの趣味の園芸」に
アップされているコモンタイムの写真は
今回のによく似ておりまして。
同サイトの
「特徴」の解説に
和名は立麝香草で
「香りのある
グランドカバープランツとして
利用されます」と
書かれています。
伊吹麝香草で
いろいろ検索してみた際
グランドカバーによく使われる
と説明しているサイトもありました。
要するにタイム系のものは
どれもグランドカバーに
使われるんだな、と。
そんなこんなで
伊吹麝香草か立麝香草か
確信を持って決められず
迷った末に
ブログのタイトルは
「麝香草(タイム)」と
誤魔化すことにした次第です。(^^;ゞ
タイムは園芸品種が多いので
いろんなものを掛け合わせた結果が
今回の種なのかもしれず
そうだとしたら
種苗屋さんにでも聞かないと
同定は難しい。
今回の種は白色がメインで
かすかに桃色が混ざっていますが
これが特徴のひとつかもと思いつつ
もしかしたら土壌の関係かもしれず。
ちなみに
「コンテンツがありません」
と表示された
Broad-Leaved Thyme
(直訳すると「広葉タイム」)。
パソコンで改めて検索して
英語版 Wikipedia を見てみても
似ているとは思えませんでしたが
「ブロード・リーフ・タイム 花」
で検索してヒットした以下のページの種は
よく似ていると思った次第で
特に葉っぱが大変よく似てますね。
花期もあってるし
イブキジャコウソウ科
だそうですので
やっぱり今回のも
伊吹麝香草でいいのかどうか。
なかなか悩ましいのでした。