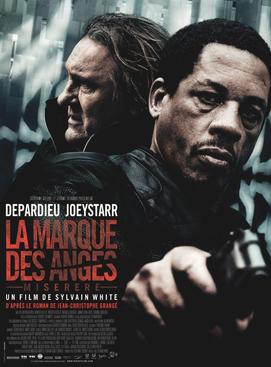ジャン=クリストフ・グランジェ
『ミゼレーレ』(2008)の下巻で
主役の1人で元刑事の
リオネル・カスダンは
アスンシオン福祉教育協会という
非営利団体が経営するコロニーが
今回の事件に深く関わっている
と確信するに至ります。
コロニーは定期的に
敷地外(地元の協会)で
音楽会を催しており
それを知った当日の午後
少年聖歌隊がコンサートを開く
ということを知って
コンサート会場に向かうんですが
その会場で渡されたプログラムは
次のようなものでした。
プログラムによると、四つの合唱作品が演目に上がっている。初めは十四世紀のアカペラ作品『トゥルネーのミサ』の一曲「グロリア」。次は十八世紀の作品で、ピアノの伴奏がついたジョヴァンニ・ペルゴレージの『スターバト・マーテル』。三曲目は――プログラムは年代順に並べてあった――ガブリエル・フォーレの『ラシーヌの雅歌』作品11を歌とピアノ演奏用に編曲したもの。そして最後は、オリヴィエ・メシアンの『神の現存についての三つの小典礼』だった。/こいつは退屈しそうだと思っていると、指揮者が登場して新たな拍手が起こった。(略)合唱が始まると、たちまち性も罪も重苦しさもない世界に連れていかれた。(略)ポリフォニーがホールに響くと、暖かみのある木の内装にもかかわらず、冷たい僧院が目に浮かんだ。厳めしい石造りの丸天井、粗末な毛織の服、生贄の図。生を否定し、さらなる高みを目指すのだ。今、ここにある現実を、陰気なマントで覆ってしまおう。(平岡敦訳、創元推理文庫・下巻 pp.217-218)
この箇所を読んで
さっそく《トゥルネーのミサ》や
フランクの《ソロモンの雅歌》
メシアンの《神の現存についての三つの小典礼》の
音盤を検索して探してみたのは
いうまでもありません。(^^ゞ
でも今回のブログは
それらについてではなく
ペルゴレージ《スターバト・マーテル》
ピアノ伴奏版について
書くことにします。
ペルゴレージの
《スターバト・マーテル》
ピアノ伴奏版というのは
さすがにCD化されてない
と思ったんですけど
もしかしたら YouTube に
アップされてるかも
と思って探して見たら
やっぱりアップされてました。
それがこちら。
合唱はアルメニア・リトル・シンガーズ
Little Singers of Armenia で
指揮はティグラン・ヘケキャン
ピアノ伴奏者は不詳です。
録音は2016年に
オランダのマースリヒトにある
アルメニア使徒教会の
行われたようです。
第12曲目と
最後のアーメンしか
歌われていないのが
残念ですけど
グランジェの小説に描かれた
コンサートの場面を
彷彿させるものがありますね。
なお
ピアノ伴奏による
ソプラノとアルトによる二重唱の演奏も
YouTube で見つけました。
演奏は
ソプラノ:神原かおる
メゾ・ソプラノ:松本やすこ
ピアノ:芦沢真里
指揮:小鉄和広で
東京オペラという団体の
コンテンツのようです。
演奏年はアップされた
2020年7月4日でしょうか。
コロナ禍のさなかであり
それがこのような
各奏者が遠隔にいながら
ネットを介して同時に演奏する
という試みを生んだものでしょう。
そして
ピアノ伴奏のみで
歌が入っていない演奏も
ヒットしました。
演奏者は
「こころぴあの♬大人のピアノ再開」
というvlogをアップされている
「こころぴあ」さんでしょうか。
Edition Breitkopf とあるのは
ドイツの楽譜専門店
ブライトコプフ社の楽譜を使った
という意味で
ヘルムート・フッケ Helmut Hucke
(1927〜2003)という
ドイツの音楽学者による
リダクションかと思われます。
手元には
それとは異なる人のアレンジによる
ピアノ独奏版があるんですけど
長くなりましたので
それについてはまた
CDが出てきたら。( ̄▽ ̄)