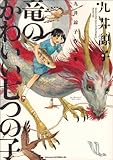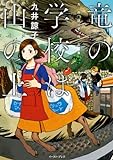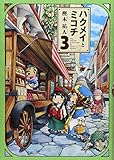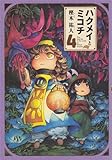リンゴの木
文:にゃんく
絵:gotogoal
私のおばあちゃんはリンゴの木を持っている。
おばあちゃんのおばあちゃんが埋めた木だから、相当立派な木だ。
その木の下で、最近おばあちゃんがよく嘆いている。
私はおばあちゃんになんで嘆いているのか聞いてみると、
「もうすぐ旬の時期だっつぅのに、夜誰も見ていない間にリンゴを盗んでいく人がいるだべ。」
もうすぐ美味しくなるリンゴをおばあちゃんは心待ちにしているのに、それを盗んで行くなんて。
リンゴの木は道に面して立っているから、簡単に盗んでいけるのだ。
私は、昼間寝て、夜ドロボウを捕まえるために張り込みをはじめた。
女では返り討ちに遭うかもしれないので、ボーイフレンドに用心棒を頼んだ。
捕まえたら、警察に突き出してやろう、と思った。
夜になった。
星明かりがあるので、泥棒が木に近づけばすぐに分かる。
私はリンゴの木がちょうどよく見える小屋の中から外をうかがっている。
ここであればトイレもあるし、いざというときすぐ出れる。
そばでは、ボーイフレンドが寝ている。「泥棒来たら起こして。途中で交代する」
そう言ってボーイフレンドは寝てしまった。
昼間は布団に入ったが、なかなか寝付けなかった。
少し眠ったようだが、なんだか目がとろ~、として眠い。
まだ時間が早いので目をつぶっていよう。すこしだけなら大丈夫だろう。
気づいた時にはすでに深夜だった。
日付が次の日になっている。
ふとリンゴの木に目をやると人影が立っている。
その人影は手に何か丸い物を持っている。
泥棒だろうか?
寝過ごしてしまったか。
いや、まだ間に合う。私はボーイフレンドを揺すって泥棒が出たよ、と言う。
ボーイフレンドは熟睡していて、いくら揺すっても目を覚まさない。
「役に立たない用心棒だわ。」
私はすぐさま小屋を出て、限りなく大きい人影に近付く。
「ちょっと待って!」
人影がびくり、と立ち止まる。
大きいと思った人影は、近付てみると子供だった。まだ5、6歳の少年だ。
少年はリンゴを1つ、右手に持っている。リンゴはまだ半分青かった。
リンゴの木を見上げると、昼間見た時より少なくなっているような気がしないでもない。
数えていないから分からなかった。
この子が盗ったのだろうか。
「君、そのリンゴ、どうするの?」
私は少年に聞いてみた。
「お母さんが病気なの。」
「それでお母さんにリンゴを食べてもらうの?」
「そう。」
「そのリンゴ、どうやって盗ったの?」少年は地面を指差す。少年の身長と同じくらいの長さの木の枝が転がっている。「これでつついて盗ったの?」
少年はこっくり頷く。
少年は髪が長く女の子のよう。その癖毛の髪の向こうに大きな目が2つ光り輝いている。
「お母さん、何の病気なの?」
「・・・癌。」
私はすこし怯む。
「リンゴを病気のお母さんに食べさせていたの?」
「そう。リンゴは病気に効くんだって」
私は少年を警察に突き出すべきか考えた。
私がこのまま少年を放置すれば、少年は病気のお母さんのためなら泥棒をやってもいいと勘違いするだろう。
「そのリンゴの木は所有者がいるんだよ。勝手に盗って行ってはいけないよ。」少年はこくん、と頷き、手に持っていたリンゴを私に差し出した。
「いいよ。それはお母さんに持って行きな。」
少年は「ありがとう。」と言って、一度だけ私の方を振り返り去って行った。
少年の言うことが本当かどうか分からない。
何処に住んでいる少年だろうか。見たこともない。
かなり遠くからお母さんにリンゴを食べさせるために毎夜やって来ていたのだろうか。
小屋に戻ると、ボーイフレンドが目をさましたのか、
「泥棒まだ来ない?」
「もう来たよ。」
「何処何処?泥棒どこ?」
「もう逃げたよ。役立たず。」
ボーイフレンドは私に叱られ、しゅんとなった。
私がむしろの上に横になって目をつむると、ボーイフレンドが私の胸を触ってきた。
「やめてよ。眠いんだから。」
私はそんな気じゃなかったのに、彼は私の下着に触れてくる。私が逃れようとしても、すごい力で押し込められる。
彼は私の下着を脱がせ、私の下腹部を猫のように舐めはじめる。私はされるがままになっている。
小屋の外に誰かがやって来る気配がする。さっきの子供が戻ってきたのかもしれない。
だけど、彼はおかまいなしに、私の中に入ってくる。
「これでも俺が役立たずだって言うの?」
役立たずの彼が役立っている。私は小屋の外にまで聞こえる声を出していた。
小屋の外の誰かが、ゆっくりと歩き去って行く音が聞こえた。
次の日から、おばあちゃんがリンゴの木の下で嘆くことはなくなった。
それから一週間後、リンゴの木の下に手紙が置かれていた。
手紙には飛ばされないようにこぶしほどの大きさの石が置かれていた。
「リンゴどろぼうより」
そこにはこう書かれていた。
「お母さんはこんしゅう、しにました。こんなにおいしいリンゴはたべたことがないといってよろこんでいました。どうもありがとう。」
リンゴの木にはたくさんの熟した美味しそうなリンゴが収穫されるのを待っていた。
私は待ち伏せして少年にリンゴをもっとプレゼントしてあげればよかった、と思った。
(了)
今回、挿絵を描いていただいたのは、gotogoalさんです。主に、水彩画色鉛筆で絵を描いていらっしゃる、ジブリ好きのアーティストさんです。
↑gotogoalさんには、ココナラから絵の注文をすることができます。