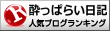呑みネタ 2014年9月30日 科学者が勧めるワインと紅茶?
心臓病のリスクのある被験者にワインを呑んでもらった結果。
運動習慣のある人は、善玉コレステロールの上昇と総コレステロールの低下が見られた。運動習慣のある人にワインは効果を発するらしい。
また、紅茶を常に飲んでいる人は、死の危険が24%も低いらしい。
「例えば、紅茶を飲む人よりもコーヒーを飲む人に、喫煙者が多く見られるように、他に要因はあるかもしれないので、紅茶が心臓を守り、紅茶を飲んでいる人が一般的により健康であるとは一概に言えません。確かに紅茶には、長生きの鍵となる抗酸化物質が含まれているので、コーヒーから紅茶に変えて損はないと思いますよ」
「たった3杯のお茶で、最大21%脳卒中のリスクを下げることができます。心臓財団は、心臓病予防や治療のために、赤ワインや他のタイプのアルコールを飲むことを勧めてはいません。十分な抗酸化物質を摂ることが大切だと考えています」
http://woman.mynavi.jp/article/140923-143/
****
なんというか、はっきりしない発表。
**
「人気ブログランキング」「にほんブログ村」に参加
ぜひ応援のバナークリックよろしくです