空の哲学「中論」に再挑戦(1)
数年前に読んで、全くチンプンカンプンだった『中論』に再挑戦しています。
ご存知のとおり、『中論』は、ナーガールジュナ(=龍樹、推定150~250年頃の人)が
「空」の思想を哲学的に構築したものです。
大乗の膨大な『般若経』類は、繰り返し「空」を説いているのですが、
その「空」思想を理論的に解説した龍樹。
大乗仏教を理解するうえで、絶対に避けて通れないのですが、
その難解さでも有名で、最初読んだときは吐きそうになって
脳内から葬り去っておりました。
たとえば、有名な『中論』第2章の、いわゆる「運動の否定」。
==============================
<すでに去ったものは去ることがない。
まだ去らないものも去ることはない。
すでに去ったこととまだ去らないことを離れて
去りつつある時もまだ去ることがない>
(ざっくりいうと、
過去に去ったものは現在去ることはできない。
未来のものは、まだ現前してないから去ることはできない。
過去と未来と切り離された一瞬間の現在だけでは、
去るという運動は成り立たない。
だから、過去・現在・未来とも「去る」という運動はありえない)
===============================
吐きそうでしょう?
万事この調子で、「Aもない、Bもない、Cもない、Dもない」
と否定のオンパレードで、論理学の本を読んでいるようでした。
私が一番わからなかったのは、
龍樹が何のためにこんな否定の論理を展開して、
それが大乗仏教の慈悲とか利他と何の関係があるのか?ということでした。
(実は、『中論』の解説を読めばちゃんと書いてあったのですが、
その解説の意味すら当時はわからなかった)
再挑戦できるかも、と思ったのは、
例の『仏典を読む
』(末木文美士著)の4章「否定のパワー 般若心経」
を読んでからです。
『中論』は、論争の書、つまりケンカを売っているらしいのです。
ケンカの相手は、主に、上座仏教一の有力部派「説一切有部」のアビダルマ論。
(知っている人からすれば、何を今更と思われるでしょうが)
『仏典を読む』では、こんなふうにかかれています。
「龍樹はほとんど過激といってよいくらい厳しく、詭弁すれすれの論法を駆使して、
我々の常識に挑戦する」
「(上記の運動の否定のような)論法は、『飛ぶ矢は飛ばない』とか
『アキレスは亀に追いつけない』といった古代ギリシャの哲学者ゼノンの
論法を思い起こさせる」
飛んでいる矢も、ある瞬間を見るとある空間を占めて静止していて、
どの瞬間もそうなのだから、矢は飛ばない、という理屈ですね。
でも、現実に私たちは「飛んでいる矢」を見るのだから、
それに反する理屈のほうがおかしいじゃん!
という態度をとることもできます。
「どうやら龍樹の言いたいことはそちらのようである。
その論法は、相手の前提に従うと奇妙な結論が出ることを指摘して、
それによって相手を論破しようという、いわゆる帰謬法に近いもので、
それによって相手の論理の前提が間違っていたことを証明するのである」。
つまり、先ほどの「去るという運動はありえない」というのは、
龍樹が「運動はありえないのです」と説いているのとは逆に、
「説一切有部のアビダルマ論師のみなさん、
あなたがたの論理によると、運動はありえなくなっちゃうでしょ?
おかしいでしょ? みなさんの論理は前提から間違ってまっせ!」
と論戦をしかけているらしのです。
という前提で、以前挫折した『龍樹』(解説+中論)を読んだら、
これが震えるほどに面白く、備忘録として何回かブログに記そうと思います。
龍樹さんは、説一切有部の何をそんなに論破したかったのかは、また明日・・・。
- 龍樹 (講談社学術文庫)/中村 元
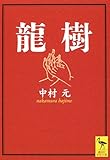
- ¥1,470
- Amazon.co.jp
にほんブログ村
創価学会とクリスチャンの夫婦、葬式をどうする?
数年前に、同年代でとても近しい親族が病死しまして、
お葬式の打ち合わせに同席したことがあります。
今ふうの新しい斎場の営業マンが来まして、
まず「何教でやるか」という話でつまづきました。
というのは、亡くなった彼女はクリスチャン、
彼女の実家は浄土真宗、彼女のダンナは創価学会なのです。
斎場の方はファイルを広げて、
「どの宗派のお坊さんでもお呼びできます。」と
自信たっぷりに言いました。
ファイルには、それこそ浄土系から、天台・真言宗、
日蓮正宗、臨済・曹洞宗、カソリックにプロテスタント、
たしかイスラムまであったような気がします。
「どれでもいいんですか?」「はい。大丈夫です」と言うのですが、
こんな通販カタログみたいに選んでいいのか?
いっそイスラムにしたりして、などと思っていたら、
ダンナが小さい声で「日蓮だけはマズいです」と。
創価学会と仲が悪いですからね。
結局、「いっそ無宗教の音楽葬にしよう」となり、
電子ピアノとバイオリンで演奏(別料金)してくれるとのことで、
彼女が好きだった曲を10曲挙げることになりました。
ダンナが挙げたのが、サザン・オール・スターズ10曲。
そんなわけで、葬儀当日は、
「いとしのエリー」でお焼香ですわ。
音大生バイトによるヘッポコ演奏でも、意外と泣けて、
やっぱりサザンは偉大なのかも、と見直しました。
お焼香にも合うサザン・オール・スターズ。
で、ダンナが、お骨は創価学会のお墓に入れたいというので、
行きましたよ、有名な富士宮の巨大霊園に。
米国のアーリントン墓地をモデルにしたというその墓地は、
富士山と桜の花が、ある意味、臨死体験のような風景でした。
広大な敷地に、「池田橋」も架かっていました。

納骨堂での共同納骨で、何十人もの人が、
「南無妙法蓮華経!南無妙法蓮華経!」と声を合わせ、
軽くトランス状態になっている人もいて、
声を合わせて読経するのは、けっこう気持ちいいものだなと。
納骨される彼女は、いちおうキリスト教の洗礼を受けてるんですけどね。
富士宮名物の焼きそばは、別においしくなかったです。
といった経験から思うに、宗派、信仰とはいったい何なのかと。
自分の信仰がはっきりしている人は、「何宗でやってくれ」と
遺言を残したほうがいいかもしれないですね。
ところが、例の斎場の「呼べるお坊さんリスト」には、
上座仏教はなかったような記憶があります。もし私が、
「葬式は不要。どうしてもやるなら、原始仏教または上座仏教で」
と遺言したら、それは可能なのでしょうか。
どこからお坊さんを呼んでくるのでしょうか。
あと、「読んでほしいお経」も遺言したほうがいいですね。
たとえば、大涅槃経の「無常偈」(むじょうげ)。
これだけでは短すぎるのかしら?
諸行無常 aniccaa vata saGkhaara
是生滅法 uppaadavayadhammo
生滅滅已 uppajjitvaa nirujjhanti
寂滅為楽 tesaM ruupasamo sukho
(怠慢してウィキからのコピペなのでパーリ語が
合ってるかわかりません……)
↓タイの中国人系のお葬式らしい。このようにやってくれと遺言したら、遺族は困るでしょうね。
にほんブログ村
善良なる「悪魔のささやき」
「サンユッタ・ニカーヤⅡ」(『悪魔との対話』岩波文庫)の続きです。
この原始経典では、悪魔が出てきて、
お釈迦さまにいろいろな問答や誘惑をしかけ、身につまされます。
悪魔というのは、自分の心の迷いや、
世間の”常識”や、それを説きたがる人たちのことだと思われます。
たとえば・・・。
悪魔「なぜに人々とつき合わないのですか?
あなたはだれとも友にならないのですか?」
ブッダ「愛しく快い姿の軍勢に打ち勝って、目的の達成と
心の安らぎ、楽しい悟りを、私は独りで思っているのです。
それ故に私は人々とつき合わないのです。
私は、だれとも友にならない。」
悪魔「子ある者は子について喜び、また牛のある者は牛について喜ぶ。
人間の喜びは執著するよりどころによって起こる。
執著するよりどころのない人は、実に喜ぶことがない。」
ブッダ「子ある者は子について憂い、また牛のある者は牛について憂う。
人間の憂いは執著するよりどころによって起こる。
実に、執著するよりどころのない人は、憂うることがない。」
どうでしょう。
これらの悪魔のささやきは、とっても身につまされるものがあります。
「子供ほど、かけがいのないものはないわよ~」と言う良き母親。
「人と付き合って成長するんだ。人脈は財産なんだぞ」と言う上司。
「ひきこもってる君へ。友達って素敵だよ」みたいなメッセージ。
「金持ち父さん・貧乏父さん」のような、すべてのマネー本。
「こだわりを持って生きようぜ」という熱い人。
私たちの周りには、こういう善良な言葉があふれかえっていますが、
その意味するところは、悪魔の言葉と同じです。
もし「あなたも親になればわかるけど、子供を愛することって、生きがいよ」
と言われたときに、
「でも子供に執着するのって、不幸のもとだよね」と答えたら、
「性格異常者」に決定です。
「たとえ悟りを開いたとしても、
愛するものがない人生に何の喜びがあるのか?」
という悪魔の問いに、誰もそう簡単に答えは出せないでしょう。
(愛と慈悲は違いますもんね)
そう考えたとき、仏教のギリギリの厳しさ、
ある意味での反社会性に、私は感動します。
にほんブログ村


