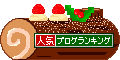なごやんのBCL史(42)北欧の福祉国
前回のヨーロッパがギリシャ(南欧)でしたので、今回は北欧スウェーデンへ行きます。
【背景】
生物分類学の父と言われるカール・フォン・リンネやノーベル賞で知られるアルフレッド・ベルンハルド・ノーベルなど、現代に連なる「偉人」たちを数多く輩出したスウェーデンはスカンジナビア半島3国で面積が最も大きな国で、隣国のノルウェー同様、立憲君主制をとっています。王室は1818年からベルナドッテ家によって継承され、現在の国王はカール16世です。
スウェーデンは高福祉の国として知られ、日本でも様々な分野で施策等を取り入れています。
【ラジオ・スウェーデン】
私がBCLにはまっていた時代のスウェーデン国王はグスタフ5世を引き継いだグスタフ6世でした。
スウェーデンからはスウェーデン放送協会の公共放送が「ラジオ・スウェーデン(Sveriges Radio,Radio Sweden)」という国際放送を外国向けに送信していました。
ラジオ・ノルウェーの英語放送が週1回だったのに対し、ラジオ・スウェーデンでは毎日放送していましたので、受信状態に波はあるものの、よく聴くことができました。
放送はカール・ミケル・ベルマン作、Storm och böljor tystna(嵐と沈黙のうねり)の最初の2小節「♪ Storm och böljor tystna,re'n」のインターバルシグナルに続き、スウェーデン語で「Sveriges Radio,Utlandsprogrammet.」、英語で「This is Radio Sweden,Stockholm.」というアナウンスが入り、ヒューゴ・アルヴェーンの「スウェーデン狂詩曲第1番(夏至の徹夜祭)」のメロディーで開始されました。
私が聴いていたのは主に東アジア向け英語放送で、最大出力は500KWありました。ニュース、解説等の他、世界的に人気のあった番組、「Sweden Calling DXers」は楽しみでした。
ただ、よく聴いた割にはあまり頻繁には受信報告をしませんでした。約10年間で、ベリカードは8枚しか持っていません。(よく聴いていたのに1回もレポートしない年があったとういうことです。)
私が聴き始めた頃、受信証(ベリカード)にはベルナドッテ家最初の国王、カール14世が描かれていました。
その後、国際放送の名称は「ラジオ・スウェーデン・インターナショナル」になりましたが、内容が大きく変わったわけではありません。受信状態のよい日にはドイツ語、ロシア語、英語と長時間にわたって聴いています。
受信報告は英語放送に対してのものですが、受信証とは別にペナントが送られてきました。
「少年」の特権でしょうか(笑)?
ラジオ・スウェーデンのペナント
受信証はプログラムや種々のインフォメーション(紛失)とは別に葉書で送られてきました。同封した方が郵送料の節約になると思うのですが、それぞれの部署が違うのでしょう。(縦割り行政みたいに。)
【そして今】
多くの国と同様、この放送局も1990年代になると分割され、国際放送も2010年以降はインターネットだけになりました。
ということで、古き良き時代の話でした。
これまでの記事はなごやんのBCL史(序)をご覧ください。
相互リンク⇒アクティブなごやん(W 杯アジア最終予選のゴートク)
豊田はでかい
ある意味私らしい、とりとめもない話です。
愛知県民に「愛知県で人口が最も多いのは名古屋市ですが、2番目に多い市はどこでしょう?」と聞くと、一宮市、豊橋市、岡崎市などと答える人が「そこそこ」います。
でも、正解は、豊田市です。
一方、愛知県で最も面積の大きい市町村も豊田市です。
愛知県には名古屋を除けばそう大きな市はなく、豊田も人口が多いといっても、40万人そこそこですから、愛知県で3番目に人口密度の少ない市も豊田なのです。とにかく、2005年前後に周辺町村をやたらめったら合併し、40万都市にしたのですから。
さて、そんな豊田市の北部、旧小原村へ先日仕事で行ってきました。職員からは「車でなければ行けない」と言われた小原地区の中でも人里離れた場所です。周辺にスーパーもコンビニも昔ながらの小売店もないところです。確かに、車がないと生きづらい場所です。
でも、私はそんな考えを受け入れません。
「そんなことはない。それを言ったら、車のない人は生きていけなくなるだろう。」
と言うことで、探しましたよ、公共交通機関を。
そして、今日のお話です。
1.名鉄豊田線
辺境の地へ行くとしても、とりあえずは市の中心部へ行かなければなりません。名古屋からは地下鉄鶴舞線に続く名鉄豊田線があります。そう、名古屋から豊田スタジアムへ行く時の電車です。豊田線は厳密には梅坪駅までなのですが、電車自体は豊田市駅まで行っています。
起点は名古屋市の「赤池駅」です。そこから豊田へ出発しました。
2.おいでんバス
野越え山越え谷を渡りはしないけど、とりあえずは豊田市駅へたどり着きました。豊田市駅前には大抵、路線バス(おいでんバス)が停まっています。
そのうちの一つ、小原方面へのバスに乗り込みました。
豊田市駅前を発車してすぐ、何台もの「おいでんバス」とすれ違います。そして、あの豊田スタジアム手前で左に折れ、小原への道に入ります。
とにかく広い豊田市です。三河はもちろん、尾張、更には岐阜県の地名が次々に現れます。
途中、旧藤岡町にある加茂ケ丘高校でも停車しますが、ここには「おいでんバス」とともに、「ふじバス」の停留所があります。藤岡地区を巡回するコミュニティーバス、ふじバスの停留所です。
3.小原突入
さらに「山奥」へ入っていくと、いよいよ来ました。和紙の里、小原地区(旧 小原村)です。
和紙の里小原
おいでんバスは小原地区の南側しか通りません。私の目的地はもっと北、すなわち奥地です。やむなく北篠平の停留所で下車しました。以前は商店があった場所のようです。
4.小原さくらバス(今日の主題)
ここで私は次の交通手段を待ちました。
「おばら桜バス」です。待つこと約5分。
 おいでんバス、おばら桜バス共通停留所
おいでんバス、おばら桜バス共通停留所
来ました。おばら桜バスです。ジャーン! こ、こ、これは・・・おわかりですよね。
おばら桜バス
そう、これはバスです。決してタクシーではありません。
タクシーは、通常、①最短距離を走り、②door-to-doorで、③料金は1走行当たりです。
バスは違います。
①'決められた路線を走り、②'決められた停留所にしか停まらず、③'料金は客1人当たりです。
ですから、この車はあくまでバスです。
ちなみにこの日のこの時間は乗客は私1人。目的の停留所まで200円(均一料金)でした。なんのことはない、目的地のすぐ前が停留所です。というか、目的地に停留所があります。
5.お金持ち豊田市
おばら桜バスの案内図を見ると、このバスは旧小原村の隅々まで運行しています。
運転士さんに伺ったところ、利用者は1日20人前後だそうです。単独ではとてもとても採算がとれるものではありません。
「経営は苦しいですよね。」と私。
「ほとんど市の補助ですよ。」と平然と言う運転士。
さすが、お金持ちの豊田市です。
このバス、予約が必要です。日時と乗車、下車の停留所名(番号)を伝えておきます。そうすると、希望する時刻に希望する停留所まで迎えにきてくれます。
地図をクリックし拡大してみてください。道(山道を含む)に沿って点々と停留所があります。そう、あくまでバスですが、まるでタクシー感覚です。
豊田市民でなくても利用できます。
次の日、職場で得々として言いました。
「電車とバスで行ってきた。車は不要だったよ。」と。
なにしろ、レンタサイクル、コミュニティーバス大好きな私ですから。(笑)
(そのうち、コミュニティーバスのカテゴリーも作る予定です。乞うご期待。)
相互リンク⇒アクティブなごやん(リーグ開幕早々ピンチのHSV、引き締めよゴートク)
なごやんのBCL史(41)かつての大帝国
今回はアジア大陸からヨーロッパにかけて歴史的には世界最大の帝国を築き、今は中央アジアに収まっている国、モンゴルの放送です。
【背景】
モンゴルの歴史を辿ると、中国やロシア、その他中央アジアの国々との関係も含め、とても興味深いのでしょうが、私にはそれほど関心のある地域ではないので、ほぼスルーします。
ただ、私の少年時代、モンゴルは「モンゴル人民共和国」という国名の下、旧ソ連邦と緊密な関係にありました。というより、1917年の社会主義革命により1922年に世界で最初の社会主義国となったソ連邦に次いで、その2年後に世界で2番目に社会主義を取り入れた国です。
政党はモンゴル人民革命党の一党だけでした。一党支配は当時の社会主義国ではよくあることでした。
【ラジオ・ウランバートル】
私が聴いていたモンゴルからの放送はモンゴル国営放送が1964年に開始した外国向け放送の「ラジオ・ウランバートル」です。
私が聴いていた時代、多分、モンゴル語と英語の放送があったと思うのですが、私はモンゴル語は全く理解できませんので、もっぱら英語放送を聴いていました。
インターバル・シグナルに次いで、開始音楽が奏でられる中、「This is the Mongolian People's Republic Broadcast from Ulan Bator.」とアナウンスされました。ただ、数年後にはインターバル・シグナルの後、モンゴル語、そして英語で局名がアナウンスされ、。英語では「This is Radio Ulan Bator.The overseas broadcasting servece of Radio Mongolia.」と言っていました。そして、その後、開始音楽が奏でられました。
開始音楽は国歌ではなく、広い草原をイメージさせる滔々としたものでした。私はこの音楽を聴くのが好きでしたが、曲名を訊ねるのを怠りました。
英語放送に対して、私は残念ながら受信証を受け取ることができませんでした。もしかすると、当時は受信証を発行していなかったのかもしれません。
ただ、新年にはきちんと季節の挨拶が送られてきました。
こんな切手帳もいただきました。
モンゴル人民共和国切手帳
中を見て、キリル文字だけでなく、モンゴル文字(蒙古文字)で書かれた切手があるのに驚きました。
この放送局から送っていただいたモンゴルの民族音楽を収めたLPレコードは私のお宝です。
モンゴル民俗音楽のLP
社会主義国の多くは、発達した資本主義の矛盾の中で生まれたのですが、モンゴルは資本主義の成熟を待たず、いわば封建的な制度からいきなり社会主義になったようなものです。そんなことを書いた書籍(By-passing capitalism:資本主義を迂回して)も送ってもらい、読みかけたのですが、「純理系」の私にはいまひとつ興味が持てず、少し読んだところで中断しました。一般向けの随筆(popular essay)で平易な英語で書かれていて、気楽に読めるのですが、なんてったって、基本的に怠惰な私ですので・・・
「資本主義を飛び越えて」というタイトルの日本語訳もあるようですが、私は見たことがありません。
シレンディブ:資本主義を迂回して.モンゴル人民共和国国立出版,ウランバートル,1968
そんなモンゴルも1991年にソ連邦が崩壊すると、翌年、社会主義国から離脱しました。
ラジオ・ウランバートルの国際放送は国が現体制になる以前の1989年、日本語放送を開始しました。そして、1997年、名称をVoice of Mongolia(モンゴルの声)とし、現在に至っています。ただ、この局が日本語放送を開始した時代、私は既にBCL から遠ざかっていました。
BCL、SWL、DXingの過去記事はここをご覧ください。
相互リンク⇒アクティブなごやん(勝てないHSV、6試合で勝ち点1)
モンゴルで見る星も美しかろう⇒
新監督初陣飾る!
第2ステージ第14節 アウェー 磐田戦
ジュビロ磐田 1-2 アルビレックス新潟
監督が代わって最初の試合、新潟は磐田へ乗り込んだ。
地理的に準地元で行われる試合なので、従来は現地へ行っていたのだが、今日は昼過ぎまで県内の2か所で仕事や私事があり、断念して帰宅した。
試合のライブ速報にありついたのが、前半30分頃、新潟が1点リードしている時だった。
私が見始めるとすぐに1点返された。見なきゃよかったのか・・・
前半は同点で折り返した。
後半、新潟はよいところまで行くのだがなかなか得点に結びつかない。
このままいくと、今日、福岡に大勝している名古屋に追い越される。
終盤、新潟は猛攻を仕掛けるが、相手のGKが必死に防ぐ。枠に飛んだシュートも跳ね除けられる。
うーん、こんなに攻めていて引き分けなんて、と不安がよぎった後半44分、左サイドからの鈴木武蔵のクロスに山崎亮平が合わせてダイビングヘッド。これが決まって、土壇場で勝ち越した。
あとはしっかり守って、なんとか勝ち点3をもぎ取った。
次の試合までは3週間ある。強豪との3試合を残しているが、そこは片渕新監督の采配に期待しよう。
応援の皆さん、お疲れさまでした。
相互リンク⇒アクティブなごやん(こちらも新監督のHSV。ゴートク、奮起せよ!)
新潟ブログです⇒
なごやんのBCL史(40)神話と古代文明の国
今回はこれまで手薄だった南ヨーロッパへ来ました。バルカン半島の先端、ギリシャです。
【背景】
世界四大文明発祥の地とひとつ、ギリシャは、また神話でも知られています。古代の神々がこの地域を作ってきました。
古代ギリシャでは建築様式も芸術的で中学校の美術の教科書には必ずと言っていいほど出現します。
【ギリシャ放送協会】
そのギリシャにも公共放送局はありました。そう、あったのです。
私の短波放送ゴールデンエイジ時代にはなかなか聴くくとができず、ようやく聴いたのは1970年代になってからです。
ギリシャ語の「Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση」をそのまま英語にすれば「Greek Radio Television」ということでしょうが、この局の英語名は下のベリカードにもある通り、「Hellenic Broadcasting Corporation」で、日本では「ギリシャ放送協会」と呼ばれていました。
私が初めて聴いたのはギリシャの軍事政権が終わり、民政に復帰したころで、最初の受信報告はどの言葉の放送についてのものだったか覚えていません。なぜかこの頃のログをゴソッと紛失してしまっているのです。(どこかの段ボール箱にうずくまっているかも。)
その時には葉書の受信証が送られてきただけでした。
その後、国際放送は「The Voice of Greece(ギリシャの声)」と呼ばれるようになり、親局の名も「Greek Radio-Television」になっています。
受信証と一緒に送られてきたプログラムでわかるように、日本向けのギリシャ語/英語放送もあったのですが、出力は100KWと特別大きくもなく、むしろ周辺諸国への送信の方が250KWと大きくなっていました。
受信証の図案はギリシャ観光地の写真シリーズになっていました。
 ギリシャ観光地シリーズの受信証
ギリシャ観光地シリーズの受信証
この放送局は1960年代から70年代の軍事政権時代に国営化された以外、公共放送として継続されてきましたが、近年、ギリシャが金融危機に直面し、電波を使った放送は2013年に消滅しました。代わって、今では「Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Ίντερνετ και Τηλεόραση(New Greek Radio,Internet and Television:新ギリシャラジオ・インターネット・テレビ)」としてインターネットによる放送を行っています。
※このシリーズはこれから原則として月・木、あるいは火・金の週2回アップします。
次回はアジアです。
このテーマの過去記事はこちらをご覧ください。
相互リンク⇒ アクティブなごやん(新監督のもと、奮起せよゴートク)