なごやんの続・鉄道日記(97)立山へ
毎月1回はアップしようと思っていた続・鉄道日記ですが、8月はついに1度も書くことができませんでした。
今年は北陸に縁があるようで、7月は1月に続いて富山へ出張でした。立山町。立山へ登ったわけではありません。
立山町へはJR富山駅から富山地方鉄道(地鉄)で行きます。富山へは北陸本線→北陸新幹線でお昼少し前に着きました。
ここから、地鉄で目的地へ行くのですが、その前に腹ごしらえです。この日は立山そば+ますの鮨。まあ一応富山ですので。
電鉄富山駅には黒部へ向かう本線、立山へ行く立山線、岩峅寺へ行く不二越・上滝線が出ています。
この日の私は
電鉄富山(1212)--<地鉄立山線>--(1239)五百石
の予定でした。
しかし、立山線の出発時刻が近づくと、続々とアルピニストたちが・・・
そうです、立山から立山黒部アルペンルートへ向かう人たちです。 満員電車か。
ここでチェンジ・マインドです。不二越・上滝線で岩峅寺へ行き、そこで立山線上り、電鉄富山行に乗り換えるのです。
その電車は12時20分発です。
乗って1つ目の駅、稲荷町で本線、立山線とお別れです。
電車は南下し、岩峅寺へ向かいます。右車窓、前方車窓からは遠くの山々が望めます。
そして、常願寺川を越すと岩峅寺です。
岩峅寺には立山線から立山へ行く電車とともに保線車両も停車していました。
そしてここで富山へ向かう電車に乗り換えました。
右手に立山方面の山々を望みながら富山へ向かいます。そして、途中の五百石で下車しました。
旅程は
電鉄富山(1220)--<地鉄不二越・上滝線>--(1253)岩峅寺(1258)--<地鉄立山線>--(1309)五百石
という長旅(笑)でした。
改札を出る時、切符に無効印をお願いしたら「裏に押してあげる。」と言って裏に押してくれました。これ、磁気切符でないからできることですね。運賃は途中下車していないので立山線ストレートと同じ600円でした。
鉄道日記/族・鉄道日記の過去記事はこちらをご覧ください。
相互リンク⇒アクティブなごやん(ゴートク見せ場を作るも、HSVホームで完敗)
ピンチは続く
第2ステージ第12節 アウェー 横浜FM戦
横浜Fマリノス 3-1 アルビレックス新潟
通常なら現地応援するところなのだが、今日は真昼間に用事があったためネットで情報を追うしかなかった。
最後のところで決めきるかどうかは、結局「個」の問題なのだろうか?
「そこはパスじゃなくシュートだろう!」とか「サイドから駆け上がってきているのになんでクロスを出さずシュートするんだよう!」と言ってみても結果論だし、精度が高ければどちらでも成功するはずだ。
ウチのラファエル・シルバの得点はボールが相手に当たってコースが変わったのがよかったということで、いわば幸運なゴールだった。
相手のゴールは・・・必然の失点だ。
とは言え、1失点目は止められなかったかなぁ?
まだ他の試合の結果が出ていないのでなんともいえないが、今後の相手を考えると相当苦しくなってきた。
もちろん、最後の最後までわからないのだから、楽観も悲観もせずに、ひたすら戦い続けるしかない。
どちらにしても「もう5試合しかない」ではなく、「まだ5試合ある」だ。
応援の皆さん、お疲れさまでした。
相互リンク⇒アクティブなごやん(ホーム、ライプツィヒ戦、ゴートク先発か)
アルビレックス新潟ブログです⇒ポンペイ in 名古屋
ヴェスヴィオ火山の噴火により火山灰に埋もれた古代ローマの都市ポンペイの壁画展が名古屋で開かれていて、私も先月行ってきました。
場所は名古屋市博物館で、私の家からは名古屋市営地下鉄桜通線で行きます。
美術館は整備された前庭を控えています。
入口ではギリシャ神話のマイナスが迎えてくれます。
この展覧会は4章に別れていました。
第1章は「建築と風景」で、一部は「平日写真撮影可」になっていましたが、私が行ったのは土曜日でしたので、写真を撮ることはできませんでした。
ポンペイの壁画には第1様式から第4様式まであるとのことですが、第1様式の壁画はわずかしか展示されていませんでした。鮮やかなのは第3様式のようでした。
第2章は「日常の生活」で、ポンペイ近郊のカルミアーノの農園別荘の復元が威光を放っていました。
第3章「神話」ではナルキッソス、ヘラクレスなど、ギリシャ神話に登場する人物が多くとりあげられていました。アリアドネ、ディオニッソスなども次々に登場します。
「アキレウスを教育するケイロン」もそのうちのひとつです。
ポンペイとともに世界遺産に登録されているエルコラーノで見つかった壁画も展示されていました。
第4章「神々と信仰」では、凶暴な(か?)マイナスがあちこちに姿を現していました。
踊るマイナス
途中にはケンタウロスの体部分が置いてあり、そこに入ってケンタウロスになった写真を撮る場所もありました。親子で来館している人たちが時に列を作りながら記念撮影をしていました。
展示は全部で63点と多くはありませんが、ひとつひとつが繊細で、全部見るには数時間かかります。
この展覧会は9月25日まで開催され、10月15日から12月25日までは兵庫県立美術館、2017年1月21日から3月26日まで山口県立美術館、4月以降福岡へ巡回する予定だそうです。
相互リンク⇒アクティブなごやん(ゴートク、ブンデス、HSV)

なごやんのBCL史(37)東南アジアの牽引車
今回はアジアです。東南アジアのインドネシアへやってきました。
【背景】
1.人類の祖先
「ジャワ原人」で知られるように、インドネシアには今の人類が住み着く以前から人類の原型ともいえる「人」が住んでいました。しかし、その後(と言っても紀元前ですが)中国やマレー半島から渡ってきた人たちが住民の主流となってきます。
2.オランダの支配
紀元後13世紀ころからイスラム教が地域一帯に広まり、中心的な宗教になりました。
17世紀に入ってすぐにオランダが「東インド会社」をジャカルタに作り、インドネシアを支配下におきます。
19世紀末にはジャワ島だけでなく、スマトラ島までオランダ領になりました。
インドシナ半島東側(現、ベトナム、ラオス、カンボジア)がフランス領インド(仏印)と呼ばれたのに対し、インドネシアの島々はオランダ領インド(蘭印)とされました。
インドネシアはずっとオランダの支配を受けていましたが、第一次世界大戦頃には独立機運が高まってきていました。
3.オランダからの解放と日本の統治
第二次世界大戦がおきると、日本は中国、朝鮮に留まらず、東南アジア諸国(フィリピン、インドシナ半島)へも領土拡張の手を伸ばし、インドネシアのスマトラ、ジャワへも侵攻しました。そして1942年、インドネシアからオランダを切り離しました。インドネシアにとってはオランダからの解放でしたが、それはまた、日本に支配されることでもありました。
4.独立
インドネシアの歴史が大きく動くのは第二次世界大戦が終了した1945年のことで、日本から解放されたインドネシアは終戦翌日の8月17日、独立宣言を読み上げ、スカルノを大統領としました。
5.オランダによる再植民地化を阻止
敗戦国日本はもはや蚊帳の外でしたが、"戦勝国"オランダがこの独立に納得せず、同じく戦勝国の英国と連合を組んでインドネシア軍との戦いに入りました。そして1949年、連合国(United Natios,日本での呼称は国際連合)が仲裁に入って、ようやくインドネシア共和国が認められるに至りました。(ただし、インドネシアでは1945年8月17日を独立の日としています。)
蘭、英との戦いには日本軍の元戦士も加わったとされていて、その意味では、日本の軍人がインドネシアのヨーロッパ植民地主義からの解放に寄与したと言えるかもしれません。
6.スカルノからスハルトへ
大統領となったスカルノは1955年にバンドン会議を成功させるなど、国際的な名声を高めていきましたが、国内で盤石の力があったわけではなく、紆余曲折を経て1967年、辞任に追い込まれ、後を継いだスハルト大統領の時代になります。
7.現在のインドネシア
その後、政権はハビビ、ワヒド、メガワティ、ユドノヨと代わり、2014年からはウィドド大統領が政権の座に着いています。東南アジア諸国連合(ASEAN)の本部は首都ジャカルタにあり、この地域では大きな力を持っています。
いわゆる「第三世界」を率いる国のひとつで、その立場で「西側」の日本とも友好な関係を維持しています。
【Inilah Suara Indonesia(こちらはインドネシアの声です)】
さて、前書きが長くなり過ぎましたが、スカルノからスハルトへの政変の頃、私はインドネシアからの放送を聴いていました。ログを見ると、放送開始前にインターバルシグナル(I S)が流れていたようです。しかし、どんな曲だったか覚えていません。インドネシア語放送は比較的よく入感しましたが、英語放送の受信状態はそれほどよくありませんでした。
聴いていたのはインドネシア共和国放送(Radio Republik Indonesia,RRI)の国際放送で、インドネシアの声(Suara Inodonesia)です。英語のアナウンスメントは「This is the Voice of Indonesia,broadcasting from Djakarta.」と言っていました。
受信報告を出すと、しばらくして受信証(ベリカード)が送られてきました。
東南アジアではベトナムの声の次によく聴いた放送ですが、ベトナムの声のようにほぼ毎日というわけではありませんでした。
時には国内向けインドネシア語放送を聴くこともできました。ただし、私はインドネシア語がわかりませんので、内容の理解には至っていません。
仕方なく、英語で受信報告を出しました。
 インドネシア語放送のログ(Warta Berita=ニュース)
インドネシア語放送のログ(Warta Berita=ニュース)
その報告に対しては民族衣装を題材にしたユニークな図案の受信証が送られてきました。
インドネシアの声からはこの他に番組表やパンフレット等も送られてきたのですが、現在行方不明です。
インドネシアの声は1977年に日本語放送を開始し、現在も短波で続けられています。ただし、私は聴いていません。インターネットでは日本語ページもあります。
ということで、あまり話題のないインドネシアでした。
次回はまたヨーロッパです。そして、その後はアフリカを少し増やし、ヨーロッパ→その他→ヨーロッパ→アジア→ヨーロッパ→アフリカ→ヨーロッパ→アジア→ヨーロッパ→その他→ヨーロッパ→アジア→ヨーロッパ→アフリカ→ヨーロッパ→アジア・・・と、全体の2分の1がヨーロッパ、4分の1がアジア、8分の1がアフリカ、残りの8分の1がその他(北米、中米、南米、オセアニア)となるように調整します。
SWL、BCL、DXingの過去記事はこちらをご覧ください。
相互リンク⇒アクティブなごやん(ゴートク、ブンデス、HSV)
インドネシアは暑かろう⇒
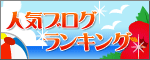
金メダルの街
先日、私は仕事で知多半島の付根にある大府市の市役所へ行ってきました。
大府市役所はJR大府駅から徒歩3~5分のところにあります。大府駅前のロータリーには「至学館大学」スクールバスのバス停もあります。
人口9万人弱の必ずしも大きくない市にしては立派な市庁舎です。
大府市役所はコミュニティーバス、「大府ふれあいバス」のターミナルです。このバスは大府市役所を起点に、5コース出ていて、利用率は高いようです。
中もゆとりがあります。さすが、裕福な地方交付税不交付団体です。市民税も高くないんでしょうね。
この方向から左へ90°体を回転させると、こんなダンマクとボードが目に入りました。リオデジャネイロ五輪で活躍した、この市ゆかりの選手のサイン入り直筆メッセージとお祝いの短冊です。
そう、大府市には女子レスリングの拠点とも言える至学館大学(旧 中京女子大学)があります。それに、吉田秀彦選手の出現で一躍有名になった柔道の大石道場もあり、その道場出身の近藤亜美選手が銅メダルを獲得しています。
地元では、「金メダルの街」などと呼ばれているようです。至学館大学も大石道場も最寄り駅は大府よりもむしろひとつ北(名古屋寄り)の共和駅なのでしょうが。
9月3日の土曜日には女子レスリング選手の市内パレードがあったようです。
→新聞記事によれば、出発点は共和駅前で、市役所にはいかなかったようです。
って、土曜日は市役所閉まってるし。
相互リンク⇒アクティブなごやん(ゴートク、ブンデス、HSV)
愛知の花はカキツバタ⇒





























