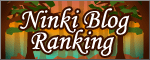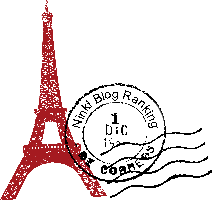ポンピドゥー・センター傑作展@東京都美術館
暑い夏の日、私は東京出張の合間を縫ってポンピドゥー・センター傑作展へ行ってきました。場所は上野公園にある東京都美術館です。
朝9時前に公園に入り、世界文化遺産に指定された国立西洋美術館の前を通り、リオデジャネイロ五輪直前で建設中のPV会場を横目にトコトコ歩きました。
上野の森へ来ればあちこちでいろいろな催しがあり、腐っても さすが首都Tokyoだなぁと溜息がでます。
9時30分会館を待つ人たちは木陰で休んでおられましたが、直前には列ができました。ただし、メジャーな展覧会ではないためか、それほど混み合ってはいませんでした。
東京はクマゼミではなくミンミンゼミ地域です。公園にはミンミンゼミの鳴き声が響き渡りますが高い梢を探っても、首が痛くなるだけでなかなか姿は見えません。ようやく、抜け殻を見つけました(笑)。
ポンピドゥー・センターはフランスの首相から大統領になったジョルジュ・ポンピドゥーの鶴の一声で(か?)建設され、1977年に開館したパリの一大文化拠点で、絵画もたくさん所蔵しています。今回の展覧会は、それらの作品のうち1906年から1977年に制作されたものを1年1作家1作品ということで、~イズム(~主義)を超えて展示されました。展示の順序も完全に年代を追っています。
会場に入って最初の絵は1906年にラウル・デュフィが描いた「旗で飾られた通り」で、革命記念日の7月14日に故郷の街がフランス国旗で彩られている様子を表しています。
 ラウル・デュフィ「旗で飾られた通り」(1906)(リーフレット)
ラウル・デュフィ「旗で飾られた通り」(1906)(リーフレット)
私の好きなマリー・ローランサンの作品は1940年の「イル=ド=フランス」です。
 マリー・ローランサン「イル=ド=フランス」(1940)(新聞)
マリー・ローランサン「イル=ド=フランス」(1940)(新聞)
1933年にオットー・フロイントリヒが描いた「私の空は赤」は強烈なメッセージを発しています。
ドイツで生まれたユダヤ人のフロイントリヒはナチスドイツの批判にさらされます。それは、フロイントリヒの画風に対してなのか、そもそもユダヤ人だからなのかはわかりません。ピカソに出会ったフロイントリヒのこの作品はキュビズムの要素を持っていることがうかがえます。「革命的作家芸術家協会」に属していたフロイントリヒにとって、赤は共産主義の象徴であり、またナチズムに対する明確な拒絶だったと思われます。
フロイントリヒは1942年、ナチにより強制収容所へ送られ、そこで命を落としました。
 オットー・フロイントリヒ「私の空は赤」(1933)(絵葉書)
オットー・フロイントリヒ「私の空は赤」(1933)(絵葉書)
フェルナン・レジェの「自由」(1953)もまた強烈です。詩人、ポール・エリュアールの詩をデザインし、大きく自由(Liberté)といくつも書かれています。さらに、「J'écrit ton nom(私は君の名を書く)」とも綴られています。「自由」はフランス人たちが最も大切にする言葉のひとつです。
1945年のコーナーには何も掲出されていませんでした。第二次世界大戦が終わった年で、ここから芸術の世界も大きく変わります。
ただ、その場所にはエディス・ピアフの歌うシャンソン「ラ・ヴィ・アン・ローズ(バラ色の人生)」が流れていました。 1945年はどの国にとっても特別の年です。
この展覧会の途中には写真コーナーなんてのもありました。
この展覧会はポンピドゥー・センターの一端を知るにはよい機会ですが、専門家にとってはどんなものだろうかと思いました。もう少し焦点(作家、年代、画風等)を絞った方がよかったのではないでしょうか。
例えば「フォーヴィズム」や「シュルレアリスム」、あるいは「フランス革命記念日を巡る」など。
素人の私もいまひとつ消化不良感を持ちました。試みは面白いのですが。
この展覧会は9月22日まで開催されています。
相互リンク⇒アクティブなごやん(日本のゴートク、ブンデスのゴートク)
なごやんのBCL史(35)ソロモン王朝の終焉
私がBCLにのめりこんでいた頃、英国のエリザベスII世を讃える軽音楽、「エリザベス小夜曲(Elizabethan serenade)」をインターバルシグナルに使っている放送局がありました。
軽く、明るいセレナーデです。(この曲を聴きながらお読みください。YouTubeからの拾い物です。)
♪エリザベス・セレナーデ(マントヴァーニオーケストラ)
少し聴いているとアムハラ語のアナウンスが入り、続いて英語で「This is Radio Voice of the Gospel, station ETLF, Addis Ababa, Ethiopia.」と言ったのです。エチオピアからの放送でした。
 エチオピア
エチオピア【アフリカ最古の独立国】
エチオピアの歴史は紀元前に遡り、長い間、皇帝が統治してきました。
 上:サルサ・ディンギル;中:ファシラダス;下:ヤス
上:サルサ・ディンギル;中:ファシラダス;下:ヤス私がこの放送局を聴いていたころは1930年に即位したソロモン朝の流れを汲むハイレ・セラシエ皇帝が長期に渡る独裁政権を敷いていました。
 ナンヨウショウビン(カワセミに近い種)切手に描かれたハイレ・セラシエ皇帝
ナンヨウショウビン(カワセミに近い種)切手に描かれたハイレ・セラシエ皇帝【福音の声】
Radio Voice of the Gospel(RVOG,ETLF)は日本語で言えば「福音の声放送」ということで、名前から想像されるように、プロテスタント系の宗教放送でした。
日本からは遠く離れているにもかかわらず、そして出力も100KWと特段に大きいわけでもないのに、良好な受信状態が得られました。
 RVOGのログより
RVOGのログより受信報告に対してはこんな受信証が送られてきました。
 上のログから作成した受信報告に対する受信証
上のログから作成した受信報告に対する受信証私が聴いていたのは英語放送ですが、RVOGの放送は13言語で行われていました。
 RVOGのプログラム
RVOGのプログラム宗教放送局と言っても、宗教の宣伝だけでなく、一般的な内容も含んでいて、ログを振り返ると、当時、アフリカ一帯でマラリア撲滅のために使われていたDDTの功罪についてのトーク番組などもあったようです。
 RVOGログより
RVOGログよりこの放送局の受信証はシンプルなデザインで落ち着いていて、結構人気があったようです。日本では一年を通して比較的よく入感する局でしたし。受信証明の中身もフォーマットに数値等を書き入れるのではなく、(定型文はあるのでしょうが)ひとりひとりに宛ててタイプで書かれていました。
 RVOGのもうひとつの受信証
RVOGのもうひとつの受信証【そしてその後】
ハイレ・セラシエ皇帝の敷いた独裁政治でエチオピア国内の産業は停滞し、一般の国民が裕福になることはありませんでした。それは経済のしくみが資本主義であるか社会主義であるかとは関係なく、「専制君主」体制下での独裁政治が辿る共通の現象だと思います。
1970年代になるとその傾向は顕著になり、旱魃による飢餓の問題もほったらかしにし、「何もしない政治」に国民の不満はつのる一方でした。そして1974年9月、反乱をおこした軍により皇帝は失脚し、殺害されました。
そうやってできた「革命政権」でしたが、実態は軍事独裁政権で、エチオピアにその後の混乱をもたらしました。
エチオピアが今の比較的安定した体制になったのは1990年代になってからのことです。
RVOGは「革命政権」により1977年、「革命的エチオピアの声(Voice of Rvolutionary Ethiopia)」として政権の情宣放送局になりました。
その後この放送局がどうなったのか。・・・私はよくわかりません。
エチオピア自体は現在、政治的に不安定な状況にあるようです。
ということで、次回はまたヨーロッパです。
これまでの記事はこちらをご覧ください。
相互リンク⇒アクティブなごやん(ブンデスのゴートク、日本代表のゴートク)
アフリカブログです⇒
天皇杯 and チャレンジリーグ
※昨日は蓄積疲労のため(笑)ブログを書くエネルギーが出ませんでしたので、今日書きます。
【名古屋市港サッカー場】
先週の土曜日と昨日、すなわち、新潟が鳥栖に敗れた日とその翌日、2日連続で名古屋市港区にある名古屋市港サッカー場へ行ってきました。名古屋駅から「あおなみ線」で21分の場所にあります。
スタジアム前の緑地帯の向こうには伊勢湾が広がり、庄内川が注ぐあたりには潮が引くと干潟(藤前干潟)が現れ、多くの野鳥の姿を見ることができます。
河口から南を眺めると、光る水面に伊勢湾岸道路がくっきりと見えます。
----------------------------------------------------------------
【天皇杯1回戦】
東海学園大学 1-2 鈴鹿アンリミテドFC
8月27日(土)に行われたのは天皇杯1回戦、愛知県代表 vs 三重県代表の試合です。
愛知県代表は初出場の東海学園大学、三重県は鈴鹿アンリミテドFCです。
 バックスタンド
バックスタンド
天皇杯に関して言えば、私の優先順位はアルビレックス新潟>>>新潟県代表>>>高校生>>大学生>社会人・JFL>J リーグ(J3>J2>>J1)なので、この日は東海学園大側で見ました。
鈴鹿側の応援は、クラブとしての体をなしていて、少人数ながらまとまっていました。一方、東海学園大学は、東海学園高校サッカー部員が大挙してきていましたが、おとなしく見ていました。特別のチャントがあるわけではないようです。
試合内容は見ごたえがありました。
まず、前半7分、東海学園大が目が覚めるようなグラウンダーのシュートでゴールを決め先制します。見事です。
鈴鹿も反撃しますが、決め手に欠き得点できません。
前半のシュート数は東海学園大が9、鈴鹿はわずか4で折り返しました。
後半になると鈴鹿が主導権を握ります。しかし、東海学園大の守備陣はきっちり防いでゴールを許しません。しかし、後半25分、前線に攻め入れられると角度のないところからシュートされ、同点に追い着かれてしまいました。このシュートも威力がありました。
試合はこのまま延長に入りました。
延長前半5分のことです。
東海学園大のゴール前で混戦になり、東海学園大はこぼれ球をクリアしようとしたのですが、これが、結果的にループシュートのようになってしまい。GKの伸ばした手をかすめて自陣ゴールに入ってしまいました。
クリアミスとも言えないような、もしGKがもう一歩後ろで守っていたら防げたかもしれなかったような、客観的には「不運」なゴールでした。
結果的にこの1点を返すことができず、この地域の大学生チームは敗れ去りました。
ただ、両チームとも気迫あふれるプレーを随所に見せてくれ、観客としては満足でした。
-------------------------------------------------------------------------
【チャレンジリーグプレーオフ第1回戦】
NGU名古屋FCレディース 3-1 JAPANサッカーカレッジレディース
日曜日に行われたのは女子のチャレンジリーグプレーオフ、9~12位決定戦です。
今季、JAPANサッカーカレッジレディース(JSCL)はチャレンジリーグで残留争いに巻き込まれてしまいました。というより、チャレンジEastの15試合で勝ち点がわずか4。当然最下位でした。プレーオフを制して自動残留なるかどうかということです。
前シーズンはひとつ上のカテゴリーにいたJSCLがこの状態でプレーオフを迎えるというのは、少なくとも私は予想していませんでした。
JSCLの選手たちは名古屋へバスでやってきたようです。朝の試合ですから、当然、前泊しているのでしょう。まさか、車中泊なんてことはないでしょうね。
客席出入り口は小ぢんまりとしていました。
この日の相手はNGU名古屋FCレディースです。今季はチャレンジWestで5位、下から2チーム目でした。
さあ、キックオフです。
試合は名古屋のほぼ一方的な展開になりました。
JSCLの前方へのパスがことごとくブロックされ、しかもそこから反撃に会います。ボールを追っても走り負け、終わってみれば1-3の完敗でした。
JSCLのゴールチャンスは何回かはありましたが、名古屋の守備陣の連携は徹底していて、最後は跳ね返されてしまいました。
JSCLの試合を見るのは初めてだったので、以前と比べてどうかということはわかりませんが、名古屋は数年前と比べると明らかに進化していました。特に守備の意識は高く、また相手がボールを持っている時の寄せにも威力がありました。
そうは言っても、この日の試合は前日の天皇杯の試合と比べると、チャレンジリーグはまだチャレンジの段階だなぁと思いました。
相互リンク⇒アクティブなごやん(ゴートク、HSV、ブンデスリーガ)
シュートしなきゃ得点できない
第2ステージ第10節 アウェー 鳥栖戦
サガン鳥栖 1-0 アルビレックス新潟
今日は天皇杯の1回戦、愛知代表×三重代表が名古屋港サッカー場で行われたため、学生>社会人>J リーグとNHK仕様の私は愛知代表の東海学園大学の試合を見にいってきた。これに関しては明日にでも日記を書きたい。
その試合が延長戦になったため、私が帰宅し、アルビレックスの試合を追うことができたのは後半になってからのことだった。
相手に先制点を許すと、ウチは攻めども攻めどもシュートまで持ち込めない。せっかく奪取したボールもすぐにカットされてしまう。
それにしても相手の先制点は見事というより、普通にフォワードとしての仕事をしたというものだった。
今日は甲府が最後までしっかり粘って引き分けに持ち込み、勝ち点がウチと並んだ。
もう後がないぞ。次節はホームだ。今節チョット調子を上げた名古屋が相手だが、相手の残留とか降格とか気にしている場合ではない。とにかくウチが勝つだけだ。
遠く九州の地まで応援の皆さん、お疲れさまでした。
相互リンク⇒アクティブなごやん(ブンデスリーガが始まった)
アルビブログです⇒
なごやんのBCL史(34)青きドナウ
【ドナウ流れる歴史の街】
日本人によく知られているヨーロッパの川のひとつがドナウ川です。恐らく、「最もよく」知られているのではないでしょうか。
ドナウ川は元アルビレックス新潟の矢野貴章のブンデスリーガ時代のホームタウン、フライブルクの近くに水源を有し、全体として東へ向かい、ドイツのレーゲンスブルク、オーストリアのリンツを通ってウィーンの街の中を流れます。そこからスロバキアとハンガリーの国境に沿ってブダペストへ入り、南下してセルビアへ入ると首都ベオグラードを通ってルーマニアとブルガリアの国境に沿い、最後はルーマニアから黒海へ注ぐ、ヨーロッパで2番目に長い川(1番目はヴォルガ川)で、各国で象徴的に扱われています。
中でも、かつてのオーストリア(オーストリア-ハンガリー)帝国の首都として世界史の中でも重要な位置を占めてきたウィーンでは、音楽や絵画のテーマにもなってきました。
 オーストリア帝国の皇帝、フランツ・ヨーゼフ1世
オーストリア帝国の皇帝、フランツ・ヨーゼフ1世
第二次世界大戦後、東ヨーロッパよりも東に位置する永世中立国の首都として、冷戦時代に東西のバランスをうまくとってきたのもウィーンです。
私はオーストリアに住んだことはありませんが、仕事で1週間ほどウィーンに滞在したことがあります。美術史博物館、国立オペラ劇場、楽友協会、あちこちに建てられている音楽家の胸像等、芸術の都であるとともに、郊外には森(ウィーンの森)が広がり、オフタイムを満喫させてくれました。
私がウィーンからの放送を聴いていたのは、それよりも前、高校時代のことです。
【ウィーンの森から】
私が高校生になり、ドイツ語の勉強を始めて2か月くらい経った頃(5月29日、JST)、ドナウ川をテーマにしたヨハン・シュトラウスのワルツ「美しき青きドナウ(An der schönen blauen Donau)」の最初の4小節をインターバルシグナルに使っている放送局に出会いました。ログを振り返っても、受信状態はよくなく、まさにインターバルシグナルが放送局同定の決め手でした。ウィーンからのオーストリア放送(Österreichischer Rundfunk,ORF)です。
受信状態の悪さでたった数分間の受信でしたが、とりあえず受信報告を送りました。
それから1か月ほど経った時(6月30日、JST)、もう少し低い周波数で、なんとかドイツ語→英語→フランス語と続く放送を聴いています。この頃にはドイツ語をいくらかは聴きとれたようです。これも受信報告を送りました。
すると、7月になって、最初のレポートに対する受信証が送られてきたのです。葉書のような厚みはありません。たった6分間の報告によくぞ返信してくれたものです。感謝!
オーストリア放送は隣国スイスのスイス放送ほどには世界的な人気を集めてはいませんでしたが、それでも、ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語で国際放送を行っていました。
私が聴いていたのは主としてアジア向け英語放送ですが、アメリカ向けやアフリカ向けがよく入ることもありました。また、ドイツ語放送の方が時間的には長かったこともあり、ドイツ語放送も聴きました。
放送局から送られてきたレポート用紙は他局のものと比べれば大型で内容を記載する欄もあり便利でした。
周波数やスケジュールが変わると知らせてくれることもありました。
最もよく聴いたのは、(26)ラジオ・プラハで書いたように、1968年におこったチェコ事件の頃です。チェコスロバキアの隣国から送られるオーストリア放送のニュースは「西側」からの一方的な情報しか得られない日本で、より客観的な情報源として貴重でした。
受信証のデザインはかなり長期に上記のものが使われていましたが、いつの頃かコンテンポラリーな絵になりました。相変わらず薄い紙質でした。
【ORFなう】
オーストリアには長い間公共放送(ORF)しかありませんでしたが、21世紀に入ってようやく「民放」が放送界に参入するようになりました。それとともに、ORFは政府によって壊滅的な縮小を強いられ、一応、短波放送はわずかに存在しているものの、ほとんど機能していないようです。
インターネット上ではサイトを持っていて、ニュース、バラエティなどを発信しています。
次回はアジア以外の地域の順番です。またアフリカへ行きましょうか。
私の記録を振り返ると、ヨーロッパ>アジア>アフリカ>オセアニア>北中米カリブ>南米の順に聴いた放送局数が多く、西方優位だったようですし。
SWL、BCL、DXingの過去記事はこちらをご覧ください。
相互リンク⇒アクティブなごやん(ゴートク、ブンデス、HSV:間もなくリーグ戦開幕)
深い森の国から⇒