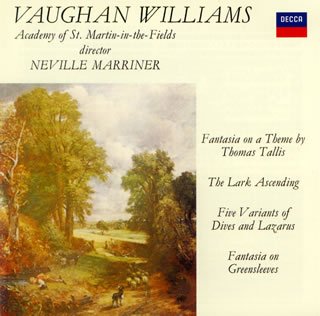仕事帰りに車で相模原市にある某ホールに行ってきた。職場の同僚がコンマスを務めるアマチュア・オケの定期演奏会である。
年に2回の定演をやっている団体だが、これまでは夏の回にしか行ったことがなかった。
演目はモーツァルトの交響曲第40番と、ベートーヴェンの交響曲第2番だった。
常任の指揮者を置いていないオケのようで、毎回違う人を呼んでいる。今回は、フェドセーエフの代行をしたN響研究員の「あの人」だった。たしか、別のアマオケのコンサートでも聴いたことがあるので、私にとっては今回で3回目である。
オケは相変わらずで、ほのぼのとしている。こういう一回きりのオファーに応えるプロの指揮者というのは、本当に大変なんだろうなと推察する。自分の思うままの音楽を造れないばかりか、オケの技量を見定めて、「果たしてどの程度まで仕上げればいいの?」という迷いが始終消えないんじゃないかと思う。
かといって、場数を踏み(キャリアを磨き)、自身の顔を売ることも拒んではいられまい。
ほんとうに、お気の毒様である。
つくづく自分がプロじゃなくてよかった。(なれないけど)
アマチュアの愉しみということをいつも考えさせられる。しかし、今日聴いた団体の活動のスタンスは、絶対に僕には合わないなと思った。
上手く言えないが、どうせやるなら「プロと見紛う」ほどの音楽を造りたい。「やっぱアマチュアだよね」とは絶対に言われたくないんだよな…。
これって欲張りなのかな…。
大学の時に組んでいたバンドのギタリスト君の言葉を僕は絶対に忘れることができない。O君は、こう言った。
「アマチュアでも、プロみたいだねって言われたいじゃん!」
ほんとそれ。
それから、プロのオーケストラ・プレイヤーには正規の「定年」があるが、アマチュアにはない。だから、どう見ても体幹の衰えた御仁が、ご老体に鞭打って弾いていらっしゃる。今日も痛々しかった。
特に管楽器はそれが顕著だと思う。弦楽器も多かれ少なかれ同様なのであろうが、我らが「打楽器」は、あまり体幹には左右されない特殊性があると思う(腕や肩が上がらなくなったらダメだけれど)。
古いアマオケには、おじいちゃんの「首席」がいて、それが生きがいになっている方々だから、絶対に若いやつに席を譲らない。お上手ならそれでも良いのだけれど…。
これはアマチュア・オケの高齢化問題である。
で、決めた。
僕はドラムや打楽器を、ほかの人が不快に思うようにしか演奏できなくなったら、(どんなに自分がやりたくても)その時点で「引退」しようと思う。
そんなことを考えさせられた演奏会だった。
それはともかく、同僚氏、今日はお疲れ様でした!