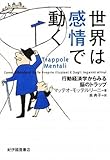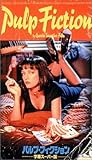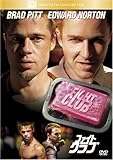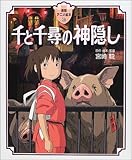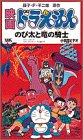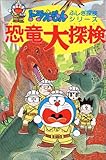生誕80周年記念特別展「手塚治虫展~未来へのメッセージ」

入り口でアトムツアーと名づけられた音声ガイドがあったので、もちろん申し込む。
ナレーションは息子さんの手塚眞さん。
以下、内容で心に残ったことをメモ。
・手塚治虫の生誕は1928年11月3日文化の日。
本名の治は、11月3日が明治節という明治天皇の誕生日が由来。
・スターシステム
宝塚歌劇にヒントを得たシステム。
言葉は聞いたことがあったが、意味は正確には知らなかった。
手塚作品で別の作品に、ひげおやじや、ロックなど顔は同じでも別のキャラクターとして出てくるが、
俳優がギャラをもらい演じているという設定なんだそう。
当時は読者もそれを楽しんでいた模様。
展示に、メモがあったが、キャラクターごとのギャラまで記載してあり、その徹底振りがすごいと思った。個人的にはそれぞれ別の作品名わけなので、別の顔でいいと思うが、人気を出すための仕組みという意味では合点がいく。読んでいても親近感がわく効果もあるかもしれない。(絵柄が違う漫画は読みはじめにパワーがいるので。まあ、他の漫画家でキャラ同士の顔が同じで髪型だけ違うなんてのはざらにあるが。)
・昆虫図鑑
とてつもなく、精密で本物のよう!赤い色がなかったので自分の血を使ったらしい。
・音声ガイドには藤子不二雄Aのインタビューがあった。
新宝島に驚いた話。
そのころ誰も乗っていなかったオープンカーに少年が乗って走り出す、映画のような引きとアップの
コマ割。その後漫画家になったものでは、皆この新宝島に衝撃を受けて漫画家を目指したものが多いとのこと。今の漫画世代がわからないが、当時の読者にはとてつもない体験だったのだろう。
今、漫画や新しいメディアの作品でそういった体験はあるのだろうか?
・新宝島には宮崎駿も影響をうけたそう
展示を出たところの新聞記事の切り抜きで宮崎駿のインタビューがのっていたが、今回の展示にあたり、
コメントを述べている。
・手塚治虫がなくなったとき、宮崎駿は訃報によせるコメントで
「手塚治虫のアニメーションは長屋の義太夫(つまり見れたものではないということ)」を話したそう。
それ以来コメントはなかったそうだが、今回の記事では、影響を認めており、新宝島を読んだときの
体験も語っている。ただ影響を認めながらも、売れるためにヒューマニズムしか書かなかったと批判的なスタンスは崩していない。
宮崎駿は手塚治虫のアニメーションをみて、これなら追い越せると思ったそう。
・仕事机も展示があった。
非常にシンプルな机。120×70ぐらいか。ただ、椅子はしっかりしたつくり。長時間労働だからなー。
・COMという雑誌を創刊。
「まんがエリートのためのまんが専門誌」がキャッチフレーズ
ここからあだち充、大友克洋も世に出たそう。
・開明墨汁エピソード
出張先で墨汁がない!と事件に。担当編集者がやっとの思いで手に入れて戻ったら墨汁の種類が違うと。手塚治虫は開明墨汁しか使わないのだが、それはなかったため、大変なことに。結局荷物の下に隠れていたことがわかったようだが、編集者は手塚治虫に試されていたと当時を振り返るコメント。
試していたとしたら、さすがに人が悪いし、それはないのでは?と思った。
・仕事に対する厳しさ
若手にも厳しかったそう。そりゃそうだろう。
・アニメラマ 世界初の大人のためのアニメーション
第一作は千夜一夜物語
キャラクターデザインは、今では『それいけ! アンパンマン』の作者として知られるやなせ・たかし
虫プロ・アニメラマ DVD-BOX (千夜一夜物語 / クレオパトラ / 哀しみのベラドンナ)

¥15,800
Amazon.co.jp
そんな言葉があったとは知らなかった。
今ではアニメは大人のものになったのだろうか?内容は相当エロチックなようだ。
・実験アニメーション ジャンピング
ジャンプする少女の視点のみですすむアニメ
あらためてあらゆることに挑戦した手塚治虫を実感した。
天才といわれるが、そのバイタリティと貪欲さがないとこれだけの作品は残せない。
しかも質を保ったうえで。
・展示では浦沢直樹の「PLUTO」の直筆原稿も展示
・今後の手塚治虫作品の映画化
・MW
・アトム CG版
正直アトムのほうは、CGの意味がわからない。特殊効果は大きいが、御茶ノ水博士まで表情が希薄になってしまう。
・最後は胃がんで亡くなられた。その死によって『グリンゴ』『ルードウィヒ・B』『ネオ・ファウスト』そして『火の鳥』が未完のまま遺された。
意識がなくなるまで書き続けていたそうで、展示にもまだセリフのみや絵コンテのみのノートが残っていた。
作品への執念を感じる。
胃がんになってから「頼むから仕事をさせてくれ」という言葉が残っている。
本当に仕事の虫だ。すごい。
・水木しげるのコメント
漫画家で集まる際には、必ず石の森章太郎と徹夜自慢をされており、編集者ももてはやした。
だから二人とも早くになくなった。まさに命を削って書いてたんだろうと。
徹夜をしなかったらこれだけの作品は残せなかっただろうけど
完結していない作品は残念。
特に火の鳥。
火の鳥が、過去と未来を順番に書いていき、最後に現代編で終わる構想だったことは
以前、読んだ本で知った。
以前ブログにも法皇編の感想を書いたが、
本当に完結編の現代編を読みたかった。
描かれていたらいったいどんな作品だったろう。
ご冥福をお祈りします。
今日はきてよかった。
まだ読んだことがない手塚治虫作品もまた読んでいきたい。