センセイ、オネガイシマス!
(一回記事が途中で消えたので多少アレになってるかも分からんね)
最終回、ある程度は(予想通りに)纏まっていたけど、やはり色々と問題があるなぁ。
まずは簡単に言える部分から
・ローマ軍は講和を促す示威行動による進軍だった
バッカじゃなかろうか
示威行動で人跡未踏の地を遠征してくる奴とか、頭が悪すぎる。
誕生日のサプライズパーティじゃあるまいし、今まで戦火を交えた国境近辺に大軍結集すればいいだけの話だろうが!
・ローマ軍はきっと戦いたがらないのでヘルベチア軍はローマ軍の捕虜を目の前で銃殺します
バッカじゃなかろうか
こんなやり方で戦端開いても不利になるだけだと思うんだけど………相手につけ込む隙を与えられるだけ。
ローマ側がそれに乗るかも分からない。
大佐クラスの判断でこういう軍紀違反(とまでは世界観的に断言出来ないけど明らかに問題の起きそうな行為)をやったって、大佐が上層部に処分されてヘルベチアが平謝りすれば、より一層不利な講和が持ち上がるだけじゃないかと。何しろ国のトップが既に厭戦気分なんだから。
あと他の国とも国境を接している場合、悪印象を与える上に従来の戦況はローマ軍に有利と推測されるので、たとえ今まで友好的な態度を取っていた国もこれを理由(言い訳)に寝返られる場合がある。
(今回の行動はホプの独断という意見がある模様。個人的には完全な独断と言うよりも状況が固まっていないので自分の望む方向に流しちゃおうという感じがする。ただこの方向性ならば短絡的でも成立はする)
・ローマ軍は夜明けに攻撃開始します
バッッッカじゃなかろうか
ローマも講和を促す示威行動で自分から攻撃してどうすんだよ!
ていうか、こういう展開になるならさっきの大佐の判断イミネージャン!
大佐側は知らなかったとは言え、ピエロだよねまるで。
何故こういう状態になったか脚本家を始めとするスタッフの脳内を推測すると……
大佐は悪い奴でなければならない(だから命令無視しても構わない)
アイシャは可哀想な立場でなければならない、けど死んでしまうと可哀想だし後味が悪いしラッパ如きで止まるのが不自然だから死んではならない
よってアイシャはカナタ達に救われなくてはならない
しかしアイシャが救われると戦争未遂が起きない
結果ローマ軍に勝手に動いて貰わないといけない
という紆余曲折を経たと思われます。
……バッカじゃなかろうか。
・停戦信号では静止しないのにアメイジング・グレイスで静止する兵士たち
バッカじゃなかろうか
この世界の中で一般的に『アメイジング・グレイス』ってのはどういう意味を持つのか全然描かれてないんだけど。
いや先週で観たとおり両軍の兵士(の一部)が同じ曲知ってるってのは理解してるよ。
でも、みんながこの曲にどういう思い入れがあるかを描かないとフィクションだと考慮しても止まる理由にはならんわな。イリア公女が吹いてたという意味でヘルベチア側には思い入れがあってもおかしくはないが、ローマからすれば敵の勝鬨みたいなものとも取れる。
要するにアイシャが知ってた理由は不明なのでそこを書かないといけない。
むしろ明確な理由はフィクションにこそ必要なんだよ。
・帰ってきたリオ
バッカじゃなかろうか
そんな物わかりのいいローマ皇帝なら始めから政略結婚(人質)とか関係なく講和するわ!
示威行動目的のノーマンズランド遠征とか馬鹿な戦略全否定だわ!
ローマ皇帝が物分かり良くて、ヘルベチア大公が怖じ気づいてるのに講和が成立しない不思議な戦争。
両方軍部の一部が熱を上げて元首が掣肘しえないパターンだったのか?
でも大佐以上の人間がそもそも出てこないからなぁ……
※ 他の人と話し合ったところ、リオはイリア亡き今、唯一の継承者である可能性が出てきた。それがローマ皇帝の側室になるというのはヘルベチアにとっては非常に痛いので、ヘルベチア側が渋った可能性はある。ただその場合リオの重要性が増すので皇帝が本国に戻してしまうのはより一層不自然になってしまう。
極端なツッコミはこれくらいにしておこう。
で、黙示録の天使(悪魔)伝承について。
炎の乙女は悪魔を退治したんじゃなくて、懲罰天使を介抱しました。
これは発想としては必ずしも否定しがたい部分がある。
価値観の変動という意味合いではカタルシスを与えられる可能性があるし、テーマとも合致しうる。
問題のまず一つは取って付けたような明かし方をした事。
最後の最後になってから台詞だけで価値転換を迫るのは、理論上はありでも作劇上は浮いて見える。
せめてこれに関する伏線を幾らか入れておくべきだった。
そもそも悪魔については1話・7話の僅かな(ほとんど一瞬と言って良い)描写と11・12話のちょっとでしか語られていない。
よって悪魔の虚像すらロクに知らされていなかったのだから、その読み直しが出てきてもカタルシスを得ようがない。純粋に悪魔としての描写と、この価値転換に繋がり得る(けどそれだけでは誤解してしまう描写)の双方を入れないと、取って付けた感が強くなる。「あの部分はああいうことだったのか!」と思わせるような類でないと、ただの説明になってしまう。
ソラヲトは全体を通じて演出は結構細かく丁寧なのに一番重要なことはみんな台詞で喋ってしまう傾向にあって、それが極端に出た部分と言えるのかもしれない。
もう一つ問題になるのは、悪魔か天使か結局判別しづらいところ。
もちろんこれは物語中で敢えて判然としないように描かれているとは思う。
従来より僕の語ってきたソラヲトのテーマ「価値の読み替え」に関わる部分だからだ。
翼を持ちて人を滅ぼさんとする(虐げんとする)者
は
悪魔かもしれない
でも
神様が人間に罰を与える為に使わした天使かもしれない
これは一神教(ローマ)と多神教(ヘルベチア)の信仰感の違いによるものだ。
多神教では悪神が存在しうるが、基本的に一神教では神以外に「人類を滅ぼす(虐げる)者」は存在し得ない。
理由を簡単に言うと力関係が、神>その他なので、神が人間を守ろうとすれば守れない訳がない。
つまり理由はどうあれ、現実として人類が窮地に立たされているのは神が看過しているか、積極的に滅ぼそうとしているかの二択になる。
実際に『ヨハネの黙示録』などでは(解釈こそ様々だが)天使によって人類に危害が及ぶ様子が描かれている。
つまりこの読み替えを行うと
人類に懲罰を与える為に下された天使は、人類の善意に逢って、善なる者達を許した
(結果他の人も救われた)
というのがローマの炎の乙女伝説となってノアの箱船などに近い物語として成立する。
これは一神教的な伝説であり、実際の所は分からない。
ローマにはこう伝わり、カナタはその価値観を受け入れたというだけだ。
だから判然としないのだが、これは結構重要な部分でもあるのだ。
一神教的な解釈は置いておき、炎の乙女たちは翼ある物を介抱したという事を仮定しよう。
そして金の角笛を用いて他の翼ある物を回避したというのも事実としよう。
異なる生物間の物語として考えてみるのだ。
結果としてコミュニケーションは成立したとされているが、今まで悪魔の一部分しか見せなかったのはやはり問題だと思う。どんな生物か(視聴者には)分からないままに交流している。
恐らく実際の所は宇宙生物かなんかだと思うのだが、それがプレデター系かエイリアン系かで大きな問題が出る。
結果論として翼ある物はプレデター系だったのだが、これはエイリアン系には通じない。
介抱=友和というのはあくまで人類的な発想でしかない。
謎の生物には逆にそれが敵対行動と写るかもしれない。
これもまた価値観の読み替えである。
○○はAかもしれない
でも
Bかもしれない
ソラヲトは基本的にBがAを優先する形で描かれてはいるが、Aを優先させてはいけない理由など何もない。特に異類間の場合には。のほほんとした人間だからBがステキに思えるのであって、他者にとってはその限りではないのだ。
これが「翼ある物」や世界観についてもう少し描かれていれば別だったかもしれないけれども、全然描かれていないので相対的な話が出来てしまう。翼ある物がもう少し元気だったら介抱される間もなく殺されていただろうし、介抱が敵対行為になりうるかもしれない。
これがキチンと成立するのは一神教的解釈だけだ(人類に対する懲罰天使なので、善意を持つ物に害を与えないのは説得力がある)やはり、こういう物をかくのは台詞だけではダメで描写をしないといけない。
でも一神教が肯定出来る明確な描写はない。だからたまたま生物との交流が出来たという事い過ぎない。
だからこの可能性を考えてフォローしなければならないのだが、それはしていない。
また、この伝説を以ていきなり分かり合いや生命尊重の話になってしまっているが、これも戴けない。
もしそういう意味に繋げるとしたら、まず先にカナタ達が(小規模であっても)そういう行動を見せているべきだ。
それは同年齢の偵察兵捕虜を助ける事だけでは表現出来ない。
自らを本当の意味で虐げてくる物に寛容さを見せてこそ成立する。
つまりホプキンス大佐のような人間を早い段階で登場させ、苦労させられたにも関わらず赦し、助けてこそ実際に表現出来る。
僕は一年くらい前にガンダム00の最終回SS
を書いたが、それと同じ。
ただ歌ってもバカバカしいだけだが、憎んでもおかしくない状況で更に虐げられ、傷付きながらも歌を辞めないからこそ心を打てる。
彼女たちは、1121小隊で苦労していない。過去の苦労はほぼ台詞だけで解消される。
もちろん、どういう経緯を辿ろうがラッパ吹いて戦争終わらせるなんてものは絵空事だが、それ自体は構わないと思っている。ただ絵空事だからこそ説得力を持たせなければならない。
それは視聴者が「こんな状態になったら絶対に人を憎むだろう」とか「これは絶対に撃つだろう」という状況で主人公達にそれを否定させることだ。視聴者の実感と登場人物の決断を引き離すことだ(『グラン・トリノ』もそうだったな)
これがキャラクタの凄さを表現することに繋がり、そういう人間がラッパを吹く事で戦争終結なんてあり得ない状況に実感を持たせるのだ。
これをやりきったのが『獣の奏者エリン』だ。
エリンは常に窮地に立たされ、苦悩し、迷う。
そして時には信念どうしが相克し、本人の望まない決断や結果をも強いられる。
それでも獣の事を考え、誠意を尽くしてきたからこそ(物語を汲み取れている人間には)最後の展開に説得力が生じた。
じつのところエリンとソラヲトの終盤は枠組みとして結構似ている。
神話が読み替えられ、両陣営の大部隊が山地に結集し、主人公は超兵器に該当する物でそこへ乗り込む。
だがソラヲトのヒロインたちは概ね日常レベルの苦悩や追い込みしか経ておらず、考えを改めた結果解消出来てしまうようなものだった。フィリシアにしてもその苦悩の根幹は「世界の意味」であり、これも価値観の読み替えによって1話の中である程度解消されてしまう。
話数の問題も当然存在するが、エリンの苦悩は
母の凄惨な死→愛着のある人々(ジョウン)からの別れ→王獣との意志疎通→王獣の怖さ→政治的な動物としての王獣→暴走する王獣と過去の大罪→王獣と人間との断絶→兵器として利用される王獣→王獣を用いて助けられる人間を救うか、母のように見殺しにするか
という幾多もの段階を経ている。
この世界観で無ければ成立しない苦悩であり、また余人(視聴者)には耐えざるものでもあった。
その中でエリンは忌避していた音無笛を吹かざるを得なかったり、兵器として王獣を用いなければならなかったりもした。
その罪を理解しながらも、敢えて選びとった。
だが決して王獣をないがしろにしていた訳ではなく、常に大切に思い続けてきたからこそ最後のシーンがある。それが分かっている人間にはむしろ当然に思えたものだった。
都合の良い作品では、エリンが決定的な決断しなくても上手い具合にいくように作られ、彼女が悪印象を受けるような状況は自然と回避されるだろう。
だが上橋菜穂子はそれを許さなかった。
いや、それでこそ表現出来る物があると知っていたのだ。
エリンにとって最も主軸は「人と獣」であり、内乱が小規模に留まったのはいわば傍論ではある。
けれどもシュナンが語っているとおり、人よりもより意志疎通の困難な王獣に対し常に誠意を持って接し続けてきたからこそ分かち合えたものがあり、それは人同士の和解に通じるのだ。
これを取っ払って部活動のような生活をしてきた者達が戦争を止めてしまったのがソラヲトであり、その薄弱さは逆に此処で描かれる戦争行為そのものを貶めているとすら言える。
苦労していない人間が(恐らく彼女たちよりも)苦労して従軍してきた人間に個人的な意見で停戦を勧告するというのは何ともはや。
一応ながらカナタが停戦信号を聞いているという展開が僅かに救いではあるものの、やはり結局は個人の意志によっている。
命令があっても個人が武器を捨てれば戦争は起きない、それはそうかもしれない。
だが逆に言えば命令が無くても個人が武器を取ったことで戦争が起きうるという意味にもなる。
厭戦気分確かに存在するかもしれない。けれど簡単に昂揚してしまうのも人間だ。
個人の感情で命令を無視すると言う事は、個人の感情でルールを破れるということ。
兵士が命令に従わず発砲しないのを是とするなら、兵士が命令も無しに民間人に発砲するのも是としうる。
ルールを破るというのはそういうことだ。
結果論として炎の乙女たちは、傷付いた天使を介抱することで他の天使を退けたとされているが、この現象が全世界に渡るものとは限らない。
つまりセーズ以外の場所は結局破壊されている恐れすらある。善意が善意で返されるとは限らない。
物語に置いては「善意が善意で報われる」という結論に辿り着いても全然構わない……どころかそういう話は好きなのだが、対立的な視点すら省かれてしまっている。
カナタは「この世界を、町を守りたい」と言うが、炎の乙女たちの行為が他の生命を危機に陥れる可能性があったのと同様に、タケミカヅチでの暴走は逆に敵を刺激させてしまうかもしれない可能性を孕んでいることは考慮の外だ。その考え自体が彼女たちには無いのだ。分かっていてやるなら良い。それは覚悟だからだ。だがこれが良いことで良い結果のみを考えていたとしたら甘過ぎる。
この危うさは紙一重なのだが、ソラヲトでは綺麗な片側のみを描いた。
それは
誰かが世界は終わりだと言っていました、でも私達は楽しく暮らしています
と語りながらも、
世界の終わりを描かずに楽しい生活に焦点を当てていた
この作品にはお似合いの結末だったかもしれない。
おまけ
別に自分最終回をやってもいいのだが、そこまで大した設定も無く情熱も湧かないのでやりません。
でも一つ面白そうな解釈をしようじゃないか。
エリンとソラヲトは似てる。
……「翼ある物」って王獣じゃね?
王獣が進化して知能を発達させて火力強化=翼ある物
炎の乙女たち=エリンさんみたいな人
王獣が住処おわれたとかで切れて人類に逆襲
その内傷付いた一匹をエリンさんみたいな人達が介抱
王獣はお礼に進化版音無笛である「金の角笛(硬直だけでなく意志疎通が出来る)」をくれた
他の王獣が攻めてくる
金の角笛ブォー
王獣帰る
これじゃね?
ここ
を見る限り、ラストエピソードに関する予言は外れたっぽいですね。
今まではそれなりに当たっていたと思うので、忸怩たる思いもあります。
ただし、このパターンだと最初の記事に記した
この予想が外れた場合、ギミックやガジェットは出てくるのにそれを充分に生かせない可能性も増加し、「結局何がやりたいのかサッパリだったね」というような結論になる恐れがあります。
これは何も僕の思い通りに行かないからダメ、というのではなくて砦の状況や小道具&大道具を登場させても物語に絡ませないという行為が創作上如何なものかな……と思うからです。
(中略)
例えば戦車を出しても戦車を使わなければならないような展開が発生しない場合は予想の範籌外です。
しかしそれは逆に「何故戦車を出したの?」という疑問が解消されない為に、お話としては違和感を残す結果になるのです。
これに近くなってしまうような方向かなと、むしろ落胆する気持ちが大きい。
戦車は一応活用されるだろうけど、足というレベルに留まってしまうんじゃないか。
こうなると悪魔は出さない可能性が高い。
で、このあらすじを踏まえて考えてみると……
敵兵発見→救出手当→情報聞き出し→匿ったのが発覚
→国家反逆罪容疑→タケミカヅチで脱出
→ノーマンズランドから両軍展開中の国境へ
→ラッパで休戦呼び掛け→和む→士官激怒→拘束or大ピンチ
→戦車が近付いてくる
→「ひかえおろー!ひかえおろー! ここにおわすをどなたと心得る! 畏れ多くも大公様のご息女にして、この度正統ローマにお嫁ぎあそばされる、リオ・アルカディア公女殿下にあらせられるぞ!!!」
→(士官)へへー
→リオ「こやつらは無罪!」→やったー→END
こんな感じかな。
地理関係が一部しか分からないのでなんとも言えない所もあるけど。
リオが無罪判定で出てくるのは、結構確実に思える。じゃないといなくなった意味がない。
少なくとも、悪魔関連が放置されることは明白のように思われ(戦争関係になると)、今まで匂わせてきた事は一体何だったのかという話にもなってしまう。
あの世界観の中での特殊な設定をなんら生かすことが無いということは、要は作品の独創性自体を薄っぺらくしてしまうもので、釣り針以上の意味が失われるし、その分使った尺も勿体ない。
或いは二期を狙っていたのかもしれないが、あまり期待しない方が良いとは思う。
あと吉野さんはインタビューに「あれは最初から書かないつもりだったんです」みたいな事を言うだろうな。
ともあれ、こういう形になるから
「この作品は何がしたいのかがよく分からない」
と言われてしまう結果になる。
ただ、僕の意見はちょっと違う。
「表現したいものはあるだろうけど描き方が下手」
だ。下手というのも印象論だが、分かり難いというかしっかり対比させないというか。
恐らくではあるが、この作品に通底している物は
「Aかもしれない。でも、人によってはBかもしれない」
というものだと推察できる。Aは基本的に現実や客観、Bは主観や理想を示す物だとかんがえて戴きたい。
これは以前のエントリ でも記したのだけれども、
「誰かが、世界はもう終わりだと言っていました でも私たちは楽しく暮らしています」
「世界は幸せばかりではない──楽しいことばかりでもない──どちらかといえば、暗く、貧しい世界なのかもしれない。でもその在り方は自分ひとつ。綺麗なものも、汚いものも、辛いことも、楽しいことも、受け止めるのは、キミ次第なんだから──」
これが公式のトップ並びにイントロダクションに記されている言葉。
代入すると
A=世界は終わり
かもしれない
でも
人によっては
B=私達は楽しく暮らしています=楽しみを見出せる
かもしれない
後者も同じで
A=暗く貧しい世界
かもしれない
でも
B=受け止めるのはキミ次第=綺麗さを感じられる
かもしれない
こう書くことが出来る。
実のところ、本編のドラマ部分もかなりの割合でそれを想起させる物が組み込まれている。
明確に出てくるのは主に後半だが、視聴者との関係性(メタ的視点)まで考えると、相当多い。
1話は紹介回だから置いておくとして(見直せばあるかも)
2話
A=幽霊は怖い
かもしれない
でも
B=自分のご先祖様だから怖くない
かもしれない
A=幽霊の正体はミミズクだった
かもしれない
でも
B=本当に居た
かもしれない
3話
A=カナタは脳天気
B=劣等感を抱えている
A=リオはしっかりもの
B=慌てん坊
4話
A=タケミカヅチは人殺しの兵器
B=使う人次第・音楽が出るからきっと良い戦車
5話
A=山登りは大変
B=楽しい発見がいっぱいある
6話
A=酒を売るマフィア(フィリシア達)は怖い
B=演技
7話
A=この世に意味はない
B=自分で意味を見いだせる
8話
A=緊急事態
B=おもらし(が本人にとっての緊急事態)
9話
A=英雄じゃない・理想の先輩ではない
B=素敵な人
10話
A=女は男に捨てられた
B=幸せだった
8話などはやや強引だとも思うが(笑)特に後半はそういったテーマが中心になっているのが理解して頂けるかと思う。特に序盤、Bの概念を担うのはカナタである場合が多い。
幽霊は怖くないと言い、タケミカヅチは良い戦車と語り、山登りでも常に楽しみを見出し、マフィアに扮するアイデアを出す。
後半(7話以降)でカナタ自身の見出しが少なくなっていくのは、カナタの性質が伝播していった為だろう。
しかしながら、この全体的な傾向に触れる人はあまり居ない。
というか、見たことがない(一話ごとの感想で触れている人は居た)
最も皮肉なのは、この作品を大変に称賛し、「分かり難い」との批判に対して怒っている人ですら気付いている様子がないことだ。
それだけ見出しにくいのだろう。
本来、こういったテーマ性というのは極端であればあるほど明確化され、突き詰めれば詰めるほど深みを増す。
けれどもソラノヲトは、こういった部分を殆ど日常レベルで完結させてしまう為に明確化がされにくく、尚かつ世界観に繋がることもない。
カナタ・劣等感
クレハ・親の不在
ノエル・機械の用いられ方(不確定)
リオ・姉の死と父親との確執
フィリシア・世界の意味
登場人物に於ける悩みの内、終末論の如き世界観に関わる根本的なテーマ(であろうと思われるもの)に必然的に結びつくのはフィリシアだけだったりする。一応ながらノエルも該当する可能性があるのだが、未だ悩みの根幹が明確に描かれていないので判断しづらい。
またノエルにしても人殺し・兵器運用というレベルの問題であって世界の絶望と自らが見出す希望というレベルからは遠いと思われる。
他の三人については言わずもがな。カナタは日常レベルの悩みだし、クレハやリオも戦争こそ絡んでくるけれども、結局の所は肉親の不在や肉親との不和であり、そう特殊な物ではない。
つまり
「誰かが、世界はもう終わりだと言っていました でも私たちは楽しく暮らしています」
この世界の特殊性と相対する心理が、描かれていない。
世界の終わりを実感させないで描かれる「楽しい暮らし」は、
我々の世界に於ける楽しい暮らしと区別が付かない。
イリア公女の死因も取って付けたような水死だった。
これはリオの子供嫌いという設定にこそ繋がるが、その先がない。
それによってリオは何を思ったか、どう人格に変容をもたらしたかに関わらない。
例えばこの事故がリオを起因とする物だったら、リオは後ろめたさや悔いを持つことになり、セーズへ赴任した理由もより明確化出来る。子供を嫌うのも「自己の投影」という一面を持つ。
暗殺だったならば、政治という物に対する怨嗟やそれを防げなかった父親への怒りがいや増す。
しかし普通の事故死として処理されてしまっては、「子供嫌い」で終わる。
ソラノヲトの困ったところは、こういう部分ではなかろうか。
細かくネタを仕込んだり、伏線を長く引っ張る割には、結果がありきたり……というか着地点が今ひとつドラマ性に欠ける。もっと広く深いレベルで捉えられるテーマを、日常生活で完結させてしまう。
悪魔関連の設定にもその余波が感じられる(悪魔が出ても誉められた作品になったかどうかは疑問だが)
果たしてこういうレベルで延々と展開してきた話が、戦争終結(再開阻止)という広い物語に拡大した時に、説得力が出るだろうか。
正直、僕にはやや疑わしい。
【追記】
第十一話にてノーマンズランドから敵の軍隊が侵入……それ一番アウトなパターン……。
思いっ切り気取られているから(ノーマンズランドを越境する唯一の利点である)奇襲の意味がない。
たとえセーズを占領しても戦略的に何の意味も無い。
そして大軍だから補給線が伸び伸び。
しかもまだ講話中なのに。
と言う訳で、どんどこ墓穴を掘ってる感じです。
コレ考えた奴(作中の作戦含め)は絶対バカだな。
もちろん長征で困難な道を越えて勝利した例もあるにはあるのですが、今回の場合
・奇襲になってない
・攻め込む先が僻地で上手くいっても勝利は局地的な物に留まる、むしろ撃滅される可能性の方が高い。
・ノーマンズランドはかなり広汎な地域なので補給路がとっても長くなる(ノーマンズランドに基地を作ってあるかもしれないが、そこに対するエクスキューズが示されていない以上、そもそも考えていない可能性が高い)
・しかも冬(雪中行軍は他の場合よりも遙かに装備や補給が重要・これも考えてないと思う)
自分達の作る設定と話を、もっとよく考えてくれよ頼むから。
悪魔も思わせぶりだけど絶対詳細判明出来ないだろうからな~。
二期をやるつもり(だった)んだろう多分。
今まではそれなりに当たっていたと思うので、忸怩たる思いもあります。
ただし、このパターンだと最初の記事に記した
この予想が外れた場合、ギミックやガジェットは出てくるのにそれを充分に生かせない可能性も増加し、「結局何がやりたいのかサッパリだったね」というような結論になる恐れがあります。
これは何も僕の思い通りに行かないからダメ、というのではなくて砦の状況や小道具&大道具を登場させても物語に絡ませないという行為が創作上如何なものかな……と思うからです。
(中略)
例えば戦車を出しても戦車を使わなければならないような展開が発生しない場合は予想の範籌外です。
しかしそれは逆に「何故戦車を出したの?」という疑問が解消されない為に、お話としては違和感を残す結果になるのです。
これに近くなってしまうような方向かなと、むしろ落胆する気持ちが大きい。
戦車は一応活用されるだろうけど、足というレベルに留まってしまうんじゃないか。
こうなると悪魔は出さない可能性が高い。
で、このあらすじを踏まえて考えてみると……
敵兵発見→救出手当→情報聞き出し→匿ったのが発覚
→国家反逆罪容疑→タケミカヅチで脱出
→ノーマンズランドから両軍展開中の国境へ
→ラッパで休戦呼び掛け→和む→士官激怒→拘束or大ピンチ
→戦車が近付いてくる
→「ひかえおろー!ひかえおろー! ここにおわすをどなたと心得る! 畏れ多くも大公様のご息女にして、この度正統ローマにお嫁ぎあそばされる、リオ・アルカディア公女殿下にあらせられるぞ!!!」
→(士官)へへー
→リオ「こやつらは無罪!」→やったー→END
こんな感じかな。
地理関係が一部しか分からないのでなんとも言えない所もあるけど。
リオが無罪判定で出てくるのは、結構確実に思える。じゃないといなくなった意味がない。
少なくとも、悪魔関連が放置されることは明白のように思われ(戦争関係になると)、今まで匂わせてきた事は一体何だったのかという話にもなってしまう。
あの世界観の中での特殊な設定をなんら生かすことが無いということは、要は作品の独創性自体を薄っぺらくしてしまうもので、釣り針以上の意味が失われるし、その分使った尺も勿体ない。
或いは二期を狙っていたのかもしれないが、あまり期待しない方が良いとは思う。
あと吉野さんはインタビューに「あれは最初から書かないつもりだったんです」みたいな事を言うだろうな。
ともあれ、こういう形になるから
「この作品は何がしたいのかがよく分からない」
と言われてしまう結果になる。
ただ、僕の意見はちょっと違う。
「表現したいものはあるだろうけど描き方が下手」
だ。下手というのも印象論だが、分かり難いというかしっかり対比させないというか。
恐らくではあるが、この作品に通底している物は
「Aかもしれない。でも、人によってはBかもしれない」
というものだと推察できる。Aは基本的に現実や客観、Bは主観や理想を示す物だとかんがえて戴きたい。
これは以前のエントリ でも記したのだけれども、
「誰かが、世界はもう終わりだと言っていました でも私たちは楽しく暮らしています」
「世界は幸せばかりではない──楽しいことばかりでもない──どちらかといえば、暗く、貧しい世界なのかもしれない。でもその在り方は自分ひとつ。綺麗なものも、汚いものも、辛いことも、楽しいことも、受け止めるのは、キミ次第なんだから──」
これが公式のトップ並びにイントロダクションに記されている言葉。
代入すると
A=世界は終わり
かもしれない
でも
人によっては
B=私達は楽しく暮らしています=楽しみを見出せる
かもしれない
後者も同じで
A=暗く貧しい世界
かもしれない
でも
B=受け止めるのはキミ次第=綺麗さを感じられる
かもしれない
こう書くことが出来る。
実のところ、本編のドラマ部分もかなりの割合でそれを想起させる物が組み込まれている。
明確に出てくるのは主に後半だが、視聴者との関係性(メタ的視点)まで考えると、相当多い。
1話は紹介回だから置いておくとして(見直せばあるかも)
2話
A=幽霊は怖い
かもしれない
でも
B=自分のご先祖様だから怖くない
かもしれない
A=幽霊の正体はミミズクだった
かもしれない
でも
B=本当に居た
かもしれない
3話
A=カナタは脳天気
B=劣等感を抱えている
A=リオはしっかりもの
B=慌てん坊
4話
A=タケミカヅチは人殺しの兵器
B=使う人次第・音楽が出るからきっと良い戦車
5話
A=山登りは大変
B=楽しい発見がいっぱいある
6話
A=酒を売るマフィア(フィリシア達)は怖い
B=演技
7話
A=この世に意味はない
B=自分で意味を見いだせる
8話
A=緊急事態
B=おもらし(が本人にとっての緊急事態)
9話
A=英雄じゃない・理想の先輩ではない
B=素敵な人
10話
A=女は男に捨てられた
B=幸せだった
8話などはやや強引だとも思うが(笑)特に後半はそういったテーマが中心になっているのが理解して頂けるかと思う。特に序盤、Bの概念を担うのはカナタである場合が多い。
幽霊は怖くないと言い、タケミカヅチは良い戦車と語り、山登りでも常に楽しみを見出し、マフィアに扮するアイデアを出す。
後半(7話以降)でカナタ自身の見出しが少なくなっていくのは、カナタの性質が伝播していった為だろう。
しかしながら、この全体的な傾向に触れる人はあまり居ない。
というか、見たことがない(一話ごとの感想で触れている人は居た)
最も皮肉なのは、この作品を大変に称賛し、「分かり難い」との批判に対して怒っている人ですら気付いている様子がないことだ。
それだけ見出しにくいのだろう。
本来、こういったテーマ性というのは極端であればあるほど明確化され、突き詰めれば詰めるほど深みを増す。
けれどもソラノヲトは、こういった部分を殆ど日常レベルで完結させてしまう為に明確化がされにくく、尚かつ世界観に繋がることもない。
カナタ・劣等感
クレハ・親の不在
ノエル・機械の用いられ方(不確定)
リオ・姉の死と父親との確執
フィリシア・世界の意味
登場人物に於ける悩みの内、終末論の如き世界観に関わる根本的なテーマ(であろうと思われるもの)に必然的に結びつくのはフィリシアだけだったりする。一応ながらノエルも該当する可能性があるのだが、未だ悩みの根幹が明確に描かれていないので判断しづらい。
またノエルにしても人殺し・兵器運用というレベルの問題であって世界の絶望と自らが見出す希望というレベルからは遠いと思われる。
他の三人については言わずもがな。カナタは日常レベルの悩みだし、クレハやリオも戦争こそ絡んでくるけれども、結局の所は肉親の不在や肉親との不和であり、そう特殊な物ではない。
つまり
「誰かが、世界はもう終わりだと言っていました でも私たちは楽しく暮らしています」
この世界の特殊性と相対する心理が、描かれていない。
世界の終わりを実感させないで描かれる「楽しい暮らし」は、
我々の世界に於ける楽しい暮らしと区別が付かない。
イリア公女の死因も取って付けたような水死だった。
これはリオの子供嫌いという設定にこそ繋がるが、その先がない。
それによってリオは何を思ったか、どう人格に変容をもたらしたかに関わらない。
例えばこの事故がリオを起因とする物だったら、リオは後ろめたさや悔いを持つことになり、セーズへ赴任した理由もより明確化出来る。子供を嫌うのも「自己の投影」という一面を持つ。
暗殺だったならば、政治という物に対する怨嗟やそれを防げなかった父親への怒りがいや増す。
しかし普通の事故死として処理されてしまっては、「子供嫌い」で終わる。
ソラノヲトの困ったところは、こういう部分ではなかろうか。
細かくネタを仕込んだり、伏線を長く引っ張る割には、結果がありきたり……というか着地点が今ひとつドラマ性に欠ける。もっと広く深いレベルで捉えられるテーマを、日常生活で完結させてしまう。
悪魔関連の設定にもその余波が感じられる(悪魔が出ても誉められた作品になったかどうかは疑問だが)
果たしてこういうレベルで延々と展開してきた話が、戦争終結(再開阻止)という広い物語に拡大した時に、説得力が出るだろうか。
正直、僕にはやや疑わしい。
【追記】
第十一話にてノーマンズランドから敵の軍隊が侵入……それ一番アウトなパターン……。
思いっ切り気取られているから(ノーマンズランドを越境する唯一の利点である)奇襲の意味がない。
たとえセーズを占領しても戦略的に何の意味も無い。
そして大軍だから補給線が伸び伸び。
しかもまだ講話中なのに。
と言う訳で、どんどこ墓穴を掘ってる感じです。
コレ考えた奴(作中の作戦含め)は絶対バカだな。
もちろん長征で困難な道を越えて勝利した例もあるにはあるのですが、今回の場合
・奇襲になってない
・攻め込む先が僻地で上手くいっても勝利は局地的な物に留まる、むしろ撃滅される可能性の方が高い。
・ノーマンズランドはかなり広汎な地域なので補給路がとっても長くなる(ノーマンズランドに基地を作ってあるかもしれないが、そこに対するエクスキューズが示されていない以上、そもそも考えていない可能性が高い)
・しかも冬(雪中行軍は他の場合よりも遙かに装備や補給が重要・これも考えてないと思う)
自分達の作る設定と話を、もっとよく考えてくれよ頼むから。
悪魔も思わせぶりだけど絶対詳細判明出来ないだろうからな~。
二期をやるつもり(だった)んだろう多分。
スポーツ・ナショナリズム上等!
先日、バンクーバー冬季オリンピックが終了した。正直僕はあまり感心をそそられなかったものの、競技とあまり関係ないところでの選手叩き、金メダル無し、八百長論争とお世辞にもカッコイイとは言えないものだったと思う。
ただ、スポーツに於けるナショナリズム自体は必ずしも嫌いではない。それは自分の所属する国家への誇りでもあるし、いかに人倫を語ったって自国が他国を超克するのは少なからず心が躍るのが人の心ってもんだろう。
だから今回の騒動もあった訳だが。
これらは対外的なナショナリズムと言えると思うが、外的な物があれば内的なナショナリズムもまた存在する。
それを十二分に表現したのが本作『インビクタス』だ。
南アフリカ初の黒人大統領ネルソン・マンデラは民族融和政策の一環として、白人主義の象徴であり、名前やユニフォームを変えられようとしていたラグビーチーム・「スプリングボクス」の存続を敢えて願い出る。
南アに於いてはラグビーは白人富裕層のスポーツ、サッカーは黒人貧困層のスポーツである。
黒人政権でありながらラグビーを称揚することで、民族融和を図る狙いがそこにはあった。
スプリングボクスには黒人地区へ尋ねてラグビー教室を開くようにさせ、初開催となるW杯で優勝させようと言うのだ。
スポーツ物でもあるが、スポーツを通した国民の連帯感、と国家の変貌、更には人の精神の崇高さをも描いていく。
イーストウッドにしてはやや王道というか、スタンダードすぎる気もするが熟練の技術はむしろ王道とは相性が良いと言えるかもしれない。
また近年のイーストウッド映画に於ける根底の精神は全く変わっていない。
スポーツで国民意識の統一と聞くと、現代日本のひねくれ者には忌避する部分があるかもしれない。
しかしこの統一は日本人が散発的なブームに乗って騒ぐだけの行為とは全く異なると言って良いと思う。
それは長らく続いた白人・黒人の壁を打ち破り、
互いが互いを認め合うことだ。
怨嗟の声を閉ざし、歓声を挙げながら抱き合うことだ。
寛大な精神で赦し合うことだ。
『ミスティック・リバー』で復讐の危うさを描き、『グラン・トリノ』で復讐による暴力を捨てたイーストウッドの精神はまさに此処にある。
マンデラは政府の役人を続投させ、スプリングボクスを存続させ、まず身を以てその精神を示した。
30年余りも投獄された苦しみを、
虐げられた怨みを、
差別による悲しみを、
当の相手にすら負わせようとしなかった。
それが故にスランプに喘いでいたスプリングボクスも、また変わることが出来たのだ。
奇しくも同日に観た『戦場でワルツを』は、
マンデラに、スプリングボクスになれなかった者達の悲劇だ。
もちろん怨みを忘れられないのは人間として当然の感情である、しかしそれだからこそ苦しみを相手に返すことしか出来ずに、結局は自らも苦しむのだろう。
理屈では子供すら分かっているけれども、本当の意味で実行するのは難しい。
追記
調べていると、イスラエルの政策について実質的にアパルトヘイトとしているものが幾つかあった。
アパルトヘイト・ウォールなるものもあるようだ。アパルトヘイトを脱却しようとする国家の映画と、アパルトヘイトに落ち込んでいく国家の映画としても好対照(もしくは『悪』対照)というべきかもしれない。
固い話はこれくらいにしておいて、小ネタ的なみどころを。
マンデラかわいいよマンデラ。SPの好みを聞いて飴を買ってきてくれるマンデラ萌え。
ラグビー日本が弱すぎて申し訳なくなった。NZに145点も取られたそうだ(国際試合史上最高得点)
ちなみにパンフレットには当時の日本代表選手の寄稿が……
もうやめて!
日本のライフは零よ!!!
その人に「マンデラとスプリングボクスのリーダーシップのあり方」を尋ねるとかイジメにしか思えません。
ロムー様 がメッチャ前振りされていたのに決勝じゃ得点出来なくてワロタwwwww
まぁ試合展開まで忠実に作って、南アが超頑張ったという事なんですけどね。
得点するのが双方キッカーのみ(しかも半分くらいペナルティキック)というコメントに困る試合でした。
最後、優勝決定の時に黒人の子供と白人警官が喜び合うシーンがあるのだけれど、
黒人の子供の動きがサルっぽくてすっごい面白い。
当時のスプリングボクス主将・フランソワ・ピナールと、それを演じたマット・デイモンが一緒に写ってる写真があるのだけれども、似すぎてて親子にしか見えない。

先日、バンクーバー冬季オリンピックが終了した。正直僕はあまり感心をそそられなかったものの、競技とあまり関係ないところでの選手叩き、金メダル無し、八百長論争とお世辞にもカッコイイとは言えないものだったと思う。
ただ、スポーツに於けるナショナリズム自体は必ずしも嫌いではない。それは自分の所属する国家への誇りでもあるし、いかに人倫を語ったって自国が他国を超克するのは少なからず心が躍るのが人の心ってもんだろう。
だから今回の騒動もあった訳だが。
これらは対外的なナショナリズムと言えると思うが、外的な物があれば内的なナショナリズムもまた存在する。
それを十二分に表現したのが本作『インビクタス』だ。
南アフリカ初の黒人大統領ネルソン・マンデラは民族融和政策の一環として、白人主義の象徴であり、名前やユニフォームを変えられようとしていたラグビーチーム・「スプリングボクス」の存続を敢えて願い出る。
南アに於いてはラグビーは白人富裕層のスポーツ、サッカーは黒人貧困層のスポーツである。
黒人政権でありながらラグビーを称揚することで、民族融和を図る狙いがそこにはあった。
スプリングボクスには黒人地区へ尋ねてラグビー教室を開くようにさせ、初開催となるW杯で優勝させようと言うのだ。
スポーツ物でもあるが、スポーツを通した国民の連帯感、と国家の変貌、更には人の精神の崇高さをも描いていく。
イーストウッドにしてはやや王道というか、スタンダードすぎる気もするが熟練の技術はむしろ王道とは相性が良いと言えるかもしれない。
また近年のイーストウッド映画に於ける根底の精神は全く変わっていない。
スポーツで国民意識の統一と聞くと、現代日本のひねくれ者には忌避する部分があるかもしれない。
しかしこの統一は日本人が散発的なブームに乗って騒ぐだけの行為とは全く異なると言って良いと思う。
それは長らく続いた白人・黒人の壁を打ち破り、
互いが互いを認め合うことだ。
怨嗟の声を閉ざし、歓声を挙げながら抱き合うことだ。
寛大な精神で赦し合うことだ。
『ミスティック・リバー』で復讐の危うさを描き、『グラン・トリノ』で復讐による暴力を捨てたイーストウッドの精神はまさに此処にある。
マンデラは政府の役人を続投させ、スプリングボクスを存続させ、まず身を以てその精神を示した。
30年余りも投獄された苦しみを、
虐げられた怨みを、
差別による悲しみを、
当の相手にすら負わせようとしなかった。
それが故にスランプに喘いでいたスプリングボクスも、また変わることが出来たのだ。
奇しくも同日に観た『戦場でワルツを』は、
マンデラに、スプリングボクスになれなかった者達の悲劇だ。
もちろん怨みを忘れられないのは人間として当然の感情である、しかしそれだからこそ苦しみを相手に返すことしか出来ずに、結局は自らも苦しむのだろう。
理屈では子供すら分かっているけれども、本当の意味で実行するのは難しい。
追記
調べていると、イスラエルの政策について実質的にアパルトヘイトとしているものが幾つかあった。
アパルトヘイト・ウォールなるものもあるようだ。アパルトヘイトを脱却しようとする国家の映画と、アパルトヘイトに落ち込んでいく国家の映画としても好対照(もしくは『悪』対照)というべきかもしれない。
固い話はこれくらいにしておいて、小ネタ的なみどころを。
マンデラかわいいよマンデラ。SPの好みを聞いて飴を買ってきてくれるマンデラ萌え。
ラグビー日本が弱すぎて申し訳なくなった。NZに145点も取られたそうだ(国際試合史上最高得点)
ちなみにパンフレットには当時の日本代表選手の寄稿が……
もうやめて!
日本のライフは零よ!!!
その人に「マンデラとスプリングボクスのリーダーシップのあり方」を尋ねるとかイジメにしか思えません。
ロムー様 がメッチャ前振りされていたのに決勝じゃ得点出来なくてワロタwwwww
まぁ試合展開まで忠実に作って、南アが超頑張ったという事なんですけどね。
得点するのが双方キッカーのみ(しかも半分くらいペナルティキック)というコメントに困る試合でした。
最後、優勝決定の時に黒人の子供と白人警官が喜び合うシーンがあるのだけれど、
黒人の子供の動きがサルっぽくてすっごい面白い。
当時のスプリングボクス主将・フランソワ・ピナールと、それを演じたマット・デイモンが一緒に写ってる写真があるのだけれども、似すぎてて親子にしか見えない。

これが戦争だ!
これが軍隊だ!
これが戦場だ!
と、某ソラ○ヲトに突きつけてあげたくなる作品でした。
軍隊物ってやっぱある種の昂揚感とか、無常観が出てこないとやる意味が無くなっちゃうと思うんだね。
あらすじ
本作の監督はレバノン侵攻に参加していたにも関わらずその記憶が欠落していることに気付く。
と、同時に奇妙なフラッシュバックに襲われる。
それは現実なのか幻想なのか、それを探る為に戦友や戦争関係者に取材して回る。
事件背景はこちらを参照 すると良いかも。
僕もそんなに分からないから、難しいと感じても気にすること無いぜ!
アニメだけれどもドキュメンタリーという、かなり珍しいんじゃないかという手法。
何故こうやったかは諸説あると思うんだけど、僕の考えるのは
「現実と幻想の境界を曖昧にしておく為」
なんじゃないかという気がする。
ストーリーを見ても分かるが、この作品は「欠落した記憶と、ある光景の真偽を追い求める話」だ。
そしてファーストショットは26匹の犬が疾走するシーンから始まる。
それは集落を襲撃する際に、26匹の犬を撃ち殺した戦友の夢で、彼に復讐を果たそうと集まってきたのだ。
しかし夢の下りが終わっても、アニメであることは変わらない。
そして主人公の見るフラッシュバックも、実際のインタビューも、全てアニメで描かれる。
他の知人も、戦争時に見た夢の光景を語る。
他にも戦争時のエピソードや、戦争カメラマンの話などが出てくるが、必ずしも主人公の記憶の欠落と直接的に関わる話とは限らない。
これらの話はとても興味深く、ハイキング気分で戦車に乗ってお菓子を食べ、歌いながら意気揚々と進軍していたらいきなり狙撃・襲撃されて、味方もさっさとトンズラこいて、命からがら逃げ延びたとか、カメラをを通している間は冷静に観れていたけどカメラが壊れてた後に競馬場の馬が酷い有様なのを見て現実感を取り戻してしまったりとか、面白い話に事欠かないのだが、それは本筋じゃないのだ。
一方記憶が戻ってくる部分もあるのだが、それもまた衝撃的なエピソードもありつつ幻想性というか、取り留めの無さが残っている。
RPGを抱えた子供との戦闘シーンでは、BGMはむしろクラシックで、神秘的な雰囲気すらある。
夢も現実も、残酷であるにもかかわらず何処かシュールで冗談のような空気感に支配されているように見える。
だがラストシーンでそれは一変する。
そこで出てくるのは、圧倒的な現実。
イスラエル軍とファランヘ党による行動の結果だ。
血流溢れる桃源郷を彷徨っていた僕らは、そこで一気にこれがリアルであることを認識する。
恐らくは、その為の表現手法だったのではないか……と思うところだ。
戦争は本来忌避されるべき物だが、同時に間違いなく人に昂揚感をもたらせる一面が存在する。
他者を蹂躙し、自らの力を誇る。
もちろん相対的な物に過ぎないが、それが出来うる状況であり、また価値観がそう設定されている。
だから戦闘で兵士が機関銃のワルツを踊り、イスラエル軍とファランヘ党員がバシールとワルツを踊る事は彼らにとってはさほど不自然ではなかったのかもしれない。
本事件の確信になるサブラ・シャティーラの虐殺 に於いてイスラエル軍は虐殺に直接的な関与をしていなかったようである。
しかし主人公(語り手)である監督もまた、直接関与はしていない。
ファランヘの民兵が動きやすいように照明弾を打ち上げていただけだった。
にも関わらず、事件の記憶を無くしている。
それは彼の両親がアウシュビッツに捕らわれており、そのイメージと重なった為に虐殺の記憶を消してしまったのだろうとセラピストは推測する。彼は傍観者だったが、その時は実行者と同じ罪を感じただけで、気に病むことはないと。
だが、果たしてそうだろうか?
迫害され虐殺されたユダヤの民が、時と場所を移して、今度は迫害や虐殺を下す側についている。
まるで自分を撃った人間に群がるあの犬たちのように。
それだけではない。
イスラエル軍は直接的に手こそ下さなかったが、難民を塞き止めてファランヘ党の虐殺をお膳立てした。
まるで復讐という病に蝕まれた狂犬をけしかけるように。
最後のシーンは、その結果を、事実を我々に見せつける。
本作は去年のアカデミー賞外国語映画部門でノミネートされ、『おくりびと』に競り負けた。
確かに僕はエンターテイメントとしてどちらを観るか、また他人にどちらを観た方が良いかと言われれば『おくりびと』を勧めるだろう。
しかし、一生涯でこの2作品のどちらかだけを観なければならず、もう片方には目を通すことが出来ないとしたら、僕はきっと『戦場でワルツを』に手を伸ばす。
これが軍隊だ!
これが戦場だ!
と、某ソラ○ヲトに突きつけてあげたくなる作品でした。
軍隊物ってやっぱある種の昂揚感とか、無常観が出てこないとやる意味が無くなっちゃうと思うんだね。
あらすじ
本作の監督はレバノン侵攻に参加していたにも関わらずその記憶が欠落していることに気付く。
と、同時に奇妙なフラッシュバックに襲われる。
それは現実なのか幻想なのか、それを探る為に戦友や戦争関係者に取材して回る。
事件背景はこちらを参照 すると良いかも。
僕もそんなに分からないから、難しいと感じても気にすること無いぜ!
アニメだけれどもドキュメンタリーという、かなり珍しいんじゃないかという手法。
何故こうやったかは諸説あると思うんだけど、僕の考えるのは
「現実と幻想の境界を曖昧にしておく為」
なんじゃないかという気がする。
ストーリーを見ても分かるが、この作品は「欠落した記憶と、ある光景の真偽を追い求める話」だ。
そしてファーストショットは26匹の犬が疾走するシーンから始まる。
それは集落を襲撃する際に、26匹の犬を撃ち殺した戦友の夢で、彼に復讐を果たそうと集まってきたのだ。
しかし夢の下りが終わっても、アニメであることは変わらない。
そして主人公の見るフラッシュバックも、実際のインタビューも、全てアニメで描かれる。
他の知人も、戦争時に見た夢の光景を語る。
他にも戦争時のエピソードや、戦争カメラマンの話などが出てくるが、必ずしも主人公の記憶の欠落と直接的に関わる話とは限らない。
これらの話はとても興味深く、ハイキング気分で戦車に乗ってお菓子を食べ、歌いながら意気揚々と進軍していたらいきなり狙撃・襲撃されて、味方もさっさとトンズラこいて、命からがら逃げ延びたとか、カメラをを通している間は冷静に観れていたけどカメラが壊れてた後に競馬場の馬が酷い有様なのを見て現実感を取り戻してしまったりとか、面白い話に事欠かないのだが、それは本筋じゃないのだ。
一方記憶が戻ってくる部分もあるのだが、それもまた衝撃的なエピソードもありつつ幻想性というか、取り留めの無さが残っている。
RPGを抱えた子供との戦闘シーンでは、BGMはむしろクラシックで、神秘的な雰囲気すらある。
夢も現実も、残酷であるにもかかわらず何処かシュールで冗談のような空気感に支配されているように見える。
だがラストシーンでそれは一変する。
そこで出てくるのは、圧倒的な現実。
イスラエル軍とファランヘ党による行動の結果だ。
血流溢れる桃源郷を彷徨っていた僕らは、そこで一気にこれがリアルであることを認識する。
恐らくは、その為の表現手法だったのではないか……と思うところだ。
戦争は本来忌避されるべき物だが、同時に間違いなく人に昂揚感をもたらせる一面が存在する。
他者を蹂躙し、自らの力を誇る。
もちろん相対的な物に過ぎないが、それが出来うる状況であり、また価値観がそう設定されている。
だから戦闘で兵士が機関銃のワルツを踊り、イスラエル軍とファランヘ党員がバシールとワルツを踊る事は彼らにとってはさほど不自然ではなかったのかもしれない。
本事件の確信になるサブラ・シャティーラの虐殺 に於いてイスラエル軍は虐殺に直接的な関与をしていなかったようである。
しかし主人公(語り手)である監督もまた、直接関与はしていない。
ファランヘの民兵が動きやすいように照明弾を打ち上げていただけだった。
にも関わらず、事件の記憶を無くしている。
それは彼の両親がアウシュビッツに捕らわれており、そのイメージと重なった為に虐殺の記憶を消してしまったのだろうとセラピストは推測する。彼は傍観者だったが、その時は実行者と同じ罪を感じただけで、気に病むことはないと。
だが、果たしてそうだろうか?
迫害され虐殺されたユダヤの民が、時と場所を移して、今度は迫害や虐殺を下す側についている。
まるで自分を撃った人間に群がるあの犬たちのように。
それだけではない。
イスラエル軍は直接的に手こそ下さなかったが、難民を塞き止めてファランヘ党の虐殺をお膳立てした。
まるで復讐という病に蝕まれた狂犬をけしかけるように。
最後のシーンは、その結果を、事実を我々に見せつける。
本作は去年のアカデミー賞外国語映画部門でノミネートされ、『おくりびと』に競り負けた。
確かに僕はエンターテイメントとしてどちらを観るか、また他人にどちらを観た方が良いかと言われれば『おくりびと』を勧めるだろう。
しかし、一生涯でこの2作品のどちらかだけを観なければならず、もう片方には目を通すことが出来ないとしたら、僕はきっと『戦場でワルツを』に手を伸ばす。
『ゲームやアニメついてぼそぼそと語る人』
のピッコロさん企画に便乗第二弾。
異形な世界と絶妙な展開
前回は古いバカ作品だったので、今回は現行放映中のシリアス作品から『戦う司書』を。
近年のライトノベル原作アニメとしては稀に見るほど暗く残酷な世界観の作品で、登場人物もみな一癖も二癖もある。その人物の書き方にしても、昨今の漫画的な属性をありったけぶち込んだそれではなく、どちらかと言えば劇画調というのか、押さえ気味に地味ではあるが根底に様々な物を抱えた存在として書かれているのが特徴。
またイラストレーターが
「高確率で表紙が遺影になってしまう無慈悲な物語」
と公言するほど死亡率高し(絶対死ぬ訳ではない)
しかしながら本当の意味で無慈悲にアッサリ死んでしまう訳では決して無く、それぞれ何かの為に死力を尽くした結果であり、根底にはある種のヒューマニズムらしきものさえ漂っていて死亡者を量産して目を引かせるだけの作品とも一線を画している。
ヘンテコ能力バトル&根底のヒューマニズム繋がりのせいか荒木飛呂彦にいたく気に入られているらしく、原作の帯には
『石雄よ!オレは君の味方だ!』
(原作者/山形石雄)
という荒木吸血鬼からの無駄に熱いメッセージが記されているほど。
死者が『本』と呼ばれる生前の体験を凝縮した石版に変化する、という独特の設定を巧みに生かして各エピソードを構築しており、その構成力の高さや長期的な伏線活用の上手さも光る。
アニメも序盤こそ取っつきにくいとの声が多いものの、物語が進むに連れて評価が上がってきており、原作既読者の目から見ても、省略されてはいるが複雑な物語を的確に消化させているという印象を受ける。
未だ終盤の尺に心配を残す部分はあるが、ダークファンタジーの好きな方には是非ともお勧めしたい一品に仕上がっている。
なお、最新話では物語の佳境の一つにして超重大なネタバレが起きているので見る場合は1話から順を追った方が賢明。
異形な世界と絶妙な展開
- 戦う司書と恋する爆弾 BOOK1(集英社スーパーダッシュ文庫)/山形 石雄
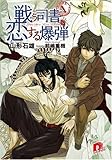
- ¥600
- Amazon.co.jp
前回は古いバカ作品だったので、今回は現行放映中のシリアス作品から『戦う司書』を。
近年のライトノベル原作アニメとしては稀に見るほど暗く残酷な世界観の作品で、登場人物もみな一癖も二癖もある。その人物の書き方にしても、昨今の漫画的な属性をありったけぶち込んだそれではなく、どちらかと言えば劇画調というのか、押さえ気味に地味ではあるが根底に様々な物を抱えた存在として書かれているのが特徴。
またイラストレーターが
「高確率で表紙が遺影になってしまう無慈悲な物語」
と公言するほど死亡率高し(絶対死ぬ訳ではない)
しかしながら本当の意味で無慈悲にアッサリ死んでしまう訳では決して無く、それぞれ何かの為に死力を尽くした結果であり、根底にはある種のヒューマニズムらしきものさえ漂っていて死亡者を量産して目を引かせるだけの作品とも一線を画している。
ヘンテコ能力バトル&根底のヒューマニズム繋がりのせいか荒木飛呂彦にいたく気に入られているらしく、原作の帯には
『石雄よ!オレは君の味方だ!』
(原作者/山形石雄)
という荒木吸血鬼からの無駄に熱いメッセージが記されているほど。
死者が『本』と呼ばれる生前の体験を凝縮した石版に変化する、という独特の設定を巧みに生かして各エピソードを構築しており、その構成力の高さや長期的な伏線活用の上手さも光る。
アニメも序盤こそ取っつきにくいとの声が多いものの、物語が進むに連れて評価が上がってきており、原作既読者の目から見ても、省略されてはいるが複雑な物語を的確に消化させているという印象を受ける。
未だ終盤の尺に心配を残す部分はあるが、ダークファンタジーの好きな方には是非ともお勧めしたい一品に仕上がっている。
なお、最新話では物語の佳境の一つにして超重大なネタバレが起きているので見る場合は1話から順を追った方が賢明。