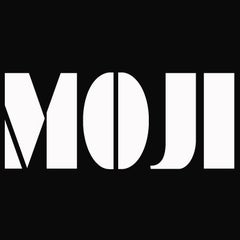TÁR(2022 アメリカ)
監督/脚本 :トッド・フィールド
製作:トッド・フィールド、スコット・ランバート、アレクサンドラ・ミルチャン
撮影:フロリアン・ホーフマイスター
編集:モニカ・ウィリー
音楽:ヒドゥル・グドナドッティル
出演:ケイト・ブランシェット、ノエミ・メルラン、ニーナ・ホス、ゾフィー・カウアー、ジュリアン・グローヴァー、アラン・コーデュナー、マーク・ストロング、シルヴィア・フローテ、アダム・ゴプニク
「ター」、観れば観るほど深みにはまる、すごい映画でした!
最初は普通にレビューを書こうとしたのだけど、この映画は解釈次第でどういう映画かがまるっきり変わっちゃうので。
自分の考えを整理するためにも、ネタバレ解説を書くことにしました。
時系列に沿って、自分なりの考えを書いていきます。
違ってることも多々あるかと思います。気づいたことがあれば、ぜひコメントで知らせてください。
最後までネタバレしていますので、要注意。
飛行機の中
冒頭、飛行機の座席で眠るターを撮影しながら、チャットしている二人の会話。
時系列から考えて、これはベルリンからニューヨークへ向かうターのプライベートジェットの中なのだろうと思われます。ということは、撮影しているのはフランチェスカ。
チャットの相手は不明だけれど、ターのことをよく知っていて悪口を言う相手なので、おそらくクリスタでしょうね。
ターが眠ってるのをいいことに、悪口を言う二人。これはまあ、上司と部下の関係ではよくある構図でしょう。(後にオルガも同じことをやっています)
一方で尊敬もあるにせよ、いろいろと振り回されて疲弊して、文句が溜まっていくのは普通の上下関係でもよくあることです。
ただ不穏さを孕むのは、チャットの相手が前は近くにいたが今は離れていること。そして、フランチェスカが表面的にはターへの不満を(それに愛も)一切見せていないこと。
クリスタは「まだ愛してるのね」と書いています。そして、フランチェスカは否定しない。
フランチェスカは以前はターと恋仲で、今は恋愛関係ではないけれど、内心ではまだ愛している、ということがわかります。
短いプロローグシーンですが、これは「ター」という映画の構造を端的に表していると思います。
すべての場面には、見えている表面と見えない裏側、2つの面があること。
情報がすべて開示されず、想像を交えなければならない場合…「ター」という映画はほとんどすべてのシーンがそうなのですが…見る側は、一般的な構図をそこに当てはめるということ。
このプロローグなら、「抑圧的で傲慢な上司と、それによってストレスを受けている部下の構図」ですね。
でもそこには見えていない一面があって、クリスタの呟きがそれを象徴している。
人は往々にして、足りない情報を想像や既成のイメージで埋めて、分かったつもりになって相手を判断する。場合によっては批判し、非難し、断罪する。
本当は、そこまで決めつけるには情報が足りていないはずなのに。
いとも容易く人は人を決めつけ、「炎上」「ネットリンチ」「キャンセルカルチャー」といったことにつながっていく。
そういう、人間と社会をめぐる現代の風潮。
それを、この映画は映画の構造そのものを使って、観客に実感させるんですよね。
ぼんやりと見ていたら、ターはただ傲慢な権力者に見えるし、その転落も「自業自得」としか思えないものになる。
でも注意深く見ていると、本当にそうか?と思えてる…という。
観る側の気持ちの置き方によって、ターという人物の見え方が変わり、映画全体の様相がガラッと変わってしまう。
そして、自分の見方の中にあった先入観、思い込み、偏見といったものに気づかされていく。
そういう、巧妙な仕掛けが施された映画なのです。
シピボ・コニボ族の歌
真っ黒な画面で通常なら映画の終わりに流れる「エンドクレジット」を流しながら、シピボ・コニボ族の歌が流れます。
講演会の経歴紹介でわかりますが、ターはウィーン大学の大学院で先住民音楽を研究し、そのフィールドワークとしてペルー東部のウカヤリ渓谷を訪れ、先住民シピボ・コニボ族の間で5年間を過ごしました。これはそこで録音された歌です。
その旅には、フランチェスカとクリスタも同行していました。
講演会で、ターはシピボ・コニボ族の歌を「歌い手が歌を創造した精霊と同期した場合のみ、歌を受け取ることができる」と説明しています。それがこの民族の歌への考え方です。
この考え方はターに大きな影響を与え、今でも、クラシック音楽を指揮する上でも、実践しています。
作曲家をよく知り、曲に込められた意図をよく知ることが、シピボ・コニボ族に学んだターの音楽へのアプローチ方法です。
シピボ・コニボ族はペルー東部のアマゾン奥地、ウカヤリ川流域に暮らす実在の先住民族です。
彼らの作る布や壺などは、独特の「六角形を組み合わせた迷路のような幾何学模様」が描かれています。これがシピボ・コニボ族を象徴するものです。
この模様は、シャーマンが薬草を摂取することで見るビジョン、あるいは聖なる蛇アナコンダの鱗模様に由来するとされています。
講演会
本作は場所や時制などを説明する字幕などがまったくないので一見分からないのですが、よく見ると分かる…という構成が全体に貫かれています。
冒頭の講演会も、司会者が「我らがニューヨークフィル」と言うところから、ここがニューヨークであることがわかります。
深呼吸して、水を飲み、手の震えを止めて舞台に上がるター。
呼吸法は、たぶんシピボ・コニボのメソッドですね。
自信満々に見えるけれど、やはり緊張と大きな重圧を感じていることがわかります。
司会者はアダム・ゴプニク。彼はアメリカの作家/エッセイストで、本人役で出演しています。
ターの経歴紹介のバックで、レコードを床に並べて裸足の足で選り分ける様子が映されます。
これは、予定されているライブ録音で発売される予定のマーラーのジャケットを検討しているんですね。
場所はターのピアノ用の部屋で、一緒にいるのはフランチェスカと思われます。
「クラウディオ・アバドのレコード」を裸足の爪先が指し示したところで、もう一方の足が愛撫するように重ねられます。
ここから、ターとフランチェスカの間にはまだ微妙にエロチックな関係が存在していることが伺えます。
ターの経歴紹介。多くの名門で音楽を学び、アマゾンで民俗音楽の研究をし、指揮者としてプロの経歴をスタートし、数々の楽団で指揮をとり、クラシックだけでなく現代の作曲家も取り上げて話題を呼び、作曲家としても活躍してEGOT(エミーグラミーオスカートニー)を総なめにし、もうすぐ自叙伝「ター・オン・ター」が刊行される……錚々たる経歴。
その様子を、観客席後方で見ている赤毛の女がいます。
これはクリスタですね。クリスタはニューヨーク在住なので、ここにいるのは自然です。
フランチェスカは司会者の経歴紹介を暗唱しています。おそらく、その原稿は彼女が書いたのでしょう。
ターはアンドリスの後任として女性で初めてベルリン交響楽団の首席指揮者となり、マーラーの9つの交響曲のうち、8つを既に録音しました。
今、最後に残った9つ目、第5番のライブ録音を控えており、月曜日からリハーサルが始まる、そういう状況です。
対談はまずジェンダーについての話になり、ターは過去の女性指揮者が差別を受け、締め出されてきたことについて語ります。
聞いているクリスタはどんな気持ちでしょうね。彼女は今まさに、ターによって音楽業界から締め出されているというのに。
指揮者はメトロノームのようなものではないかという司会者に、ターは時間が重要であると語ります。
ただし、指揮者は時間を支配している。指揮者は時間を止めることができ、指揮者がいなくては時間は動き出さない。
時間さえも支配しコントロールするのが指揮者である、という認識は、彼女を「すべてをコントロールしようとする人」にせざるを得ないのかもしれません。
ターはまた、師であるレナード・バーンスタインについて語ります。
バーンスタインから学んだもっとも大事なことは「カバナ」。ヘブライ語で「注意」を表します。
マーラーの意図に注意を払う。そこでターが注目したのは、楽譜の表紙に書かれた妻アルマへの献辞でした。
マーラーの5番を理解するためには、マーラーの複雑な結婚生活を理解することが必要だとターは言います。
作曲家の意味や意図に注意を払うこと。これとシピボ・コニボ族の考え方が結びついたものが、現在のターの流儀ですね。
バーンスタインは自分のアプローチで「過去を変える」ことができると信じていましたが、ターはシピボ族にならって、「過去と現在の融合」を目指しています。
講演会から始まる意図
この講演会のシーン。舞台の上で椅子に座ったまま、司会者とターのペダンティックな難しいクラシックの話が延々と続く。
ちゃんと聞いてないと意味がわからないし、聞いていてもだんだん上滑りしていくような。
ここで表面的に伝わるのは…劇中の観衆も映画の観客も、クラシックの専門家でないほとんどの人に伝わるのは…「何やら意識の高い難しい話を得々とするターの印象」ですね。
「頭良さそうですごい」でもあるし、それは同時に「なんだか意識高くていけすかない」でもある。「偉そう」とかね。
そういう印象。どうせ一般人はクラシックの詳細な理論などにさほどの興味はなく、そのような印象だけが残る。
これ、映画をエンドクレジットで始めて、本編が始まっても座って難しい話を喋ってるだけという、あえての構成も狙ってやってますね。
あえて、観客がターにちょっとフラストレーションを感じる…「嫌いとまでは言わないまでも、なんか偉そうだし、ちょっと感じ悪いなあ…」くらいのバランスに、持っていってる。
それによって、「劇中の一般人にとってのターの受容のされ方」と、観客の見方が同期されていきます。
自信満々で、あらゆる質問に博識で答え、場を支配していくターからは、「すごさ」と同時に「怖さ」のようなもの、それこそ「こんな人が上司だったらしんどそう…」と思うような、圧力がどうしても伝わってしまいます。
でも、実際の会話の内容をよく考えてみると、別にターは真摯に質問に答えてるだけなんですよね。
別に誤魔化したり、煙に巻いたり、適当にあしらったりしていない。無意味にマウントをとることもない。一つ一つの質問をよく考えて、真剣に答えている。
そしてそのために、大変な緊張と重圧に耐えている。
ここから見えてくるのは、ターのむしろ愚直なまでの「真面目さ」ですね。でも結局、彼女は「真面目で好ましく見えるには、偉くなりすぎている」から、そんなふうには受け取ってもらえないのです。
ホイットニー
講演会の後の交流会で、ファンの女性ホイットニーと楽しげに話すター。
それを時間を気にしながら見守るフランチェスカ。
この時もフランチェスカは携帯で何か打っており、クリスタとチャットでターの悪口を言ってるのかもしれません。
なんてことのないシーンのようですが、ここから伝わるのは、レズビアンであるターが、自分好みの女性を前にすると機嫌が良くなり、リラックスする…ということですね。
そのことを、ターをよく知る人はよくわかっている。フランチェスカもわかっている。
後で、ターがオルガを前にした時の態度や、それを見守るシャロンにもつながっていく。
音楽の話をしながら、さりげなく相手のバッグを褒めたりして、親しみやすさを演出していく。その辺りはもう、無意識でしょうか。
このシーンはホイットニーが「メールしてもいいですか?」と聞くところでブチっと終わり、その後に何が起こったか…起こらなかったか…はあえて曖昧にされていますが…。
ターは、この後であらためてホイットニーと会ってると思われます。
カプランとの会食
エリオット・カプランはユダヤ人の実業家で、ターの有力な後援者の一人です。
彼は女性指揮者のためのバックアッププログラムを支援しており、ターは(フランチェスカ、それにかつてはクリスタも)そのメンバーです。
カプランとターは「問題があったメンバーの一人」について話しています。おそらくこれはクリスタのことでしょう。
「具体的にどのような問題か」は話されないのですが、カプランはそれを共有しています。
クリスタの父親が銀行家で、クリスタの問題は融資に影響を与えているようです。
カプランは自身も指揮者です。しかしその実力は怪しいようで、観にこなかったことを問われたターは娘ペトラの行事を言い訳にします。
ターは、明らかにカプランの指揮者としての能力を認めていない。
だからこそ、自分の代わりにカプランが…という終盤の展開は許せなかったわけですね。
ターはカプランに「近くのテーブルの男が見ている」と言い、「席を外そうか?」と言います。
カプランはゲイであるようなんですが、これもちょっと示唆的です。
レストランで居合わせただけの見知らぬ相手と交流することを提案するということは、ター自身も普段から、似たようなことをやっているのかもしれません。
ホイットニーのことが頭にあったから、ターはカプランにそんな提案をしたのかも。
「最終楽章の弦」について、カプランはターのやり方を知りたがるのですが、ターは「人真似に栄光はない」と手厳しい。
「人真似をする人」をターは「ロボット」と呼んで軽蔑します。
パトロンであっても、音楽に関しては忖度しない。ターの「音楽への真面目さ」が伺えるシーンです。
ジュリアード
ジュリアード音楽院はニューヨークに本部を置く名門音楽学校です。ターは知人に頼まれ、特別ゲストとしての講義を受け持つことになったようです。
マックスという学生がアンナ・ソルヴァルドスドッティル(アイスランドの女性現代音楽家)の楽曲を指揮していて、そこからターとマックスの対決になっていきます。
この長回しのシーンでは、マックスがターに徹底的に論破され、追い込まれていきます。
マックスは自分は「BIPOC(黒人および先住民および有色人種)」であり「パンジェンダー(男性でも女性でもなく、第3の性)」だから、生涯に多くの妻と20人もの子供を作った家父長制の権化のような白人男性であるバッハは受け入れられない、だから聴くつもりもない、と言います。
それに対して、ターは音楽家を出自や属性によって評価すべきでないと言います。
音楽家を音楽以外のことで評価するなら、自分自身もやがて性別や性癖などの、音楽以外の要素で評価されてしまうことになる。だから、自分がどんな人物かに関わりなく、バッハも学ばなければならないと。
ここは、表面的には、非常に一方的で抑圧的なハラスメントに見えてしまいます。
圧倒的に実力と権力を持った年長者が、まだ何もわかっていない子供のような若者を理詰めで追い込み、説得し、友達の前で恥をかかせ、論破してやり込めていくのだから。
更には、民族や性自認に関わる属性を否定したり、今日的な目では「政治的に正しくない人物」を受け入れることを強要しているようにも見えてしまう。
でも、ここは「学びの場」であるわけで。教師と生徒に上下関係があるのは当たり前だし、学生が一方的に教えを受ける立場であるのも本来当たり前のことですね。
それに、もしターが不真面目なら、ハイハイって言って適当に流していただろうと思うんですよ。
音楽を学びに来た学生が音楽を学ぶことより自分らしさを優先するのであれば、勝手にそうさせとけばいい。
その結果、その学生が大事なことを何も学べなくても、指揮者になれなくても、そんなことは自己責任なのだから。
実際、ターは高名な指揮者であって、本領は全然別のところにあるわけで。
この講義にそんなに真剣にならなくても、別にどうでもいい…という立場であるはずです。
それでも、放っておけない。あそこまで真剣になって、マックスの考えを変えさせようとするのは、彼の将来の利益を考えての優しさだし、学びの門戸が閉ざされないようにせねばならないという生真面目さ…ですよね。
しかし結局マックスはターを受けいれず、ビッチと呼んで立ち去る。
ターはマックスを、「魂がSNSに形作られたロボット」と呼びます。
このシーン、僕は結構初見からターに全面的に感情移入して、「絶対ターが正しい。こんなアホ学生はさっさと追い出すべきだ」と思いながら観ていたのだけど。
でも、観る人によっては、違う感想を持つかもしれないなあ…と思います。若い人とか、実際に今学生である人とかは、どんなふうに感じるだろう。
同じように教師に「抑圧された」経験を持つ人は、トラウマのように感じるかもしれない。
ここ、ターとマックスは違う側面を見ていて、その見方はまるっきりすれ違ってるんですよね。
ターは、音楽を見ている。音楽を学ぶにあたっての心構えの話をしていて、優れた音楽家になるにはそれは不可欠なことだと経験的に信じているから、それを若者にも伝えなければならないと思っている。そういう、使命感で行動している。
マックスは、自分の気持ちを見ている。音楽を学ぶどうこうはさておき、今、ここで自分の気持ちがどうであるかの話をしていて、受け入れ難いものは受け入れられない、と言っている。
ここが音楽を学ぶ場であり、彼らが教師と生徒であるという側面からは、ターが正しい。
でも、それ以前の一人の人間としては、心が感じたことに忠実であろうとするマックスにも、正しさはあると言える。
だからこれはもう、どこまでもすれ違いにしかならないわけです。
ニューヨークの夜
その夜、カーライル・ホテル。
フランチェスカはターと一緒に夜を過ごしたいように見えますが、ターはさっさと一人でピアノに向かい「夕食もここで済ませる」と言います。
ターはいかにもフランチェスカを追い払って一人になりたいように見えます。
これ、後にターとオルガで立場を変えて繰り返されることになります。
フランチェスカはターに、フロントに預けられていた誰かのプレゼントを渡します。
バスルームで、ターはテレビのアナウンサーの声を復唱しています。
彼女はニューヨークの下町出身なので本来は訛りがあり、きれいな言葉を話すのは訓練のたまものなのです。(後に、リディアという名前も本名ではないことが明かされます。)
この時、ターは先ほどのプレゼントからの「不吉な気配」を感じています。ここで既に、ターはプレゼントとクリスタをつなげて考えていたのかもしれません。
後での繰り返しの時、オルガはターには寝ると言って、おめかしして出かけていきました。
この夜のターも、同じだったのだと思われます。
後で、シャロンが「電話したけど出なかった」と言っています。
フランチェスカは気づいているし、シャロンも薄々気づいているんでしょうね。ターは出張のたびに、こういうことを繰り返しているんでしょう。
この夜、ターは外出してホイットニーと会ったのではないかと思われます。
家に帰ったターは、ホイットニーが持っていた赤いバッグを持っていました。シャロンには「カプランからのプレゼント」と言ってたけど、そんなシーンはなかった。
ターがそのバッグをお気に入りだったと知ってるのは、フランチェスカを除けばホイットニーだけ。
自分で買ったのであれば、シャロンに「カプランから」と嘘をつく必要もない。
赤いバッグはホイットニーが講演会から夜までの間に買ったバースデープレゼントでしょうね。二人はこの夜、どこかで会っているのです。
「挑戦」
翌朝、移動中の車の中で、ターとフランチェスカは昨日の講演について話します。
マーラーと妻アルマについて、フランチェスカはマーラーがアルマに作曲の仕事をやめさせ、主婦にしたことを思い出させます。
これは、ターとフランチェスカの関係と同じですね。フランチェスカも指揮者だけど指揮者の仕事は許されず、ターの雑用ばかりやらされています。
フランチェスカは、クリスタからまたメールが来たことを知らせます。
ターは「返事はしないで」と命じます。
「今回は特に必死」と言われても、「Hope dies last」とそっけない。
ここ、フランチェスカがメールでやり取りしていたのがクリスタなら、フランチェスカは自分がクリスタと今もやり取りを続けていることをターには隠していることになります。
飛行機のトイレの中で、ターは薬を飲みます。それはシャロンの持病の心臓の薬を、自分用の抗不安剤としてちょろまかして来たものです。
昨夜受け取ったプレゼントを開けるター。それはヴィタ・サックヴィル=ウェストの「挑戦(Challenge)」という本です。
ヴィタ・サックヴィル=ウェストは1892年生まれのイギリスの詩人・作家です。
ヴィタは両性愛者であり、ハロルドという夫がいる身でありながら、ヴァイオレット・ケッペル=トレフューシスという女性と駆け落ちしています。
ヴィタはオープンマリッジ(夫婦が互いに夫婦以外の性関係に無干渉)主義者で、夫ハロルドとの関係を精算する気はなく、ヴァイオレットがハロルドとヴィタを共有することに耐えられなくなったことから、二人の関係は破局しました。
「挑戦」はこの関係をもとに書かれた小説です。
クリスタはこの小説の内容に、ターへのメッセージを込めたはずです。
ターの周囲の人間関係を小説に当てはめるなら、ヴィタ=ター、ハロルド=シャロン、ヴァイオレット=フランチェスカということになります。
ターはフランチェスカと恋愛関係になりながら、シャロンとのパートナー関係を解消するつもりもない。
フランチェスカはそんな関係に耐えられず身を引いたのでしょうが、今でもターを愛していて、苦しんでいる。
この本には、そのことを当てこする意味が込められているのでしょう。
本の扉ページには、シピボ・コニボ族に由来する六角形を組み合わせた迷路のような幾何学模様が描かれています。
そこから、ターは本の贈り主がクリスタであると確信して、本を破って捨てます。
本の贈り主が本当はどうだったかも、実は曖昧です。
フロントに預けられていたというフランチェスカの発言からは、クリスタが贈り主であると思えます。
しかし、それが嘘である場合、贈り主はフランチェスカかもしれません。
本の内容からは、贈り主がフランチェスカである方が、メッセージとしては自然であるように思えます。
そのページを破って捨てた後、ターはクリスタの名前の文字を並べ替え、アナグラムを作ります。
KRISTA TAYLORから「AT RISK(危険)」に。
この名前のアナグラムは、劇中で何度か登場し、フランチェスカがやっているシーンもあります。
これもおそらく、シピボ・コニボ族から学んだ占い的なものなのだろうと思われます。
その2に続きます!
このブログ著者のホラー小説が予約受付中です。よろしくお願いします!
Discover usという映画マガジンでも映画の記事を書いています。よろしかったらこちらもどうぞ。