行動分析学と山本五十六
~行動分析学2~
■確立操作
飽和化:好子のマンネリ化
遮断:好子をストップすると好子効果は上昇する
→確立操作
Barでのピーナッツは酒の好子効果を増加させる
たとえば営業活動を強化する場合↓
目標により、結果の好子は増加される:確立操作
インセンティブを与える:弁別刺激
■自己強化
・標的行動の強化
・行動記録
・ベースライン作成
・グラフをつける
・随伴性の導入→自己好子=トークン
■レスポンデント反応
『中性刺激』:メトロノーム 人の顔
『無条件刺激』:肉 叱責
→組み合わせることで『条件刺激』化する。
これをレスポンデント反応という。
■ヒューイット・アソシエイツ社
欧米では行動分析学に基づく組織作りのために、
HRビジネスパートナーという役職が定着しつつある。
良い企業文化・悪い企業文化は存在しない
↓
その組織が求める企業文化は存在する
↓
企業業績を向上させる企業文化は存在する
↓
望ましい企業文化に向けて変革は必要
どこの会社でも、レスポンデント反応が生じていて、
これは社員の成長や、サービスの低下に寄与している。
あるいは、シェイピングやバックヤードチェイニングなども
できる人が経験的に提供しているだけで、
どのMGRにつくかでその人の成長速度は大きく異なる。
分化強化や確立操作も基本的には
経験値からの提供なので、使用できる幅が広がれば
簡単に業績も伸びると思う。
自社では人件費かさむので、中々難しいが、
お客さんに提供する商品に組み込みながら、
組織活性に寄与していきたいと思う。
○山本五十六
最後になりますが、山本五十六の名言は
行動分析学的にもやはり正しいことが証明されますね。
『やってみせ、言ってきかせて、させてみせ
ほめてやらねば人はうごかじ』
バックワードチェイニング
(やってみせ)
↓
シェイピング
フィードバック
(言って聞かせて)
↓
シェイピング
(させてみせ)
↓
承認
好子
(褒めてやらねば人はうごかじ)
- 行動分析学マネジメント-人と組織を変える方法論/舞田 竜宣

- ¥1,890
- Amazon.co.jp
- 連合艦隊司令長官 山本五十六の大罪―亡国の帝国海軍と太平洋戦争の真像/中川 八洋
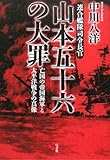
- ¥2,310
- Amazon.co.jp
行動分析科学
- 行動分析学マネジメント-人と組織を変える方法論/舞田 竜宣

- ¥1,890
- Amazon.co.jp
- 変革を定着させる行動原理のマネジメント―人と組織の慣性をいかに打破するか/中島 克也

- ¥1,680
- Amazon.co.jp
~行動分析科学~
・組織を変革する行動を定着させるために、
好子と嫌子という概念がある。
一般的な行動原理の承認>処罰>脅迫>無視の概念を
さらに詳細なレベルで分解した要素である。
好子とは、行動直後に行動を強化するものであり、
嫌子とは、行動直後に行動を弱化するものである。
その他にも、
消去:強化の随伴性を中止することで行動を減少する
復帰:弱化の随伴性を中止することで行動を回復する
などなど様々な基礎行動分析科学が存在する。
だめな上司や伸び悩んでいる会社は嫌子で行動を管理し、
まあ普通の上司やぼちぼちの企業は好子で行動を管理している。
さらに仕事ができる人間や、真の経営者は、
好子でも変比率強化と部分強化をうまく用いている。
また、バックワードチェイニングやシェイピングで、
部下の成長スピードを早める技術を持っている。
あるいは、分化強化を用いることで、
行動定着レベルを向上させ続けている。
組織変革を起こすには、ツールではなく背中で見せる実力と
適切な行動を起こし、それを定着させることである。
というわけで、納品の中でも目線を上げるステップや、
各項目で意見を引き出し、
その行動をコミットするフェアプロセスを踏みながら、
承認や好子特に分化強化を用いたファシリテートを行うと共に、
自分のスキルとして、シェイピングやバックワードチェイニングを用いながら、
社長がそれを扱えるようにサポートすることで、
日本の中小企業の幸せ度を増して行きたいと思う。
一番大事なのは、社員の仕事と社員の夢に架け橋をかけること。
- コーチングの神様が教える「できる人」の法則/マーシャル ゴールドスミス

- ¥1,890
- Amazon.co.jp
ザ・ドリーム・マネージャー
■ザ・ドリーム・マネージャー
●introduction
・チームは配属されてイコール結成ではない。
・飲み会で表面的仲間意識はチームではない。
・チームにはビルドする段階が必要である。
→志の共有、フェアプロセスが重要だと仮設立てられる。
(組織が活きるチームビルディングと思考より)
●セッションⅠ
・組織を動かす一人一人が理想の自分になろうと懸命に
努力すれば、その組織は理想に近づく。
・社員は会社の目標を達成するためではなく、
理想の自分になるために仕事をする。
→人が会社のために存在しているのではなく、会社が人のために存在。
●セッションⅡ
・ドリームマネージャーの仕事は、
『現在の仕事』と『夢の実現』に架け橋をかけること。
・仕事が夢実現につながると具体的に示す。
・夢実現への道筋が仕事にリンクしなければ、
あるいは道筋がわからなければ、実現に励めない。
→夢があっても仕事とのリンクのさせ方と歩み方がわからない。
=偉大な書物を読まないのは、字が読めない人と得るものが変わらない。
・人はただ、夢を語るだけで実現に近づく。
・常に一人一人違った夢があることを忘れてはいけない。
※夢の共有は最大の承認プロセス
行動原理のマネジメントより、
行動の定着には承認と脅迫(承認>脅迫)
行動の弱化には処罰と無視(無視>処罰)
●セッションⅢ
・ビジネスにおける失敗は少ない戦力に大きな間接部門がぶらさがる
成功するのは全員が戦力でそのために夢と仕事にリンクが絶対的に必要。
・夢追求への協力はあらゆる人間関係への基本。
※この協力こそ、チームビルディングにおける
究極のラポールだと仮説立つ。
○成果 ドリームマネジメント 5年間の成果
・離職率 400%→12%
・社員数 407人→743人
・年商 3倍
・持ち家率 3倍
・夢実現 2785件
チームビルディングにおいて、
①お互いの夢を共有する。
②夢実現と仕事のリンクの具体性を示す。
③夢による究極のラポールと承認を繰り返し、
チームビジョン達成に向けて進捗する。
この3段階が強いチームを作る上で重要である。
- ザ・ドリーム・マネジャー モチベーションがみるみる上がる「夢」のマネジメント/マシュー・ケリー
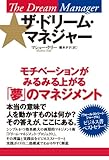
- ¥1,890
- Amazon.co.jp
- 変革を定着させる行動原理のマネジメント―人と組織の慣性をいかに打破するか/中島 克也

- ¥1,680
- Amazon.co.jp
- 組織が活きるチームビルディング―成果が上がる、業績が上がる/北森 義明

- ¥1,680
- Amazon.co.jp
人気ブログランキングへ