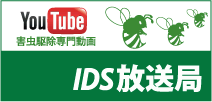前回
https://ameblo.jp/ids-gaichu-h/entry-12536666337.html?frm=theme

今日は捕獲されることが極めて珍しい健康なタヌキが2頭同時に捕まり、アライグマの気配がないのでこの隙にセミナーに戻りましょう。もう来週木曜日にありますけれども、次回も加藤先生には講演して頂きます。今の内に前回の講演内容を振り返りましょう。

今回は海外のアライグマ状況についてです。もちろんアライグマの原産地は北米大陸ですが、ここでもなかなかに厄介な生態を展開しています。そもそもこの原産地の範囲を見る通り、北米の南から北までカナダやメキシコ、カリブ海―じゃないや、メキシコ湾周りにも生息しています。彼らの元々の生息地はやや湿地の多い平地とされていて、おそらくアメリカ南東部のミシシッピとかルイジアナとかなのだろうと思います(ここは完全に個人的憶測なので信憑性はなし)。しかし日本で既に分かり切っているように、彼らの適応力を以てすればテキサスの砂漠からカナダ国境を越えた寒冷地域までどこにでも生息でき、繁殖しているようです。カナダに旅行をした人の話を聞いても、公園のそこら中にアライグマが我が物顔でいるということでした。
さらに北米のアライグマで厄介なのが狂犬病です。狂犬病は哺乳類ならばどの種でも媒介、発症する病気で一旦発症すれば致死率はほぼ100%。既に北米大陸の野生動物の間では伝染しており、アライグマはその筆頭とされています。
アライグマに潜む狂犬病、米国の壮大な根絶計画
https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/19/100100563/
既にこの記事は登録しないと読めなくなっていますが、現在アメリカの東部のアライグマたちの間で狂犬病が確認されており、狂犬病の根絶のために政府はワクチン入りの餌を各地でばらまいています。この記事の関係者の見通しですと根絶にはこの先2,30年はかかるという話でした。植林した木が林になるよりは近い将来の話かもしれませんが、いずれにせよかなりの労力と金を要する計画なのは間違いありません。日本では今のところ生息する動物の間で狂犬病の発症は何十年も確認されていませんが、今後海外からヒトや動物を介して狂犬病がどこかから入り込み、よりによって日本列島各地に勢力を広げて根絶どころか減少もままならないアライグマの間で蔓延でもすれば・・・今以上に対策費用も被害も広がることだけは言えるでしょうね。
外来アライグマ 生息適地はもっと広がる 研究
https://natgeo.nikkeibp.co.jp/atcl/news/19/073100447/
同じくナショナルジオグラフィックの記事ですが、この記事の1ページ目の地図によると加藤先生の記事以上にアライグマの生息図は世界中で広まっている様で、中東(イラン、アゼルバイジャン)にもカリブ海にも狭くはありますが生息しており、緑色の生息可能地域なんて5大陸のほとんどですからその潜在能力の末恐ろしさを感じられます。
講演に戻ると、現在の所の主な移入地域は日本とヨーロッパ(主にフランス、ドイツと周辺国)です。導入は日本より古く、目的は主に毛皮用でした。しかし狩猟の獲物として大して受けなかったようで、以降は愛玩用として扱われることも多かったようです。ともかく現在では日本以上に増えているようで、ヨーロッパ諸国の対処方法としてはあまり駆除はしないようです。狩猟が盛んな地域であるにしても、ハンターが狩るのはもっと素早く狩り応えのあるキツネやイノシシ、鳥などで、今は毛皮の人気も愛護的な風潮で低く、獲物としても人気が低いアライグマは見向きもされないそうです。ただ、人々の意識も被害がある人なら餌付けの禁止や疾病対策など意識は持っていますが、知らない人なら

こうして餌付けしてしまう。加藤先生は以前ヨーロッパ現地のアライグマの生息状況の調査で水鳥の生息する公園に行ったのですが、その公園ではアライグマの駆除を禁止していたため、GPSをつけて生息調査をしていたようです。

このような洞のある大きな木に生息し、

周辺に住む水鳥の卵や雛を捕食して暮らしていたそうです。アライグマは本来こうした木の洞に生息するのですが、日本列島ではそんなに大きな木は北海道でもなければほとんどないため、代わりとして寺社の天井裏、空き家などに住み着いています。高い場所にある空洞スペースさえあればアライグマはどこにでも住みかにできてしまうわけです。
そして特に加藤先生が仰っていたことで印象深いのが、現在導入の中心地であったドイツには、100万頭以上のアライグマが生息しているのではないか、という話でした。これはもちろん推測の域を出ませんが、もはやどうしようもない途方もない数だというのは間違いありません。かといって、日本全体でのアライグマの年間捕獲数は3万頭ほどはあるので、毎年それ以上の数を生産できるだけのアライグマが生息していることになり、このまま増加し続ければヨーロッパに近づくのも時間の問題でしょう。そうなれば農業被害はさらに増え、生態系はさらにぐちゃぐちゃになり、ついにはペットやヒトにも被害をもたらすようになってしまう・・・。このくらいは予想ができます。
どこかではヨーロッパのあまり駆除をしない姿勢を「共存」と言っていた人もいた気がしますが、加藤先生によればヨーロッパの学界では誰も駆除しないことを良しとする意見はなく、半ばその繁殖力と適応力を諦観した結果が現在だという話でした。日本では特別外来種指定にして、少なくとも捕獲したものは全て殺処分しているわけですけれども、それですら減ることはない。現状の対策方法に問題があることを認めざるを得ないでしょうし、駆除をするならするで、もっと別の方法を模索する必要があると思われます。
まっ、そんなことをまた来週木曜にお話しする予定です。今回はここまでにしておきます。





































 0120-673-052
0120-673-052